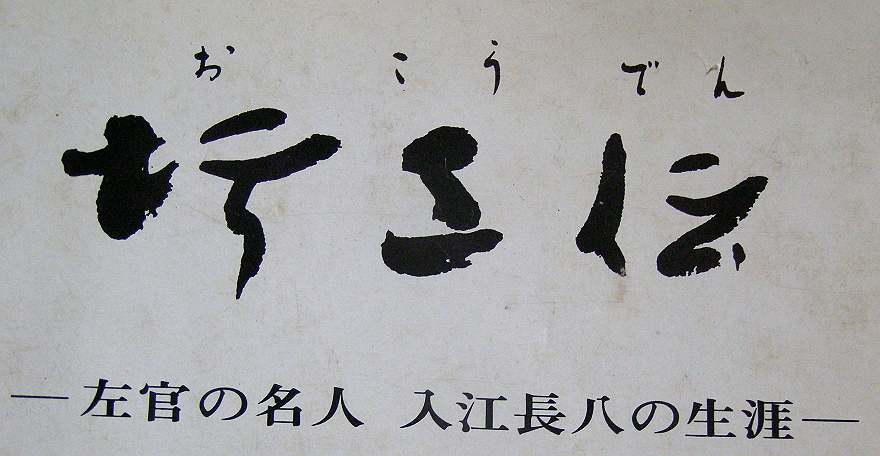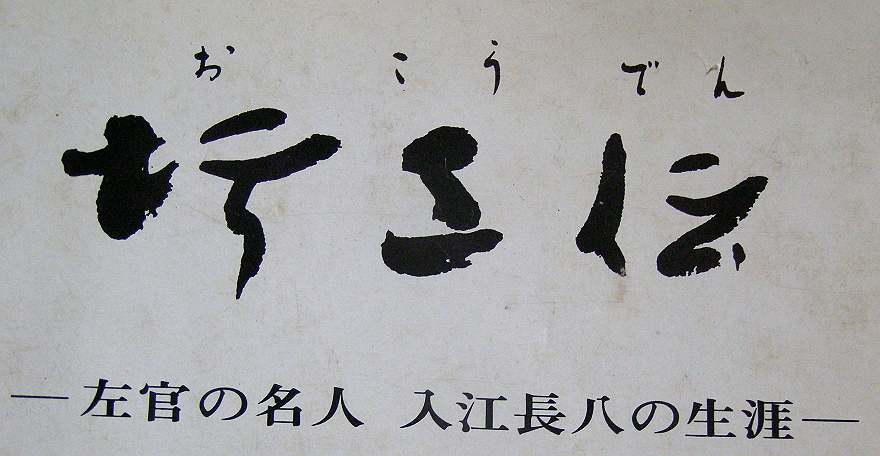須 田 昌 平著
第2章 断 層
|
江戸に出た長八は、時の流れの中で、不況
のどん底で、泥まみれに働きながら、夢を
思って生き抜こうとする。夢こそが、彼の
青春の支えであった。
(十九歳から二十二歳まで)
|
①
伊那上神社の森が辺りを暗くしていて、僅かな空明かりが、点々とそこに散っていた。
森の中である。長八はおむめをしっかりと抱いていた。
森の外が急に明るくなった。見ると、満月が異様に大きく浮かんでいた。二人は月に誘
われるように、手を握り合って森を出た。田道を歩いて川土堤に出た。
川土堤に登ると、笹やぶがはげしく鳴っていた。竹の穂が大きく揺れていた。二人は影
を踏みながら歩いた。
突然、笹やぶの中から黒い影が出て来た。いきなり長八につぶてのように突き当たった。
長八は反射的に撥ねのけようとした。枯れ草の上で揉み合った。
長い時間が経ったような気がした。ふと、おむめの姿が見えないと知った。黒い影もな
かった。月の光だけが冷たく流れていた。
「おむめちゃーん」
と叫ぼうとしたが声に出なかった。もう一度呼ぼうとする長八の眼の前に、金五郎の顔
が大きく映った。あざ笑っている顔だった。
「金五郎!」
と、拳をあげて打ったが、手答えなかった。立ち上がろうともがいた。
………夢だった。長八は猫越山の頂きに、枯れ草にまみれていた。松崎村を出て、江奈
山を越えた。仁科川沿いの村々を過ぎて、ようやく夜の明け方に宮が原村に着いた。空腹
だった。麓の小さな茶店で煎餅を一袋買って、かじりながら猫越の山を登った。頂上に来
て、ほっと一息すると眠ってしまった。
眼を覚ますと、熊笹がせわしく鳴っていた。薄曇りの春の日が、もう昼近いことを示し
ていた。
「夢だった」
長八はつぶやいた。昨夜のことが否応なく思い出された。すると、故郷の人々の顔が浮
かんだ。昨夜そのまま出て来てしまったことが早計だったように思われた。おむめ以外は
誰にも知らせなかった。仁助はどう思っているだろう。特に父母は、正観は、福太郎は…
……と思った。妙に心が重かった。
「今更」
長八は自分の中の未練を振り切るように、独りごとを言った。ここまで来て引き返すこ
とはいやだ。長八はすくっと立ち上がった。そして足早に峠の路を曲がって行った。
天保四年春三月の初めのことである。
長八がそういう径路をたどったか、それは物語の本筋には関係ないが、当時の交通事情
を一応知って置く必要があろう。松崎から江戸へのコースは、およそ三つあった。一つは
海路を沼津に出て、沼津から東海道を下るもの。二つは海路又は陸路を下田に出て、そこ
から相模湾を横断して東京湾に入るコース。この二つのコースは便利であるが、多額の船
賃を支払わなければならず、一般庶民は余程の事態ではない限りこのコースは選ばない。
残る一つが長八のたどった猫越峠越えで、田方平野をよぎり三島に出る。日数はかかるが
費用はかからない。多くの人々はこのコースを使った。長八がこのコースをとったのは当
然である。
長八は若葉のにおう山路をたどって湯が島村に着き、そこから、乞食のように、何とか
かとか食を得ながら、江戸にたどりつく。旅費の用意もなかったから、日雇いや雑役や物
乞いなどもして、恐らく一と月位はかかったろうと思われる。
江戸に来て、長八は眼を見張った。途方もなく広く、人が多過ぎた。駿府に滞留したこ
とがあったが、駿府の比ではなかった。長八はその真ただ中に放り出されたようにとまど
った。伝手があってのことではない。これからどうして暮らして行けばいいのか、手のつ
けようもない気持ちだった。
当てどもなくさまよって、廻り廻って、深川の場末の安宿に、ともかく草鞋を脱いだ。
主人は親切に世話を焼いてくれた。翌日から、教えられたように、仕事を探しに町を歩い
た。去年からの大飢饉の影響は、江戸の町にもまだ残っていた。土地不案内だし、とうと
う一日足を棒にして歩いて、何も得るところはなかった。次の日も、その次の日も、職は
なかった。宿賃がとどこおった。
口入れ屋に頼んだ左官職人の口も、いつまで経っても音沙汰なかった。もうこれ以上は
徒食して居れなかった。同宿で知り合った者に誘われて日雇い仕事を始めた。それも三日
に一度の仕事だった。雨が降れば、安宿にごろごろ寝た。こうして、たちまち日が経って
行くのが長八にはいらだたしかった。職人の腕を磨くなんてことは、田舎で考えた夢だっ
た。まして絵の勉強するなど、思いも及ばぬことだった。
苦しい日が続いた。やがて一と月と経ち、二た月経った。が、長八は江戸に出て来たこ
とに後悔してはいなかった。三年という約束が彼の心を支えていた。幸いにも彼の頑健な
体は、激しい労働に堪えられたし、粗食も彼にとっては何のこともなかった。
やがて彼は、一挺の鏝を古道具屋で買い求めた。町を歩いているうちに、不況の風にあ
おられた家々を眼にして、一案を考えたのである。どの家も、ちょっとした修理をも怠っ
ている。忘れているといった方がいいのかも知れない。長八はそこに着眼した。壁や屋根
の修理から、土べっついの手入れまで、自分の足で行ってその場で仕事をし、手軽く安価
にやって、その日の糧を得ようというのである。一日ぐらいの仕事では、頼んでも職人は
来てくれない。そういう仕事をやろうというのである。
この着眼は、うまく図に当たった。町を歩いていて、壁の壊れた家を見つけると、家人
に掛け合う。向こうも願ったりかなったりで、早速仕事に掛かる。半日ですむこともあり、
一刻ですむこともある。手軽で、労賃は安い。日によっては、二軒も三軒も仕事をする。
だんだんやっているうちに、話を聞き伝えて、頼みに来る人も出来た。こうして、長八は
いつ知れず江戸の生活に溶け込んで行く。一人暮らしの長八には、これで結構食って行け
た。
こうした生活がいつまで続いたか、その確証はない。が、相当の長い期間であったこと
は想像出来る。というのは、この年天保四年は、前年に劣らぬ大飢饉で、幕府は救援米を
放出したがさしたる効果もなく、江戸市中では、群衆が蜂起して市中の富商を襲い、その
土蔵を破り、米俵を掠奪するという騒動が随所に起こった年である。米価は高騰し、それ
につれて諸物価があがり、悪質な買いしめがあり、庶民の生活は苦しい限りだった。そん
な時代には、建築や土木も手控えられ、万事控え目になるのが当然で、職人を雇うどころ
か、人減らしに苦慮したことであろう。とすると、長八は依然として安宿生活をせざるを
得なかったし、日々の賃仕事で食っていたと考えざるを得ないのである。
この年の記録には『四月中旬より、朝暮日輪丹のごとく、光なく』とあり、また『六月
土用に入り、なお袷を用う』とある。昔風の表現として多少割引して考えても、その状況
は異常であったに相違ない。九月に入って収穫期を迎えたが、予想以上の大凶作だった。
『東北諸国違作、特に陸奥出羽はなはだしく、三分五厘二毛作と称せられ、米金一両に
六斗二升ないし四斗に高騰し、江戸飢饉し、幕府窮民を救恤する三十一万八千余人に及び、
江戸の米価百文につき六合、あるいは五合五勺』という有様だった。これだけではどれほ
どの高騰かわからないが、資料によると、米一升について、三年前(天保元年)には六十
六文だったし、この翌々年(天保六年)には八十四文だから、天保四年の百十一文は法外
の高値だったと言えよう。
こういう事情で、恐らくは、長八の安宿生活はこの年中続いたであろうし、彼の賃仕事
も相変わらずであったに違いない。
こうして年が明けて天保五年となる。春になって、江戸は一層困窮したであろう。幕府
は関東諸国に命じて、米を廻送させたのも当然な処置だった。が、それも市民にとっては
一時しのぎに過ぎなかった。
ところが、二月、突然江戸は大火に見舞われた。神田から出火して、折からの西北風に
あおられ、見る見るうちに下町一帯に燃えひろがり、多くの人々が住居を失った。これは
大変なことであった。長い間、食に苦しみ物価高に悩み不況にあえいでいる時に、今度は
住居や家財を失ったのである。
が、長八の生涯にとって、これは大きな転機になった。というのは、この大火で、長八
は左官の本業に就くことが出来たからである。
江戸の大火は、建築関係の業者や職人たちを一斉に立ち上がらせた。不況のために江戸
を離れたり転職したりしていた職人たちも、急いで元の職場にもどって復興に当たること
になった。それでも手は足りなかった。近国はもちろん、関西からも職人が集められた。
長八もそういう事情で左官としての第一歩を踏み出したのである。
長八は誰のもとで働いたかについては、いくつかの説があるが、どれもはっきりしてい
ない。榛葉長兵衛、豊田安五郎、豊田長五郎(あるいは源太郎)など挙げられているが、
これには何の手掛かりもない。手掛かりのあるのは、波江野亀次郎ただ一人で、恐らく、
長八は波江野の職人として出発したものと思われる。
波江野亀次郎は、日本橋近くの中橋に住んでいて、中橋の亀次郎とも『ガジュ亀』とも
呼ばれ、江戸で屈指の棟梁榑正(クレマサ)組に属していた。
長八が波江野の配下になったろうという憶測は、次の三つの理由による。
一つは、この伝説の出所が、長八の晩年に最も親近な弟子であった石井巳之助であるこ
とで、巳之助は比較的長く晩年の長八に仕えたので、長八から幾度も回顧談を聞かされて
いたことは確かであろう。二つには、後に述べる日本橋茅場町の薬師堂の造営に、波江野
亀次郎が左官工事一切を請負ったという事実である。この造営で、長八は新しい芸術を発
見し、以後の研究労作の契機となったのであるから、当然波江野の配下でなければならな
いはずである。第三に挙げたいことは、ずっと後になって、長八の養子になった竹次郎は
亀次郎の次男で、後に二代目長八を名乗るほど長八と関係深かったという事実である。
榛葉、豊田などの棟梁も実在しているが、一時的にしても、この際の長八を雇用したと
いう確証はない。
さて、この天保五年の江戸大火では、波江野亀次郎も焼け出されて、深川八名川町の播
磨屋別宅に仮住まいをしていた。播磨屋というのは深川八幡の妓楼で、当主は源次郎と言
い、深川の顔役であった。亀次郎とは幼ない頃からの親友であった。長八が波江野の職人
として働くようになったのはこの時である。
一時は茫然として何も手につかなかった江戸の市民も、次第に焼け跡に家を建て始める
ようになり、日増しに復興の音が高まって行った。そのうちに、各地から資材が続々と集
まって来る。いよいよ復興は進められる。やがて夏になり、秋には商家の本建築が始まる。
仕事は絶え間なく続いて、とうとうその年も暮れた。
長八が故郷を出て、早くも二年の歳月がめぐっていた。約束の三年も、はや半ばを過ぎ
てしまった。考えていた絵の勉強は何もする暇がなかった。
正月、静かな時が長八にいろいろなことを思わせた。故郷の人々のこと。父母のこと。
わけてもおむめのこと。どうしているだろうか。おむめは十八歳の春を迎えたはずである。
が、反面では、江戸へ来た目的が、何一つ果たされていないことをさびしく思った。あと
一年。そう思うとあせりを感じた。
②
大火復興の日々は、それこそ埃と汗にまみれての激しい労働であった。
日暮れて、八名川町へ帰ると、ただぐっすりと眠りたいだけだった。家の中は、職人た
ちの汚れと臭気が立ちこめていた。
そんな所へ、播磨屋源次郎が妻のおりせを連れて、時折り慰問に来た。そのたびに職人
たちにささやかな酒肴が運ばれた。職人たちは待ち望んでいたように馳走になり、陽気に
騒いだ。夫婦はよく新内節を語ったり小唄をうたったりした。
新入りの長八も日が経つにつれて仲間と親しくなっていった。ただ、田舎育ちの田舎弁
が、江戸職人からは冷やかされて小馬鹿にされていた。こんな周囲では絵を描くこともは
ばかられた。
春が過ぎて、波江野の仮建築が出来上がり、主だった者は中橋へもどって行き、八名川
町には臨時の職人だけが残された。が、播磨屋源次郎は引き続いて慰問に来てくれた。そ
の頃、長八は新内節や小唄を何となく口ずさむようになっていた。もともと長八にはそう
いう素質があったようで、後にはこれが大変な結果を生むようなことになる。
新内節は多く男女の恋の物語で、その哀しさが主題になっている。長八が新内節に索か
れたのは、故郷に残して来たおむめの面影を描いて、切ない思いにかられるからであった
ろう。三味線の音にからまりながら、たえだえに流れる哀調は、恋の物語の哀しさと共に、
長八自身になぞらえて、涙のこぼれる時さえあった。
夏の始めのある夜、源次郎夫婦が訪ねて来た。たまたま亀次郎も来合わせていた。持っ
て来た新茶を振る舞い、にぎやかな談笑が続いた。やがて職人たちが部屋にもどると、源
次郎はいつものように、女房のおりせに三味線を持たせて、新内節を始めた。さえた三味
線の音色が長八の部屋まで響いて来た。源次郎の渋い声が聞こえた。
長八はその声を聞くと、寝ていた体を起こした。聞き耳を立て、思わず立ち上がって、
奥の間の障子に耳を寄せた。じっと聞き入っていた。それを、かわやからもどって来た亀
次郎が見とがめた。
「長八じゃないか」
「へえ」
長八は恐縮した格好で頭を下げた。
「何だ」
と詰問するように言ったが、直ぐさとって、
「播磨屋の喉を聞きたいのか」
と亀次郎が言った。
「へえ」
「好きか」
「へえ」
すると、障子があいて、そこに明るい灯が流れた。
「誰だい?」
と妻のおりせが顔をのぞかせた。
「職人で」
と亀次郎は言った。続けて、
「こいつ、新内が好きなんで、聞かせてやってくんなせい」
と言った。三味線も歌も止んでいた。
「若いのになあ」
奧で源次郎の声が聞こえた。
「棟梁、入れておやんな」
源次郎が重ねて言った。
「長八、入れ」
亀次郎がそう言いながら、自分から先に入って、
「ここに来い」
と亀次郎のそばの畳をたたいた。
長八は遠慮深く敷居の中に入った。
「長八と申します」
すると、亀次郎が付け加えるように、
「伊豆の男です」
と言った。
「それじゃあ、もう一度始めから」
源次郎が居ずまいを直した。三味線が静かに鳴った。源次郎が語り出した。次第に三味
線の音と新内の語りが、長八の心を柔らかく溶かしていった。
ひとくさり語って、ぴたりと三味線が止み、急に夜がひっそりとした。おりせが茶を入
れて、長八にもすすめた。
「長さんと言ったな」
源次郎が茶碗を手にして言った。
「へえ」
すると、おりせが、
「新内がお好きのようだねえ」
と、おはぐろの口をほころばせながら言った。優しいおっとりとした声だった。長八は
返事に窮して、膝をもぞもぞと動かした。
「聞くだけ野暮だよ。好きだからこそ、こうして来てるんじゃないか」
源次郎が笑った。重い声の中で暖かさが感じられた。
長八は仕方なく、
「好きと言っても、ただ聞くだけで」
と頭を掻いた。
「聞くことが大事さ。聞いてるうちにだんだん覚え、覚えると歌いたくなるんだ」
源次郎がさりげなく言った。
「こいつ、器用な男で、左官の仕事もなかなか手早くて」
亀次郎が相槌を打つように言った。
源次郎は五十五、六歳、父の兵助と似た年配だと長八は思った。妻のおりせは五十歳前
後、どこか上品で若々しい。
「さ、折角の客だ。もう一つやろう」
源次郎が言うと、おりせが三味線をとった。再び新内の哀しい物語が三味線の音と共に、
静かな初夏の夜を流れた。
こんなことがあって、源次郎夫婦が来る時には、長八は、奥の間に呼ばれるようになっ
た。
「今夜はひとつ歌ってみな」
そう言われて、覚えたところを歌ったりした。
長八という人は、伝説の中にいくつか出て来るように、声がよかったらしい。声ばかり
でなく、音感もよかったようで、若い時代は、よく当時の流行歌を歌ったそうである。
復興の仕事はどしどしはかどって、秋には中橋の亀次郎の家も本建築が出来、長八たち
は八名川町からここに引き移る。
こういう忙しい仕事の間に、長八の腕は亀次郎に認められる。他の職人たちも眼にとめ
る。鏝さばきの速さと確かさは、江戸職人の悠長さと格段の違いだった。亀次郎は次第に
長八を重用するようになる。が、職人たちには、そのことが長八に対する違和感となる。
「田舎者が」
「若僧が」
と、冷たい眼で見られるような時がしばしばあった。けれども、長八はそんなことに頓
着なく、黙々として働いた。職もなくさまよっていた去年一年間を思えば、左官の忙しさ
など、むしろ楽しくさえあった。だが、そういう長八の態度も、かえって江戸職人の反感
をかっていた。
こんな話が伝わっている。ある時、日本橋の商家の本建築で、屋根瓦の漆喰塗りが始ま
って、二人の職人と長八でやることになった。二人の職人はしめし合わせて、長八を中に
して仕事にかかった。やがて日が暮れかかる頃、二人の職人は仕事をすませて屋根を下り
た。
「やい、長八、まだやっているのか」
「のろいじゃねえか。日が暮れるぞ」
「江戸職人はいざとなりゃこんなもんだ。田舎っぺに負けられるかってんだ」
「どんなもんだ」
と、口々に悪口を言って、
「ま、ゆっくりやれよ」
と捨てぜりふを残して帰って行った。
長八の仕事は間もなく終わった。下りようとすると、梯子がない。職人たちのいたずら
であった。折よく裏庭にいた弟子を呼んで梯子を渡してもらって、下に下りた。
しばらく日が経ってから、その話を亀次郎が聞いて不思議に思った。長八に事情を聞く
と、
「いえ、私が遅かったのです」
と、別に屈託のない返事である。
二、三日して、亀次郎は日本橋の商家の前を通った。何の気なしに屋根を仰いだ。そし
てそこに異様なものを見た。中央の部分だけ、一面に瓦に白い点がついているのである。
「梯子」
亀次郎は屋根に上がった。上がって見て驚いた。下で見た白い点は、それぞれ七福神の
顔をかたどって、それが瓦の一枚一枚に、きれいに塗られているのである。
「うーむ」
と、亀次郎はうなった。長八が職人のたくらみを見抜いて、わざと計略にはまったよう
に見せかけて、その暇に塗ったものであろうと亀次郎は思った。同時に、長八の抜群の腕
前に驚嘆しないわけにはいかなかった。
このような伝説は外にもある。恐らくこの時代はしばしば同僚の職人から意地悪く扱わ
れたであろう。田舎出の職人として、江戸での生活はなかなかなじめなかったであろう。
が、どの伝説でも、長八は受け身で、しかも、報復らしい報復をしていない。思うに、長
八その人の性格で、手荒いことを好まなかったのではなかろうか。
大火復興のために、あわただしい一年間を過ごしたが、この一年間の勤労は、長八にか
なりのたくわえをつくらせた。酒も飲まず、遊びも知らず、ただ仕事一方の長八だったか
ら、それも当然であった。が、それは長八自身が絵の勉強のためにひたすら無駄をはぶい
て来たことにもよるのである。
江戸へ出て来て、ついに絵筆を握る機会もなく過ぎてしまった。しかし長八は、絵を捨
てたのではなかった。彼はひそかに時を待った。そのための準備をしていた。そうして、
いつのまにか二年が経ってしまったのである。『三年経ったら』という重大な約束が、後
僅かに一年となってしまった。そのことは、長八にとって、絵の勉強をせねばならぬ差し
迫ったあせりとなった。
「残り一年を絵の勉強に」
長八は、そう決心しないではいられなかった。
明けて天保六年。正月がすむと、長八は中橋の家を出た。町にはまだ肌寒い風が吹き抜
けていた。山の手の道を池袋に出た。ここから川越街道が北に向かって、武蔵野をよぎっ
ている。長八はためらうことなく川越への道に入った。
雑木林は固い芽を寒風に揺らしていた。が、遠山は霞んで何となく春めいていた。村を
通り、牛車を追い越し、彼は足早に歩いて行った。小さな風呂敷には絵道具と谷文晁の書
面が入っていた。
③
当時の江戸では谷文晁が最も高名な画家であった。文晁は古土佐、狩野、一蝶などの各
画流を吸収して、その上に宋元明の中国風にも学ぶところがあり、いわゆる『文晁風』と
いう彼独特の画を創造した人である。
絵の勉強をするなら当代一流の画人について学びたい。………と長八はかねがね考えて
いた。江戸の生活の中で文晁の名声を聞き、文晁を師としたいと思った。ある日、彼は文
晁を訪ねた。が、文晁には会えなかった。文晁はすでに七十歳を越えた老境で、一切の入
門を許さなかったのである。しかし、その代わりにと言って、川越に住む愛弟子の喜多武
清に師事するがよいと、わざわざ添書を認めてくれた。
文晁門下の高足として、田能村竹田と喜多武清を挙げることが出来る。田能村竹田は豊
後の人で、すでに江戸には居らなかった。喜多武清は江戸下町の生まれだが、江戸をきら
って、小京都といわれた川越を愛してここに閑居していた。
喜多武清については、百科辞典に、
『喜多武清(一七七六~一八五六)画家。名は武清、字は子慎、可庵と号し、別に新竹館、
五清堂、笑翁、鶴翁等の号がある。通称栄之助。江戸の人。少時より谷文晁の門に学び、
終始師に随従した。壮年既に一家を成して画名あり。晩年には探幽風の草画を能くした。
また鑑識に長じ、平常古画の研究に勉めて、臨本の蓄蔵おびただしきものがあったという。
安政三年、八十一歳で没す』
とある。
長八が喜多武清に師事したことは確実であるが、いつ頃かという点はあいまいである。
伝説では『若い頃』とか『江戸に出て間もない頃』とかいう表現だけで、はっきりとして
いない。私は前後の事情から推測して、この時期を天保六年の春からと想定した。それは
すでに述べたように、長八が江戸に来てからおよそ二年間は、到底絵筆を持つような余裕
はなかった時代であることが第一の理由である。しかし、伝説の『若い頃』も『江戸に出
て間もなく』も、漠然としてはしているが間違いではない。それはまた『三年間、川越で
絵の修業をした』と長八自身が語ったことにも首肯されるように、やはり青年期であった
ことに間違いない。
ところが、もう一つ有力な理由を、私は見つけた。それは、天保九年三月、父兵助の死
を知って長八は始めて帰郷する。その時、恋人のおむめがすでに結婚していたことを知っ
て、失意の余り、江戸へもどって、それからは自暴自棄の放蕩生活を送る。この時期は、
曲折はあるが、天保十二年まで続く。つまり天保九年から十二年まで、足掛け四年間には
絵の修業など絶対に考えられない時期と言える。しかし、天保十二年には、彼の名を高か
らしめた日本橋の茅場薬師の造営があり、そこで制作した竜は明らかに狩野派の画風を示
して、すでに絵の修業は終わっている事実を物語っている。
以上のことを考え合わせると、長八が絵の勉強をしたのは、天保九年以前であり、また
天保六年以後であるということになる。そうすると、川越修業三年間が、天保六年から天
保九年までと、ぴったり当てはまることになる。従って、私のこの小文は右のような想定
によって進められる。
長八は川越に来て待望の絵の勉強を始める。文晁の添書を受けた喜多武清は、長八を快
く迎え入れた。独り暮らしの武清には、住み込みの下男兼業の弟子は、万事に都合のいい
ことだった。長八はその日から、武清の身辺の雑用や使い走りなどをしながら、画道に精
進するようになる。時に武清は六十歳で、絵も円熟していたものと思われる。
長八は後年、この時のことを述懐して、次のようなことを言ったと伝えられている。
「わしは毎日薪割り、炊事、使い走り、洗濯、掃除と下男下女兼用の仕事で結構に忙しか
った。しかし、暇さえあれば先生の傍らで絵の勉強をした。
大体、先生から教えられたのは、絵を描くことではなくて、絵を見ることだった。見る
眼を養ってもらったことだった。絵とはこういうものだと講釈しない。自分の眼と心で会
得するのだと、いつもしつけられた。一枚の絵を毎日毎日見せられて、始めのうちはわか
らなかったがだんだん見ているうちに、いつのまにか絵が頭に入っていくようにしつけら
れた。頃合いを見て、先生が描けという。その時には、さっさと絵をひっこめて、決して
見せてくれない。『心に映っているはずだ。それを描け』と言われるだけで、始めのうち
は随分恥をかいたもんだ」
これは弟子たちに単なる模倣をしてはならないということを戒めとして話したものと伝
えられているが、長八の言葉として傾聴すると共に、喜多武清という画人の風格がしのば
れる話である。長八は生涯この精神をつらぬいて、弟子たちに手をとって教えるようなこ
とをしなかった。
川越の生活は、長八にとって明るい未来を想望させた。日々の雑用も苦にならなかった。
夕食後、師弟相対して語り合うことも、夜が更けるのを忘れるぐらいであった。こうして、
平穏で楽しい年月が過ぎて行った。いつしか春も去り夏になった。ところが、冷温が続い
た。夏だというのに、北風が城下町を吹き抜けた。一昨年の大飢饉を人々は思い返した。
武清は庭先に立って、生垣越しに野の景色に眼を向けていた。黄に濁った砂埃が青田の
上を這うように走って行った。
「早くからっとした暑さにならないものか」
と、庭先で薪を割っている長八に眼をやった。
「こんな調子では、稲作も心配ですねえ」
長八も腰をのばして、額の汗を手でこすった。武清の住居は川越の城下町を少し離れた
船場近くにあった。一帯の田圃の向こうに町の屋並みが見え、喜多院のこんもりとした森
が見えた。
「川越は米が不作でも甘藷があるから何とかしのげようが、他国では困っているだろうな」
そう言って、武清はふらりと裏木戸をあけて出て行った。長八はそのうしろ姿を見送り、
ついでに日を仰いだ。薄い日が大分西に傾いていた。
長八は急にせかされるように薪を割り出した。城下町の七つ(午後五時)を知らせる自
鳴鐘(時報の鐘)が鳴るのが聞こえた。
ひとしきり薪を割り、割った薪を抱えて、納屋に収める。もう日が落ちそうである。急
いで夕食の支度に掛かる。風呂もわかさなければならぬ。
そのうちに武清が帰って来て、夕食をすませる。食膳を片付けると、武清は縁先に机を
出して、長八の来るのを待つ。勉強の時間である。もう半年になるが、毎日型のごとくこ
ういう時間がやって来る。勉強の時間は、絵を見ること、その絵について話すこと、それ
は各流各派にわたっていた。時には、歴史を語り、和歌を講義し、漢詩漢文にも及んだ。
「今夜は漢詩をやろう」
長八が向かい合って座ると、武清はそう言って、立って書物を持って来た。
「唐詩選だ」
と、自分も座って、ぱらぱらと紙を繰った。気の向いた詩を探すふうだった。
「これがいい」
書物を机の上に置き、手で押さえ、
「李白だ」
と言って、長八の方へ書物を向けた。
長八は改めて座り直して、眼を書物に向ける。武清は指先で文字をたどりながら、ゆっ
くりと読み始める。
「黄鶴楼に、孟浩然が広陵にゆくを送る」
長八はそれを眼でたどる。もう一度、武清が読むのに和して、長八も声を出す。
続けて、
「故人、西、黄鶴楼を辞す。烟火三月、揚州に下る。…」
と読む。長八がついて読む。そして、もう一度通して、今度は朗々と吟じる。
「孟浩然というのは、唐の詩人でな、大層節義のある人じゃった」
と、武清は詩について語る。
「孤帆遠景、碧空に尽く。………帆の影がたった一つ、遠くはるかになって、青空に没し
てしまいそうになって行く。こういう言葉の中に、友情がにじんでいるな。それだけに別
れの哀愁が深い」
と詞句の解明をする。
武清はこういう場合几帳面な解釈をきらって、ただその情感を尊ぶようだった。
武清の教育は、更に有職故実にも及び、古画にもくわしかった。それらのことは、長八
にはほとんど未知のことでそれだけ興味は深かった。何より好都合だったことは、淨感寺
塾での学問が大きく役立ったことである。教える武清にとっては、そういうことさえうれ
しいことで、張り合いがあった。長八の理解も早かった。こうして師弟の間は暖かく過ぎ
て行った。
秋八月、稲の実りは心配した通り悪い出来だった。早くも凶作だと人々は口にしていた。
その八月半ば過ぎ、江戸の谷文晁から飛脚があって、画友田能村竹田の死を知らされた。
大坂の藩邸で病死した由である。
その夜の対話は、自然と田能村竹田の話になった。
「竹田は立派な男じゃった」
と武清は心から竹田の死を惜しんでいた。
「江戸で修業したのはたった半年で、竹田は藩用で帰ってしまったのだが、わしは生涯忘
れられない友じゃ」
と言った。
武清は戸棚から一幅の掛け物を出して、おもむろに床の間に掲げた。山水の墨絵であっ
た。
「竹田の絵じゃ」
と武清は言った。長八は武清のうしろから、その絵に眼を注いだ。長八には始めて見る
絵であった。どこかわからないが、一種変わった絵だと思った。武清がその気持ちを察し
たように、
「わかるか」
と言った。長八は黙って首を振った。
「よく見い」
武清が絵を指さした。
「黒色の美しさ、線の柔らかさ」
とつぶやくように言いながら、しげしげと眼を寄せていた。
「描線のこの緩急の見事さ」
さも感に堪えないように、武清は絵に見入っていた。長八はそう言われてみて、なるほ
どとうなずいた。
「みんな竹田独特のものじゃ。竹田だけが描ける絵じゃ」
が、長八には、まだよくわからなかった。
「結局、絵とはその人の心なのかな。竹田が谷文晁先生に師事したのは僅か半年、それで
いてこれだけの域に達したのだからな。わしは生涯かけて竹田の半年にも及ばない気がす
る」
半ばは独りごとのように、半ばは長八に言い聞かすように武清はしんみりと言った。武
清の言葉は自卑とのみは受け取れなかった。それは芸の厳しさを長八に教えてくれている
ようだった。それにしても、僅か半年でこれほどの絵を描き得た竹田の非凡さに打たれざ
るを得なかった。
「私など、もう半年になりますのに」
長八は思わず言った。
「そうだったな」
言われて気がついたように、武清が言った。
長八はふと自分の行く末を考えた。一年間絵の勉強をしようと思い立って川越に来たも
のの、一年で何ほどの勉強が出来ようかと、心細い思いがよぎった。
「早いものだな。もう半年になる」
と、武清は別な思いでつぶやいた。
二人は元の縁先にもどった。すっかり秋めいた風が吹き込んでいた。庭で無数の虫の音
がしていた。
「だが、あせってはいけないぞ。竹田は半年で成熟したが、わたしたちは生涯かけて熟す
時を待たなければならぬのだ。竹田は竹田、わたしたちはわたしたちじゃ」
それはそうに違いないと、長八は思った。がしかし、長八には、あと半年の期間しかな
い。その間に、どれほどのことをなしうるか。
武清は言葉を続けた。
「わしはあれもこれもと手をつけて、師の真似をして来た。それは師に近づこうと思って
のことだが、実は形にとらわれて、結局師から離れることが出来なかった。もちろん、師
以上になれなかったし、師以外の道を拓くことも出来なかった」
このような話は前にも聞いたことがある。師の文晁から離れようとして、この川越に居
を構えたことを話したこともある。
「竹田は違う。竹田は師に頓着しない。みずから文人画だけを選んで、そしてその一本道
をわき目もふらずに進んだのだ。それだから、文人画においては、師以上のものをつくり
得たのだ。師を踏み越えて、新しい竹田の世界を開いたのだ」
武清の言葉は、ほんとに竹田を知っている言葉だと思った。長八はそんな男になりたい
と思って苦笑した。
「ただ惜しいことに、竹田は病弱だった。医者の子でありながら、そして、自分も医者で
ありながら」
武清の口がゆがんだ。
「人間、そんな立派な仕事をしようとしても、どんないい考えを持っていても、体が弱く
ては、存分に働けない」
それは自分にも長八にも言い聞かせるような武清の言葉だった。
竹田の絵の前に、武清はもう一度向いた。正座して、絵に見入った。
「いい絵じゃ」
ため息をついた。
「竹田の絵は、形が整っていないとか、崩れているとか、墨色が薄過ぎるとか、随分悪口
を言われたが、竹田はそんなことに耳をかさなかった。他人のために描いているのじゃな
いと言って、笑っていた」
そんな思い出を懐かしんでいるようであった。
「長八、よく見るがいい」
と長八に顔を向けた。長八が床の間に座ると、
「竹田は何を書いているのかな。なぜこんな細筆で針のような線を使っているのか。ここ
に竹田がある。竹田の心が潜んでいる。神韻とか高韻とかいう言葉があるが、竹田にはそ
ういう響きがある。つまり、竹田の魂の響きじゃな」
武清は一幅の絵の中からその響きを聞き澄ますようであった。長八はよくわからないな
りに絵に見入っていた。不思議な清らかさ、涼しさが湧いて来るような気がした。
④
田能村竹田の死は、喜多武清に心境の変化を与えたようだった。武清は時折ぼんやりと
物思いにふけっていたり、机に端座したまま瞑目していたり、書物を開いていながら長い
こと空間を見詰めていたりした。急に忙しそうに手廻りの品や秘蔵の画幅などを整理して
いる時もあった。
だが、夜になると、長八に対する教え方は厳しく熱っぽくなった。長八の勉強ぶりを見
ていて、いら立ちを強いてこらえているような時もあった。長八はそういう師の姿を、こ
わい思いで見て、一心に勉強した。
こういう変わり方は、竹田との間の友情以上のものを長八に感じさせた。
いつか秋が深まり、稲の収穫が始まり、案の定、凶作という結果になった。昨年はとに
もかくにも平年作で、かろうじて生活が立ち直ったのに、今年はまた凶作である。引き続
く不運に、百姓たちの愚痴は痛々しかった。
そんな頃、師の武清は城下の行伝寺に通うようになった。朝出掛ける時もあった。夕刻
にぶらりと出ていくこともあった。百姓の苦悩など無頓着のような姿が、長八には何か不
満だった。いや、百姓だけのことではなく、自分たちの生活にさえ無関心に見えた。師の
心が長八にはおしはかれなかった。何か思いつめたもの………竹田の死を悲しむ以外の…
……があるように思えた。だが、それが何なのか、長八にはわからなかった。
今日も武清は行伝寺に出かけて行った。夕方になって、そろそろ帰る時刻だと長八は思
いながら、庭に散らした薪木を束ねていた。自鳴鐘が鳴った。夏とは違って、この頃では
もう日が暮れかかっていた。
薪を納屋にしまい終わっても、武清はまだ帰って来なかった。急いで夕餉の支度をして、
長八は裏木戸をあけて外に出た。野路を見渡した。どこにも師の影は見えなかった。たち
まち夜になっていた。長八はもどって、しばらく縁先で詩書を見ていたが、それをふとこ
ろに自室に入って灯を入れた。机に座って、もう一度詩書を開いたが直ぐ止めた。落ち着
かなかった。灯を消した。
長八は裏木戸を出た。月が昇っていた。黒い野面がまだ刈られない稲が点々と見えた。
暗い野道をたどって、長八は城下町の方向へ歩いて行った。風が寒かった。師の武清の帰
りを迎える気持ちだったから、急ぐのではなかった。道すがら、何となくいろいろなこと
を思った。故郷の父母たちも凶作で苦労していやあしないかと思った。美濃では百姓一揆
があったというが、故郷ではどうだろうなどと思った。と、連鎖的に、おむめの姿が浮か
んだ。
「どうしているだろう」
長八は暗い田面に向かってつぶやいた。別れてから、もう二年半になる。約束の三年が
眼の前に迫っている。急に心が騒ぐ。
ぼんやりと歩いていると、向こうから声を掛けられた。
「長八か」
直ぐ前に師の武清が立っていた。
「あ!………お帰りなさい」
長八は驚いた声で言った。
「迎えに来てくれたのか」
武清は静かな声だった。
「へえ、あんまり遅いので」
「そりゃすまなかった」
二人は細い道を前後して歩いた。
「熊野村の百姓が、五人ばかり挙げられたそうな」
武清がさりげなく語った。熊野村は川越から一里ばかり離れた近在の村である。
「へーえ」
長八は返事ともつかぬ返事をした。
「やはり一揆の相談をしていたらしいな。役人がかぎつけて、今朝方捕えられたそうな」
川越などにもこんな事態がやって来たのかと長八は思った。遠い国のことではなかった。
「この不作では、百姓も苦しいでしょう」
「うん、思い余ってのことだろう」
裏木戸を開いて、二人は庭を横切った。武清は縁先に重たく腰をおろした。
「ただ今、お茶を持って参ります」
長八は庭から台所に走って、引き返して、茶碗を武清の手に渡した。
「ああ、うまい」
武清は舌打ちして、一気に飲みほした。
「お疲れでしょう。風呂にしますか、それとも夕食に」
「風呂はわいているか」
「へえ」
「そうか、じゃあ、先にひと風呂浴びよう」
武清は重そうに腰をあげた。
間もなく、風呂場から湯を流す音が聞こえて来た。長八は急いで台所に入って、夕餉の
膳を整えた。
風呂からあがった武清は、さっぱりした様子になって夕食の膳についた。長八は武清と
向かい合って下座に座った。一汁一菜の食事は直ぐに終わった。
食膳を引くと、いつもの師弟対座の時間である。たまたま起こった熊野村の事件から話
は始まった。自然、百姓の労苦に及んだ。話がひとくぎりついたところで、長八は、
「先生」
と口を切った。
「私も百姓の子ですから、百姓の苦労はよくわかるつもりです。この頃の百姓を見ている
と、黙って見ていていいのかと思うのです」
と言った。心の隅にわだかまっているものを吐き出すような言い方だった。言葉は静か
だが、若者らしい激しさがこもっていた。
「うん」
武清はうなずいた。考えるように、そのまま何も言わなかった。長八はもどかしく言葉
を続けた。
「方々の国で、不穏な動きがあるといううわさを聞きます。それは無理もないと思うので
す。政治が悪いという人もあります。もっと百姓を大切にしなければとも思います。しか
し、さし当たって、こんなに百姓が困窮しているのに、それをよそに、絵なんぞ描いてい
いのだろうかと思うのです。何かうしろめたいものを感じるのですが」
長八がこんなことを言うのは珍らしいことであった。武清はそう思って、考えるように
腕を組んだ。しかし、黙っていた。長八はもっと言いたかったが、師の言葉を待つつもり
でじっとしていた。
「長八、お茶」
武清が茶碗を差し出した。長八は、はぐらかされた気持ちで、苦笑しながら土瓶の番茶
をついだ。武清はそれをうまそうに音を立てて飲んだ。ゆっくり茶碗を置きながら、
「長八」
と、武清はようやく口を開いた。
「うしろめたく思うのは、そりゃあ、わしだって同じじゃ。だがな、問題はその先じゃ」
「その先?………と言いますと?」
「百姓衆が苦しんでいる。それを見て自分もつらいと思う。それだけでは、何の答えも出
て来ない」
「そうですね」
「その先へ考えを持って行かなければならない。百姓衆が困っている。それをどうするか」
「そうです」
長八はうなずいたが、直ぐ、
「が、それがわかないのです」
と言った。
「うん、わからないでは問題は解決しない」
武清は他人ごとのようにあっさり言った。
長八はただ、
「へえ」
と言った。思考がそこのところで空転していた。それがまたもどかしかった。武清はそ
ういう長八に頓着なげに言い出した。
「わからないということは全然何もないというのか。それとも、考えがあるけれどもどう
していいのかと、迷っているのか。そのいずれかであろう。長八のは、全然ないのではな
い。つまり、迷っているのだな」
「へえ」
長八はそう言ったが、よくわからなかった。
「迷っているなら、もっと迷うんだ。迷って迷って迷い抜いて、そうすれば、どこかに落
ち着く。つまり、答えが出る」
長八は心の中ではなるほどと思った。が、それだからといって納得されはしなかった。
思考がさんざん崩れていた。行き場を失ってうろたえていた。
「迷って迷い抜くと、そこに一つの道が開ける。そうなったら、もう迷ったではない。迷
うということは、どっちにしていいかわからないということだ。どっちか決まるまで悩み
続けなければ問題解決にならないのだ」
その通りに違いないと長八は思いながら、それでも、すんなりと自分の胸を通らなかっ
た。正直に、
「それはわかっていますが」
と長八は言った。
「わしが毎日のように行伝寺に行っているのも、いわば、そのためだ。わしにも心の迷い
があり、その迷いがなかなか解けないのじゃ」
武清は始めて長八に自分の悩みを告げた。
「齢六十になって、わしはこんなにも愚かだったかとあきれている」
武清は苦笑の顔を長八に向けた。
「わしは今、鉄心和尚に教えてもらっている。死とは何か、生とは何か。が、なかなかわ
からない。盲滅法じゃ。今、沢庵禅師の法話を学んでいる。『不動智神妙録』というのじ
ゃ」
長八は武清の言葉を傾聴した。死とは何か、生とは何か。人間究極の問題だった。
「その書物の中に、『溝をばずんと飛べ』という言葉を、今思い出した。行く手に溝が横
たわっている。そこを越えなければ先に行けない。が、その溝を跳び越えることが出来る
かどうかわからない。ことによると、誤って溝に落ちるかも知れない。つまり、それが迷
いじゃ。その時、『溝をばずんと飛べ』と沢庵禅師は言うのじゃ。こちら側の岸で、どう
しようかと思っているだけではどうにもならんのじゃ。『ずんと飛べ』じゃ。落ちたら、
泳いでなり這い上がればいい。とにかく溝を飛ぶことだと教えているのじゃ」
長八は噛みしめるように聞いていた。
「さっきの話じゃが、なるほど百姓は苦しんでいる。助けたい。しかし、どう助けたらい
いのか」
長八の気持ちはまた元へもどった。どうしたらいいのかわからない。以前として気持ち
は重く灰色だった。
武清は少し調子を軽くして話を続けた。
「まさか、お前さんは百姓衆の苦しみを助けるために、お前さんが百姓になればいいと思
っているんじゃなかろうな。まさか金持ちから金を奪って、百姓衆に恵んでやろうなどと
思っているんじゃなかろうな」
「そんな」
と長八は声を強く否定した。
「そうだろうな」
武清はそれにうなずいて、
「百姓衆を百姓になって助けるもいい。しかし、百姓になったとして、百姓は救われるだ
ろうか。金を奪って恵む。物取り強盗は別として、自分の金を恵むのもよかろう。しかし、
これとて限度がある。いい加減なことでは救われまい」
「それはそうですが」
「お前さんが絵を捨てれば、百姓は救われるか。そんなことはなかろう」
「へえ」
「とすると、むごいようだが、百姓衆は百姓衆で『溝をばずんと飛べ』ということになり
そうじゃ。だが、われらもわれらで『溝をばずんと飛』ばねばなるまい」
「すると、私は絵を描いておればいいのですか」
「そうさ、しかし、百姓衆の心を心としてだな」
「それはどういうことでしょう」
「百姓衆の生命は食べ物を作ることにある。われらはその食べ物で生きている。われらは
食べ物を節約し、百姓衆の苦しみを少しでも軽くする。それが百姓衆の心を心とするのだ
と思うが」
「そんなことでいいのでしょうか」
「それで我慢できないなら、外に手だてを考えるがいい。百姓になるのもいい。が、絵師
には絵師の道がある。もちろん百姓には百姓の道がある。絵師の道を捨てて百姓になる。
それは、百姓の方が絵師よりは重要だと思っているのだな。それは大変な間違いだと思う
が」
武清は冷たくなった茶をすすった。長八には武清の論理はよくまだわからなかった。顔
が青ざめていた。
「百姓と絵師とてんびんに掛けて、どっちが重いか、どっちが軽いか」
そう言われると、長八は百姓を重く見ていたようである。絵は遊びごとのように思って
いたのではないかと思った。
「百姓には百姓で、絵師には絵師で、仕事こそ違え、価値に高下はないはずだ」
武清の言葉は自信に満ちていた。
「百姓の苦しみは、わしにもよくわかる。がしかし、わしは百姓には劣らぬ苦しみを持ち
続けて来たつもりだ」
きっぱりと言い切った言葉が、長八の胸に強く響いた。
「お前さんにはまだ絵師の苦しみがわからないのかも知れない」
武清はつぶやくように言った。
長八は何かわからないが、心の中のもやもやとしていたものがほぐれて来たような気が
した。
「むずかしい話になってしまったな」
と、武清は微笑した。
「で、お前さんはお前さんで、百姓衆の苦しみを受け止めるんだな」
そう言いながら、武清はゆっくりと腰をあげた。
「さ、やすもう」
そう言い捨てて、もう長八には眼もくれず、静かな足取りで寝間に入って行った。
夜風が冷たく流れていた。長八は座ったまま考えていた。
⑤
刈り残されていた稲もいつのまにか刈り取られて、野良一面が間が抜けたようにさびし
くなった。冬になった証拠のように、秩父おろしが吹き始めた。
長八はようやく絵の勉強に力を入れるようになった。迷いの雲が、いくらか晴れたとい
うのであろうか。それとも、約束の三年がもう直ぐだからというのであろうか。いや、迷
いの雲は、あんなに師の武清に言われても、まだほんとに晴れてはいなかった。が、約束
の三年が迫っていることが、絵の勉強をせねばならぬと急き立てているのだ。ようやくわ
かりかけた絵の道であった。これからが大切だと思うのだった。今のままではいけないと
思った。とにかく、絵の修業だと思うようになったのである。
日一日が短く過ぎていった。そして、年の暮れがひしひしと近寄って、長八の気持ちを
いら立たせた。
ところで、稲の刈り入れが終わってみると、収穫は半作であった。米価は当然高騰した。
諸物価も釣り上がった。川越でも施米小屋を設けて救済する状態だった。それは長八たち
の生活にも容赦なく襲って来ていた。日々の食事も切り詰めた。その苦しさの中で、長八
は悲壮に絵の修業に打ち込んだ。
こうして年が明けた。天保七年である。年の暮れから暖かい日ばかり続いて、年が明け
ていよいよ暖かく、ようやくその異常さに気付いた。もやは喜びではなかった。裏作や畑
作の麦が徒長していた。『冬暖かければ稲作は不作』という。米が足りなくて、麦をと思
って育てた裏作、畑作もだめで、その上また稲が不作ということになりそうな予感が、百
姓たちの心をおびえさせていた。
幕府は前年九月に天保通貨を新鋳した。それが国中に大量に出廻り、不況の上に更に不
況をあおった。天保通貨………いわゆる天保銭である。当初百文相当として通用されたが、
その粗悪貨幣はたちまち世の不評をかってしまった。それは当然なことで、実質は五、六
文ほどの価値しかなかったものである。幕府はしかしこれによって幕府財政の窮迫を切り
抜けることが出来た。味をしめた幕府は、年々これを増鋳して、莫大な利益を得た。記録
によると、年々四十万両、多い年は百万両の益金があったという。幕府はそれでいいかも
知れないが、それはたちまち物価高を誘発し、庶民の生活に脅威を与えた。通貨の信用は
薄く、明治初年には百二十五枚でやっと一両という馬鹿げた相場になってしまっていた。
いわゆる『天保銭』という語が、役に立たぬものの代名詞として使われたのも、庶民の恨
みの象徴なのかも知れない。この天保銭が、稲の不作に苦しみ、先行不安になっている時、
一層拍車をかけて横行したのだから、庶民の生活は堪え切れないほどであった。
天保七年の先行きは暗かった。人々の心は陰湿であった。こんな春を、長八は迎えた。
そして、約束の満三年である。 長八の心は揺れていた。生活の困窮と、約束の三年と、
絵の修業と、長八の心の中は三つのものが巴になって渦巻いていた。
三年の約束は大切だ。そこにはおむめとの夢のような未来がある。もう江戸職人の金五
郎は仁助の所に居ないだろう。おむめとの結婚、そして仁助の後継者となる。
が、折角志した絵の勉強はまだまだである。始め、一年間を修業してと思ったことは、
今にして思えばあさはかであった。一体この一年間に何をなし得たか。僅かに門に入った
程度に過ぎないと、長八は思うのだった。芸の道は厳しく険しいことを今こそ知った。お
のれの未熟がようやくわかった。折角ここまで来たものを捨て去るにしのびなかった。実
際には、もう二年も三年も勉強しなければならない気持ちだった。
もう一つ、今の生活の困窮は、師の武清が老齢であるだけに、長八は川越を離れられな
い気持ちだった。三年の約束を盾に帰郷すれば、師はどうなる。飢え死にもしかねない。
こういう師を振る捨てて去るわけにはいかない。
三つの問題が長八の頭の中で互いにしのごをけずって争っていた。そして、長八に決断
を迫っていた。しかし、長八は決しかねていた。苦しみ迷った。二十二歳の青春がそこに
うちひしがれていた。
思い切って「帰郷しよう」と決心する時があった。おむめのことを思うと胸がうずいた。
おむめは待ちこがれているだろうと思うと、矢も盾もたまらなくなるのだった。毎夜のよ
うにおむめの夢を見た。夢の中でおむめはすっかり成人して、あでやかにほほえみかけた。
そうかと思うと、悲しげに眉を寄せていた。長八の帰りを待ちわびて、その苦しさに堪え
ている表情であった。そういう時、「いっそ帰ろう」と思うのだった。
が、師の前にいる時、そんな思いは露ほどもなかった。一日一日を厳しく絵に打ち込ん
でいた。絵に向かっては一心不乱だった。それだけに楽しかった。師の武清は、そういう
長八に多くのものを与えようとして努めているようであった。もう行伝寺へ日参しなくな
った。今は長八のために打ち込んでいるように見えた。
日が過ぎて行った。一月が終わろうとしていた。長八はもはや決心をしなければならぬ
土壇場に追い詰められていた。
「いっそ師に相談してみようか」
と思った。そして止めた。恐らく、師の武清は何の答えも示さないだろう。『お前が決
めなければ』というに決まっている。そういう人なのである。
「おむめに手紙を書いて、後一年延ばすようにしたら」
とも考えた。しかしこれも止めた。後一年が確かに保証出来るか。またおむめがそれを
認めるか。二つとの疑わしいことであった。
そういう間にも不況の嵐は一層深刻になっていた。もう日々の生活で、一食を抜くとか、
水粥をすするとか、そういう差し迫ったところへ来ていた。武清は大切にしていた書画を
手離し始めた。命をけずるような思いだろうと、長八はそのたびに思うのだった。
一月が過ぎた。二月が過ぎた。三月になると、もう約束の三年が過ぎていた。あわただ
しく船場の桜が散り、若葉が青葉に変わった。近くの野良では田仕事が始まった。
三年という約束の期限が通り過ぎると、長八の迷いは、少しずつ変化して行った。やが
て別な思考を組み立て始めた。
「少しぐらい過ぎても、おむめちゃんはおれを信じて、待っていてくれるだろう」
虫のいい考えであるとは、長八自身思うのだ。しかし、そうでも考えなくては、息がつ
まって堪えられなかった。
四月下旬、『冷気は二、三月のごとく、日々霧深く、北風吹き』と記録されているよう
な天候だった。稲苗の生育が遅れた。六月には綿入れを着るという寒さで、麦は大減収だ
った。七月、穂ばらみ季だというのに穂が出なかった。今年も去年にまして凶作だと、百
姓たちは田圃を眺めて嘆息した。こうなると、長八はいよいよ覚悟を決めざるを得なかっ
た。帰郷はあきらめた。おむめを信じた。ここに踏みとどまって、師の武清の生活を支え
なければならないという気持ちになった。
ある日、長八は師の使いで江戸に行くことになった。谷文晁が長く病臥しているので、
その見舞いのためであった。師の武清は年齢のせいもあり、昨今の食事情もあり、めっき
りと老い込んだ様子で、江戸へ出向く気力がなく、長八に代理させたのである。
川越と江戸との交通は、陸路は川越街道を池袋に入る。別に荒川を利用した水路があっ
て、物資の輸送はもっぱらこれによっていた。長八は日帰りの予定で、往きを荒川で下り、
帰りは川越街道を歩くこととした。
荒川下りの船は新河岸川の船場から出る。長八は早朝の便船に乗った。ゆるい流れに沿
って下った。もう左右の稲田は黄色っぽく秋の収穫の近いことを示していたが、その色は
鈍く汚れて、不作を物語っているようだった。乗合いの人々は、口々に不況をかこってい
た。
下り船だから意外に早く江戸に入った。直ぐ谷文晁の写山楼へ急いだ。道々、久しぶり
の江戸の町を見て通った。ここにも空気は重く沈殿しているようで、浮浪者が固まって無
気力な眼で何かを求めていた。
当時の記録を見ると、病者や行き倒れなど七十余万人とあるから、途方もない残酷な世
情であったのだ。後には犬猫を捕らえて食い、藁を刻んで食料にしたという窮状で、中に
は苦しさに堪えられないで自殺したものも数多かったという。
そういう町の姿を、長八はおびえた気持ちで通り過ぎた。川越の町にも、こんな状態が、
遠からず来るのではないかと思った。
写山楼に着いて、玄関先で口上を述べ見舞いの品を渡した。応待に出た内弟子の話では、
文晁の老衰がひどく、半年近く寝た切りで、口をきかないという。七十四歳の高齢であっ
た。これが一世を風靡した巨匠の晩年であった。
写山楼を出て、久しぶりで江戸が懐かしく、浅草、上野と見て歩いた。さびれたとはい
え、この附近はさすがに人が群れ、江戸らしい活気が見られた。昼時になって、小さな茶
店で食事をした。
注文した蕎麦を持って女中が来た。長八はその時女を見た。心なしかおむめに似ていた。
びっくりした顔で見られて、女は悪びれもせずにっこり笑った。これが後に長八の最初の
妻になったおきんであった。この時、長八はそんなことを夢にも思わなかったろう。
帰りは池袋に出て、川越街道の一本道である。まだ日が高かったが、長八は早く帰るつ
もりで足を早めた。上野の黒門の下で、偶然土屋宗三郎に出会った。
「おい!」
と呼び掛けられ、びっくりして振り向くと、宗三郎が微笑していた。
「やあ、宗さん」
思わず声が弾んだ。
宗三郎は体も一段と大きくなり、たくましくなっていた。
「久しぶりだなあ」
と、二人は手を握り合った。顔を見せ合って笑った。
「元気そうだな」
と長八が言った。
「うん、お前も」
と宗三郎が言った。二人は歩き出した。
「今、どこに居るのだ?」
宗三郎が言った。
「川越だ」
「川越?………江戸に居ると聞いていたが」
と宗三郎が聞き返した。
「うん、川越に来てもう一年半になる。それまで江戸に居た」
「川越で何をしている?」
そう聞かれると、長八は返事に困った。が、宗三郎に黙っているわけにはいかないと思
った。
「絵を勉強している」
と、さりげない調子で長八は答えた。
「絵を?」
と、宗三郎は驚いた顔をした。
「池へ行こうか」
宗三郎が先に立って、不忍の池へ道を曲がった。
「何年ぶりかなあ」
歩きながら長八が言った。
「六年になるな」
と宗三郎が答えた。
⑥
「長さんが江戸へ来ているということを、誰かからか聞いていた。いつか会えると思って
いたが、ついぞ今まで会えなかった」
「そんなものさ。江戸は広いからなあ」
宗三郎と長八は、池の端の石に腰をおろしていた。
「そうして、思い掛けない時に、こんなふうにばったりと会うのさ」
宗三郎がうれしそうに笑った。
「それに、こちとらは食うや食わずの暮らしだから、年がら年中あくせく働かなくちゃな
らないし」
長八は江戸での生活を思っていた。
「それはお互いさまだ」
宗三郎が言った。
「宗さんの学問も進んだろう?」
「うん、まあ」
宗三郎の返事はあいまいだった。
「うらやましいよ」
長八は宗三郎のように学問に専念出来る身分がうらやましかった。のびのびとしている
宗三郎に自分を対比してさびしかった。二人の間にはかなりの距離が出来たように感じた。
「しかし、学問というものは遅々として進まずだ」
宗三郎が言った。長八はそうかも知れないと思った。
「長さんは絵の勉強をしていると言ったな。川越に居るのはそのためか」
「うん」
「そう言われれば、長さんは絵が好きだったな」
宗三郎は昔のことを思い出して言った。
「去年の春からだ。もう一年半になるが、勉強はさっぱりだ」
「むずかしのか」
「うん、むずかしものだな」
「やっぱり、遅々として進まずか」
宗三郎が笑った。
「それに、こんな時勢になって、絵なんぞ描いてはいられない気にもなるさ」
「そうだな。学問とて同じだ。こんな時勢では、学問が何の役にも立たないような気がす
る。実行をともわない学問が、馬鹿馬鹿しくなる時がある」
「おれも同じようなことを考える」
長八はそう言って、直ぐ言葉を続けた。
「絵が大切なことはわかっている。だが、食べることを無視しては、ろくな絵は描けない」
「うん」
「絵を描いて何になる、と思う時がある。絵を食って生きるわけにはいかない」
「学問だって同じだよ」
と宗三郎が言った。
「学問のためなどと口はばったいことを言っても、学問は飯にならない」
すると、長八が思い出したように、
「そのことで、以前に先生と話したことがある。そして、ひどくやっつけられた」
と、いつかの夜のことを言い出した。
「どう言ったんだ」
「先生は、食うことと絵を描くことと別に考えているのだな。人間にとって食うことは大
切だが、絵を描くことも大切なんだ。百姓の苦しみと絵師の苦しみと、どっちが大きいか
と言うんだ。それは人によって違うだろうが、少なくとも絵師にとっては絵師の苦しみが
大きいと見なければならない。おれは、ひどくやっつけられたというのは、絵師の道にあ
りながら、絵師を遊びごとのように思っていた、そんな軽率さを戒められたのだ」
「わかるような気がするな」
宗三郎が言った。
「おれもわかるような気がする。しかし、ほんとうにはわからないんだ」
と長八が率直に言った。
「うん、そうだな」
と宗三郎は相槌を打ち、しばらく黙った。考えているようだった。
「おれは学問に志した以上、学問から離れたくない気持ちだ。しかし、今の世の中は一刻
も猶予のならないところへ来ているような気がする。そんなら学問を捨てるべきだ。だが、
捨てるに忍びない。そういう矛盾に生きている自分がいやになる」
と、宗三郎はさびしそうに言った。
「おれもそんなことを考えていた」
と、長八がつぶやいた。
「勉強をしなければならないことが山ほどもある。が、落ち着いて学問して居れば、その
まに時勢がどんどん先へ行ってしまう。そうして取り返しのつかないことになりそうな気
がしたり、要するに、おれは迷っているのだ」
宗三郎の言葉を聞いていて、長八は同じようなことを考えるものだと思った。
「おれは絵を描いていて、こんなことをしていていいのかと思う時がある。すると筆が思
うように進まない。絵がだんだん駄目になって行くような気になり、そんな経験を何度も
した。が、やっぱり絵の勉強をしたいのだ。が、そう思いながら迷っている」
「同じだな」
宗三郎が笑った。
「迷っているんだな。おれたちは。しかし、迷うってことは、そこでは学問も絵も進んで
はいない。大げさに言えば、学問も絵も捨てているのかも知れない」
宗三郎が念を入れるように言った。
「うん、そうだよな」
長八も同意するように微笑した。
が、長八はそう言いながら、ふとやましいものを感じていた。「おれの迷いは、そんな
純粋なものではない」そんな気がした。おむめのことがいつもからんでいる。ここで二重
に三重に迷いがこんがらがっている。
池の周囲の木々の影が、いつのまにか斜陽を受けていた池が冷たい光に変わっていた。
長八は大分時間が経ったように思った。わくら葉が一枚音もなく二人の前に落ちた。
「じゃあ、おれは帰るよ」
長八は腰をあげた。
「帰るか」
宗三郎が残念そうに言った。立ち上がりながら、
「久しぶりで会えて、うれしかった」
と言った。
「うん、おれも」
二人は黙って歩き出した。
「福さんはどうしているだろうな」
と思い出したように宗三郎が言った。
「さあ、どうしているかなあ」
長八にも彼の消息はわからなかった。二人は思い思いに友のことを想像していた。
元の黒門通りに来ていた。
「じゃあ」
ここで別れようと、長八は足を止めて宗三郎を見た。
「元気でな」
「お前も」
二人は手を握り合った。「いつまた会えるか」という感慨があった。
長八は歩き出した。しばらくして振り返ると、宗三郎が手を振った。長八も手を振った。
もう、長八は振り返らなかった。宗三郎と会って、意外に時間を費やしたと思って道を
急いだ。
池袋に出て川越街道に入った。早くも夕風が流れていた。
川越街道を歩きながら、去年の春、絵師を志してこの道を歩いたことを思い出した。そ
して、一年半の間に、世の中も変わったが、自分も変わったと思った。あの時は一年の修
業と心に決め、故郷に帰っておむめとの約束を果たすつもりでいた。今は違っている。約
束の三年が通り過ぎてしまって、約束不履行のうしろめたさが尾を引いているけれど、も
っと絵の修業をせねばならぬと思うようになっている。時勢に無関心であったのが、こん
なにも厳しくものを考えるようになった。今日宗三郎と会って、対等に語り合い、同じ思
いで苦しんでいることを知ったことも、長八の心を一層固めたようでもあった。
そんな思いにふけりながら、長八は歩いていた。人通りも少なかった。武蔵野が絵のよ
うに展開した。
「宗三郎の言う通り、おれもやるだけのことはやりたい」
と長八は思う。が、どうしてもおむめのことがひっかかる。
「おむめちゃんは待っていてくれる」
と長八は信じようとする。
「そのためにも、一心に絵の修業をしたい」と思う。が、そう思う下から不安がちらつく。
おむめはもう十九歳の花の盛りである。金五郎はまだ居座っているかも知れない。二人の
危険な関係が、いやおうなく、長八の胸の中を黒い霧となって流れる。それにからんでさ
まざまな妄想が影絵のように映る。
「無駄な心配だ」
と、長八は強いて打ち消す。
「おむめちゃんのことは忘れて、しっかり絵の修業をしなければ」
と言い聞かす。
川越街道はすっかり暗くなっていた。暗い野に点々と小さな灯が見えた。
長八は夜更けて川越船場の家に帰った。
八月に入って、稲作は決定的に大凶作であった。人々は甘藷を買い漁り、畑地に蕎麦を
播いた。風の便りに、山向こうの甲州の百姓騒動のうわさが流れた。九月下旬、霜が降り
て、折角の蕎麦も全滅の状態だった。刈り惜しんでいた稲がやられた。
記録によると、西国で半作、東に向くに従って悪く、信州で三分作、奥羽では『収穫皆
無』となっている。米価は暴騰し、一両につき三斗二升五合、やがて二斗二升と跳ね上が
って行った。江戸では百文につき二合八勺しか買えなかったという。全国各地に、しきり
に暴動が起きた。暴動はその様相を変えて、小作農だけでなく、地主も加わり、村ぐるみ
で代官屋敷にむしろ旗を押し立てるという、為政者への恨みになっていた。
不穏なままにこの年も暮れて行った。この中で、喜多武清と長八は、馬耳東風と絵を描
いてすましているわけにはいかなかった。次第にその惨めさのるつぼに落ち込まざるを得
なかったのである。
第2章 終り
動画