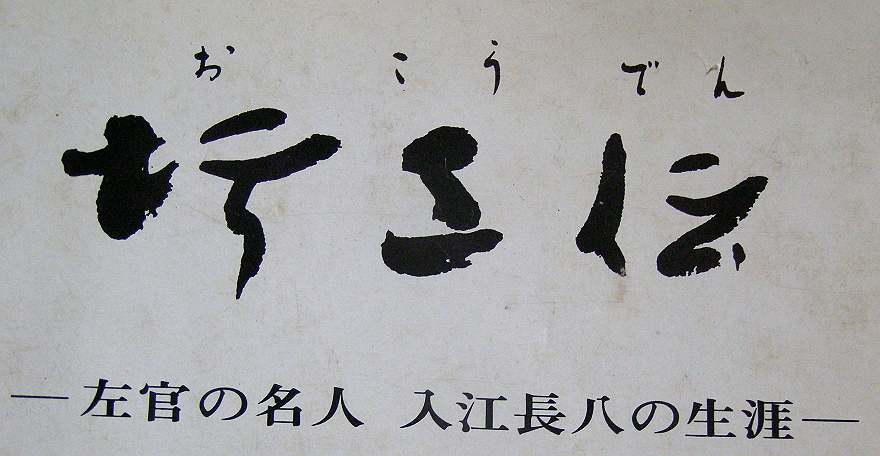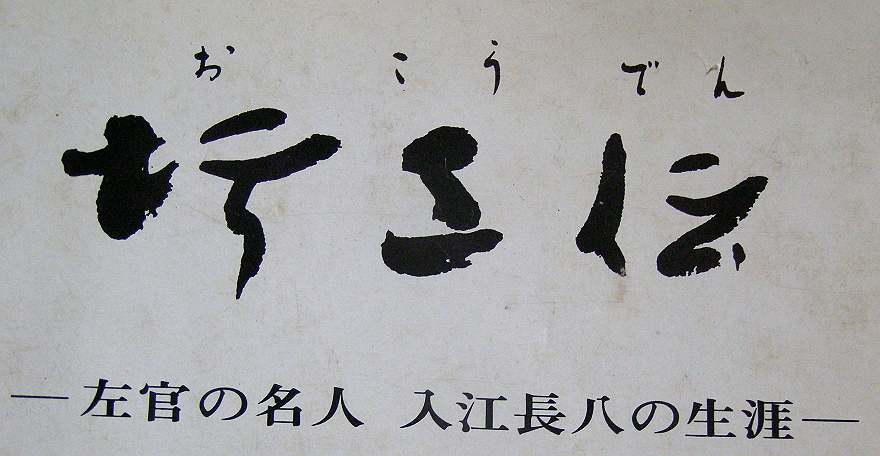須 田 昌 平著
第5章 新しき生へ
|
やがて明るい朝が来る。おたきとの結婚、
棟梁として独立………。世の険しいさの中
で、彼は黙々とめざす光明に向かっていた。
鏝と泥土との美の世界、鏝絵の創造への飽
くことなき探究………。
(三十三歳から四十三歳まで)
|
①
亀次郎は真面目な顔になっていた。
「播磨屋からの話なんだが、お前さんは養子に行く気はないかい」
と言った。長八には、突飛もない話だった。返事にまごついていた。
「親方!」
と、長八は正直に驚きの表情をした。
「びっくりしたか」
亀次郎は急にほぐれた顔になって、
「驚くのも無理はねえ。おれが驚いちゃったんだから」
と笑った。そう言われて、長八も少し落ち着きを取りもどした。
「だしぬけの話なので、驚きました」
と言った。
「で、どこの誰です。そんなことを言い出したのは?」
別に気があるわけではないが、聞いてみた。
「播磨屋だよ」
「播磨屋さんは、誰に頼まれて?」
長八がそう言うと、
「誰から頼まれたんでもない。播磨屋の養子の話だよ」
と亀次郎が言った。
「播磨屋!」
長八が思わず口走った。一体、どういうことなのかと思った。
「昨夜、源次郎さんが見えてな、たっての頼みだと言うのだ」
そう言われても、長八は半信半疑だった。
「播磨屋さんの養子に、私をってことで」
「そうだよ」
「向こうが、私に名指しですか」
「そうだよ」
ここまで来て、長八は一層納得が行かない顔で、
「冗談でしょう」
と言った。
「冗談なもんか。真面目な話だ」
「しかし、播磨屋といえば、深川で名の通った家柄でしょう。私なんぞ職人の行くところ
じゃあありませんよ」
「いや、いや」
と亀次郎は、表情を真面目さにもどして言った。
「ほんとのことなんだ。源次郎さんは、ああいう人だ。お前さんを見込んでのこと、家柄
なんど問題にしちゃあいなんだ」
それでも長八は信じられなかった。
「それにしても、私は傷者ですよ。播磨屋さんは、ようく知っているはずです」
すると、亀次郎が追いかぶさるように、
「源次郎さんは、そんなこと百も承知だ。承知の上での話なんだ」
長八は、考えるまでもないと思っていた。これ以上、話を深入りさせる必要はないと思
った。
「まことにありがたい話ですが、ことわって下さい」
と長八は言った。
「そうにべもない返事をするなよ」
亀次郎は笑いながら言った。
「播磨屋でも、そんな話をしたそうだ。しかし、源次郎さん夫婦も、当のおたきさんも本
気で頼んでいるんだ」
「しかし」
「実は、おれも賛成したんだ」
「そんな」
と、長八が反発しようとするのを、亀次郎は手で押さえて、
「まあ、聞けよ」
と言った。
「おれは、播磨屋とは幼な友達だし、永い付き合いだ。ことに、今度の火事で、家を建て
るについても、大変な世話を掛けた。だが、この養子の話は、そんな義理から持ち出した
んじゃない。源次郎さんも同じことだ」
長八は、多分それはそうだろうと思った。
「播磨屋から言われてみると、これは結構な縁談だと、おれは思うようになった。という
のは、播磨屋のためにも、お前さんのためにもいいと思ったのだ。おまけに、当人のおた
きさんは、いくつもの縁談はことわってきたが、今度の話には機嫌よく承知したというん
だ」
「そんなことはありません。月とすっぽんです。釣り合いません」
「そんなことはない。播磨屋にしてみれば、ひと頃の全盛はない。今は昔の播磨屋とは違
う。子供運が悪く、おたきさん一人になってしまったし、何しろ寄る年波だ。早く後継ぎ
を決めたいんだ。そういう点では、お前さんの方がお月さんかも知れねえ」
「そんなことはありません」
長八は本気で打ち消した。
「だが」
亀次郎は、長八に構わず、
「お前さんの方からすると、今までのことはとにかくとして、これからのことを、おれだ
って考えないわけには行かない。お前さんは、これからの人間だ。おきんさんとの縁が切
れたのは、お前さんにとってはいいことかも知れないと、おれは思っている。これから新
しい生活を始めるんだ。もうそろそろおれから離れて一本立ちをしてもいい時期だ。それ
に、お前には大事な仕事があるじゃあねえか。それを成し遂げるためにも、はっきりと身
を固める必要がある。おれは、そう思って、この縁談に賛成しているんだ」
こうまで言われてみると、長八には返す言葉もなかった。
亀次郎は、一息入れると、また話し出した。
「お前さんがこれから仕事をする上で、何よりも大事なものは女房だ。おきんさんは、そ
こへ行くと落第だ。それに比べておたきさんは大丈夫だと思う。よく出来た人だ。優しい
し利巧だし、屋敷奉公の関係で、とうとう二十六になるまで独り身で居たんだが、それだ
けの分別もあろうというもんだろう」
長八はだんだん追い込まれて行くような気がした。だんだん考え込む姿になっていた。
「お前さんは、たしか三十三だったな」
「へえ」
「おたきさんが二十六。いい齢格好じゃあねえか」
亀次郎は念を押すように付け加えた。
聞いているうちに、長八の気持ちは少しずつ変化していた。といって、右にも左にも踏
み切れない気持ちだった。とりとめなく考えていた。
「それとも、外にいい人があるのか」
「いえ、そんな」
長八はあわてて打ち消した。
「それじゃあ、播磨屋に文句があるのか」
「そんな。………文句のあるわけはありません」
こう追い詰められて、長八はしどろもどろになっていた。
「そんなら承知してくれよ」
有無も言わさぬような亀次郎の口振りで、長八は途方に暮れた。
亀次郎は調子を変えて、静かに言った。
「ま、直ぐここで返事をしろとは言わねえ。二、三日ようく考えてくれ。おれとしても、
お前が身を固めてくれればうれしい。播磨屋へも義理が立つ」
「へえ」
長八はそうとしか返事が出来なかった。
亀次郎との間で、こんな話をしてから、幾日か過ぎた。仕事も忙しかったが、何となく
自分にひけ目を感じ、どっちとも心がきまらず、返事をしかねていた。
時折おたきのことを思った。ほんの少ししか顔を合わせたことのないおたきだったが、
不思議に印象が鮮明だった。良家の娘らしい物静かな様子、どこかしっかりした動作、二
十六歳というが若々しい顔立ち………そういうものが、長八のまぶたに映った。が、そう
いう好ましさと反対に、古傷のある田舎出の長八自身を考えざるを得なかった。
結局、この話はことわるしかないと思うようになっていた。一日一日と返事が遅れた。
亀次郎からも何の催促がましいこともなかった。
そうこうしているうちに、三月十五日、播磨屋に突然の不幸が見舞った。母親のおりせ
が死んだのである。源次郎が去年の秋から体をこわし、毎日ぶらぶらしている状態だった
ので、おりせには苦労が多かったのであろう。一家の中心でいた母親が、こんなことで急
に居なくなると、播磨屋では、代わっておたきが立ち働かなくてはならない。そして、当
然婿養子の話が切迫したものとして考えられなければならなくなった。
おりせの四十九日忌をすますと、源次郎は病躯を押して中橋に出掛けた。もちろん、お
たきの婿とりの話である。亀次郎も、もう猶予すべきではないと思った。同時に、長八に
何としても承知させようと決心した。
その年六月、長八は播磨屋に婿入りした。すべて源次郎と亀次郎の熱心にほだされての
ことであった。長八とおたきとの夫婦生活は平和で幸福であった。少なくとも、長八にと
っては、過去のおきんとの生活のようなものと全く裏腹なものであった。
小説的に空想すれば、いろいろなことが潤色されそうな二人の結びつきであるが、そし
て、実際私はこの研究の始めにはそんな可能性を予想してもいたが、事実は極くありふれ
た結婚であったのである。
しかし、長八が、こういう平凡な結婚に極く自然に入ったこと自体に、私は長八の心境
の変化とか、心の脱皮とかということを考えさせられるのである。事実、おたきと結婚し
てから、長八の仕事は充実し、芸術的志向が純粋に表われるようになる。思うに、日常の
精神的動揺がなくなり、一筋に精進する機運がつくられたためであろう。
②
長八は播磨屋の婿となり、名を金兵衛と改める。間もなく、源次郎は隠居し、当主とな
り、波江野亀次郎のもとから離れて、独立した棟梁として働く。こうして、急に環境も立
場も変わり、従って心境も変わり、新しい世界がひらけて行くのである。
源次郎は病身を理由に、素早く隠居した。長八に権利と責任を与えたのである。おたき
はきびきびと家事を処理し、長八の身の廻りに心を配り、万事控え目な静かな挙措で、い
かにも長八を敬愛する誠実さを見せていた。長八は、ここでは過去のあやまちも、田舎出
の貧農の子であることも、一切を忘れ去ったような明るい日々を得るようになった。一見
平凡な中に、暖かい深い理解が通っていた。
大火の跡もすっかり復興して、江戸は以前にも増して立派になった。仕事は次々と亀次
郎が世話をしてくれ、弟子を持つようになった。こうして、平穏のうちに秋になり冬にな
り、やがて年が改まった。弘化五年である。正月になったが、当時の慣例として、母親の
おりせが死んで一年を経ていないので、服喪中である。平常なら、源次郎に代わって、深
川の正月行事に参加し、主だった賀客を接待しなければならないのだが、服喪中だから、
それら一切をしなくてもいい。播磨屋一家はこうして静かな正月を過ごした。
正月が過ぎた頃、学友の福太郎から年賀を兼ねた手紙が届いた。三島の在の新宿という
所に塾を開いたという知らせであった。淨感寺の塾が閉鎖されると、篤学を見込まれて、
新宿村から招かれたのであった。こうして、一人の友も一人前の学者教育者として出発し
たことを、長八は心から喜んだ。同時に宗三郎のことを思った。福太郎へは、祝いの言葉
と同時に、近況を報じた。
二月、改元して嘉永元年となる。
春めくと共に、源次郎は元気をとりもどし、彼岸には、「わしが寺参りに行って来る」
と言って、菩提寺の浅草の正定寺へ出掛けるほどになった。いい日和だった。彼岸だと
いうので弟子たちも朝から出ていた。源次郎が出ていくと、夫婦二人きりになった。
昼過ぎ、長火鉢を間に、二人は茶を飲んでいた。
「早いものですねえ、もう半年になります」
おたきが思いついたように言った。
「何が?」
考えごとをしていた長八が、おたきの言葉に顔を向けた。
「いやですねえ」
おたきが笑った。
「わたしたちの結婚です」
「ああ、そうか」
長八はようやく気付いて、
「そうか、もう半年過ぎたか」
とつぶやいた。長八の言葉の中に、淡い影のようなものがよぎった。それが表情に沈ん
だ色をにじませた。
「ねえ、お前さん」
おたきは、それを目ざとく見た。そして、それが何ゆえなのか、おたきは察した。
「何だい」
「お前さんの仕事、もうぼつぼつ始めたらどうなの」
「仕事?」
「鏝絵のことさ」
「ああ、鏝絵か」
今考えていたのはそのことだった。図星を指されたようにたじろいだ。が、言葉はさり
げなく受け流した。ここ半年の間、環境の変化のために、鏝絵のことを忘れるともなく過
ごして来た。
「もう始めていいじゃないかしら」
「おれもそれを考えていたのだ」
長八は正直に言った。
「今まで忙しくて落ち着かなかったものねえ。もう始めてもいいと思うわ」
「そうだなあ」
「おとっつあんも元気になったし」
「うん」
「うちの中のことも、後はわたしがやれると思うし」
「うん」
おたきにそう言われると、長八の胸に鏝絵のことが渦を巻くように湧き出るのだった。
「ねえ」
おたきが促すように言った。
「わたしねえ、ずっと考えていたのよ」
と、おたきは庭に眼をやった。植え込みが板塀を背にして並んでいる。中の桜がつぼみ
をふくらませている。
「この庭広いでしょう。おとっつあんの道楽も、もうこんなに広くいらないと思うのよ。
だからね、庭の隅にお前さんの仕事場を造ったらどうかしら」
長八も誘われるように庭を見渡した。
「しかし、この庭はおとっつあんの大切な庭だよ」
「でもねえ、仕事場を造るんだといえば、おとっつあんも喜んでくれると思うわ」
「そんなことは言えないよ。おとっつあんに甘えてはいけない。鏝絵をやりたくなったら、
縁側でも庭でも出来るんだ」
「だって、それじゃあ」
長八は、そういうおたきの言葉をさえぎって、
「そんなことおとっつあんに言っちゃあいけないぜ」
と釘をさした。
こんな話があって、源次郎はおたきから話を聞いたのか、あるいは自分だけの考えだっ
たのか、突然大工を呼んで見積もりをさせて、とうとう秋には仕事場が建てられた。時折
り縁側で土を練っている長八の姿に、源次郎も見兼ねたのかも知れない。
長八は、こうなった以上遠慮する必要はなかった。彼は暇をみては仕事場に入って、鏝
絵の仕事をするようになった。まだ解決されていないことがいくつもあった。今度は本腰
でやろうと、長八は思うようになった。
この年も、外国船がしきりに近海に現われたといううわさが飛んだ。人々は次第に実感
として、異常な関心を持つようになっていた。一つには、幕府に対する批判と非難になっ
ていた。国論がそこから二つに分かれた。江戸の市中にも、それは反映していた。それは、
長八の心にかげりをつくっていた。鏝絵の研究を続けたいという心と、そんなことをして
いる時ではないぞという心が葛藤を呼んでいた。
………が、おたきの提案を聞き、更に源次郎の独断によって仕事場が出来てみれば、長
八ははっきりと心を決めることが出来た。鏝絵に精進することである。そう思った。
が、仕事場に入って、土を練っていると、時々雲のように彼の心によぎるものがあった。
やはり世の動きが気に掛かった。世の移り動きにくらべれば、鏝絵のことなど詰まらぬこ
とのようにも思われた。しかし、そんな時、川越での武清の言葉を思い出し、その言葉を
噛みしめた。そして、おれはやはり鏝絵をやりとげようと思い、がむしゃらに土を練った。
こうして、またこの年も暮れた。嘉永二年………外国船の来航は一層しげくなった。世
論は一段とやかましくなった。時代が大きく変化して行くようであった。そういう不安を
かり立てるかのように、閏四月、イギリス船マリーナ号が浦賀の港に入った。やがて、悠
々と江戸湾内に入り込み、測量を始めた。江戸を目の前にしてのこの行動は市民を驚かせ
た。憤激させた。恐怖させた。今にも戦争になりそうな議論が横行した。それは、八名川
町の播磨屋にも大きく伝わった。播磨屋は深川での顔役である。町役の人々が事態を重く
見て、播磨屋に相談に来る。当主である長八はこれに応待する。したがって仕事も思うよ
うにいかない。おたきも源次郎も心を傷め、時世のかげりが平和な一家にひと刷毛の雲を
浮かべる。
この期間が、長八にとっては停滞期であった。が、およそ芸術家は誰彼となく、多かれ
少なかれ、大なり小なり、その時代を超越することが出来ず、それに苦闘し、矛盾に突き
当たり、突き破って、自己を成して来たのである。時代の影を帯びていない芸術などあり
得ないと言ってもいいだろう。しかし、停滞で終わっては失格である。停滞は一歩も前進
しないからである。
五月、幕府は重ねて諸大名に海防を布達する。諸藩は布達に従って、それぞれの警備計
画を始める。そのため百姓をも動員する。世はあわただしく過ぎて行く。
長八の仕事場は、ほとんど何の変化もなく、夏を迎え、秋を迎えた。が、播磨屋の中に
は不安の影が消えなかった。そして、当然長八の仕事も思うように進まなかった。
長八はよく弟子たちに「おれは播磨屋の十代目だ」と語ったという。その言葉の中には、
播磨屋という名門の自負があり、それには責任もあり、義務もあると言えよう。長八はそ
ういうものを強く感じていたようである。彼が終生播磨屋金兵衛を名乗っていたことや、
播磨屋の過去帳を整理したり、菩提寺の修理に尽くしたり、養子問題で苦労したりしてい
る事は、それを実証していると言えよう。そういう長八が、芸術に専心しようとしながら、
播磨屋の責任や義務のために打ち捨てなければならなかったのは、当然とも言える。
年が明けた。嘉永三年である。日本国内は依然としてあわただしい空気だった。その二
月、江戸では神田から出火して、またも大火となり、長八はその復興に若い棟梁として働
き廻り、また夏を迎え、秋を迎えた。長八の鏝絵の研究は依然として停滞を続ける。
十月、高野長英が自殺する。十一月、朝廷は幕府に再度の海防警告を発する。越えて嘉
永四年一月、土佐の漂民ジョン万次郎が帰る。二月、水野忠邦死去。………そんなことよ
りも、去年の秋から米価が高騰し始め、難民が続出し、正月になって、それは一層激しく、
盗賊が出没して、米屋や物持ちをねらって、目に余る状態になってしまった。幕府は手を
焼いて、盗賊の切り捨て差しつかえなしと布令するような事態だった。おまけに、はやり
風邪が正月から二月にかけてはびこり、播磨屋でも、次から次へ感染して、長八もしばら
く臥床する身となった。
この病臥は、長八に内省の機会を与えてくれた。もともと強健な長八が珍らしく家にこ
もるのだから、静かにものを思うのも当然のことかも知れない。こうして静かに一人で考
えると、世の中の動きが透明に頭に浮かんだ。だんだん暗く重苦しい時代に移って行くよ
うであった。それにつけても、鏝絵の仕事がはかないものに思われたりした。長八は、そ
ういう内省の中で、人間の運命とか生命とかということに思い至っていた。長八は三十七
歳になっていた。今までがむしゃらに生きて来て、時には無価値な生活をしていたことが
くやまれた。年齢のせいなのであろう。鏝絵のことも結びついて、自分の怠情が情けなか
った。これから、いくばくの生き方が出来るか、予測しがたいことだが、前途は暗いよう
な気がした。
③
しかし、長八はようやく体が快復すると、激しい意欲にかられて仕事場に入った。その
年の秋の末、年来の宿願であった色土の研究がほぼ完成した。漆喰に顔料を混ぜ、それを
ていねいに練り上げ、それを膠を薄く溶かして加え、変色しない潤沢な光沢のある色土を
造り出したのである。それはすべての色に同じようにするわけには行かなかった。ことに
緑や紫に苦心をした。
この色土は、主な弟子には教えたようであるが、弟子たちは皆秘伝としたため、詳しい
ことは伝わっていない。
色土が一つ一つ出来上がるごとに、長八は試作をした。彼のめざす鏝絵が彼の頭に炎と
燃えた。彼はそんな時寝食を忘れた。試作につぐ試作に、彼は飽くことを知らなかった。
だんだん冬になって行った。雪の散らつく夜もあった。寒さに手が凍った。が、長八は緊
張で、そんなものを苦痛と思わなかった。もはや、時世の変移も超越していた。
こうして試作を繰り返しているうちに、そして、次第に色土が仕上げられて行くにつれ
て、不思議なことに、別な問題が彼の頭の中に生まれていた。………それは、今まで実験
して来たことが、絵画そのものと何にも違わない、いわば筆を鏝に代えただけの、紙を壁
土に代えただけのことで、それでは鏝が生きないし、土が土としての意味を持たないので
はないかという疑問であった。やはり鏝と土で創るところに意味があり、鏝と土が絵とは
違ったものを表現すべきではないかという問題であった。
単なる絵であってはならない。紙と何にも違わない壁であってはならない。鏝には鏝の
命があり、土には土の価値がある。それをはっきりさせないでは、鏝絵の道は創造されな
い。………と考えたのである。
「鏝は筆ではない。色土は絵の具ではない。壁は紙ではない」
長八は強く思った。したがって、喜多武清に学んだ画法をそのままに置き替えただけで
はいけないのだと思った。この時、長八は田能村竹田を思い出した。墨一色の彼の絵は、
彼の芸術である。竹田そのものである。
「おれにはおれの絵がなくてはならぬ。鏝の絵が、土の絵が………」
と長八は思った。
長八の研究心は、次の段階に入ったといえる。新しい思考と苦心とがここから始まる。
壁絵をぬり、つぶし、また塗ってはつぶした。こうして時が過ぎて行った。明けて嘉永五
年となる。
正月の末、たった一人の姉のおたみが死んだ。貧窮の中で、病弱で、とうとう結婚もせ
ずに、一生を薄暗い藁屋の下で暮らして死んだ哀れな姉であった。もう四十を越えていた。
思い出すのは、先年淨感寺の普請のため帰郷した時、長八は姉のために凧絵の版木を彫っ
てやった。これを刷って、色付けをして、凧を作って、縁先に並べて、子供相手の商売を
させようとしたのである。病身の姉が家内で気ままに仕事をして、それでいくらかでも生
計のたしにさせたいと思ったのである。この着眼は意外に子供に受けて、「長八さんの凧
だ」と喜ばれ、姉も喜んでくれた。
姉の死を知っても、帰郷は簡単には出来ない。長八は自分で位牌をつくって仏壇の隅に
飾った。それだけのことしか出来なかった。
この年、外国船の来航は頻繁で、世論は一段と高まって行った。いろいろな憶測が江戸
市中に不安な気持ちを撒き散らしていた。が、長八は世情に余り耳をかさなかった。いつ
のまにか、そういう自分になっていた。逃避でも、利己でも、白眼でもない。長八は自己
の本分を長い放浪の中で悟っていた。長八は自分の鏝絵に賭けていた。鏝絵に命を燃やし
ていた。それだけのことである。
五月、幕府は大森海岸に砲台を築かせた。八月、オランダ総督が、印度総督の書状を幕
府に差し出した。それには、アメリカ使節が近く日本を訪問する旨が予告されていた。こ
のことについて幕議は繰り返されていた。
長八は、仕事場にこもって、しきりに鏝を動かしていた。鏝絵というものの本質をつき
とめようと努力していた。頭では一応はわかっているのだが、実際には難しいことだった。
何か、力の限界を感じる時があった。身心を磨り減らすような苦痛を味わう時があった。
薄暮の仕事場で、じっと一点を見詰めているような時があった。狂気のように泥だらけの
手を板になするつけている時もあった。険しい岩場に差し掛かった山男のような必死なも
のが、そんな時の長八の心であった。
十一月、江戸城の宝蔵が焼けた。無頼の浪士たちの放火だとうわさされた。
嘉永六年。世間のあわただしさをよそに、播磨屋では明るい静かな正月を迎えた。病父
は寝るほどではなく、正月の屠蘇を祝った。長八は病父に代わって、年頭の挨拶廻りをし
た。妻のおたきは甲斐甲斐しく家事を切り廻していた。五人の職人や徒弟ものんびりと正
月を楽しんでいた。
久しぶりで、病父と一しょの茶の間にくつろいでいると、病父が急に養子話を持ち出し
た。まだ薄ら寒い晩だった。
「そろそろ養子をもらわなくちゃなるまいな」
養子については、前々から時折話題になっていたが、その都度笑いながら軽く焦点から
はずれて消えていた。というのは、長八とおたきの間に実子が生まれるかも知れないとい
う望みがあったからだ。が、正月早々、こんな話になると、夫婦は何となく笑ってすまさ
れないような気がした。結婚以来六年経っている。年齢をいえば、長八は三十九、おたき
は三十二になる。夫婦の間に子供は出来ないかも知れない。そういう感慨がないわけでは
なかった。
「そうですねえ」
長八は、そういうあいまいな返事をした。おたきの方を見た。
「そうねえ」
おたきは口ごもった。が二人とも笑わなかった。確かに子供のないのはさびしかった。
夫婦よりも源次郎の方が欲しがっていた。
「中橋の竹次郎はどうだろうな」
源次郎が具体的に名指しをした。竹次郎というのは、亀次郎親方の次男である。当時十
二歳のまだいたいけな子供であった。
「そりゃいけませんよ」
と長八は言った。亀次郎は喜んでくれるかも知れない。素直ないい子でもある。だが、
それでは播磨屋の血が絶える。
「お前は播磨屋の血筋のことを考えているのだろう。そりゃあ、出来ることならその方が
いい。が、播磨屋の血筋といえば、湯島の省三の子しかない。しかし、省三の子ではお前
の後は継げないよ」
源次郎は長八の心の中を知っていた。播磨屋を大事にしているのがよくわかっていた。
それだけに、長八を主にして養子問題を考えてやりたかった。
「清太郎じゃあねえ」
おたきが不満そうに口を入れた。
「おとっつあんの言う通り、清太郎じゃあ、お前さんの後は継げないよ」
そう言われると、それでもと押し切る気持ちには、長八はなれなかった。
「お前が早く子を生んでくれりゃあいいんだがなあ」
と冗談にして笑った。しかし、養子問題は、早晩具体化されねばなるまいと、長八は思
った。恐らく夫婦の中に子が生まれないだろうという悲しむべき予感がないわけではなか
った。
正月が終わると、長八はまた仕事場にこもった。少しずつ試作品が壊されないで残って
居た。いくらか解決の曙光が見えて来ていた。
正月も末になって、長八がいつものように仕事場で仕事に熱中している夜、突然大きな
地震が起こった。長八は思わず鏝を放り出して母屋に走った。病父を案じたからである。
病父はもう床についていた。長八があわただしく障子をあけて入ると、病父は枕から頭
をあげた。
「ひどい地震だな」
と、平然としていた。
「大丈夫だったか」
長八は拍子抜けしたように言った。そこへ、おたきが入って来た。
「おとっつあん、起きて着物を着て!」
命令するように、源次郎の布団を剥いだ。
「何のこれしき」
源次郎は微笑していた。が、おたきの言うままに着物に手を通した。
「それより、長八、深川を見て来い」
源次郎の声は、厳しく長八の胸に届いた。
「へえ」
長八は、はっと思った。いきなり外の闇に消えて行った。
地盤の弱い深川一帯はひどい被害を受けていた。不幸中の幸いは、夜分のことで火災が
なかったことである。江戸市中いたる所に災禍は及んでいた。
長八は翌日から深川を中心に復興の仕事に立ち働いた。そのため、鏝絵の仕事もしばら
く棚上げになった。
大地震は相模方面がことにひどく、小田原では町屋が半数以上も倒壊したというし、城
郭が崩れたといううわさだった。江戸はそれほどではなかったが、軽微な損傷は無数で、
復興は意外と手間どって、初夏を迎えても、まだ仕事は続いていた。
そんな時、降ってわいたように、江戸市中に重大な事件が伝えられた。それは、アメリ
カ使節ペリーの来航である。ペリーは、軍艦四隻を率いて、浦賀に入港した。国書を将軍
に手交して国交を迫った。いわゆる黒船騒動である。幕府はあわてた。悪いことに、折り
も折り、将軍家慶が死んだ。幕府の要人は、御三家(紀州公、尾張公、水戸公)の外に、
会津、忍、川越、彦根の親藩を招集して、緊急に評定したが、なかなか結論が出なかった。
六月三日朝、城ヶ島沖三里のところに黒船を発見したという届けが浦賀奉行にあった。
そのことが早馬で江戸城に報告される。たちまち江戸市中にうわさが拡がる。四日、「櫛
の歯をひく如く」浦賀から江戸へ早馬が続いた。だんだん黒船の実態が市民の間にわかっ
て来た。蒸気船であること、大きい軍艦であること、朝夕大砲を撃って人々を驚かすこと
………。五日、芝から品川へかけて警備を固める。幕閣の評定はらちがあかない。江戸の
騒ぎは六月九日まで続く。鎧や武具が飛ぶように売れ、陣羽織や簑笠が売れた。火薬を買
いあさった。黒船が江戸湾に入り込んだ。八日には市中のお触れが出る。『夷国船万一内
海へ乗入、非常の場合には、老中より八重洲河岸火消宅へ連絡、同所で早鐘打ち、このと
きは曲輪内出火のときと同様に登城、持ち場を固めること、場末まで早半鐘を打ち鳴らす』
………町人たちへの触れは、町年寄を通じて、町の火の見櫓でも半焼を鳴らし、火消し人
足も消防道具を持って集まると指示された。物価は急騰した。梅ぼしが倍の値で売れた。
流言が乱れ飛んだ。疎開する者が右往左往した。大名が急造の陣屋を建てるため、大工、
職人、日雇を狩り出した。
こんな有様で、地震の後始末も終わり近くになって思うに任せなかった。
ペリーが去って、ほっとしたのも束の間、一箇月後には、ロシアの使節プチャーチンが
またも浦賀にやって来た。こうして、世は急転回してゆく。八月、品川に砲台を築く。各
藩に大船建造を許す。十一月、水戸に大船建造を命ずる。オランダに軍艦や鉄砲を注文す
る。
秋も末になって、ようやく長八は仕事場にもどった。再び入念に鏝を動かし始める。
その年の暮れ、母親のてごが死ぬ。長八は急いで帰郷し、母を葬り、後始末をする。後
始末といっても、事は簡単であった。もはや長八の血縁は一人もいないのである。ちなみ
に、長八には弟と妹があるが、弟の寅吉はすでに成人して、八王子で大工をしていたし、
妹のおふでは江奈村の大工寅松に嫁して、この時にはもう江戸に出ていた。というわけで、
居宅と僅かの耕地を誰かに頼めばいい。幸いなことに、淨感寺のおもんとその娘のおしゅ
んが留守を守ってくれることになって、長八は年の明けないうちに江戸にもどった。
④
明けて嘉永七年、アメリカ使節ペリーは、前年の約束通り軍艦六隻を引き連れて小柴沖
にやって来た。ついに日本は開港を余儀なくされ、いよいよいばらの道を踏み込むことに
なった。そして、これを契機に国状は急変して行く。
が、長八はもう世間の騒ぎに耳をかさなくなっていた。ひたすら自分の仕事に打ち込ん
で、鏝絵の新機軸はほぼ完成されようとしていたのである。彼はしきりに額装の小品を制
作していた。鏝と土を十分に生かすことを試みるためであった。
渦巻く世相をよそに、長八は仕事に励んだ。そして、何事もなく平穏にこの年も過ぎて
行った。が、十一月、またも伊豆、相模を中心に大地震があり、地震は津波を呼び、大き
な災害となった。長八の郷里松崎村も大津波のために田畑や家屋が流された。この時の津
波で、たまたま下田に停泊していたロシア船デイアナ号が大破した。東海大地震である。
明けて安政二年である。正月半ばに、福太郎から手紙が届く。福太郎は、駿河の新宿村
から下田に移っていた。ペリーの来航によって、下田が開港されるについて、逸早く下田
に来たのである。ここで学塾を開いて子弟に教えるかたわら、外国事情を知り、外国語を
習い覚えようとしたのである。真意はどこにあったかわからないが、時勢を敏感に見てと
っていたのである。彼は名も堂々と、高柳天城と名乗っていた。手紙は、さりげなく年賀
の言葉を述べ、下田転住の事情を報じてあったが、長八は、その手紙から、大きく成長し
変貌した福太郎の姿を、驚きと共に畏敬の気持ちで受け取っていた。
手紙の末尾に、淨感寺の建築の折りに出会った石田半兵衛の息子馬次郎のことがあった。
あの眼光鋭い若者のことである。いつからか父から離れて放浪し、今は甲州を根城として
江戸や京に出没している。まさかの時は匿ってほしいとあった。
馬次郎は激しく外国排斥を主張しているらしいが、開国模様となって、どう考えているか。
どう変わったか、長八はそんなことを思った。
世の中は大きく変わろうとしている。福太郎も馬次郎も、その渦中に飛び込んで生きて
行こうとしているのである。長八はしかしその刺激に動かされなかった。長八は自分の歩
むべき道を信じるようになっていた。
ふと、宗三郎を思った。しばらく会っていない。どうしているのだろうか。こういう時
勢に、何を考えているのだろうか。幼ない頃の竹馬の友らは、もはや皆別々な道を歩いて
いるのだなと長八は思った。
長八は鏝絵の仕事に没頭していた。幾度かの試作で、自信を深めて来ていた。自信を深
めて行くにつれて、制作に心を打ち込んだ。世上の騒がしさを他所に、作品が次々と作ら
れて行った。この年は平穏に春が過ぎ、夏が過ぎた。長八の制作慾はそれだけ一層満たさ
れるようだった。
秋が来て、やがて冬に入ろうとする十月二日、その夜の四ツ半刻(午後十一時)突然異
様な音響と共に大きな地震が襲った。八名川町では皆平安に寝静まっていた時であった。
一家中、寒い夜空の下に飛び出した。建物から離れて、庭の立木を支えにして、震動の静
まるのを待った。皆着のみ着のままだった。一揺れ収まって、人々はほっとして家に入る
と、またもおびやかすように激しく揺れた。こうして、明け方まで揺れ続けて、とうとう
寒夜を寝もやらず過ごした。記録によると、三十数回に及んでいる。
いわゆる安政の大地震で、山手は地盤が固く損害は軽微だったが、深川、下谷、浅草な
ど下町一帯は被害甚大であった。悪いことに、地震の最中に火災が起きた。寒いから暖を
とるため火をおこしたのであろう。各所に起こった火災は、折り柄の西風に次々と飛び火
して、明け三日の昼時には、手のつけられないほどに燃え拡がってしまった。記録を見る
と、倒れた家一四、三〇〇余、倒れた土蔵一、四〇〇、死者四、三〇〇、重傷三、八〇〇
とある。火災については明白でないが、震災に更に輪をかけた大災害であったろうと想像
される。
江戸は大変な騒ぎとなった。幕府は救助に乗り出し、救小屋を各所に設け、町会所に焚
き出し、医療を命じた。途方に暮れている市中に、お定まりの夜盗が横行した。
八名川町の播磨屋は、幸いにも倒壊しなかった。が、深川一帯は無惨な有様だった。去
年に引き続いての被害だからやり切れない。長八は町役人の人々の指示に従って、寒さし
のぎの小屋造りから、食糧、衣服の調達に奔走しなければならなかった。
困窮している人々を尻目に、季節は足早やに寒さに向かっていた。復興は夜を日につい
て、年の暮れ、ようやく人々はいくらか落ちつきをとりもどすことが出来た。
この大地震は伊豆にも大きな被害をもたらした。浸水、山崩れなどがいたる所に傷々し
い跡を残した。
直ぐ安政三年正月であった。大地震の後始末は不十分ながら、静かな正月を迎えた。長
八は久しぶりに仕事場に入って、作品を眺めたり、土をこねたりする余裕を持つようにな
った。
ある日、春は浅く、梅はまだ固いつぼみを木枯らしに揺らしていた。仕事場の戸口がこ
とことと鳴って、
「お前さま」
とおたきの声がした。
「何だい」
長八はそう言いながら、鏝を持ったまま立ち上がった。戸口があいて、おたきの黒い襟
がのぞいた。
「今ねえ、祐天寺さんのお使いだというお坊さんがお見えになりました」
「祐天寺?」
長八は何の用件か見当がつかない。
「お願いがあって、と言ってました」
長八は鏝を置き、前垂れをとった。
「とにかく、座敷にお通しして」
そう言って、長八は着物の襟を直した。
「はい」
おたきは先に走るように母屋に去った。長八は後からゆっくりついて行った。
座敷には祐天寺の僧が待っていた。
「私が長八でございますが」
「申し遅れました。拙僧は祐天寺の番僧淨善と申します」
「わざわざ、こんなむさくるしい所へおいで下さって恐縮です。で、何か御用の筋でもお
ありでしょうか」
「はい、突然伺いいたしまして恐縮に存じます。早速でございますが、用件と申しまする
のは、祐天寺の修復について、是非ともあなた様にお願いいたしたいと存じまして、いや、
このことは御上人様の直接のお意向でございまして」
ていねいな口上であった。突然の話なので、長八にはよくわからなかった。祐天寺とい
えば、江戸でも有数の大寺である。前年の大地震で(といっても三箇月ほどしか経ってい
ない)で建物が損傷したので、大修理をするということだった。が、長八を指名したのは
どういうわけだろうか。江戸には有力な棟梁がたくさん居る。年若い長八が何で選ばれた
のか。長八には飲み込めなかった。
翌日、約束通り、長八は祐天寺へ行った。立派な山門や本堂を仰いだ。直ぐ方丈へ通さ
れた。方丈には住職が待っていた。六十歳を越えたと思われる老僧であった。長八が障子
をあけて敷居際に膝をつくと、
「長八さんか。よく来てくれた」
と、いきなり言われて驚いた。
「長八でございます。昨日はわざわざお使いを頂きまして」
「まあまあ、こっちへどうぞ」
住職は自分で座布団を置いた。
長八がにじる寄ると、
「私がわかるか」
と、住職がいたずらっぽく顔を突き出した。笑っている。長八は最初見た時からどこか
で見たような気がしていたが、そう言われてもまだわからなかった。長八が、黙っている
のを見て、
「無理もないな」
と、改めて微笑した。
「お前さんがまだ鼻垂れ小僧の頃だったからな」
そう言われて、長八ははっと気がついた。
「あなた様は、淨泉寺の方丈様」
確かにそうだと思った。時々子供の頃に寺内に入り込んで、池の鯉をおどしたり、山の
木の実を採ったりした。そんな時、方丈に叱られたりしたこともあった。
「わかったかな」
住職はいかにも愉快そうに笑った。
郷里の松崎村には寺が二つある。一つは淨感寺、もう一つは淨泉寺である。淨泉寺は浄
土宗で、淨感寺より遙かに格式のある寺で、ここに座っている老僧は、長八が幼年の頃の
淨泉寺の住職であった。今は祐天寺に迎えられて、十二世祐興上人となっているのである。
二人の間に話は弾んだ。故郷の話。淨感寺大改築の話も上人は知っていた。茅場薬師の
ことも知っていた。やがて本題に入って、祐天寺修復を懇望されて、長八は快諾した。
祐天寺の工事は祐興上人以後はほとんど松崎村の大工、左官にやらしていた。今度の修
復についても連絡したところ、左官の仕事なら江戸にいる長八にやらせるようにとの返事
があってのことだという。
祐天寺の修復は一箇月余を費やした。ここで始めて大建築を長八は手掛け、後の仕事に
大いに役立つことになる。祐天寺で何をしたかということは、今はさだかでない。明治二
十七年九月、火災で焼失してしまったからである。が、恐らく完成に近づいていた鏝絵を
ここの随所に施したであろうことは想像される。それは長八の芸術にとっても画期的なも
のであったろうとも考えられる。
そればかりではない。この一箇月余の祐天寺の仕事は、長八の今後の生活や仕事の上に
影響があったことをいくつか指摘することが出来る。
一つは、彼は恐らくこの時『天祐』という署名を始めてしたであろうと推定されること
である。現存作品のなかで『天祐』と署名した最も古いものは、成田に奉納した塗額で、
これは祐天寺の仕事後、僅かに三箇月しか経っていない。『天祐』は祐天に拠ったもので
あることは確かであろう。恐らく、寺社の装飾的な作品には作者の署名を要したろうし、
あるいはそのために祐興上人から与えられたのではないかと想像される。とにかく、署名
をするほどに、一箇の作家として自分自身が認めるようになった証左であると思うのであ
る。
その二は、祐天寺の作品の中に、立体的な彫塑風のものがあったのではないかと思われ
ることである。長八は長い研究期間、特に後半の「鏝と土」の芸術を志向して、その中に
彫塑風に試作もしたのではないかと思うが、なぜそんなことを想像するかというと、この
祐天寺の仕事後間もなく、彼は成田不動の修復を頼まれ、これをやり遂げているからであ
る。成田の不動尊といえば、この寺の本尊である。最大の宝物である。そういうものを未
経験な人間に依頼するわけにはいくまい。長八が頼まれたということは、また、長八自身
が承引したということは、すでに実績があったことを立証するものと思うからである。そ
して、その実績はいい加減なものであろうはずもない。祐天寺の立体彫塑はそこから考え
られて当然であろう。
もう一つ重要な意味があった。それは、一箇月余の祐天寺生活で、宗教的なものを感じ
とったと思われるのである。それは祐興上人の感化教導であったかも知れない。また寺内
の環境雰囲気からの影響であったかも知れない。そういう宗教的精神は、以後長八の芸術
の上にも、私生活の上にも、深く投影して行くのである。
⑤
時代は険しい風雲に包まれていた。ペリーの来航によって、幕府は開港を決した。開港
反対の渦は国内にごうごうと巻き起こった。攘夷論は勤皇討幕に変わった。血なまぐさい
風が江戸の市中に吹き始めた。が、市民にはまだ太平ののびやかさがあった。
二月の二の午の日は成田山新勝寺の祭りで、俗に出世稲荷とも言って、火防の守り札を
出し、関東一円から参詣者が集まった。特に大工、左官などの建築業者は、毎年毎年この
守り札を受けて神棚にまつり、火防に気をつけるしきたりで、江戸では成田へ行けない人
のために、深川不動堂を建立して、ここで出開帳をし守り札を渡すほどだった。
この年、安政三年、
「今年は成田詣でをしようじゃないか」
榑正組の職人たちの中でこんな話が持ち出された。去年十月の大地震で苦労した後だけ
に、縁起直しの気持ちもあって、榑正組一同打ちそろって行くことになった。
長八も、丁度祐天寺の仕事も終わったし、独立して始めてのことでもあるし、その仲間
に加わることにした。
総勢五十人ほどになった。前日の朝にぎやかに江戸を発ち、二泊して無事に参詣をすま
せて帰った。
帰った日の夜、中橋の亀次郎の家で、左官仲間だけの酒宴があって、その席で、亀次郎
が思いついたように、
「めでたく参拝をすませたが、成田へは度々出掛けるわけにはいかない。わしは道々考え
て来たのだが、今度の参拝を記念して、絵馬堂に願掛けをして、御加護をお頼みしたらど
うだろうかと思うんだが」
と提案した。一同は異議なく賛成した。
「誰がつくるのか」
ということになって、いろいろな案が出されたが、左官の奉納額だから塗額にしたらと
いう話に落ち着き、結局、長八がつくることになった。
長八は快よく引き受けたが、さて何を描こうかと迷った。元来、長八は仕事には手早く、
正確であるが、一種の凝り性でもある。これを描こうと決めるまで、さんざん苦心し、そ
れに時間を掛ける傾向がある。
考えあぐねて、ある日、ぶらりと外に出た。もう三月、春たけなわであった。河岸に出
ると、川風が肌に心地よかった。向こう岸の桜が点々と咲いていた。川舟がゆったりと動
いていた。あてもなく歩いて行くうちに、土堤下の裏町の細い小路にまぎれ込んだ。そこ
の一軒の狭い庭先に、鶏が一羽こぼれ籾をついばんでいるのに眼がとまった。そばに臼が
ころがっている。今しがたまで誰かが籾を搗いていたのであろう。
長八は立ちどまって、鶏の姿を見ていた。
「絵になる」
と長八は思った。懐から紙を出し、矢立ての筆をとって、鶏の動きを追いながら写生を
し始めた。何枚も写生をした。長八の心に新しい感動が湧いていた。『絵を描いているの
ではない』『生きている動いている鶏を描いているのだ』長八はそんなことを思いながら、
せっせと写生した。
ようやく満足するような気持ちになって、紙を懐にもどした時、後から声を掛けられた。
「長八さん、じゃないですか」
振り返ると、異様な鋭い眼をした乞食姿の男が立っていた。薄汚れた顔が笑っているよ
うであった。長八はけげんに思って、返事もせずにその男の方に近寄って行った。男は笑
っている。
「覚えていますか。私ですよ」
男は、長八の前にぬっと汚れた顔を出した。長八は、じっとその顔を見た。が、直ぐ、
「半兵衛さんの息子さんの、馬次郎?」
と言った。男は黙って大きくうなずいた。
あの時の小生意気な表情が髭の中にあった。これほど年月を経ながら、すぐ名前が口に
ついたのは初対面の印象が強かったからであろう。それに淨感寺塾の後輩で、宮大工半兵
衛の息子、福太郎の手紙にあったためか、妙に親近感を覚えた。この広い江戸の中で、同
郷人に偶然出会えた不思議な心境である。うわさによれば彼は三年前、無難車船を試作、
伊豆の海に浮かべたが失敗、後に本所竹蔵で実験して成功したことはうわさに聞いていた。
「馬次郎さん!」
長八はそのうわさに触れず、馬次郎の薄汚れた肩をつかんだ。黒い顔が笑っていた。
「どうしたんだ、この姿は」
と、長八は改めて馬次郎の姿を眺めた。
「今年一月から江戸に来ています。忙しくって、会って話したいと思いながら会えなかっ
た。鏝絵を創り上げた長八さんに会って見たかった。私も宮大工の端くれですからね。会
えてよかった。でも今日、この足で京までのぼらなくちゃあならない。すぐまたもどるが
ね」
「急ぐのかい」
「うん、だが、私は明るいうちの旅は出来ない。日暮れまで、長八さんと会ってと思って」
「その格好は?」
「格好なんていいじゃないですか」
馬次郎は屈託なく笑っていた。
二人は土堤に出た。
「福太郎さんに会いましたか」
馬次郎が言った。
「いいや。正月手紙をもらった。下田で塾を開いているそうだ」
「そうだってね。イギリス語を勉強しているってね」
「そうらしい。手紙にもちゃんと書いてあった。福さんらしい」
「変わったね」
「みんな変わった」
「そうだ。みんな変わる」
馬次郎は立ちどまった。川面の芥の流れるのを見た。広い川の流れの中に、小さな芥が
流れるともなく流れている。
「不思議ですね」
馬次郎がつぶやいた。
「何が?」
「みんな、てんでに流されている」
馬次郎がやはりつぶやくように言った。
長八は黙っていた。しかし、馬次郎の言葉が胸にしみるようだった。
二人はゆっくり歩き出した。
「宗さんに会ったか」
と、長八が聞いた。以前、福太郎が馬次郎に宗三郎を紹介したと聞いていたからである。
「ええ、ひと月ばかり前になりますが、偶然、お玉が池の千葉道場で会いました。藩侯召
し抱えの儒者として引く手数多とも、帰郷して塾を開き子弟の教育に当たりたいとも言っ
ていました。迷っていました」
「迷い?そうだろうな。宗さんの学問の目的は、民百姓を教育して武士に対抗するところ
にあったからな。それで元気だったろうな」
「ええ、元気でした。立派な人物になりました」
長八はずっと以前、会った時のことを思い出していた。
八名川町の家についた。表から入ろうとすると、馬次郎が袖を引いた。
「こんな格好では、上がれません」
長八は苦笑した。
「じゃ、庭へ廻ろう」
裏木戸をくぐって、二人は縁先に腰をおろした。おたきが茶を運んで来て、挨拶をすま
すと、気をきかして去って行った。
「福さんの手紙で、馬次郎さんが郷里を出たことは知っていたが、………」
「ええ、それが珍談でしてね。無難車船の失敗ならいいが、間男をして、村に居られなく
て逃げ出したと、村では評判なそうな」
「まさか」
「私が間男とは、………」
二人は笑った。が、長八には、馬次郎の現在が気になった。乞食姿は仮装だと思うが、
こんな風体をしなければならないのか、それが不審だった。
「それで、今何をしているんだ」
馬次郎は茶をすすって立ち上がった。
「甲州のある神主に仕えている」
「神主に?、それで?」
「京と江戸と、甲州を行ったり来たり」
そう言われても、長八には飲み込めなかった。
「今の世の中は大変なんだ。世の中はどうひっくり返るかわからない」
馬次郎は自分から話し出した。
「京には脱藩者が盛んに動いている」
「江戸にもたくさん居るそうな」
「江戸にもまぎれ込んでいる。多くは幕府の老中などをねらっている。井伊を倒そうとい
う話もある」
「物騒だな」
「そういう状勢を探るのが、………それが私の役目」
「命を粗末にしなさんなよ」
「でも、いざとなれば………」
馬次郎は笑いもしなかった。
長八は身のしまる思いをした。国家のため身を賭してまで働こうとしているのだ。続け
て「親に心配かけなさるな」と言おうとしたが口をつぐんだ。
「こんな格好をしなければならないほど、時局は厳しいのです。が、それだけに面白い」
馬次郎はそう言って、肩を揺すって笑った。と、急に、長八の方に向いて、
「いや、飛んだお邪魔をしました。元気で暮らしてください。またいずれ会いましょう」
と言うなり、くるりと背を向けて、裏木戸から出て行ってしまった。
この頃の江戸市中には、どこにも浮浪人がいた。野良犬のように、所きらわず食を漁り
歩いていた。馬次郎の後ろ姿はそんな格好に見えた。あの姿で京へのぼるのであろうか。
すたすたと歩いて、やがて家角を曲がって行った馬次郎の姿を、長八は無量の思いで見送
っていた。
もう日が暮れかかっていた。長八は我に返ったように、そのまま仕事場に入った。が、
馬次郎との会話が頭から離れられなかった。しばらくぼんやりと障子明かりに向かってい
た。
夕食をすませて、ようやく自分を取りもどした長八は、その夜、一心に土を練った。成
田山に奉納する額をつくるためであった。
翌日も終日仕事場にこもった。そして五日目、奉納額は仕上がった。
この額は今も残っている。『臼に鶏』の図で、これに始めて彼は『天祐』と雅号を署名
している。
亀次郎は奉納額の出来上がるのを待ち構えていた。月が改まって四月、長八は亀次郎と
同道して、もう一度成田へ出掛ける。成田に着いて、その日のうちに額を奉納し、夜は門
前町に泊まってくつろいでいた。
⑥
その夜のことである。二人がくつろいでいるところへ、女中が来客のあることを告げに
来た。
「どなたさんで?」
と亀次郎が聞くと、女中は、
「新勝寺のお坊さんです」
と言った。不審ではあったが、
「ともかく」
座敷に通すように女中に言って、待っていると、品のよい四十年配の僧が静かに入って
来て、ていねいに挨拶をした。
「早速でございますが」
と、僧はゆっくりとした口調で来意を説明した。
「奉納額は実に見事な出来栄えで、驚嘆つかまつりました。住持の仰せられるには、これ
ほどの力量の人は日本でも珍らしいと、大変な驚きようでございました。ところで当山の
本尊の不動尊像でございますが、前々年の大地震と、続いて去年の大地震で、御尊体が毀
損いたしまして、もうどうしても修理しなければならないほどになっておりますが、何分
にも御本尊さまのことゆえ、確かなお方に修理をお頼みせねばなりませず、随分以前から、
その人を探して居ったのでございます。そこへあなた様の奉納額を御覧になって、住持は
大層なお喜びで、これこそ御仏のお導きと仰せられて、江戸に帰らぬうちにお願い申して
来いとの仰せで、拙僧がお伺いに参った次第」
と、事の次第を語った。二人は、突然のことで、顔を見合わせているだけだった。僧は
調子を柔らげ、
「奉納額には『天祐』と署名してございましたが、そのお方のことをお聞きして来いとい
う住持の言いつけでござります」
「それは、この男で」
と亀次郎は言った。
「長八と申します」
長八は頭を下げた。
「長八様と言われますと、あの日本橋の茅場薬師の竜を塗られた長八様で?」
「さようで」
亀次郎が答えた。
「道理で」
僧はつぶやくように言って、うなずいていた。
こういういきさつがあって、長八は成田不動の修理をすることになった。
成田不動は木像の上に漆喰塗りをしたもので、弘法大師作と伝えられる由緒ある仏像で
ある。
長八はそもまま居残って、成田不動尊の修理に当たることになり、亀次郎一人が江戸に
帰った。
翌日、長八は新勝寺に出向いた。住持にも会った。そして、僧に案内されて参籠堂に入
った。水垢離をして身を清め、本堂に入って不動尊像をつぶさに調べた。仏体は古く黒く
冷たかった。数個所に剥落があった。ひび割れもしていた。
長八は参籠堂にこもって精進潔斎をし、直ちに不動尊像の修復作業に取り掛かった。
薄暗い本堂の奧に大蝋燭が何本もともされた。僧侶は不動尊像の前に香を焚き、念誦し
た。長八は不動尊の巨体に触れ、心をこめて修理に当たった。参籠絶食七日間、不動尊は
原形のままに、完全に修復し終わった。
不動………一切衆生の無明煩悩に向かって仏陀が叱咤する姿である。その忿怒の形相は
邪を破り正を顕わす宝釼そのものであり、不動智の磐石を信ずる宝珠そのものがあり、そ
こに人間の淨菩提を現前せしめんとする悲願が「」あった。長八はその不動心と七日間対座し
た。対談した。肌と肌を触れ合い、肌をもって不動心を知った。かって、ここに、道誉上
人、祐天上人が参籠したという。白河楽翁、二宮尊徳も水垢離したという。長八はこの人
々の必死な心にも触れたような気がした。
長八は不動尊修復が終わると、七日間水垢離をした水行場に、水にちなんだ竜の丸額を
記念に掲げて、静かに江戸に帰った。この時、長八の心には、今までと違った新しいもの
が生まれていた。これは多分に宗教的な心情のようで、長八はこの時から後、彼の仕事場
の入口に『無用の者入るべからず』と掲示し、内部には注連縄を張るようになった。自ら
の仕事を戒めるためであったろう。
成田不動の話は、後に深川不動と混同して、こんな伝説が残っている。長八の弟子で、
郷里から来ている富蔵という若者があった。至極真面目な従順な性質だったが、左官の腕
はよくなかった。そこで、腕が上がるようにと深川不動に願を掛け、毎朝はだし参りをし
ていた。そのことを知った長八は、ある日、富蔵に、
「富蔵よ、お前は深川不動に願掛けしているそうだが、それは止めた方がよい。その代わ
りにおれを拝め」
と言ったという。富蔵はけげんに思って、
「それはどういうことですか」
と聞くと、
「深川の不動さんはおれが塗ったんだ。おれが塗った不動さんを拝むよりは、塗った御本
尊を拝んだ方がよかろう」
そう言って笑ったという話である。
この話の中の富蔵は明治になってからの弟子で、深川不動は長八が手掛けたという根拠
はなく、古くからあったもので、長八が製作したものでもない。成田不動の修復と混同し
た挿話である。
この年七月、アメリカ総領事ハリスは下田に駐留して、間もなく唐人お吉が登場する。
八月、関東一帯に大暴風が襲来し、海岸は高波で浸水する。深川も被害を受け、長八はこ
の復興に当たる。この復興は意外に手間どって、十一月に及んだ。江戸の一部で、下町と
いうことで、幕府が救援の手をさしのべなかったし、したがって資材が思うように整わな
かったのが原因だった。実は、幕府はそれどころではなかったのである。
時局は険悪で、開港を契機として、幕府への風当たりは急速に激しくなっていた。不穏
な言動が伝えられていた。九月になって、アメリカ総領事ハリスは江戸出府を強行し、通
商を要請し、十月にはアロー号事件が起こり、隣国支那に戦火があがっていた。内憂外患
の時だったのである。
十二月、ようやく復興の仕事も片付いて、ほっと一息している時、川越から喜多武清の
死が知らされて来た。長八は急いで川越に走り、僅かな近親者と共に遺骸を焼いた。形ば
かりに葬式を済ませて、遺骨を江戸に持ち帰り、芝二本榎の青林寺に葬った。喜多武清、
時に八十一歳であった。
あわただしい年が暮れた。年が改まって、安政四年である。長八は師の喪に服して正月
を過ごした。師の恩寵を思った。長八はやがて仕事場にこもって、師の菩提のため、師が
最も愛した川越の喜多院に、開祖天海僧正の像を奉献することを思い立って、その製作に
取り掛かった。
川越………喜多武清はここを愛し、ついにここを離れず、文字通り終焉の地とした。関
東の小京都と言われた、閑雅な自然や沈静な風土や人情を愛したのである。
喜多院………天台八檀林の一つ、北院または無量寿院ともいう。慈覚大師(延暦寺第二
世座主円仁のこと、伝教大師の第一の弟子)の創建と伝えられ、江戸期には東叡山と称し、
僧天海が住んで、徳川家尊信の寺であった。喜多武清は、ここの広大な庭を愛した。思索
の道であり、憩いの場であった。
長八は喜多院の慈眼堂に奉祀された天海僧正像を拝したことがある。その記憶を便りに
自らの手で天海像を塗り上げようとしているのである。不動尊像修復によって得た力を、
天海像に示そうと、あえて立体像を製作していた。しかも、それに得意の彩色を施し、独
特の彫塑様式を実現しようとしたのである。
三月末、完成した天海像を抱いて、長八は荒川をさかのぼった。川舟で見る春はたけな
わで、菜の花が咲き桃が咲き、野一面の緑が眼も覚めるようだった。
川越に着くと、直ぐ喜多院に天海像を奉献し、あわせて師の喜多武清の供養を頼んだ。
その夜、城下に宿をとった。町は昔と変わらなかった。おっとりと静かに夜がふけて行
った。長八は遠い思い出に、床に入ってもなかなか眠られなかった。
夜明け方、通りを過ぎる突然のあわただしさに眼を覚ました。障子をあけて見ると、川
越藩士たちの群れが川越街道へ走っていた。
「お客様、今朝がたは街道が騒がしくって、眠れなかったでしょうね」
と、宿の女中が朝食の膳を運んで来て言った。
「何かあったのかえ」
長八は何気なく聞いた。
「急に殿様がご出府とのことで、供ぞろえも間に合わず、お侍衆が殿様のお篭をあわてて
追って行ったんだそうです」
「へえ、何か変事でもあったのかえ」
「さあ、でも、急に御評定があるとかで。何かあったんでしょうねえ」
去年の九月、アメリカ総領事ハリスが通商を要求した。幕府はそれに対して、いまだに
回答していない。そこで、ハリスは再び江戸に出向して、幕府に決断を促す態度に出た。
幕府はもはや何れかを選ばなければならない土壇場に追い込まれた。その協議のために、
川越藩主の急な出府となったわけである。
長八には関係のないことであった。長八は昼過ぎまで、川越の町をなつかしく見て廻り、
やがて川舟に乗って江戸にもどった。
江戸では、ハリスが再度出府するというので、厳重な警戒がなされていた。市中は何と
なくあわただしげであった。
幕府はついに開港通商に決した。たまたま将軍継嗣問題が起こり、天下はごうごうたる
有様であった。対立し、互いに画策し、陰謀がくわだてられ、暗躍がくり返された。国内
の混乱をよそに、下田条約がついに調印された。続いて、通商条約、大坂、兵庫、新潟三
港を開港する。世論の反撃は一段と激しくなる。外国の圧力に屈した侮辱を憤る声、勅許
を得ずして決定した幕府の独裁専横をののしる声が、国中に渦巻く。
時の老中井伊直弼はその矢表に立ち、反対論者の絶好の攻撃目標であった。すでに単な
る論議ではすまされず、密々のうちに井伊刺殺の計画がなされていた。
そういう世情の中で、長八はほとんどそのことを口にすることはなかった。彼はひたす
ら仕事に没頭した。鏝絵の製作も、これで終わりという限界がないように思われた。長八
にとっては、政治よりも大切な鏝絵であった。次々に浮かんで来る新しい試みに、彼は力
一ぱい立ち向かおうとしていたのである。
彼は額縁仕立ての塗絵に、額縁そのものを漆喰塗りにする新しい形を考え出した。それ
は黒檀とか竹とかという材質を、漆喰で表現して、いかにも黒檀のように、また竹のよう
に製作することだった。 ………これは今残されている作品に見事な成果を見ることが出
来る。中高のもの、中くぼみのもの、二重わくのもの、紋様を施したもの等々、種々ある
が、何れも長八の非凡な技術と精進の深さを示すものである。
こうして、彼は彼の拓いた新しい道を、飽くことなく歩み続けた。それは、友人福太郎
が開国必至と悟って英語習得に熱中したことや、宗三郎がやがて新生日本を想望して農村
の教育に生涯を捧げたことや、馬次郎が勤皇討幕に挺身したこと、琵琶湖運河を計画した
ことと同じであると言えよう。長八にとっては、鏝絵こそ生き甲斐であったのである。
第5章 終わり
動画