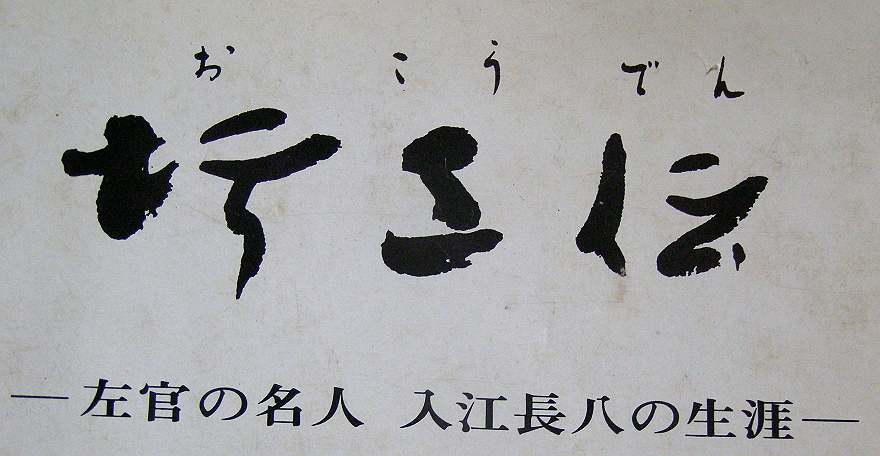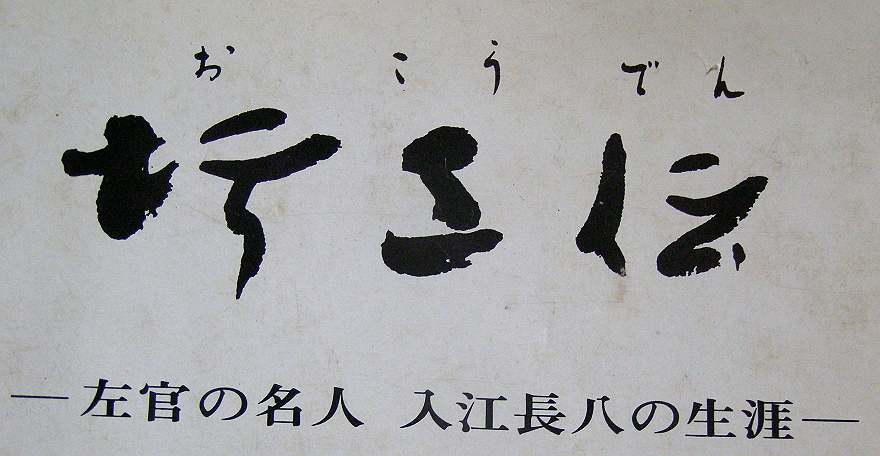須 田 昌 平著
第6章 渦 潮 の 中 で
|
世はいつか幕末から維新へ、狂乱の時代が
移っていった。江戸が東京と変わった。彼
の身辺も変わった。尊敬する義父を失い、
続いて愛する妻を失う。その寂しさの中で、
彼は、なお、おのれの芸術を求め続けた。
(四十三歳から六十一歳)
|
①
あわただしい時局のままその年も暮れた。そして安政五年である。正月だというのに、
江戸市中には物騒なうわさが立っていた。浪人者が潜入して、幕閣の要人をつけねらって
いるという。詮議が厳しくなり、市民は不安がった。浪人狩りという言葉がしきりに使わ
れて、目明かしなどが気ぜわしく歩いていた。
しかし、格別なこともなく一月が過ぎた。が、事なく過ぎたことは、尚無気味な予感を
一層かき立てていた。こんな状態の時、またも大火が発生した。二月十日の夜のことであ
った。日本橋安計町から出火して、霊岸島、佃島に及び、深川も大方灰になった。記録に
よると、十二万戸焼失とある。
この火災で、八名川町の播磨屋も焼けた。日本橋の茅場薬師も焼けた。春の突風のいた
ずらだったかも知れないが、人々は不吉な何かを連想していた。はっきり浪人者の仕業だ
と言うものもあった。
長八一家は着のみ着のままで、中橋の波江野の家に避難した。とりあえず仮小屋を建て
て、長八と職人たちが住み、火事後の復興に当たった。春とはいえ、まだ寒かった。毎日
のように風が吹いて、焼け跡の灰が空高く舞い散らしていた。
二月二十一日朝、その焼け跡の灰の上に淡雪が降っていた。荒涼たる有様だった。そん
な町筋を、あわただしく一隊の行列が東海道を上って行った。老中堀田正睦が、アメリカ
との通商条約について勅許を乞うための上京であった。
大火復興ははかばかしくはなかったが、徐々に進んでいった。時局はいよいよ険しくな
っていた。その一つの証拠のように、四月、井伊直弼が大老に就任した。
六月、やっと播磨屋の建築がすみ、病父とおたきが中橋からもどり、久しぶりに一家が
顔をそろえた。が、その頃から、江戸の市中は一段と険悪な空気に包まれるようになった。
水戸斉昭が井伊大老の軟弱外交を衝いて、幕府攻撃の火蓋を切った。これに、将軍継嗣問
題がからんで、策動、謀略、懐柔、暗闘が綾をなしていた。大老に就任した井伊直弼は、
あくまで強気に反対派を制圧する構えであった。将軍世嗣を紀州慶福と公表したのも、そ
の表われであろう。しかし、それはかえって反対派の激怒をかい、反対派の結束を固くす
るような結果になった。井伊はついに反対派の主謀者たちを処罰した。反対派は一層いき
り立った。こうした悪循環が事態を容易ならざるところへ追い込むのだった。
七月、秋風が吹き始める頃、長八は日本橋の商家の本建築に掛かっていた。もう次々と
新しい家々が建ち、前にも増して立派な町並みになっていた。こうして、江戸の町が整っ
ている時、コロリ病が流行し始める。
コロリ病というのは、コレラのことで、日本で最初に流行したのは、文政五年八月であ
った。下関に発生し、長州にひろがり、次第に山陽道を東進し、八月末には大坂、やがて
京都、伊勢と伝わり、東海道をどんどん進んで、十月には沼津に来、ここで冬を迎えると
共に終息して、ついに箱根を越えないですんだ。が、今度のものは長崎から始まり、たち
まちひろがって、七月には箱根を越え、八月に入って江戸に流行し始めたのである。
幕府は応急対策を協議したが、コロリ病に関する経験も乏しく理解も薄く、記録による
と、芳香散とか芥子泥とかという漢方薬を使ったらしい。芳香散は下痢止めの薬で、芥子
泥というのは腹痛止めの貼り薬であった。こんなことでコロリ病が防げるものではない。
江戸に入ったコロリ病はたちまちはびこり、火災後の不衛生状態もたたって、手の施しよ
うもないほどにひろがった。記録を見ると、八月初旬に流行し始め、九月まで続いた。そ
の間、五万人が死んでいる。『二日三日ハゲシキノハ一ト時フタ時ニテ命終ラス、誠ニ珍
ラシキコトナリ。前代未聞ニテ、医師モ療治ノ仕方ワカリカネ、末ニナリテハ様々薬法出
来候エドモ、始メハ見殺シナリ』という状態であった。コロリと死んでしまうから『コロ
リ病』と名付けた。悲しいしゃれである。
八名川町の播磨屋では、父親の源次郎がコロリ病にかかってしまった。永い間の病気で
体力も衰えていた。長八とおたきの看病も効なく、三日病んで死んだ。
虫が知らせたというのであろうか、源次郎は菩提寺の正定寺に行って、住職と会談し、
その時、鎮守堂建立を約束していた。死ぬ十日ばかり前のことであった。二月の大火で、
正定寺では飛び火の厄に遭って、鎮守堂を焼失していたのである。源次郎はコロリ病にか
かって死期の近いことを自覚した。鎮守堂建立の約を果たさず死ぬことを悔やんで、長八
に懇々と頼んだ。
父源次郎の死で、日本橋方面の建設を中断したが、初七日の忌をすますと、直ぐ働きに
出た。次第に秋も深まっていた。
父の四十九日忌を迎える頃には、復興の仕事も片付いていた。長八は父の遺志を果たす
ために、鎮守堂再建に取り掛かった。十月半ばに、土蔵造りの小さいながらも立派な鎮守
堂が出来上がった。長八はこの堂にたくさんの鏝絵を描いた。正面に『極楽浄土』の図、
三面に『近江八景』の図を描いた。別に、普賢菩薩の塑像を制作した。これらは関東大震
災で焼けてしまったが、その作品の名前だけは伝わっている。恐らく、成田山参籠後の長
八の制作態度を知るべき貴重な作品であったろうと思われるが、今日知る由もなく残念で
ある。
源次郎の死によって、長八は名実共に播磨屋の主人となり、対世間的にも重く見られる
ようになる。
こうなってみると、父親源次郎が口にしていた養子問題が切実なこととして考えなけれ
ばならなくなった。
九月、いわゆる安政の大獄が断行される。幕府は幕府の方針に反する言動をする者を一
網打尽に捕らえる強硬策に出たのである。大名、公卿や諸藩士から浪人小者に及ぶ弾圧で、
翌年十二月まで、一年余にわたっての大嵐であった。江戸の町にも嵐は吹き荒んだ。罪も
ない町民までがその巻き添えを食って、市民は戦々兢々の有様であった。不穏な世情は物
価の騰貴をあおった。夜盗がしきりに出没した。そして、夜となく昼となくどこかで捕り
物騒ぎが起こった。そういう中で、紀州慶福は将軍世嗣として迎えられる。後の第十四代
将軍家茂である。
そんなある日の朝、八名川町の家に馬次郎が訪ねて来た。今度は薄汚れた大工姿をして
いた。もう冬に入って、庭に落葉が散っていた。長八とおたきが落葉を掻き集めて、焚き
火をしようとしている時であった。垣根の外からのぞいている男をおたきが見つけて、そ
っと長八に耳打ちした。長八がその方を向くと、ひげだらけの顔をにやっとさせた。馬次
郎であった。
「馬次郎さん」
長八は思わず大きな声で呼んだ。
「しっ!」
馬次郎が口に指を当てた。
長八が裏木戸をあけると、馬次郎は黙ったまま素早く庭に入って来た。
「よく生きていたな」
長八はほんとにそう思った。激しい江戸や京都で捕り方の眼を潜っている馬次郎を、長
八は折りに触れて思い出し、身の上を案じていたのだ。
座敷にあがって、二人は対座した。
「よく生きていた!」
と、長八はもう一度言った。
「いや、辛うじて命をつないでいるのです」
馬次郎はそう言って、にがっぽく笑った。
「九月初めに江戸に来たのですが、京でのうわさ以上ですね。同志の者も七、八人は捕ら
えられました。私も度々あぶない目に会っていますが」
馬次郎は存外平気な様子だった。おびえたところはなかった。
「江戸には、水戸や薩摩の脱藩者が潜入しています。互いに秘密に連絡し合って、幕府の
動静を探っています。私はそれらと会って、甲州や京へ情報を伝えています」
臆面もなくこんなことを話す馬次郎に、長八はひそかに気をもんだ。
「危ないぞ」
「はい、わかっています」
「何でそんなことをしなければならないのだろう」
「幕府を倒すためです」
馬次郎の言葉が長八の胸に突き刺さるようだった。
「そんなことを言っちゃあいけない」
「いや、長八さんの前だから言えるのです」
「そんなこと、出来るのか」
「出来ます」
馬次郎はきっぱりと言い切った。そして、声を低くして、
「そのために、井伊の首を斬ります」
と言った。長八は愕然とした。そんなところまで来ているのかと、長八は考えた。
「御大老を斬れば幕府は倒れるのか」
長八は思った通りを言った。
「今はそれが先決です」
馬次郎は明快だった。
「しかし」
と、馬次郎は低い声で言い、
「こうなると、江戸には居られません。私たちの目的も、あるいは失敗するかも知れませ
んからね」
と続けた。
長八は馬次郎の言葉に素直に従えなくて、黙って聞いていた。長八は皇武合体の話を聞
きかじっていて、それで国内が収まるような気がしていた。が、そのことを言えば、馬次
郎と論争になる。今ここで論争したくなかった。論争しても始まらないと思った。
「お茶漬けをくれませんか」
馬次郎が言った。
「三日ばかり何も食べていない。追われっ放しでね」
と笑った。
おたきが運んで来た食膳に、馬次郎は待ちかねたように向かって、うまそうに食べた。
食べ終わると、
「もう一つ無心があります。普段着を恵んでくれませんか。この姿では道中も出来ない」
「京へのぼるのか」
「ええ」
おたきは冬着をそろえて持って来た。
「すまない、すまない」
そう言いながら立ち上がって、気ぜわしく着物を着た。角帯をしめて、一見堅気な番頭
になった。
「これで中仙道をひと走りです」
馬次郎はもう庭先に向いていた。長八はその後ろ姿に、一抹の不安なものを感じていた。
②
やがて秋が去り冬が来た。世間は不穏であったが、長八は再び仕事場に篭もって、静か
な日常にもどっていた。
安政の弾圧は京都、大坂にも厳しかった。十月、家茂が将軍となる。家茂はすなわち紀
州慶福のことである。十二月、幕府は京で捕らえた志士たちの審判を始め、厳しい処罰を
する。こういうあわただしさのうちに、安政六年となり、弾圧は一段と苛酷になって行く。
走り出した悍馬に、鞭を打ち振って一層暴れ狂わせるような有様で、井伊の圧政は続いて
いた。
二月、またも江戸は大火に見舞われた。この災禍では、青山、四谷、牛込、早稲田の山
手が焼けた。が、長八はこれには関係なかったようで、相変わらず仕事場での鏝絵を続け
ている。思うに、左官仲間にもおのずから範囲が決まっていて、山手には長八の勢力は及
んでいなかったのであろう。
山手の火災が復興して、早や六月の暑さであった。この年、山王祭、神田祭が練物や装
飾を許され、曲輪に入ることも認められて、町人は気負い立つはずなのに、案外に簡素な
静かな祭りで終わった。安政の弾圧が続いていて、町人たちは、そば杖を食うことを恐れ
たからである。
七月、暴瀉病流行。暴瀉病とは赤痢やチブスのことらしい。先年のコロリ病についでの
悪疫で、この時も多くの死者が出た。が、そんなことよりも、弾圧の手の無惨さの方が、
もっと人々の耳目を震撼させた。弾圧はいよいよ中心人物に向けられ、八月、水戸斉昭、
尾張慶篤、一橋慶喜らは謹慎となり、すでに捕らえられていた頼三樹三郎、吉田松陰らは
十月に処刑された。その間に、梅田雲浜は獄死している。こうして井伊の勢力は圧倒的に
なっていくが、しかし、不穏は一層底深く、陰湿にうごめいていた。十二月、水戸浪士が
井伊打倒ののろしを挙げた長岡事件はその証拠とも言えよう。
こうして悪魔のような一年が過ぎた。この一年間、長八はとり立てた仕事をしていない。
仕事場に篭もっていながら、その作品すら見当たらない。そこには、時世に対する長八自
身の苦悩があるような気がする。大きな嵐の中で、僅かにおのが心をかばうことで精一ぱ
いであったかも知れない。あるいは、おのが生命ともしていた鏝絵に不安や疑問を感じて
いたのかも知れない。それは、つづめて言えば、この狂瀾怒涛の世に芸術をどう定置すべ
きかという問題になるのかも知れない。今私たちはそれを的確に指摘する方法を知らない。
長八はこの時代のことについては余り語らなかったからである。
明けて、安政七年となる。長八は相変わらず仕事場に篭もりがちの日々であった。話題
になるようなことは、たった一つ、遅い年賀の便りが宗三郎から届いたことであった。意
外にも、宗三郎は故郷の那賀村に帰っていた。手紙には、江戸を離れる時、会って別れる
つもりだったが、物騒な世の中で、とうとう会えずに帰ったというわび言と、大獄騒ぎで
江戸にとどまって修学することの難しさを感じ、思い切って帰郷することにしたというこ
とがしたためられていた。『わが家を改造して学塾を開くことにした。村の子弟を教育し
て、他日に備えようと思っている』と簡単に書いてある。長八は宗三郎の気宇を思った。
それは、福太郎や馬次郎の気持ちとも相通ずるものであった。それは、故郷の正観上人の
気持ちでもあった。長八は自分の中にも共通なものが流れているような気がした。
宗三郎は故郷へ帰って学塾を開いた。『三余塾』と命名した。三余とは三種の余暇を言
う。『冬は歳の余、夜は日の余、陰雨は時の余りなり。冬と夜と雨と、これをもって学に
従うなり』と彼の学塾記に示している。つまり、春夏秋は勤労に費やし、昼は働き、晴れ
の日も労働する。その余暇を勉学するという仕組みで、産学兼修の教育である。当時とし
ては異色の方法で、やがてこの塾から、各地の指導者が輩出されるのである。
長八は宗三郎の手紙を読み終わって、しばらく感慨に沈んだ。宗三郎もついにおのれの
道を選んだと思った。福太郎は下田で英語を勉強して、新しい開国日本を夢みている。馬
次郎は今も勤皇攘夷に奔走しているであろう。伊豆の片田舎で育った四人の少年が、馬次
郎を除き不惑の年齢を越え、それぞれの道を歩いている。そういうことが長八には不思議
に思えた。
誰が幸福なのか、誰が立派なのか、それは今はわからない。が、しかし、四人が四人と
もそれぞれの人生をつくっていることに違いはない。長八は、それがどうであれ、人それ
ぞれに運命に導かれているような気がした。そして、もはや四人とも引き返すことの出来
ない地点にまで来ているように思えた。
正月が過ぎて、新見正興ら幕府使節がアメリカに出掛けた。咸臨丸がこれに随行した。
幕府の開港策はもはや引くに引けない所に来ていた。が、反対側の人々も引くに引けず、
強硬に反撃するしかなかった。その険しい対立がついに破裂した。三月三日の井伊大老刺
殺事件がそれである。三月三日は上巳の節句であった。折りから降り積もった春雪を乱し
て、桜田門外に浪士たちの凶行が行われた。一瞬のことであった。さしもの権力者井伊直
弼も、この一瞬に短い生涯を閉じた。これを境目として、幕府の勢威は急速に衰え始める。
三月十八日、万延元年と年号が改まる。四月、和宮降嫁を奉請。五月、咸臨丸帰る。
長八はそういう騒がしい世の様を無縁なものとは思っていない。むしろ心を痛める日々
であった。しかし、長八にはそれらのことに介入する気持ちはなかった。この点が宗三郎
や馬次郎などと違っていた。彼はただ制作に心を注いでいた。世の様が憂わしいと思えば
思うほど、制作に打ち込むのだった。
五月、白象の塑像を制作して、これを菩提寺の正定寺へ納めた。白象は普賢菩薩の愛用
の動物で、さきに奉納した普賢像に付属させるためであった。
この頃、長八は仏教に心を傾斜させていたようである。もともと長八には仏教的な素地
があった。淨感寺の正観上人の感化、三島の茂平との交遊、父源次郎の信仰。が、そうい
う素地に更に仏教的な理解を加えるようになったのは、祐天寺の修築であろう。そして、
成田不動の参籠であろう。それは、初めは人間的修養として、後には次第に信仰としてと
らえているようである。その気持ちが決定的なものとなったのは、岳父の死と、それにと
もなう正定寺鎮守堂の建立であったと思われる。正定寺の普賢菩薩を制作した彼は、仏教
書により、住持の講説により、普賢のみならず数々の菩薩如来の精神を知り得た。単なる
偶像ではないことを知った。仏像を単なる姿体としてでなく精神として権化として見なけ
ればならないことを知った。仏教の底深さを知った。一年後に、白象を追加したという事
実が、長八のそんな気持ちを物語っているように思える。以後、長八は仏像制作にかなり
熱意を示すようになる。
しかし、恐らくそれだけではなかろう。年齢のせいもあるかも知れない。いや、それよ
りも、この険しい世相の中で、市井の無力な人間として、仏に眼を向けざるを得なかった
のではないか。
八月、水戸斉昭が死ぬ。十月、遣米使節帰る。十一月、和宮降嫁決定、十二月、アメリ
カ書記官ヒュースケン暗殺される。
年が明けて万延二年。二月、文久と改元。ロシアの軍艦対馬に上陸。五月、水戸浪士が
英国人を傷つける。六月、毛利利敬の公武合体、開国遠略策を朝廷に進言。七月、品川に
各国公使館を許可。十月、和宮降嫁。
こう並べてみると、時の動きの激しさがひしひしと身に響くような気がする。それは、
底に渦巻き流れていた潮流が表面にあらわれて、すさまじい勢いで高くしぶきをあげてい
るような、怒濤のうなりを発しているような様相である。
翌文久二年正月十五日、老中安藤信正が坂下門外で襲撃される。二月、毛利敬親が幕政
改革を進言する。三月、島津久光上京。その月二十三日、寺田屋騒動。五月、大原重徳が
勅使として江戸に下る。七月、幕政改組。八月、生麦事件。閏八月、毛利敬親攘夷奏請。
島津久光時務策建言。九月、朝議攘夷決定。十一月、三条実美勅使下向。十二月、高杉晋
作ら英国公使館に放火。
こうして急角度で時代が動いて行った。ここには複雑な要因がからみ合い、攻めぎ合っ
て、変幻不思議な姿を見せ、それがどう結末を示すか判断しかねる状態であった。
長八はこの年、一枚の山水塗額をつくった。『春江帰帆』と題するのどかな風景で、お
よそこの時代にふさわしくない作品である。不思議なことに、これには乾道山人と署名し
ている。宋画風の構図で、遠く白雪をいただいた山があり、凪いだ海に白帆が三つ浮かび、
それを近景としたありふれた風景画である。長八はどうしてこのような絵を描いたのであ
ろうか。時勢とは全く無縁なこの絵は長八の何を意味しているのであろうか。私はこう想
像する。長八は時世に苦悩している。一人の庶民としては、ひとえに平和を願うのみであ
る。そこにある権力争奪も大義名分もいらない。そういうはかない悲願が、天地自然の静
穏さを心に描いたのではなかろうか。それはあるいは、長八の一種の宗教画であるかも知
れない。そう思ってみると、この鏝絵は明快ではない。色調もやや暗い。春江というには
少々濁っている。そんな感じさえする。
さて、文久三年である。いよいよ動乱期である。くわしい事件はもはや不要である。勤
皇と攘夷が結びついて、それがやがて攘夷が倒幕に変形して行く。天下がそのために二分
される。藤本鉄石らの挙兵、生野の変。いよいよ世は騒然としてくる。
元治元年十一月、幕府は長州征伐の軍を起こす。江戸の町を威風堂々と旗本の一隊が東
海道をのぼって行った。三条実美ら長州派の公卿が捕らえられた。一方では武田耕雲斎の
水戸浪士が謀反していた。もはや、幕府の威力は地に落ちていた。討幕の計画は着々と進
められていた。そして新しい年を迎えた。元治二年である。一月早々、高杉晋作らが長州
で兵を挙げた。幕府は再度長州征伐を起こす。四月、改元して慶応元年。五月、将軍家茂
上京。そして、長州征伐失敗。薩長連合。続いて将軍家茂の死去と急速に時局は変転する。
そして、慶応元年はめまぐるしく過ぎて、いよいよ倒幕の大きな潮が渦巻き始める。
③
この三年間、すなわち元治元年から慶応二年までの三年間、長八は何をしていたのかほ
とんどわかっていない。作品としては僅かに『三保松原富岳の図』が残っているだけで、
しかも、慶応二年秋の作である。
この塗額は手前に彎曲した三保の松原を配し、清水港を描き、袖師の浜、薩陀峠、そし
て峠の上に白雪の富士、空には朝日が昇った風景画である。これは模写ではなく、実景描
写であることは一見してわかる。
すると、長八はこの風景をいつ写生したのであろうか。若い頃の画稿をもとにしたもの
か。しかし、その描写は適確で、かつ新鮮である。あるいは、この時期旅をしていたので
はないかという想像もされる。
しかし、それよりも、この塗額の持つ意味を考えたい。私の感想は二つある。一つは写
生の要領を示していること。一つはこの構図や描写に見られる活力である。
写生については、後の作品にも見られるが、恐らく円山応挙などの影響であろう。長八
は他流でも勇敢にその技法を取り入れているから、そんな気持ちで制作したと思われる。
ただしかし、単なる模倣ではなく、彼の持つ狩野派の強い筆致や簡潔な技法を十分に表現
しているものである。
そういう制作態度は、彼の精神的な意図と結びついているようにも思われる。それは構
図の上で、広い清見潟の全景を捉えていること、海と富士と朝日を配していること、色彩
の上でも筆致から見てもそこには雄健な情感がうかがわれることなど、前作『春江帰帆』
の暗さ弱さはなく、新しい朝を迎える生気が躍動している。そこに、長八自身が、新しい
時代を迎える喜びのようなものを感じていたのではないかと思われるのである。
長八は一人の市井人として、表には現わさないが、やはり時勢を見ていたのであろう。
そして、混沌とした世相に憂いを持って、『春江帰帆』のような作品が出来、一筋の明る
い光明を予感するようになって『三保松原富岳の図』が生まれたのではないかと思うので
ある。そして、極めて寡作であったというところに、彼の深い悩みがあったと言えるので
あろう。
あるいはその中に、宗三郎が慶応二年七月、死んだ影響もあったかも知れない。三余塾
には遠近から教えを請いに来る者は絶えず、安政六年開塾以来、万延、文久、元治、慶応
にかけて繁昌し、幾多の秀才を輩出して幕を閉じたのである。
慶応二年十二月、一橋慶喜が将軍となる。その月、孝明天皇崩御。そして、慶応三年、
幕府最後の年となる。一月、明治天皇践祚。続いて、王政復古、大政奉還、明治政府樹立
と、足早やに新しい世に変わってゆく。
そんな中、長八は馬次郎のうわさを八橋の善吉から聞いた。先年類焼した茅場町の薬師
堂の再建について、関係者が会合した時、長八も左官工事者として出席したが、結果は資
金不足で再建は延期となった。その帰り道、八橋を訪ねた時のことだった。
八橋の善吉は、薬師堂再建の熱心な世話人の一人だが、この日はあいにく所用があって
欠席した。長八はついでの足で、今日の会合の様子を知らせるつもりで、廻り道をしたの
である。
八橋というのは新大橋のたもとにある茶店で、当時、八橋だんごが看板で大繁盛してい
たという。当主の善吉は長八より二つ三つ若く、商人ではあるが信心深い男で、長八とは
格別親しかったようである。
長八は八橋ののれんを潜った。顔見知りの女中が直ぐ善吉に知らせた。直ぐに座敷に通
された。早速だんごと茶が出る。食べながら今日の会合の模様を話す。
資金不足で延期になった結末を聞いて、善吉は嘆息まじりに、
「そんなことではらちが明きませんな。早速世話人みんなで手分けをして金集めをしなく
ちゃあ」
と言った。
それから四方山の話になったところで、善吉が京の話を始めた。
「京では諸国の脱藩者が随分集まっているそうな。それが幕府方と衝突して、毎日のよう
に血生ま臭い事件が起こっているそうな。天朝さまを大切にすることは結構だが、どうも
天朝さまを笠に着て危険な火遊びをしているようで、いやな世の中になりました」
という話から、
「突飛もないことを考えるもので、私は驚いたんですがね。加賀の国から近江の湖をつな
ぐ疎水をつくって、米や雑穀をどしどし京、大坂へ送り込もうという話があるそうな」
長八もそれを聞いて驚いた。
「へえ」
とだけ言った。何程の距離か見当もつかないが、とにかく何十里の道のりだろう。それ
に湖水面と海面の高低差を考えると首をひねざるを得なかった。
「そんなことが出来るものですかねえ」
善吉が言った。
「さあねえ、見当もつきやしない」
と長八はあいづちを打った。
この話の加賀というのは誤伝らしく、敦賀の間違いのようである。この誤伝は、百万石
加賀藩の後援を得ての計画からきたのであろう。この疎水は北前船の貨物を敦賀港に集め、
川を閘門方式でさか上り、山を刳り抜いて水路トンネルを作り、琵琶湖を航行、瀬田川な
どを通じて京、大坂へ早く安全に運搬する方策であった。
「それがねえ」
と、思いついたように善吉が興ありげに言った。
「この意見を述べたのが、何でも伊豆の出身だと言うことでしたよ」
善吉は長八が伊豆の人間だということを知っていたから、こういう話になったのだろう。
「伊豆の者ですって?」
長八は思わず言った。馬次郎のことをちらっと思い浮かべた。
「心当たりはありませんか」
「ないねえ、で、名前は?」
長八にそう言われて、善吉は思い出そうと腕を組んだ。
「何と言ったかなあ」
と小さくつぶやくように言った。
「確か、小沢と言ったような気がするが」
と首をかしげ、
「そうだ、小沢一仙と言った」
善吉は腕組みを解いて膝をたたいた。
長八は予想が的中したのに、へどもどした。
「やっぱり」
と腹の中でつぶやいた。
「知っているのかね」
善吉が長八の顔色を見ていた。
「いや、いや」
長八は手を振って打ち消した。
馬次郎が小沢姓を名乗っていたことは知っていた。しかし、あの忙しい体でいつの間に
運河構想など、長八は半ばあきれ、半ば彼らしく思い、また、不審に頭を傾けたた。
馬次郎は若い頃、黒船が下田へ来たというと、若い仲間を誘って見学に行った。そして、
無難車船を考案し、江奈村が掛川藩の飛び地だったことから藩主太田資始に建白して百石
侍の身分を得たことがあった。奇抜な着想と実行力を持つ男であることを、長八は思い起
こした。たぶん資始が老中の時、外人に接して得た知識からの発想であろう。
「何でもその父親というのは、江戸でも知られた宮大工だそうですよ」
「馬次郎に違いない」
と、長八は独りうなずいて確信した。
慶応三年といえば、長八はいつか五十三歳の初老になっていた。おたきは四十六歳であ
る。二人の生活も二十年の歳月を経ていた。二十年といえば長いが、二人の生活はいろい
ろなことがありながら、何の不満もない静穏なものであった。が、ついに子供に恵まれな
かったことが、たった一つの傷であった。
新しい時代が眼の眼に近づいて来ることを感じると、急に養子問題が気になって来た。
もう年齢的にも切迫していた。せき立てられるように、二人は養子について話すようにな
った。
養子の候補は三人あった。一人はおたきの兄の子清太郎、一人は波江野亀次郎の次男竹
次郎、もう一人、新たに挙げられてのが、長八の妹の子幸太郎であった。
清太郎は播磨屋の血を引くたった一人の男で、それゆえに長八は強く清太郎を支持した。
が、おたきは反対した。自分の身内から養子をとることが心苦しかった。その上、清太郎
は遊び好きでとても長八の跡を継ぐ器でないと、おたきは信じていた。そのおたきは、長
八の血統の幸太郎を推した。気立てが優しくて、働き好きであった。何よりも長八に親し
みを持ち、長八を慕っている子だった。ところが、これには長八が反対した。年が若過ぎ
るという口実だが、ほんとうは播磨屋という血筋を大切に考えていたのである。おたきは
それなら竹次郎をと言う。竹次郎ならば、気心はわかっているし、血はつながらなくても
父源次郎と亀次郎との友情からも、はるかに幸太郎よりはいい。長八は、そうは思うけれ
ども、それをもこばんだ。ひとえに播磨屋の血を絶やしてはならないと、かたくなに思っ
ていたのである。
夫婦の間で幾度となく同じようなことが繰り返された挙げ句、湯島から省三の子清太郎
を迎えることに決まった。おたきが折れたのである。長八の播磨屋思いの一徹さに負けた
のである。
清太郎のことについては、おたきの死後に迎えた後妻のおはなの連れ子だという説もあ
るが、これは明らかに誤りである。播磨屋の過去帳によれば、明治四年六月、清太郎の子
が生まれて直ぐ死んでいる。後妻のおはなが播磨屋に来たのは、その翌年十一月であるか
ら、つじつまが合わない。
しかし、清太郎は省三の子であったという証拠は見当たらない。省三の子としたのは私
の独断である。なぜそんな独断をあえてしたのか。私は、長八の気質から、播磨屋という
家門のことから、そして長八の周囲の人間関係から、省三の子とする以外にないと判断し
たのである。尚、当時は戸籍がなかったので、誰の子であるかがわからない。ただ、前後
の事情から手繰る外はなく、結局省三の子と考えざるを得なかったのである。
清太郎の年齢もはっきりしていない。が、恐らくこの頃二十歳前後で、間もなく嫁をと
ったと推定される。嫁の名はおさくと言って、これも年齢、素性はわかっていない。ただ、
遊び場にいた女らしいということだけしか伝わっていない。
④
この年、もう一つ変わった伝説が伝えられている。それは長八が相撲の争いの仲裁した
という話である。
その頃の江戸相撲は、春秋二回両国回向院で興行されていた。その秋場所のことのよう
である。興業に先立って番付が発表されるのは今も同じである。この時、陣幕と境川が争
いを起こし、場所に出る出ないの悶着となり、ひいては部屋の対立となって、不詳事件に
まで発展しかねない雲行きだった。親方や世話人が調停しようとしたがうまく行かず、そ
の解決を長八に依頼した。
長八は播磨屋の当主として、父親からの引き続いての地元代表として、相撲の後援者で
あったらしい。長八は頼まれて引くに引かれず、四方手を尽くして和解させ、めでたく秋
場所を開く運びにしたという話である。
どんないきさつであったか、どう説得したのか、一切不明であるが、当時の力士がうた
ったという甚句が伝えられている。
『東に廻れば 陣幕で
西に廻れば 境川
今を盛りのお関取
仲をとりもつ 左官長八』
というのである。
ここに出て来る陣幕と境川については、年代が食い違っていて、争いの原因であった大
関争いにはならないようである。すなわち、陣幕は安政五年に入幕、慶応二年冬三十八歳
で大関となっており、明治二年まで四年間大関を勤めているが、一方、境川の方はその頃
は番付に名も出ていない。陣幕に対抗していたのは不知火という力士で、これは陣幕より
二年早く入幕、文久二年に大関と一足ずつ陣幕より早く出世をし、慶応三年には西の大関
を張っている。とすると、境川ではなく不知火だったということになる。よくよくたぐっ
てみると、不知火の親方が境川という年寄であることがわかった。そこで想像されること
は、不知火が引退して境川を名乗ってから後に出来た甚句か、あるいは、陣幕と不知火の
大関争い(ここでは、東の大関を争ったようである)に、不知火側の親方境川が表に出て
いたのかも知れない。境川の現役時代に大関だった関係で、こんな甚句になったのではあ
るまいか。
これらのことについては、『相撲今昔』の著者池田雅雄氏にお骨折りを願ったことを付
記しておこう。
この年から『おかげ参り』が流行し、たちまち全国にひろがる。『おかげ参り』という
のは、伊勢参りの変形で、集団を組んで伊勢参りの道中をすることを言う。始めは五年目
ごとだったが、幕末の及んで毎年となり、集団は年ごとに増加した。農民の不満のはけ口
であったようである。また、『お降り』といって、各地の神社の守り札が天から降って来
るという異様な騒ぎもこの頃各地に見られた。これら一連の大衆の動きは、少なくとも時
代の不安を象徴したものと言える。倒幕派の謀略と見る向きもあったが、それもまた民心
の不安動揺の証拠でもある。
年が変わって慶応四年、すなわち明治元年である。一月、鳥羽伏見の戦、そして幕府討
伐令。早くも二月には東征大総督が京を進発し、東海、中仙、北陸の三道を江戸に向かう
のである。
江戸は重箱を引っくり返したような大混乱となり、武士だけではなく、町民までがこの
混乱の中に巻き込まれる。江戸を決戦場と考えて息まく、幕府側の武士たちは、血まなこ
になって戦争の準備を始める。これに加担する町民もある。荷車を引いて田舎へ逃げよう
とする人がある。うろたえて仕事も手につかない人もある。物価が急騰する。物盗りがは
びこる。
東征の官軍が一日一日と江戸に近づくにつれて、市民はあわて、いらだち、おびえた。
播磨屋でも日ごとの不安は隠せなかった。商売どころではなかった。しかし、長八は黙
りがちに、毎日のように仕事場に入っていた。
時は早や春たけなわであった。官軍は箱根を越えたという。不安は一層江戸の町をかき
乱した。人々は桜の花も見る余裕はなかった。
そんな時、長八は馬次郎が捕らえられたといううわさを聞いた。馬次郎が以前から討幕
運動に明け暮れていたことは知っている。東征軍に加わるだろうことも想像していた。が、
よもや江戸に入らないで囚われの身になるとは頷けぬことであった。そのうわさは「若い
公家に騙し入れ、勅使と偽って中仙道から甲府へ進み、民衆からしこたま金品を巻き上げ
た」というのだ。馬次郎の物取り欲しさの単独犯であった。あの男は国を憂いて行動して
いたはずだと、長八は強く打ち消した。
実は、琵琶湖運河計画は平和時でなければ着工出来ない。たまたま京都は大政奉還など
で混乱していると聞き、機を見るに聡い馬次郎は京都に出た。そして甲州神主の親玉武藤
外記の諜報活動、宮大工、器械師と称しての兵器売り込みなどで、高松保実とは知古の間
柄であった。高松家は三条家系統の中流公家で、三条実美が長州と関係があることは周知
の間柄であった。そこへまず身を寄せると、館林藩中老格の岡谷繁実を紹介された。
館林藩主秋元志朝が長州藩からの養子であることから、藩中老格の岡谷繁実と馬次郎は
三条家系を通じて出会うのである。岡谷は御陵の修復、「名将言行録」を著すなど秀才で
ある。これ前、第二次征長の仲裁役をかって出る。が、成功したかに見えた仲裁案も、京
都での幕府と朝廷の立場が逆転して反古となり、岡谷は藩から蟄居謹慎、幕府からは永の
暇という厳罰が下される。それを潜って京都へ出て来たたのである。そして、左大臣近衛
忠房に、旧藩主志朝の冤罪や足利学校や学習院の再興を申し出る。この学習院復興につい
ては馬次郎も関係していた記録がある。
高松隊の挙兵理由は、「関東要衝の地は甲州である。東山、東海両道の咽頭の地である
から、まず甲府を取るのが上策である。馬次郎は甲州人であるからこれを嚮導として」と、
のちに繁実が口述している。
また、偽勅使条目とされるものは、年貢半減令なるものが含まれ、朝廷深く暗黙のうち
に認められていた。実は朝廷内部では半減令を公布したなら、軍資金提供者、米相場商人
の協力が得られないという感触を得ていた。
三条実美を通じ今や御沙汰が降ろされるという矢先、挙兵を見合わすようにとの返事に、
高松保実の嫡男実村と馬次郎は御所に出た。そこで岩倉具視に会って大激論となり、馬次
郎は顔面朱となって眼をきっと岩倉に向け、「私の素志とは甚だ違う。私も天下の有志で
ござる。皇恩に尽さんと身命を擲って錦を挙げようとする赤心なのに」と滔々述べ立て、
躍り上がって飛びかかろうとして、囲ってあった屏風を転倒させた」という。ここで三条
実美に出兵を制止されるが、すでに出兵準備がしてあったことから一月十八日暁、十四人
で京都を脱走したのである。
馬次郎は小沢雅楽助と名乗って総帥高松実村の後見役、岡谷繁実は斯波弾正を名乗り、
家老格の参謀役となった。
僅かな人数の隊も、近江八幡の弘誓寺が高松家の縁戚にあることから資金、また彦根城
では兵器を調達、行く先々で神主などで膨れ上がり、甲府では三千人の隊となる。これも
保実と武藤外記が通じての下工作からである。
繁実は甲州入りした二月十日、「江戸を抜くのは後にして、横浜を掃攘せん」と演説し、
京都へ錦旗と綸旨の要請をする。これが高松隊弾圧の原因と繁実は自ら述べる。そして翌
十一日、一仙が甲府城代と折衝中、東海道鎮撫使の使者黒部治之助が来て「偽勅使」と断
定されるのである。なお、一月二十三日の段階で、朝廷は保実に「実村を引き戻すように」
と要請されている。それでも二月十五日には石和まで進軍して反乱軍を鎮圧し、蔦木宿で
大方は解散する。
ここまで同行する馬次郎だが、東山道が封鎖されていることから、一徹な彼は東海道か
ら京へ出て弁明しようと、共に参加した弟の平太郎と出る。そして、韮崎付近で捕らえら
れたのである。獄中彼は「当殿の恥辱は、朝廷の御恥辱」と言い放ち、「京都で公明正大
の裁きを受けたい」と言上した。一方、実村や繁実らは京都に入る時、烏帽子姿に正装し、
「凱旋」したという。
こんな話は維新の中では降るほどあったことだが、長八にとって単なる話として聞き流
せないことであった。無念であった。
間もなく、官軍は三方から江戸に迫って来た。江戸では決戦派と見られる旗本たちが眉
を上げていた。市民は戦争必至と見て、それぞれ生きた心地もなかった。
「どうなることでしょうねえ」
と誰もがそのことに心をとがらせていた。
「さあ、どうなることやら」
返事は決まっていた。長八夫婦も、そんな言葉を毎日のように言い交わしていた。
すでに養子となって八名川町の家に来ていた清太郎も落ち着けなかった。昼も夜も家に
は居らず、遊び呆けているようだった。こんな時代の若者の不安がこういう形で現われるの
だと、長八は清太郎に同情的であった。かって長八自身がこうだった時代がある。黙って
見ていてやるべきだと、長八は思うのだった。が、おたきはそうはいかなかった。おたき
にしてみれば、肉親の甥である。長八に気に入られるような生活をしてほしかった。それ
を気にもせず、今までの不しだらな生活を平気で続けている清太郎が気に入らなかった。
おたきは時折り清太郎を説諭するが、さほどの効果はなかった。
清太郎には、養子に来る前からの馴染みの女があった。「嫁にしたい」と言い出したの
で、長八夫婦は、一しょにしたら落ち着くだろうと考えて、茶屋勤めをしていたおさくを
播磨屋に入れた。すると、清太郎はすっかり落ち着いて、神妙に家で暮らすようになった。
東海道を下って来た官軍は品川に来ていた。戦争が今日にも始まりそうな江戸の空気だ
った。
「家財道具はいつでも運び出せるようにまとめて置く方がいい」
と、長八は家族の者に言い渡した。あわただしい日が過ぎていった。
「いよいよ戦争が始まるそうな」
外から帰って来た清太郎がそんなことを言った。真相はわからないが、江戸の町ではそ
んなうわさで持ち切っていた。旗本小者が上野の山に立てこもったという。上野へ砲弾を
積んだ車がひっきりなしに行くという。
その日、突然、上野の山に大砲の音がとどろき、市民は「すわ、戦争!」と色めいた。
早やばやと逃げ出す者、家財を持ってうろたえ廻る者、道は一度にごった返した。この日
まで江戸に残っていた者は、口では強いことを言っては居るものの、皆逃げてゆく先がな
かったり、金がなくて行けないという人々であった。
やがて、上野の森に煙が湧き立ち、煙の中から焔が燃えて、いよいよ戦争かと市民の心
を暗くした。が、市民が逃げ惑ううちに、砲火は止み、上野の煙も薄れ、間もなく、
「戦争は終わった」
と誰ともなく言い触らされた。
元の静けさに返った市中に、異様な服装をした官軍の兵士たちが闊歩し始めた。江戸は
官軍の支配下になっていたのである。
四月、東征大総督が江戸城に入り、ついに幕府は倒れた。が、江戸は残った。くやしが
る者もあったが、ほっとした者も多かった。町中にはまだ物騒な事件が起こっていたが、
市民の気持ちは意外に平穏であった。
こんな頃、馬次郎が甲府の山崎刑場で斬首されたと聞いた。江戸城無血開城三日後の三
月十四日、享年三十九歳であった。後日伝わるところによれば、高松実村や岡谷繁実らは
軽い謹慎処分で終わり、維新の功労者となる。長八は、身分差というものがこれほど命の
軽重を左右するかと嘆いた。そして、思うたび甲州の方角に手を合わせ、明治の世まで生
き永らえたら、その才能を充分に発揮できたろうにと口惜しかった。
七月、江戸を東京と改称した。いずれここが都になるとうわさされたが、江戸遷都を最
初に提案したのは岡谷繁実その人であった。八月、天皇即位。九月、明治と改元。この月、
新政に抗して、榎本武揚らが幕府の艦船を奪って東北に走った。東北鎮圧のため、官軍の
部隊が動き出す。やがて、会津若松が陥落し、十月までに、東北各地の反乱もしずまり、
いよいよ明治新政の時代に入る。
新しい時代に入っても、人間の気持ちなど、そう簡単に切り換えられるものではない。
長八は依然として、八名川町の仕事場に息をひそめるように暮らしていた。新しい時代が、
ほんとにいいのか、わるいのか、長八にはわからなかった。従って、どう処してゆくべき
かも知らなかった。そして、彼は彼なりに悩み続けていた。
長八の三人の友が、それぞれ時流に敏感に行動したのに対して、彼だけは何も出来なか
った。時流にうとかったのだろう。時流に巧みに乗るすべを知らなかったのだろう。伝説
はこのことについて何も語ってくれない。が、私はこう観察する。長八は時流に無関心で
あったのではなかろう。しかし、彼は時流に乗ることは考えず、ひらすら鏝絵に眼を向け
ていたのだと。長八は身のほどということを知っていたようである。鏝絵が身のほどで、
それ以外は考えていなかったのではないかと。世の中を変えるような大きい動乱に対して、
無関心であるわけはないのだが、自分のかかわることではないと考えていたのであろう。
逃避ではないが、一見逃避のごとくであった。ただ自分の芸術を死守することに心をくだ
いた。実は逃避どころではない。体当たりの懸命な執着だったのである。それゆえに、彼
は時流に乗らなかった。時流に乗ることを恐れた。いや、時流に乗る愚かさを厳戒してい
たのではなかろうか。とは言うものの、潮のように寄せて来る時代の動きに、ともすれば
押しつぶされそうな自分を、何とか支えようと苦慮した。そんな長八の心情を、福太郎や
馬次郎や宗三郎と対比して、さげすみ笑うべき理由があるであろうか。すでに二人は鬼籍
に入っている。生きている有り難さを喜ばないわけにはいかなかった。
⑤
明治二年春二月、江戸は東京と改め、若い天皇を迎え、新しい時代の波に洗われるよう
になる。とは言うものの、古い町が急に新しくなるはずもなく、当然のことながら、新旧
の摩擦が随時、随所に現われた。官兵は時を得顔に威張っているように見えた。市民はこ
れを田舎者として軽べつした。
しかし、とにかく暗雲は吹き払われて、市民はようやく陽の目を見る思いがした。長八
の心にも生気がもどった。事の善是善悪はどうであれ、庶民の願うものは平和な生活であ
ったのだ。
長八はよみがえったように制作欲がわくのを感じた。そして仕事場にこもった。しかし
一時空白だったものが、そうやすやすと元にはもどれないで、もどかしい日々を送った。
戦火はなかったが、江戸の町は荒れていた。東京となり新都と変わっただけで、これか
ら新しい建設が始まろうというのである。左官の仕事も徐々に忙しくなっていた。それだ
けに長八の制作意欲ははばまれ、もどかしさが重なった。
ある日、向島の花便りを聞いて、長八はおたきを誘ってぶらりと出掛けた。
「随分花見なんぞしなかったな」
「ほんとに。忘れたように」
二人は長い間のうっとうしさを思い出した。
「長い間、いやな思いをした」
「無事にこうして花見をするなんて、考えてみると夢のようですわ」
と、道すがら語り合った。一しょに歩くのも全く久しぶりのことだった。
向島は桜が満開だった。花が風に誘われたように影もなく散っていた。人々は楽しそう
に歩き、群れて踊り、歌っていた。長八夫婦にはそれが物珍らしかった。二人は微笑を思
わず交わした。その人群れの中に、異様な格好をした官兵の姿が見えた。
長八は人群れの中で何かを探していた。時々立ちどまって、どこかを眺めた。おたきは
そんな長八に寄り添うようにしていた。
二人はやがて浜町に出た。
「八橋へ寄って行こう」
と長八がおたきをかえり見た。
「私なら大丈夫よ」
おたきは長八が自分が疲れたと思って、いたわって八橋に寄ろうと言い出したと思った。
「いや、外の用事があるんだ」
「それなら」
二人は大橋を渡って、八橋ののれんを潜った。
「やあ、久しぶり」
丁度主人の善吉が店に出ていた。眼ざとく長八を見て声を掛けた。
「向島の帰りだよ」
長八はそう言って、手近な場所に腰をおろした。
「おかみさん、お久しぶりで」
善吉はおたきにも愛想よく言った。
「私の方こそしばらくで」
おたきはていねいにお辞儀をした。
「奧へどうぞ」
善吉が気がついたように促した。長八はそう言われると、
「それじゃあ遠慮なく」
と腰をあげた。
「どうぞ、どうぞ」
善吉が手の平を見せて、奧へ招じ入れた。
川に面して、開け放った障子の向こうに、対岸の家々や桜が見えた。
「二人で花見とは珍しいことですな」
善吉は布団をすすめながら笑っていた。
「ほんとうだ」
長八とおたきも顔を見合わせて笑った。
八橋の女房のおよしが、茶の支度をして持って来た。四人でなごやかに茶をすすった。
「向島は満開でしょう」
「そうだねえ。明日あたりは散ってしまやしないかねえ」
「桜は全く一っ時ですからねえ」
「何でもそうだが、桜も七、八分ってえところがいいんじゃないかねえ」
「今日なんぞ、もう散ってる桜もあるんだから、かえってさびしいよ」
「咲いたと思えば散って」
「無常というのかねえ」
「しかし、棟梁はうらやましいよ」
「どうして」
「気ままに御同伴で出歩けるんだから」
「馬鹿を言っちゃあいけねえ。さっきは珍らしいと言ってたじゃないか」
「そりゃあ珍らしかったからね。しかし、珍らしかろうと何だろうと、こちとらはそんな
ことが出来ないのだから。こんな時は余計忙しくって、どこへも出られやしないんです」
「その代わり、居ながら名所じゃないか。こうして自分の家から向島の桜を見るなんて」
長八はそう言って、川を隔てた向こう岸に眼をやった。
「それもそうですねえ」
善吉もおかしくなって笑った。
「けど、眺めている暇もないんですよ」
およしが、おたきに言った。
「ほんとにおかみさんがうらやましいわ」
「そんなこと言って、ばちが当たるわよ。あんた方は年中一しょに暮らしているんだもの。
あんた方こそうらやましいわ」
とおたきはいつになく陽気に言った。
女中がだんごを運んで来た。長八は直ぐ皿を手にした。
「うまいな」
と舌つづみをうった。
長八と善吉は薬師堂再建の話に移った。維新の騒ぎで持ち越されていたのだが、時勢が
変わったことで、二人の気持ちは早速にも始めたいということで一致していた。
「資金はもう集まっているはずなんで」
と善吉が言った。
「そんなら尚のこと、一日も早く」
と長八は言った。
「ところが、日本橋の旦那衆は、今は新政府にとり入ることで夢中になっていて、薬師さ
まのことを忘れているらしい」
「お前さんまで腰が重くちゃあ困るね」
「いやいや、近いうちに旦那衆に掛け合うつもりです」
善吉が、ひょいと思いついたように、
「腰が重いで思い出したが、お前さん、私の頼みを忘れているんじゃないでしょうねえ」
そう言われて、長八は苦笑した。
「普賢さまか」
「まだなんですか」
善吉がいたずらそうに長八の顔をのぞいた。
「まだなんだ」
「もうひと月余りにもなりますよ」
「それがねえ、さっぱり手がつかないんだ」
と長八が困ったように頬を掻いた。
善吉は信心深い男で、辰年生まれの六白ということで、その守り仏として普賢菩薩を信
仰していた。新しい時代になって、何か心に期するところがあって、長八に普賢菩薩の像
の制作を依頼してあったのである。
「まあ、いいやね。御本尊のこの私がこうピンピンしていたんじゃあ、守り仏様も退屈す
るだろうから」
善吉がふざけた口振りで言った。
「それで、今日は向島へ行ったのさ」
長八は正直に言った。
「何ですって?」
善吉はよくわからない顔付きで聞いた。
「普賢さまを探しにね」
「へえ、普賢さまと向島、妙なとり合わせですねえ」
善吉が笑うと一しょに、皆も笑った。
「どういうわけで?」
笑ったが、善吉にはまだはっきりしなかった。
「ちょっと趣向があってね」
長八はまた微笑した。
「花見の人の中に普賢さまがいらっしゃりはしないかと思ってね」
「それで?」
「居たんだよ」
「へえ」
善吉にはよくわからなかった。わからないなりに、そういう話が面白かった。
「だからね、今夜にも仕事に掛かろうと思う」
長八は自分に言い聞かせるように言った。
長八が『趣向』と言ったのは、後にわかったことだが、『西念寺縁起』の普賢菩薩を考
えていたのである。長八は菩提寺正定寺のために普賢菩薩を制作したことがある。が、八
橋の店にふさわしい仏として、違った普賢を構想していたのである。この『西念寺縁起』
の話をする前に、八橋について補足して置こう。
八橋という名称は、ここの二階からの眺望が、隅田川に渡す八つの橋が見えるところか
ら、狂歌の名人蜀山人が名付けたと伝えられている。生醤油をつけただけの団子が、江戸
人の好みに合ったのか、粋人や芸妓、役者などに評判となり、江戸の名物になっていた。
さて、長八はその夜仕事場に入った。四、五日して、八橋の注文の普賢像をつくり上げ
た。木心漆喰の塗額で、遊女姿の普賢菩薩が六牙の白象に乗っている図である。白象は静
かに横たわり、紅衣に白のうちかけを着た遊女が長い手紙を読んでいる。背景は岩山が群
青色にそびえ、一見浮世絵風な構図だが、浮世絵のような淫靡さは微塵もない。長八が『趣
向があって』と言ったが、まさに『趣向』である。
先に述べたように、これは西念寺縁起、くわしくは『西念寺宝物縁起』のよったもので、
恐らく、正定寺の普賢を制作した時、書物で知っていたのを、八橋のためにつくったもの
と思われる。
播磨の国に書写山という名山がある。そこに西念寺という寺があって、いつの頃か、そ
の寺に性空上人という名僧がいた。かねて普賢菩薩を信仰していて、その生ける姿を拝し
たいと思うようになっていた。すると、ある夜の夢枕に仏のお告げがあった。『普賢の化
身を見たいなら、室津の遊女町に行きなさい。そこの遊女の長者こそ普賢です』と教えて
くれた。そこで、早速上人は室津に行く。尋ね尋ねて行くうちに、ふと女の歌声が聞こえ
て来た。歌に合わせて鼓の音も聞こえる。何とも言えない気高さに打たれて聞き澄ますと、
『周防室積の中なるみたらいに、風は吹かねども、さざら波、さざら波』と繰り返してい
る。うっとりと眼を閉じて聞き入っていると、遊女が忽然と普賢菩薩になり、六牙の白象
に乗って、経文を唱え出した。上人は随喜の涙と共に普賢を拝した。すると、たちまち遊
女の姿に返り、『上人よ、今の有様を人に語ってはいけませんよ』と言って、姿を消した
という。上人はこの不思議な感動を遺すため、その姿を刻んで日夜礼拝した。これが『西
念寺宝物縁起』の荒筋だが、これを基に八橋の普賢像を制作したのであり、制作に当たっ
て、女人の姿を工夫するために、向島の花見に出掛けたのである。
浮世絵的な表現は以後も何度か試みている。長八という人が、単に自分だけの世界にと
じこもっていないで、他の世界のものを導入することに努めたことの証拠であろう。
以後、彼は堰を切ったように、多くの制作を始める。あたかも鬱屈していた幕末の苦し
みから解放されて、明治の新しい時代の潮に乗り入れた観がある。
⑥
徐々に新しい東京に変わって行った。と共に長八にも左官の仕事が次々とあった。職人
も揃うようになり、世帯も大きくなった。長八という腕と人物を慕って、中橋の波江野の
家から移って来た腕利きの職人も幾人か居た。波江野亀次郎は老齢で病気がちのため廃業
して、職人たちは分散した。その主立った者たちが長八の下に来たのである。後に出て来
る中橋善吉、芝の市(井上市五郎)、天神の梅、江口庄太郎などがそれである。こうして、
左官の方は軌道に乗り、職人たちで運営出来るようになり、長八はもっぱら鏝絵の制作に
力を注ぐことになる。
普賢像を制作し、意欲をかき立てられた長八は、間もなく、八橋の大改築に、蓄えられ
た力を発揮する。
八橋は明治になって、いよいよ繁昌し、店が手狭になった。古い江戸の姿から明治の形
に改めなくてはならぬ。たまたま、ある大名の屋敷が売りに出たのを買い取って、店を新
しくすることになったのである。
八橋の仕事は、主人の善吉との親交もあって、長八が自ら仕事をする。弟子二人を手伝
わせて、一切の壁を長八がやることにした。これには長八の意図があった。親しい友人の
ために、渾身の制作をしてみようと思ったのである。たしかにここには鬱積していたもの
が一時に発露したような、華麗な作品がつくられたのである。
大座敷正面の床の間に、全面を砂壁で塗りつぶし、そこに極彩色の菖蒲の図を描いた。
八橋の名にちなんで、伊勢物語の故事に拠ったものである。これに対して、地袋には蓮池
を描き、欄間には鶴の群れ飛ぶ様を描き、これらの風趣が隅田川の景色と照応して、一幅
の典雅華麗な情緒を漂わせた。
彼はすでに五十五歳になっていた。心技共に円熟していた。制作中から八橋を知ってい
る者はこのことを知って待望していた。開店と共に、長八の鏝絵は八橋の新しい名物とし
て、東京人の話題になったという。恐らく傑作であったろうと思われるが、残念なことに
今ではその片鱗すらうかがい知ることも出来ない。明治二十一年、新大橋が老朽して掛け
替え工事をすることになり、その時、八橋は他所に移転し、全部を取り壊してしまったの
である。
八橋の隣に土造りの大橋稲荷と呼ばれる祠があって、これにも長八の作品があったとい
う。正面破風に雌雄の狐と宝珠をあしらい、狐格子の裏に竜虎の図が描かれていたという。
これも今は見ることが出来ない。
五月、五稜郭が平定して、維新の騒乱は全く終わった。六月、管制改革、六省設置、版
籍奉還。
十月、下田から横浜に転住していた福太郎こと高柳天城が死ぬ。天城は横浜に来て、外
人との通訳をしていたが、英国公使館に嘱望されて、貿易事務を担当する事務官になって
いた。
長八は死去の報を受けて、急いで横浜に行った。この頃すでに乗合い馬車が走っていて、
長八はそれに乗ったようである。高柳天城には妻も子もなかった。葬儀が終わっていたが、
墓地をたずねて、新しい墓標に手を合わせた。一別以来、とうとう会うこともなかった。
正直と重厚と努力の一生を思った。異郷で孤独で終わった友が哀れであった。これで三人
の友、全部を失ったことになる。
東京、横浜間の往来が重要となって、この年四月、乗合い馬車が開通していた。十二月
には電信線が張り渡された。電線を伝わって飛脚が走るといって、一日中見ていたという
笑い話は、この頃のことだったのであろう。
明けて明治三年、長八五十六歳。この年は長八にとって多難な年であった。
二月、菩提寺の正定寺に大黒天像を寄進する。亡父源次郎の十三回忌の供養のためであ
る。ところが、この時、長八は正定寺の和尚から明治新政府が廃仏論を言い出していると
いう話を聞いて驚く。
明治政府は五箇条の御誓文によって出発した『旧来の陋習を破り』『知識を世界に求め』
そこから改革が始まった。その考え方は立派であると長八は思っていた。ところが、それ
が廃仏棄釈になるとは思わなかった。政府は明治改元と共に神仏分離を命令していた。こ
れは必ずしも非難すべきことではないと、長八は了解していた。が、和尚の話によると、
それが一つのわなだったというのである。
「神仏分離の考えは、神道主義者の意見だ。神と仏を分離して、神を第一にし仏をその下
に置く。下に置くだけならいい。仏をつぶしてしまおうと考えている」
と和尚は言うのである。
「神仏分離は、そんな上下の差別をつけることでしょうか。まして、つぶしてしまうなん
て、無茶ですよ」
長八は正直に感じたままを言った。
「しかし、現にこの寺にもいろいろと悪口やおどしを言って来る者がある。新聞にも、寺
をこわしたとか仏像を焼いたとかという事件が見えている」
「それは一部の過激な者のしわざでしょう」
「たしかに一部の過激派のしわざだと思う。しかし、それはどこから出ているかが問題だ。
どうなることやら」
と、和尚は沈痛な口調だった。
長八は廃仏的な動きは知っていた。が、それが何を根拠にしているのか知らなかった。
世相はまだ落ち着いていない。そういうところから、こんな突飛もない不心得者が出るの
だろうと軽く考えていたが、和尚の話はまんざらではなさそうであると思った。
長八の成長過程には仏教的なものが濃く流れて入るということは、すでに述べた。
それらは、すべて長八の人間形成の上に重要な意味を持っていると思われる。
そういう長八に、正定寺和尚との対話は、心に大きな波紋を与えた。しかし、和尚が予
見したように、三月には『惟神大道宣布の詔』が示され、国策として、仏教を廃し神道を
国教とすることになった。長八は、こうはっきりとなると、むしろ憤りを感じた。新政府
への期待がこの一事で裏切られたように思えてならなかった。やがて、彼に反骨の精神が
芽生え成長して行く。それは、制作の上で、より強烈に仏教へ傾斜していることによって
実証される。
彼は仏像が次々とこわされて行くのを嘆いた。そして逆に仏像をみずからつくり始めた。
そのために、仏像を知る必要があった。暇をみては寺を訪ね仏像を見、写生して廻った。
梅雨時に入ると、長八は一層熱心に寺々を廻った。しかし、一方では職人たちに鏝絵の
技術を教えなければならなかった。鏝絵の系譜を調べると、長八の直接指導した者は二十
に達している。そのうち、世間から四天王と言われた中橋善吉、天神の梅、江口庄太郎、
靴亀(吉田亀五郎)は、皆この時代の職人たちであった。
そんなうっとうしい日、妻のおたきが食当たりで寝込んだ。さして心配な病状ではなか
ったから、看病は清太郎の嫁のおさくがしてくれた。清太郎は相変わらず落ち着いていな
い。長八は忙しさにまぎれて日を過ごしている。が、おたきの病気は一時快方に向かった
が、はかばかしく行かず、いつか五月が終わろうとしていた。おたきは五十歳になってい
た。いわゆる更年期症状だったのかも知れない。また、清太郎のことで気を使っていたた
めかも知れない。
おたきの病気が長いのに、長八はだんだん心配になって来ていた。気のせいか、おたき
は気弱くなって行くように思われた。
六月になった。梅雨も明けて天候も定まったが、急に暑さが募った。ある日、
「今日はいい天気だから、体をふこう」
と長八が言い出して、おさくに湯をわかさせた。職人たちは仕事で外に出て、家の中は
静かだった。
湯が出来ると、長八はおたきの体を抱くようにして縁先に連れ出し、肌脱ぎをしてふい
てやった。すっかり痩せてしまったのが痛々しかった。
どこかで蝉の声がした。おたきが耳を澄ますように聞いていた。
「蝉って、寿命が短いもんだってねえ」
と、おたきは不意にそんなことを言った。背中をふいていた長八は、その言葉に胸をど
きっとさせた。
「………」
何も言わなかった。「不吉な」と言おうとして、そのまま口をつぐんだ。
「すっかり夏になったなあ」
と、まぎらわすように言った。
「そうねえ」
おたきが言った。いくらかさっぱりした声だった。
「もうじき山王さまの祭りだ」
「そうねえ」
おたきは過去を思い浮かべるように、遠くの雲の峰を見た。
「その頃には床を上げたいもんだな」
「ええ」
体をふき終わって、おたきを寝床にもどした。
「さっぱりしたわ」
と、おたきは青く透けた頬に薄い微笑を浮かべた。おさくが薬湯を持って来た。直ぐと
って苦がそうに飲んだ。薬のにおいが流れた。
「山王さまの祭り、見たいわ」
と、思い出すように、子供っぽくつぶやいた。
「二人で行ったのはいつだったかなあ」
すると、おたきが数えるような眼をして、
「もう十年も昔になるわ」
と言った。
「そんなになるかなあ」
長八は感慨深く言った。つい、この間のような気がした。その頃は世間が騒がしかった
が、それでも楽しいことが多かった。あれから、いろいろなことがあった。そんなことを
長八は思っていた。
「井伊さまが殺された年だった」
「あの時は大騒ぎだったわねえ」
「考えてみると、長いようでもあり、短かいようであり、夢のようだな」
「そうねえ、いろいろのことがあったわ」
話しているうちに、おたきを疲れさせてはいけないと思った。
「さ、いい加減にして、ひとねむりするさ」
長八は夏布団を掛け直した。
長八は縁先に立った。蝉の声がおたきの言葉を思い出させた。
その翌朝、未明に半鐘が鳴った。おたきが直ぐ眼を覚まして、かたわらの長八を起こし
た。
「火事!」
長八は跳ね起きて耳を澄ました。近い。寝巻のまま雨戸をあけた。と、ぱっと明るい赤
い空があった。
「大変だ、おたき」
長八は、すぐ隣室の清太郎夫婦を起こした。職人部屋から中橋善吉が下りて来た。
長八は『危ない』と思った。
「避難しよう」
後は、清太郎と善吉に任せて、おたきを背負った。
「湯島へ行く」
と言い残して長八は赤い炎の空の下へ消えて行った。湯島は清太郎の実家である。
八名川町の家は全焼した。湯島に移ったおたきは病状が悪化して、その日夕方危篤とな
り、次の日の明け方、静かに息を引き取った。
⑦
おたきの葬儀は湯島でささやかに行われた。が、いたずらに悲しみに打ち沈んではいら
れなかった。深川復興の仕事が彼を待っているのである。それでも、初七日までは外出せ
ず、おたきの位牌を前にして過ごした。
火事は深川遊郭(遊郭は明治になって復活していた)から出火し、深川一帯を灰にして
いた。長八は職人たちを督励して、八方に立ち働いた。その間に自分の仮住居を建てた。
そのさ中に、中橋の亀次郎が死んだ。老衰で長く床についていたが、暑さに弱り、食事を
とらず、枯れるように死んでいった。後継ぎの松太郎と次男の竹次郎の遺児を助けて、盛
大な葬儀をすませた。
あれやこれやと忙しく過ぎ、一つ一つ不意の行事をすませ、深川の復興一本になると、
長八はしみじみと孤独を感じ出していた。おたきのいない仮住居は一層わびしかった。
養子夫婦はいるのだが、何かよそよそしかった。年齢のへだたりのせいだろうか。血の
つながっていないためだろうか。こうなると、余計おたきのいないことがさびしかった。
おたきが死んで、仮住居に帰っても、長八は鏝絵の仕事を忘れたように、ぼんやりと過
ごしていた。職人たちはそういう長八を同情の眼で見ているが、どうしようもないようだ
った。
「こんなことではいけない」
と、みずから鞭打つ時もあったし、
「これが煩悩というものか」
と吐息する時もあった。
深川の復興は着々と進捗していた。が、まだ半分も片付いてはいない。もう七月で、暑
さが続いていた。やがて盂蘭盆で、おたきや亀次郎の新盆をすませた。
そして、間もなく、おたきの四十九日忌であった。この朝、中橋の善吉に頼んで、長八
は頭を剃った。そして夜の法事の客を迎えた。
「棟梁は!」
と、客は口々に僧形になった長八の頭に驚きの言葉を発した。
「そんなにおたきさんが忘れられないのかねえ」
と陰口を言う者もあった。
「新時代ですからねえ」
と、長八は冗談のように言って薄く笑った。このことは後に弟子たちに語っていること
だから、その理由ははっきりしている。
長八はこの時、おたきに寄り掛かり、甘え、頼り切っていた過去を強く反省していた。
おたきが居なくなって、それがわかったのである。そして、もはやほんとに一人で歩いて
行かなければならないと知り、みずからの芸術をつらぬくためにも、おたきから離れなけ
ればならないと思った。おたきを忘れねばならないと思った。いわば、妄執を断つことで
あり、未練を捨てることである。その証拠に頭を剃ったというのである。後に元の場所に
は仕事場を再建し、鏝絵を始めることになるが、その時長八は成田山からもらった袈裟を
掛けて仕事をするようになる。これもその証拠というべきであろう。
その夏、清太郎の女房おさくが身ごもった。さすがに遊び好きの清太郎も、責任を感じ
たのであろうか、人が違ったように働き出した。順調に、十月には腹帯祝いをした。深川
の復興も大方出来ていた。八名川町の家も新築した。そして、あわただしかった一年が終
わった。この年、人力車が東京の町を走るようになった。四月に種痘法が施行された。九
月、庶民に氏姓を用いることが許可された。この時長八は上田の姓を名乗った。上田は播
磨屋の姓である。したがって、正確には、上田金兵衛ということになる。しかし、通称長
八で、後に長八を本名とする。十二月、庶民の帯刀を廃止する。
明治四年になる。次々と新施策が出される。新貨幣の発行、太政官設置、廃藩置県、十
月には岩倉具視らが欧米視察に出掛ける。こうして、明治は文明開化に向かって発進する。
東京の町も徐々に変貌し、洋風建築が出来始める。洋服紳士が山高帽にステッキという姿
で通る。人力車が洋傘をさした婦人を乗せて走る。中村正直の『西国立志編』、仮名垣魯
文の『安愚楽鍋』など、この年に出版された。
六月、生まれるはずの清太郎の子が月足らずで死んだ。すると、清太郎は再び遊びにふ
けり出す。もともと清太郎には左官としての力量も職人統御の才腕もなかったから、真面
目に働き出したといっても、長八の代理はつとまらない。半年ばかりの仕事で幾分いや気
がさしていたのかも知れない。そこへ、心の支えにして来た生まれるべきわが子が死んだ
ので、急速に元通りの遊び人にもどってしまったのであろう。おまけに、今度はおたきが
いない。始終にらまれていた叔母がいないということで、清太郎は今は堂々と遊びに出掛
けるようになる。
清太郎が家に落ち着かなくなって、おさくも職人たちも心配した。長八にありのままを
話した。長八は懇々と清太郎を諭したが効果はなかった。むしろふてくさった態度さえ見
える。しばらく様子を見ていたが、女遊びは絶えなかった。長八はあきらめざるを得なか
った。しかし、清太郎は播磨屋の血を引き継いでいるただ一人の人間である。縁を切るわ
けにはいかない。そのうち、また子どもが出来れば行状も改まるだろうと、長八は気休め
に考えていた。ただ、左官の仕事は清太郎にやらせるわけに行かない。養子問題をおたき
と話し合った時のことを思い出す。あの時、おたきの言う通りにしていたら、こんな苦労
はしなかったかも知れない。左官の仕事の方は、やはりおたきの言ったように竹次郎にや
ってもらうしかない、と長八は思うようになっていた。上田の姓は清太郎に、そして入江
の姓は竹次郎に 、………とうとうその考えを実現することにした。
竹次郎は喜んで八名川町に来た。が、それは清太郎の気持ちをそこねる結果になり、二
人の折り合いはうまく行かなかった。そんなごたごたのうちに、その年も暮れて明治五年
を迎える。
次第に世の中は落ち着いて来ていた。が、長八個人はわずらわしいことにかまけていた。
一月早々、不幸なことが起こった。八橋の善吉が急病で、三日ばかり苦しんで死んだ。江
戸以来のたった一人の親友であった。五十八歳になった長八に、寒々とした無常感が襲っ
た。先に妻のおたきを失い、また親友をなくし、長八の心境は、次第に仏の道に寄ってい
た。こうしてさびしい一月が過ぎ、二月が過ぎた。外目には何事もない静穏な日々であっ
たが、長八はすでに自分の死というものを考えていたようである。
その証拠に、彼は仕事場にこもって、観音像を描いていた。もちろん鏝絵である。この
塗額は、後に仏壇に飾られる。そして、お寺通いが多くなる。経文を読誦するようになる。
四月、品川の遊郭で有名な土蔵相模という家があって、そこから是非にとの頼みで仕事
に出る。明治五年と言えば、品川、横浜間に鉄道が開通した年で、品川は古い宿場町から
一躍新都の玄関口となり、文明開化の繁栄をもたらした年である。開通したのは五月だが、
開通を目前にして品川は活気づいていた。新しく外部から商人が入り込み、地元でもこれ
に対応する方策を立て、急速に町が変貌していた。土蔵相模の普請もそのためだった。
この時の逸話が、後の国定教科書に掲げられた『伊豆の鯛と江戸の鯛』である。この伝
説には同巧のものがいくつかあり、矢田挿雲の『江戸から東京へ』では魚河岸の細屋佐兵
衛の話となり、別に日本橋の魚屋という説もある。伝説というものは、時と共に変形して、
どれが原形かわからなくなるもので、品川の話も原形であるかどうかわからない。
土蔵相模は品川の海を背にして建っていた。名の通り、土蔵造りの二階屋で、この仕事
は鉄道開通までの短い期間に仕上げなければならないというので、中橋善吉、芝の市、江
口の庄太という腕利きが長八と一しょに来ていた。それぞれ分担を決めて、泊まり込みの
仕事であった。
終わりに近いある日、長八は河岸につないであった小舟に乗って沖へ漕ぎ出した。いい
天気だった。海べ育ちの長八は楽しむように漕ぎ廻った。沖から見ると、土蔵相模がまば
ゆく、下半面のなまこ壁が美しかった。が、
「はて!」
と長八は櫓を漕ぐ手を休めて、上部の白壁に眼をやっていた。長八は何を思ったか、急
に引き返して、河岸に面した壁に高い足掛かりを作らせ、それへ登った。白壁の中央に、
彼は大きな鯛を描いた。
翌日、一人の魚売りが土蔵相模に来て、その鯛の話をした。
「あれは残念ながら伊豆の鯛だ。品川の鯛にしてもらいてえ」
と言うのである。長八はその話を善吉から聞いた。長八は魚売りの新助の住所を女中か
ら聞くと、ぶらりと外に出た。新助を訪ねた。若い男だった。がらんとした店の板縁に寝
ころんでいたが、むっくり起き上がると、
「ああ、お前さんかい、あの鯛を描いたのは」
と、いきなり不敵な眼を向けた。
「お前さんが伊豆の鯛だと言ったそうだが、確かに伊豆の鯛だ。が、品川の鯛とどこがど
う違うか、わたしは知らないんだ。教えてくれ」
長八は物静かに言った。
「どうって言ったって言えないな」
と新助はもどかしい表情をした。
「困るなあ」
と頭を掻いた。長八も困っていた。と、
「そうだ、本物を見ればわかる」
新助は急に眼を輝かせた。
「ひとっ走りして買ってくらあ」
そう言うと、いきなり長八の前をすり抜けるようにして、表の道を走って行った。
一刻ばかりして、新助は息を弾ませてもどって来た。仕事半纏にくるんで抱えて来た鯛
をひろげた。三尾の鯛を並べた。新助は並べながら言った。
「これが伊豆の鯛、これが品川の鯛、これが活け鯛」
言われて、長八はしげしげと見比べた。並べてあるのを見ると、三尾ともまるで違う。
「なるほどねえ」
と長八は嘆息した。
「がしかし、どう違うのかよくわからない」
すると、若い魚売りは得意気に、まず品川の鯛を両手に載せた。
「これを見な。品川の鯛は江戸中の流し汁で育って、しかも静かな海で遊んでいるから、
上品で肉も厚い、味もいい」
と比べるように両手に載せた鯛を板の上の鯛に当てがった。
「これは活け鯛だよ」
と、新助は今度は手にせず、
「これは沖で育ったにゃあ違いないが、生け簀に入れられて、始終狭苦しいところでびく
びくしながら暮らしているから、いつの間にか顔に皺が寄って、品がない」
「なるほど」
「これが伊豆の鯛だ」
新助は鯛の尾を引っぱった。
「伊豆の鯛は荒海で岩をつっついて生きて来た。そのせいで鼻が曲がっている」
長八はまた、
「なるほど」
とつぶやいた。
「この齢になって、いい勉強をした。ありがとうよ」
その翌日、長八は土蔵相模の鯛を品川の鯛に描き改めた。
逸話というのはこういう話である。
⑧
品川ではその外に松登楼(これも妓楼)、寄木神社、袖が崎神社、善福寺などの制作を
している。恐らくこの時期のものであろう。
土蔵相模の仕事が終わると、職人たちを東京に帰して、上記の仕事は長八ひとりでやっ
た。そうこうしているうちに、待望の鉄道が開通する。長八はその鉄道で新橋まで来、人
力車で八名川町にもどる。
この品川での一箇月余りの滞在は、もう一つ、長八に大事な要因を持たせた。というの
は、松登楼の仕事をしている間、一部屋を借りて寝泊まりしていたのだが、その世話をし
てくれた女中がおはなという中年の女であったことである。おはなは千葉の漁師の娘で、
一度結婚したが、どういう理由かわからないが離婚して、ここに住み込んでいた。他所に
一人の息子があった。一説には、品川芸者をしていたともいう。海べ育ちをいう共通点か
らか、長八と話が合った。こまめな働き者で、長八の身の廻りの世話を親切にしてくれた。
二人の関係はどんなものであったかはわからないが、ここでは想像をたくましくする必要
はなかろう。このおはなが後に長八の後妻となり、長八の人生はまた変化するのである。
長八が東京に帰ったのは、五月の末であった。帰ると、待っていたように、清太郎夫婦
が別れ話を持ち出した。事情はもちろん清太郎の放埒にあるが、それだけではなかった。
中橋から竹次郎が来たことにも原因があった。清太郎夫婦は播磨屋の跡取りとして養子と
なったのに、竹次郎が来たことによって、立場があいまいになって来た。竹次郎が真面目
な仕事好きな若者であるだけに、清太郎の心に動揺が始まっていた。おさくにしても、そ
れは同じことだった。長八はその事情を察して、二人を播磨屋から自由にしてやることに
した。つまり、養子のまま別居させることにしたのである。深く詮索すれば、清太郎夫婦
へのいやがらせかも知れない。おたきが死んだ後、おさくが家事一切を担当していたのだ
から、いなくなっては困るのである。長八はそれも察していた。が、あえて夫婦別れをさ
せたくない気持ちで別居ということにしたのである。
この年の夏、東京に氷水が売り出される。『氷』と書いた小旗が東京の風物詩として登
場したのである。八月、学制発布、国立銀行設置。九月、新橋、横浜間の鉄道が開通する。
おさくがいなくなると、職人や弟子たちが交替で炊事、洗濯をしなければならぬ。幸い
夏の間は大きな仕事もなかったから、何とかやれたが、そういつまでも続けられるもので
はない。一そ後妻を迎えては、という話になり、話はとんとん拍子に進んで、先に述べた
品川松登楼のおはなを迎えることになった。
伝説によれば、おはなは小柄な美人で、てきぱきと仕事をする女で、そういう点では長
八の内助者として適任であった。長八はそれを見込んだろうと思われる。だが、反面評判
のよくないところがある。それは金銭にこまかく、例えば金を持って来ない仕事の注文は
断るとか、工事を中止するとか、また職人たちの手当をも出ししぶるとか、仕事の材料を
値切るとか、そういう話が残っている。前妻のおたきやおさくのような人の好さがないの
である。弟子たちの心証は、ほとんどおはなに対して、この点でよくない。長八、時に五
十八歳、おはな、四十歳。
晩婚だから、色恋沙汰ではない。何とか家庭内が一応落ち着いて来たが、それはそれと
して、別に新しい問題が生じつつあった。それは、清太郎との衝突で、やがて事件にまで
発展するが、それは後日の話である。ともかくも、無事に年が暮れて、明治六年となる。
明治六年、この年から太陽暦になる。ちなみに、今までの記載はすべて太陰暦で、読者
は季節の叙述に異和を感じていたかも知れない。これからは太陽暦で説明することになる。
新政も軌道に乗って来たが、問題がないわけではない。この頃眼立って来たものは、欧
米一辺倒、欧米模倣で、そのために国民生活を粗略にし無視する傾向があった。その批判、
不満、反感が国粋論を生んだ。そして、東京という新都は、日本風と西洋風の混血児のよ
うな姿になっていた。人々は、欧米派と国粋派とに分かれていた。………ここには、日本
がいくどか繰り返して来た、外来現象と固有現象との相剋の伝統が見られた。
長八は日本固有の伝統を大切なことに思っていた。伝統を守るために一生懸命な気持ち
を持っていた。事実、この頃から、長八はいろいろなことに顔を出している。
例えば、歌舞伎俳優と親交があったとか、陶工、乾山焼六代三浦乾也、人形師小松豊次
郎、松本喜三郎と交友関係だったとか、浅草奥山の『見立て人形』展に出品したとか、ま
たそれらに関係する逸話も多い。
一つには長八の名声のせいで、いろいろな芸能人が接近したであろうし、一つには家庭
的経済的にゆとりが出たためでもあろうが、やはり根本的には、国粋的であったというべ
きであろう。長八は、すでに東京において有名人になっていた。明治五、六年頃の発行と
推定される『東京無双当以長揃』という、豊原国周の錦絵に、
『鏝絵、左官長八、前代未聞のわざ』
と出ている。この錦絵は当時の東京の一流芸能人の名を掲げたもので、例えば、『新聞、
岸田吟香』『老練、菊池容斎』『落語、柳亭燕枝』『高手、松本楓湖』などと並んでいる。
余談ついでに、もう一つ、ここで述べたいのは、長八の作品がこの年には何にも記録に
残っていないことである。ただ僅かに一つ、高村光雲の思い出話として、浅草奥山で長八
の『魚尽くし』の塗り衝立を見たという話が残っている。『その図取りといい、鏝先の働
きが巧みで、私はそこでいかにも長八が名人であることを知った』としるしている。
この年の秋の末、長八は十八年ぶりで故郷に帰る。父母の法要をするためであった。後
妻のおはなは家事があるから連れて行くわけにはいかず、単身帰郷である。
故郷の人々は長八の名声を知っていて、どこへ行っても喜んでくれた。もはや二十八年
前の長八ではなくなっていた。
法要をすますと、作品の依頼が次々とあった。皆断り切れない義理ある人々で、長八は
思いがけない長い滞在をする。
この間に、国情は韓国問題でもめていた。岩倉具視帰朝、韓国問題急転、西郷隆盛ら征
韓論者の退陣という一連の事件があった。
やがて年が明けて明治七年である。長八は久しぶりに故郷の新年を楽しんだが、仕事が
また続いて、ようやく一月末に東京に帰った。この滞在中の作品は『二十四孝図』『天鈿
女命』などである。
長八が帰った東京には、暗い不穏がにじんでいた。岩倉具視が傷つけられ、征韓派の官
人は続々と下野し、これに同情して政府要人をつけねらう過激分子があったりした。三月、
東京銀座にガス灯が点く。四月、台湾征伐。だが、新政は最初の曲がり角にさしかかって
いた。
長八は帰ってから、仕事場に入って制作に励んでいた。政治向きのことは余り考える男
ではなかったのだ。この時期の作品は、しかし、わかっていない。ただ一つ、明治八年の
正月の作として、『湖上観月』がある。現在静岡県岡部町柳沢稲荷の所蔵で、昭和二十八
年以後、氏子総代の石田康一氏が保管している由である。岡部町に私の知人青野たつ江氏
が居るので、調べてもらったところによると、長八が杉山家(昔の岡部宿の旧家らしい)
に旅の途中しばらく居て、その時作ったもので、柳沢稲荷は、元杉山家の屋敷内にあった
のを、今から六十年ばかり前に、向いの山に移した由である。この話のように、長八がど
こかへ旅をしていたという形跡は何もない。ただこの頃の東京における長八の行動はほと
んどわかっていないし、作品すらないということを考えると、あるいは旅に出ていたのか
も知れないとも想像される。もし岡部町に来ていたことが真実なら、そしてその目的や行
程などがわかっていたら、長八の研究に新しい発見があったろうと思われるが、はっきり
しないで残念である。
しかし、少なくとも明治八年になって、三月にはどこかを旅行していたか、滞在してい
たことは間違いない。
それは三月末、東京に突発事件が起きて、長八は急いで帰京している事実があるからで
ある。
突発事件というのは、別居していた清太郎が、殺人未遂の罪を犯して逃亡したことであ
る。事件は三月三十一日起こった。清太郎は日頃馴染みを重ねていた芸者おさくを傷害し、
無理心中を図ったが失敗して、行方をくらましたのである。市井のありふれた事件だが、
長八にとっては一大事で、その通知を受けると、長八は直ちに帰京している。
当時の新聞に掲げられた荒筋を見ると、木挽町九丁目の田毎という料理屋で、清十郎(も
ちろん清太郎のこと)が三十日の夜来て、金春の芸者おさくを呼んで、口説いたところ、
おさくが意に従わないので、あらかじめ用意していた出刃包丁で、おさくの喉へ突き刺し
た。おさくの叫び声に驚いて、家人が駈けつけて大騒ぎとなり、清十郎は庭に飛び下りて
逃げ失せたという話である。この新聞(東京日々新聞)は四月二日にこれを掲載している。
この新聞記事を信じれば、清太郎は当時浅草に住んでいたのである。
清太郎も考えてみれば不幸な男である。早く父を失い、播磨屋の養子となり、恋女房を
持ち、何の不平もないはずだが、生来の遊び好きが影の形に添うように清太郎につきまと
って、とうとうこんな事態になってしまった。播磨屋へ養子になったところに最初の誤算
があった。この点、おたきの計算は当たっていた。次の誤算はおたきに死なれたことであ
る。肉親のいなくなった播磨屋は、清太郎にとって何もかも不安だったであろう。それに
拍車を掛けるように、竹次郎の養子入り、更に後妻おはなの来たことで、いよいよ清太郎
は播磨屋からはみ出していったのである。特におはなとの対立は決定的であった。遊び好
きの清太郎と金に厳しいおはなとの対立は、おたがいを犬と猿の間柄のようにしてしまい、
たがいに口汚くののしり合う親子にしてしまったのである。そして清太郎は次第に自棄の
方向へ加速度に走っていったのである。
清太郎の行方は、八方手をつくしたがわからなかった。長八は止むなく播磨屋から清太
郎を除籍した。そして、そのことは、長八の心に暗い影を落としていた。
第6章 終わり
動画