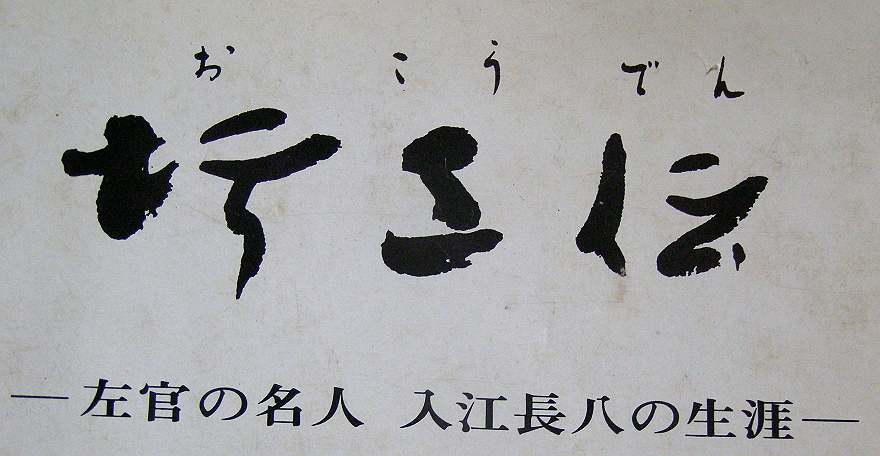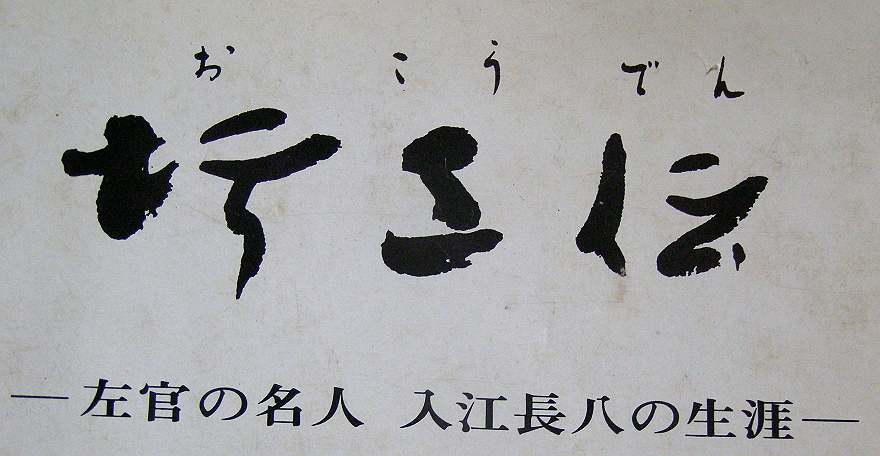須 田 昌 平著
第7章 夢 不 動
|
文明開化の新しい波を眼にして、長八は、
一層日本を考え、仏教を考えるようになっ
た。そして、次第に『おのれの道』を形づ
くるようになる。山岡鉄舟との出会いも、
竜沢寺百日の参篭も、そのおのれに徹する
求道の道であった。
(六十一歳から六十五歳まで)
|
①
清太郎の不祥事件は、長八の心に暗いものを漂わせるようになる。心静かに晩年を生き
ようと思っていた矢先のことで、長八にとって大きな衝撃であったようである。
長八はまず清太郎を播磨屋から除籍した。家名に傷をつけまいとしたのである。長八
は何より播磨屋の家門にこだわっていたのである。
と同時に、播磨屋を誰に継がせるかも、重大な問題となった。すでにもう一人の養子竹
次郎があるが、これには入江を名乗らせている。清太郎を除籍したからといって、直ぐ竹
次郎を後釜にというのは不自然であった。おまけに、おはなは自分の子をこの機会に引き
入れたかった。が、これには長八は絶対に拒否した。彼は播磨屋の名にふさわしい人物を
という堅い考えがあったからである。
長八は他に幸太郎をも考えたが、すでに大人になっている男を引き入れると、おはなと
の折り合いがうまく行かないと思ってやめた。考えに考えた末、ようやく四月も終わろう
という頃、長八は末弟の寅吉のところの次男兼吉を養子にすることに決める。兼吉は十四
歳の少年で、素直な子であった。年が若いから、みっちりと仕込めば播磨屋の後継者にな
れるだろうと判断したからである。
養子が決まっても、長八の心は片付いてはいなかった。東京で暮らしていると、何かと
清太郎のことが心にひっかってやり切れなかった。六月、彼が再び郷里に帰ったのは、そ
の気持ちをまぎらしたいためだった。しばらくのんびりと暮らして、いまわしい記憶を捨
てたかった。
この時、長八は養子にしたばかりの兼吉を連れていた。まだ播磨屋になじんでいない兼
吉であった。旅を共にしながら、いろいろなことを教え、故郷の姿をも見せて置きたかっ
たのであろう。
故郷に帰り着くと、早速仕事を頼まれた。近藤家から神農像をという注文である。この
間、長八は近藤家に寝泊まりし、兼吉は淨感寺に預けて勉強させた。
近藤家は通称大阪屋という薬屋で、後に文化勲章を受けた薬学博士近藤平三郎の実家で
ある。長八の家とは眼と鼻の距離で、古くからの知り合いであった。
長八は大阪屋の裏手の薬倉のひさしの下に蓆を敷いて、そこで制作を始めた。そこから
は淨泉寺が見え、牛原山の緑が迫っていた。こうしていると、不思議と心が落ちつけた。
神農とは中国古来の帝王で、医薬の祖として、日本でも信仰されていた。いわば薬屋の
守護神である。長八は何を原型として制作したのかわかっていない。が、私の想像では、
近藤家にあった掛軸の神農像であろうと思う。江戸後期から、商業の興隆と共に商売繁盛
を願って、こういう守護神がつくられていたから、それに拠ったものであろう。近藤家は
私の家とも親類筋であるから、私も度々訪ねているが、掛軸の神農像を見た記憶がある。
近藤家の仕事が終わると、淨感寺のために天神像をつくる。天神とは菅原道真を擬した
もので、学問の神である。学制が発布されて、淨感寺が学校として代用されていたので、
そのための制作であった。
こうして八月まで郷里で暮らす。その間、数々の作品を残している。
長八が来ていることを知って、同じ西海岸の戸田村から使いがあって、八月末戸田村に
移って来る。戸田の松城家から迎えの舟が来、長八と兼吉は晩夏の船旅を楽しみ、風光を
賞でながら戸田に着く。よい凪ぎで、海上を涼しい風が走った。移り変わる風景、島山の
緑、白く舞う鴎、真帆片帆、遠くの富士。飽くことのない楽しさだった。舟はゆったりと
潮に揺れ、櫓の音はのどかに響いた。長八は兼吉と並んで故郷の美しさを語った。思い出
を語った。時に興を覚えて、移りゆく風景を写生した。長八はこうして兼吉を身近に置い
て、いろいろと親しげに語った。そこにはやはり肉親の愛が強くつながっているようだっ
た。
戸田村の静かな内湾に舟は滑るように入って行った。岸近く石塀に囲まれた屋敷が直ぐ
眼についた。
「あれが松城の家ですだ」
と船頭が櫓を漕ぎながら指さした。近付くと松の木立の中に白壁の家が光っていた。
松城家は代々兵作を名乗り、回船業や造船業を営んでいた。安政元年から二年に掛けて
のロシア軍艦ディアナの代船ヘダ号の建造に関わり、用度調達係を担当した。のち明治に
なって新しい網漁法を採り入れ、それに成功し、伊豆西海岸屈指の分限者と言われていた。
陸に上がると、石垣沿いに道があり、一つ角を廻ると、大きな石門が開いていた。船頭
が先に立って案内した。庭の踏み石伝いに行くと二階建ての和洋折衷の新築したばかりの
本屋があり、船頭はつかつかとその中に入って行った。
長八はここに一箇月余り滞在して、室内装飾の鏝を振るった。和室には和風を、洋室に
は洋風を、それぞれ工夫した装飾を施した。丸柱、天井飾り、唐草模様など、洋風を考慮
した制作がここにある。松城家の仕事をすますと、続いて同村の太田家からの依頼があっ
て同じような仕事をする。
両家の主人は、
「大工棟梁は石田半兵衛にやってもらいたかった」
と嘆息混じりに言った。半兵衛は馬次郎が処刑されたあと気弱になり、明治四年十二月、
甲州で死んでいる。長八も淨感寺で手合わせした時の丁々発止、職人同士の戦いをしたか
った。ちなみに明治十六年、修禅寺の彫刻をしたのは半兵衛の子徳蔵で、馬次郎の弟と伝えられる。
仕事中に東京から郵便で、おはなの実母が死んだことが知らされる。仕事をすませて、
直ぐ東京に発つ。すでの十月に入っていた。
やがて程なく、いまわしかった年も暮れ、明治九年となる。清太郎の行方は依然として
不明だった。
三月、佩刀禁止令が出る。六月、天皇東北に巡幸。東京から三島まで、長距離馬車が輸
送を開始する。明治は徐々に平穏になりつつあった。
長八は、七月になると又も帰郷するが、それまでの半年余り、彼には何の伝説も作品も
残っていない。が、思うに、この期間に家庭問題があったためのようである。
清太郎事件の後、兼吉を養子にしたことはすでに述べた。竹次郎のことにも触れて来た。
この二人の養子について、長八は突然模様替えをしたのである。つまり、竹次郎には入江
姓を名乗らせていたのを、上田姓(播磨屋の姓)に変更し、兼吉に入江姓を与えたのであ
る。このことは、明らかに竹次郎に播磨屋を継がせることで、これが後妻のおはなにとっ
て不服の原因となった。
長八にしてみれば、やはり播磨屋に最も親しかった波江野亀次郎の子の竹次郎が、播磨
屋を継ぐべき者と当然考えられたし、一つには、年齢的にも老境に入った長八には、早く
家督を譲りたい気持ちもあった。それには、兼吉では若過ぎた。こんな理由があったもの
と思われる。
ところが、おはなは以前から自分の腹を痛めた子にと執着していた。それでも、兼吉が
播磨屋の後継者になった時は、年が若いということで、長八の意向に従った。それが急に
竹次郎になっては、何ともいえない不満があった。竹次郎とはすでに同居して久しい。そ
の間に、二人の性格の相違は、互いにうまくいっていなかった。ただ、竹次郎は入江の養
子であるために、強い衝突もなく過ぎて来たというに過ぎない。それが今度は播磨屋の方
に廻った。おはなにとっては、全く面白くないことになった。
いつかおはなと竹次郎の間に気まずい溝が出来、時折りは衝突し、竹次郎はついに別居
を言い出すようになった。
二人の間に入って、長八は説得してみたが、感情的なものはなかなか和解しがたい。長
八は止むなく、竹次郎を別居させることにする。
竹次郎が別居するようになると、長八は家庭内の気まずさに耐えられず、又も故郷へ逃
げるように帰って行くのである。長八は、以後ほとんど毎年のように帰郷しているが、長
八にとっては、故郷とはそれほどに住みよい所であったようである。
この時の郷里滞在は延々十箇月に及び、翌年の春まで続く。そして、東京ではほとんど
制作しなかったと思われるのに、郷里ではおびただしい作品を残している。こんなところ
に、東京生活と郷里での生活の相違が感じられる。ことに十箇月に及ぶ滞在は異常ですら
ある。長八にとって、東京がいとわしものであったことを察する。
この時、人々から依頼されるままに作ったものは、恐らく二十点を越えたであろう。現
存するものだけで十六点に及んでいる。この作品を一々列挙することは、この述作の本意
ではない。概略だけを述べることにしよう。形式的に三つに分類すると、一つは立体彫塑
形式、二つは額装作品、三つは小品群ということになる。その中で、めぼしい作品につい
て若干の考察をしてみようと思う。すでに円熟した長八が、全くの自由な気持ちで存分に
制作したものとして、この時の作品は重視されていいと思うからである。
第一の立体彫塑形式の中では、先ず彼は関仁助像を制作している。帰郷第一作である。
そして、これは誰に頼まれたものでもない。長八自身の発意である。関仁助はすでに説明
したように、長八の少年期の左官の師匠である。彼は十九歳で故郷を出奔し、その後仁助
には会っていないから、彼が制作した仁助像は四十三年前の面影を追って作ったものであ
る。にもかかわらず、いかにもその人を的確に表現した写実的な作品で、当時の人々はそ
の似姿に驚嘆したという。この制作は、先師思慕の情からで、菩提寺に供養のため奉納し
た。次いで制作したのは聖徳太子像で、これはこの地の左官職人組合の依頼によるもので、
その発起人の中に、かっての恋敵金五郎もその名を連らねている。聖徳太子像は、仁助像
のように無彩色ではなく、精密壮麗な着彩の像で、その点、鏝絵の妙技を発揮している傑
作である。
額装作品群は十点を数えることが出来るが、その中の異色は、応神天皇、神功皇后、竹
内宿弥の三神像で、しかも、いわゆる見立て人形の型をとったもので、長八作品の中でも
数少ない形式である。大理石風の額装に三神が浮彫的に塗られて、彩色も鮮やかである。
ついでに付記したいと思うのは、長八はこの頃からしきりに歴史に取材した作品を手掛け
ている。その理由はさだかではないが、当時の西洋化に対する反発のようなものが感じら
れる。それは、直ぐ後に出て来る内国勧業博覧会の後の心境から想像されるのである。
小品群については、日常眼に触れるものに鏝絵を施したという点に注目したい。恐らく
は近隣の人や知人に頼まれて、仕事の暇に気楽につくって与えたものであろう。素焼の皿
におかめの顔を描き、杉板の切れに花鳥を塗るという類で、そこには即興的な、それだけ
に軽妙自在な庶民的な親しさが感じられるものである。どちらかといえば重厚な生真面目
さのある長八の別な人間的側面を示しているものとして興味深い。
明治十年、韓国問題のもつれは、政治的危機を生んで、各地に反政府の動きが出始めた。
やがて、それは西南戦争となって、鹿児島軍の熊本城包囲となった。草深い松崎の村から
も、兵隊が徴用されて行った。風評はさまざまで、故郷の人々に不安を呼んだ。そういう
中で、長八は悠々と制作していた。
四月末、ようやく熊本城の囲みが解け、鹿児島軍は後退する。政府軍の勝利がおよそ確
定するようになる。
②
西南の役も、長八にとっては何のかかわりもなかった。ひたすら芸を楽しんでいるよう
であった。東京のことが気にならないわけではないが、すでに竹次郎が仕事一切を代行し
ているし、兼吉も竹次郎になついて修業しているし、格別なことはないと信じていた。
五月に入って、竹次郎から手紙が届いた。手紙には近況を簡単にしるし、二つの用件が
書かれていた。一つは深川墨江町の火災についてで、復興のことで世話人の間の意見がま
とまらず、長八の帰京を切望しているということ。もう一つは内国勧業博覧会が開かれる
について、政府から長八に出品を依頼して来たこと。そんなわけで、至急帰ってほしいと
いう文面であった。
長八は故郷の人々に、またの約束をして、長い滞在を終わって帰京する。
東京に帰った長八は、墨江町の復興の取りまとめをすると、仕事は一切竹次郎に任せ、
博覧会出品作品の制作に取り掛かる。
この内国勧業博覧会というのは、先年アメリカのフィラデルフィアで開かれた万国博覧
会にならって、日本だけで実施しようというもので、一種の外国向け宣伝であった。日本
の貴重な技術を諸外国に紹介し、日本独特の美術工芸を売り出そうとする政府の意図によ
るものだが、形式的には西洋の模倣だった。時あたかも西南の役が起こり、一時開催を見
合わせていたが、四月になり、内戦も終結する目途がついたため、いよいよ実施に踏み切
ったものである。
この時の出品作は『望富岳於伊豆之奈島図』と題した額装仕立てのものと伝えられてい
る。この作品は今も残っている。これで見ると、長八が戸田村に向かう舟の上で写生した
ものをもとにして仕上げたらしく思われ、円熟期の代表作とも言える傑作である。その他
にもいくつか試作をしたらしく伝えられているが、よくわからない。この作品が完成した
のは七月半ばであった。この作品の特徴は、薄肉浮彫の従来の手法に、その描線にわざと
鏝の跡を残している点で、その凹凸によって一層深みを持たせている。長八の新しい技法
といえる作品である。
内国勧業博覧会は、八月二十一日開場式、当日天皇、皇后ご臨席。十一月三十日閉場し
た。この展覧会で、長八は褒賞を受けた。
『鏝ヲ用イテ各種ノ泥灰ヲ塗抹シ、水彩ノ設色ヲ描写ス。衣紋骨格、毛筆ヲ用ユルニ勝レ
リ。但シ、浮起ノ法、欧洲ニ倣ウアラバ更ニ佳妙ニ至ルベシ』
というのである。この『衣紋骨格』の字句が一つの疑問を持つ。出品したのは人物か、
仏像ではなかったかと。
実は前述の『望富岳図』を出品したという確証はない。『明十丁丑仲夏写』と書き入れ
てあるところから、出品作ではないかと推定されただけのようである。
もう一つの疑問は『浮起ノ法』で、人物だとすると、見立て人形形式のもののようでも
あるが、それもわからない。
さて、長八はこの博覧会出品によって一つの転機に立たされる。伝説ではこのことに何
も触れていないが、以後の彼の行動から証明されるのである。
その一つの証明は、長八は以後開かれた内国勧業博覧会には一度も出品していないこと
である。恐らく博覧会そのものに失望し、不満があったのであろう。その原因は言うまで
もなく政府の欧化主義に対してで、具体的には褒賞文に見られる偏狭な批評に対してであ
ったろう。
その第二の証明は、褒賞文に見られる作品批評が、長八にとって実に意外だったことで
ある。『但シ、浮起ノ法欧洲ニ倣ウアラバ』とは、何という言い方であろうか。芸術は『倣
フ』ものではないと長八は信じていた。そういう長八の芸術的自尊心が、この言葉に強く
傷つけられたのである。
この審査は川上寛(冬厓)がした。彼は当時の洋画家で、当然洋画技法の眼で長八の作
品を批評したのである。が、それはいいとして、長八の独特な創造であることが全然無視
されているのである。長八の芸術は絶対に洋画ではない。洋画的でもない。純粋の日本的
技法であり、彼の独創である。そこを見ないで、一片の洋画として批評されたのがやり切
れなかったろう。
明治十年といえば、長八は六十三歳になっている。彼の芸術は円熟していた。そこには
確固とした自信があった。それが、西洋追随に反発したのである。以後博覧会には出品し
ない。長八の矜持が許さなかったのであろう。
彼はこの時を契機に、更に日本的に東洋的になって行く。彼は彼なりに『おのれの道』
を固めるようになる。それは老人の固陋とも見える。また一徹とも言える。
内国勧業博覧会が、長八に与えたものがもう一つある。山岡鉄舟との出会いである。
内国勧業博覧会の閉会式は十一月三十日、天皇、皇后を迎えておごそかに執行された。
席上、出品者に褒賞状が渡され、式後、一同うちそろって祝宴となった。大広間に西洋流
のテーブルが並び、大勢の人がにぎやかに祝杯を挙げた。その中には、政府の高官やその
夫人たちの洋装姿も見られた。出品者の多くは職人で、和服に白足袋という服装で、その
対象が珍妙であったろう。明治初年の世相そのままを一堂に活写した観があった。
この時、長八は静岡から出て来た寄木細工の名手山本安兵衛と席を並べていた。始めて
の知り合いだったが、静岡ということで話がはずんだ。二人とも酒は余り飲まない。職人
育ちの二人には場違いな空気で、二人だけで静かに盃を交わしているだけだった。そこへ
人波を分けて、一人の男が近寄って来た。官服を着ていた。相当の高官のようだった。安
兵衛が眼ざとく見て、
「山岡様」
と言いながら、椅子から腰を浮かせた。
「安兵衛さん、よく来なさったね。この度はおめでとう」
「はい、ありがとう存じます」
「元気なようだね」
「はい、山岡様も」
立ちながらの会話だった。長八はぽつりと取り残されたように、手持ちぶたさに窓に眼
をやっていた。
「長八さん」
安兵衛が腰をかがめて、座っている長八の耳にささやいた。
「御紹介しましょう」
言われて、長八は椅子から身を起こして、先方を向いた。長髪で、ひげを深々と垂らし、
眼が大きい男だった。
「入江長八さんです。鏝絵の名人で」
「こちらは山岡鉄舟様、ご存知でしょう」
安兵衛は続けざまに二人を引き合わせて、心持ち一歩さがった。
「入江長八と申します」
「山岡です」
二人は互いに挨拶を交わした。山岡鉄舟は五十歳前後と見受けられた。
「御出品の富士の図、まことに立派な作で、感動しました」
鉄舟が言った。
「恐縮です」
長八が答えた。
「あなたのことでしょう。伊豆長と言われるのは?」
「へえ、さようで」
「お名前は以前から知っておりました」
「恐れ入ります」
三人は立ちながら雑談に入って行った。
山岡鉄舟。本名鉄太郎。人も知る幕末維新の立役者。維新後、しばらく徳川慶喜に従っ
て静岡に居たが、やがて宮中に仕え、宮内大書記官の要職にあった。剣をよくし、自ら無
刀流の祖となり、書にも優れ、勝海舟、高橋泥舟と共に三舟と称せられていた。更に禅に
参入して、深い信仰の人であった。
高名な顕官でありながら、少しも尊大なところはなく、長八にも親しい友人のように話
し掛けた。
「長八さんは伊豆のどこの生まれで」
「松崎という村です。西海岸の漁村です」
「そうですか。三島にはよく参ります」
「へえ」
長八が驚いたような顔をしたので、鉄舟は補足するように言った。
「禅の修行にね。三島の在に竜沢寺という寺がありましてね」
すると、長八はそこで急に言葉をはさんだ。
「すると、星定禅師に?」
鉄舟は驚いたように、
「そうです。よく御存知ですねえ」
「いえ、人から聞いて知っているだけで」
長八は三島の茂平を思い出していた。竜沢寺も星定禅師も、皆茂平から聞いた話である。
ふと、長八は鉄舟が茂平を知っているかも知れないと思った。
「先生は、三島の茂平という老人を御存知でしょうか」
と思わず言った。すると、
「茂平さん、無外居士ですね。よく知っています」
「そうですか」
「あなたとどいう知り合いで?」
鉄舟は意外に思ったらしく、今度は長八に質問した。
「へえ、実は同郷でして」
「ああ、そうそう。無外居士から松崎生まれだと聞いたことがありました」
鉄舟は思い出したように手を打った。
「というより、私にとっては大恩人でして」
と、長八は付け加えないではいられなかった。
「大恩人というと?」
興味を持ったように鉄舟は聞いた。
「若い頃、私がぐうたらな生活をしておりました時、茂平さんからきつく注意されまして、
そのおかげでやっと一人前の人間になれました」
長八は悪びれずに言った。鉄舟の前では何でも思うとおりを言ってしまいたいような気
がしていた。
「そうでしたか。あの人は誠実な人ですからねえ」
祝宴は終わった。人々は散り散りに大広間から消えて行った。気がついて、三人は互い
に促がすように、ゆっくりと外に出た。
この時以来、鉄舟と長八は次第に深い友情を持つようになり、名人と達人は共に肝胆相
照らす仲となる。
③
内国勧業博覧会があって、長八の心境は『おのれの道』ということでいろいろと考える
ようになっていた。悩み始めたといった方が当たっているかも知れない。それは、川上冬
厓の『西洋の技法を習う』といった言葉とも無関係ではない。また、山岡鉄舟が雑談の中
で示した人間味ともつながるようだった。とは言うものの、長八の考えは漫然としたもの
で、これからの『おのれの道』をどう考えて歩いて行こうか、ということだった。ただ純
一な芸の道だけではいけないということだけは、心の底に固いしこりを持っていた。
鉄舟と別かれて十日ばかり経った。もう十二月で、町には木枯らしが吹き始めていた。
そんなある日、鉄舟から手紙が届いた。長八は待っていたように、急いで官邸に出掛けた。
この時のことは会話体で書くとくどくなるので、概略を記述することにしよう。
実は、長八は鉄舟に会った最初から、その風格にひかれていた。それは心の深さを感じ
させるものであった。そして、長八はそれを芸術の上に移して、深い反省をしていたので
ある。芸術とは自分の向こう側にあるものではなくて、内側、つまり自分の側にあるもの
だという意識が一つの問題として提起されていたのである。そんなことを、鉄舟先生に会
って話してみたい。教えてもらいたい。長八は鉄舟邸に着くまで繰り返していた。
鉄舟は世間話から始めた。時節柄、西郷隆盛の人柄に触れた。すでに九月二十四日に、
西郷は城山において自決していた。それだけに山岡鉄舟にとっては感慨深かったのであろ
う。懐かしく鉄舟は西郷という一人の人間を語った。が、長八はその話を聞きながら、人
間の深さというものを強く感じた。それは逆に自分自身の浅薄さであり、芸の上にもそっ
くりそのまま当てはめられることだった。
やがて、話題は転じて芸術の問題になった。鉄舟は書の話をした。大師流の書法を学ん
で大師流から脱け出す苦労を語った。合わせて、剣の道も同じだと説いた。無刀流という
一派をつくった理由を語った。剣を剣とせず、心を刀とし、心で斬るという無刀の極意を
話した。その話の中に、しばしば禅の話が挿入された。長八は終始聞き役に廻って鉄舟の
話をうなずきながら、自分の心に刻んでいた。鉄舟の話は、剣も書も一つであった。長八
はそこに大切なもののあることを感じていた。………鏝に手頼っていてはいけないのでは
ないか。心で描くのだと概念的にはわかっているが、それはどういうことなのか。長八は
考えているのだった。
話は三転して、信仰の話になっていた。禅の話から、茂平の話になり、そこにある人間
的な深さが、いやというほど長八の胸を強くゆさぶった。長八が考えていた仏教とか信仰
とかはまるで幼稚なもののように思えた。………おれは芸術の上の知恵としてだけしか仏
教を考えていなかったのだ。芸の上の信仰としか考えていなかったのだ。鉄舟先生の話は、
方便の宗教でも、信仰でもない。それは絶対だ。それ自身だ。長八はまだはっきりとはし
ないながらも、心の問題が少しわかって来たように思った。
話が三島の話になり、竜沢寺の話となった。ふと、長八は心の一隅に抱いていたことを
鉄舟に話してみたいと思い出した。
「先生」
と長八は言った。
「変な話ですが、聞いて下さい。お話を聞いているうちに思い出したのですが、もう十年
も昔、私は成田山に参篭したことがございます。不動明王を修理するためでした」
「うん、そういう話を聞いたことがあります」
「その時以来、私は時々不動明王の夢を見るようになりました」
「ほう、夢をねえ」
「その夢というのが、いつも決まって同じような夢なのです」
「なるほど」
「お不動様が必ず童子を二人左右に連れて現われます。そして、何か言われるのですが、
それがはっきりとしません。しかし、おしまいには必ず富士の南に住んでみたいと、その
ように言うのです。そこだけがはっきりと聞きとれるのです」
「富士の南ねえ」
鉄舟は何かを考えるように腕を組んだ。
木枯らしが閉め切った障子の向こうで寒々と音を立てていた。二人の間の火鉢に、炭火
がほんのりと暖かかった。
「で、先生のお話をうけたまわりながら、ふっと思い付いたのですが」
「何です?」
「先生のお話の三島の竜沢寺です。あそこは富士の南に当たります」
「そうだ。富士の南だね」
「不動明王が住んでみたいというのは、竜沢寺のことではないかと思ったのです」
「なるほどねえ」
「で、先生のお話のように、私も参禅をしてみようかと思います。そして、不動明王が住
みたいと言ったのは、確かに竜沢寺かどうか確かめてみたいと思うのですが」
「なるほど」
鉄舟はまた腕を組んだ。
「それはそれで結構なことだが、不動明王をどうするんですか」
と鉄舟は聞いた。
「私の手でつくって、安置するのです」
長八の答えを聞いて、鉄舟は膝をたたいた。
「なるほど。竜沢寺にあなたの不動明王を安置するんですね。いいじゃありませんか」
長八は鉄舟の同意を得て、ほっとした気持ちになった。
「もし先生が御同意なら、直ぐにも竜沢寺へ参りたいと思います」
「随分急な話ですねえ」
「で、先生から星定禅師へ手紙をお願い出来ませんでしょうか」
「それはお安い御用です」
「もし竜沢寺に不動明王を安置することになれば、私は力の限りを尽くしてやり遂げよう
と存じます」
長八は顔に必死な色を浮かべた。
「そこにほんとうの芸があるかも知れませんね」
「承知してくれますか」
「もちろんです。星定禅師に一筆したためましょう」
鉄舟はそう言うと、直ぐにかたわらの硯箱の蓋をとった。静かに墨を磨った。筆をしめ
すと、さらさらと手紙を書き始めた。
さすがに、長八は直ぐに三島に発てなかった。年の暮れだから何やかやと忙しく過ごし
た。この間に旅の支度もした。
年が明けて、明治十一年である。三が日をすますと、長八は急いで東京を発った。出発
の前夜おはなと竹次郎、兼吉、それに中橋善吉を呼んで、始めて参篭の決意を述べ、こま
ごまと後事を頼んだ。竹次郎や善吉が、老齢を危ぶみ、仕事を心配して引き止めようとし
たが、長八はがえんじなかった。
「今度のことは命がけのつもりだ」
と長八は言った。百日の参篭は季節的にも容易なことではない。生きて帰るか、死んで
帰るか、はかり知れない。そんな憂慮が皆の心を固くしていた。が、長八は、それはどっ
ちでもいいと思っていた。ただ必死に自分の願いを遂げたかった。
ささやかな別れの盃を交わした。互い胸の底に重いものを抱えているような寡黙な夜が
更けていた。が、長八はひとりさっぱりとした気持ちでいた。後事を托して、後はおのれ
のことしか心になかった。竜沢寺へ行くだけである。百日の参篭がどうであろうと、そし
てどのような結果になろうと悔いはすまいと思った。
三島に着いて、茂平を訪ねた。茂平は七十一歳の老齢だが、昔のままの元気さだった。
息子の儀三郎夫婦が家業をしていて、茂平は奧の隠居所で起居していた。息子夫婦を混じ
えて、その夜は晩くまで語りあかした。
翌朝、茂平が案内役で竜沢寺へ行った。道すがら、農家の庭の梅の花を賞でたり、田圃
の麦の生育ぶりに足を止めたりした。冬枯れの箱根の山に雲が影を引いていた。
竜沢寺の山の険しい坂道を登って行った。大杉の立ち並ぶ下道は冷え冷えとしていた。
赤土の地肌に霜柱が立ち、微かな音を立てて崩れた。杉林を抜けると、からっと眩しい日
が照っていて、そこに山門が曝された姿で立っていた。二人はためらうことなく山門を潜
った。広い庭には人影もなくひっそりしていた。
長八は茂平の後から庫裡に入った。案内の僧に導かれて、黒光りのする廊下を渡った。
冷え冷えとした山気が、長八の心を緊張させていた。
隠寮に来る。番僧が開けてくれた戸口から二人はそっと入った。星定禅師は庭に面した
障子に向いて読書していたらしく、本を机に開いたまま、くるりと向き直って、二人の姿
を見定めるような顔を向けた。
「いらっしゃい」
禅師は二人に笑顔を見せた。茂平が挨拶するのにつれて、長八も頭を深く下げた。茂平
が長八を紹介した。長八は、
「入江長八と申します」
と、懐中から鉄舟の手紙を出した。
「鉄舟先生から」
禅師は手紙を手にして、封筒の裏書を懐かしそうに眺めた。
「鉄舟先生はお元気だったかな」
封を切りながら禅師が言った。
「はい、暮れにお眼に掛かりましたが、大層お元気で」
禅師は返事もせず、鉄舟の手紙を読み出していた。達筆の文字が日に透けて見えていた。
裏山からうぐいすの声がのどかに聞こえていた。禅師は手紙を読み終わり、もう一度独
りうなずくように手紙をたどった。手紙を机の上に置くと、
「長八さんとやら、あなたは鉄舟居士とどういう知り合いなのかね」
と禅師が聞いた。
「はい、去年の十一月、勧業博覧会で偶然お眼に掛かりまして」
「うん」
「二度目はお宅に呼ばれまして、お手紙を書いて頂きました」
「余程気が合ったと見えますな」
禅師はそう言って笑った。物静かな、優しい表情が暖かく感じられた。
「不動明王を造立したい由だが、あなたは不動尊を信仰していなさるのかな」
すると、茂平が代わって答えた。
「実は、この男は私と同郷でして、若い頃ちょっとしたことで知り合いになりました。東
京では、伊豆長と言えば左官の名人で通っている程です。成田山の御本尊を修復した縁で、
不動様を信仰しております」
「なるほどね」
「おかしなことですが、夢にしきりに不動様が現われて、富士山の南に住みたいというの
で、鉄舟先生に相談したんだそうです」
「そこで、この寺がいいということになったというわけか」
禅師は面白そうに微笑していた。
「ま、そういうことです」
「夢を実現しようというわけだね」
「そうです」
「そういえば、ここには不動尊が祀られていない。あなたの言う『富士の南』とは、ここ
のことを言っているのかも知れない」
④
「ま、やってみなされ」
不動明王像について一部始終を聞いた禅師は、禅僧らしく簡明に了解してくれた。
「ありがとうございます」
長八は深く頭を下げた。
「いやいや、礼はこちらから言わなければならない。奇特なお心じゃ。是非とも立派な不
動明王をつくって下され」
と禅師が答えた。長八の心に、強い厳しい決意が改めて動いていた。
「とすると、場所だが、どこがよかろう」
禅師は今度は茂平に話し掛けた。
「そうですねえ」
茂平はちょっと考え、禅師の顔を見て、
「老師、山を歩いてみませんか」
と言った。
「実地を調べた方がいいでしょう」
と付け加えた。
「そうしよう」
禅師は言葉と一しょに、身軽く立ち上がった。
三人は庫裡から庭に出た。ひと廻り庭から山を見渡した。無言のまま裏山の林に入り、
岩角を曲がり、かさかさと落葉を踏んだ。冬草が風にそよいでいた。やがて、ひとめぐり
して、元の庭に出た。
「どこがよかろう」
禅師が茂平に言った。
「あそこはどうでしょう」
茂平が指さした。山門に向かって左側の山際のやや小高い地点に、苔におおわれた岩が
いくつか重なり合って、その直ぐ後に、大杉が高く黒く立っていた。
「うん」
と禅師がうなずきながら、すたすたとその方へ歩いて行った。
「格好な位置じゃ」
と、禅師は岩に手を当てて辺りを見た。
「長八さんはどう思う?」
「私には異存ありません」
「そうか。それではここに決めよう」
三十分ばかりで不動堂の位置が決まった。
竜沢寺は三島市沢地にある。臨済宗妙心寺派の寺で、白隠禅師の開基という。人里離れ
た幽寂の地で、今日も尚禅道修行の好適な環境である。創建は江戸末期で比較的新しいが、
白隠の道統を承け継いだ高僧が輩出し、高名な軍人や政治家などもここに参禅している。
竜沢寺に『天祐居士造立不動尊記』という一文が今も残っていて、その当時の状況を伝
えている。
『去る明治十一年冬日、たまたま吾山に登り、しかして独妙老祖に誓礼す。ゆえに得々孤
杖、徐々扶老、ここにおいて一路林をうがって歩む。青苔なめらかに、片雲岫に出で、塵
外の域に卜して、鬱々たる喬木屋舎を囲統し、洒々たる乱水山腰を曳帯し、南隅に直下数
千畝の田圃を視、東鱗には則ち数十戸の村家羅列す。四神相応の霊地というべきなり。あ
に欣喜せざるべけんや』
と、長八が竜沢寺に来て風物を見た状況を述べ、これに続けて、
『即ち踊躍して、急率に予の陋室に敲着し、委曲円満、霊感夢想の付嘱を約し、尅期一百
日を誓う。沐浴斎戒、しかのみならず、二六時中明王の秘密の咒を口誦し、一匕の泥土、
寝食倶に忘る。遂に明王の尊形を模造し、当山の安じて措きおわんぬ』
と、不動尊造立のいきさつを簡潔に記している。文章が仏家らしい句調でやや難解では
あるが、大よその意味は了解出来よう。この文章は星定禅師の筆になるものと言われてい
る。
さて、長八はそのまま寺に居残り、茂平は一人、山を下りる。いよいよ不動明王造立の
生活に入るのである。
伝説によれは、この時長八は円頂(坊主頭)に白衣をまとい、香を焚いて制作したと言
われているが、長八の円頂、白衣はすでに明治三年妻おたきの死後からずっとのことで、
この時始めたというのは誤りである。
ついでに、長八と不動尊との因縁をここに考えてみよう。幼少時代、長八は郷里の牛原
山麓の不動堂を知っている。この不動堂は長八の家から見られる位置にあり、長八にとっ
ては幼少時の思い出の中で忘れられないものであった。村人は毎月おこもりと称してここ
に夜を明かすことがあった。そんな時、読経の声が不動堂の夜明かりと共に、神秘な感動
を呼んだことであろう。たまには祖母や母に連れられて夜を過ごしたこともあったろう。
遊び盛りの頃は、よくこの不動堂の前を通って山に登った。こうして、不動明王のいかめ
しい姿は長八の脳裡に鮮やかに焼きついていたはずである。十二歳で左官になってからは、
職業柄不動尊を信仰したのは当然で、ことに江戸に来ては、月々の参詣は欠かしてはなら
ず、祭事も丁重であったから、長八の不動尊への関心は生活に密着した深いものであった
と言える。そんな関係で、成田の本尊不動の修復に当たったのだが、この七日間の参篭は
いよいよ不動尊信仰の心を深めたに違いない。すでにこの時長八は不動明王の仏教的意味
を理解していて、以後の生活に深い関係を持つようになっている。世俗的な火防の信仰以
上のものを感得していたのである。人間の上に、芸術の上に、彼は不動明王の心を加えよ
うとしたのである。しかし、それは当然苦悩をともなう。自分の弱さ脆さを打ち砕くこと
で苦しまなければならなかった。青年期の自棄と虚無と無頼と不倫は、彼にとっては一時
的なものとして軽く考えることは出来なかった。家庭的な不運、不幸も常に心につきまと
っていた。それらは芸術の上に何らかの形で撥ね返っていた。芸術の上でも、彼の仕事が
独創的であるための悶えがあった。それらが迷いでもあり、悩みでもあり、いわば彼の弱
さ脆さにつながっているのであった。不動への信仰はこうして彼の心の中に強く結びつけ
られたものである。もう一つ重要なことは、欧洲思潮の流入に対しての彼の反逆である。
文明開化にある種の価値を認めながら、彼は一点において反感を抱いていた。しかし、そ
れが果たして正しいかどうかということになると、彼ははっきりした判断を持てなかった。
そこに迷いがあった。自然に『おのれの道』を考えるようになったが、それは見ようによ
っては孤立であり、また逃避でもあった。この矛盾の中で、彼は不動明王に救いを求めた
と言える。彼の夢枕にしばしば不動明王が現われたということは、彼の心の願いの象徴で
あったといえよう。
とにかく、こうして竜沢寺に来た。そして百日の参篭に入った。
竜沢寺の早春は冷たかった。が、彼は心の戦いをいどんだ。不動明王を造立することに
命を賭ける気持ちだった。
禅師が定めてくれた一隅に、一坪の仮小舎を建てた。三島の町へくだって行って、仕事
の材料をととのえ、それを背負って、何度も往復した。そして、準備がととのって、いよ
いよ百日の参篭に入った。
竜沢寺の早暁は天にも地にも冷気が固く凍って動かない。寺も杉林も岩も、山に懸命に
しがみついている。突然僧寮の一角から板木の音が重く空気をゆるがす。一つまた一つ。
すると東の空にほのかな明るさがにじんで来る。
雨戸を繰る音がする。僧たちの姿が暗い廊下を動く。しばらくして、元のひっそりとし
た寺になる。と、静かに湧くように僧たちの勤行の声が流れて来る。勤行の声と共に、朝
の色が真上の空にひろがって来る。
長八は板木の音よりも先に眼覚めていた。仮小屋のむしろの上に端座していた。板木の
音を聞くと、庭を横切って道場へ入った。
座禅一刻。警策の音が時々道場の外まで響くように聞こえた。長八の脳裏にはさまざま
な想念が浮かんでは消えた。入り乱れたり渦を巻いた。
勤行が終わると、僧たちと一しょに朝の粥をすすった。食事がすむと、仮小屋にもどっ
た。そして再び端座して読経専念に入った。やがて、静かに紙をひろげ、不動明王の姿を
描いてゆく。描いた上に筆を加える。はては形もわからないようになると、紙を替えてま
た描き出す。
昼が過ぎ、一刻ばかり日が射して暖かだったが、直ぐにかげって、早くも日暮れの冷気
が漂って来る。長八はそれも知らぬげに、黙想し描画している。
夜が来る。食事、勤行、座禅、僧たちとの勤めをすますと、仮小屋にもどって、また端
座し黙想する。
二日三日と日は過ぎて行った。不動明王の絵姿はまだまとまっていなかった。単調な日
々であったが、長八は真剣であった。しかし、時々空をよぎる雲のように俗念が浮かぶこ
とがあった。おはなと竹次郎は。兼吉は。清太郎は。また過ぎ去ったことがなまなましく
想い出されることもあった。おたきとのこと。源次郎のこと。
十日経った。さすがに疲れが感じられた。長八はそっと手首を握って見た。少し痩せた
ように思えた。夜もすがら頭の上で杉の枝が激しく打ち合う時があった。こがらしが杉の
梢をうなり続ける日があった。朝眼覚めると、暁闇の中に雪が積もっていた。昼も仮小屋
の中に冷たい風が吹き込んだ。手足が凍ってしびれた。こんな日が続いた。まだ長八は不
動明王を描き続けていた。
やがて二月になった。寒さはますます厳しかった。長八はめっきり痩せた。ある夜、ま
たしんしんと雪が降り出し、一晩中微かな音を立て、朝になって止んだ。竜沢寺の屋根も
杉林も一面の雪であった。勤行からもどる長八の足跡が雪の中に一筋の点線を描いた。雪
は止んでも、風は身を切るように冷たかった。
仮小屋ではすでに土が運ばれ、長八は荒土を練り、練った土を積んでいた。不動明王の
絵姿は彼の眼の前に鮮やかに描かれてあった。土を練る手が凍った。
五日経ち六日経ち、土の塊は徐々に不動明王の形をなすようになっていた。しかし、長
八の頬はこけ、頬骨が尖り、円頂には白い毛がのびていた。気力も衰えて来たことが自分
でもよくわかった。疲れて眠りに落ちそうになると、彼はわざと立って、小窓の外に首を
出して寒気に曝らした。
二月も半ば過ぎると、春めいた日射しを感じる日があった。早くも五十日になろうとし
ているのである。そう思うと、長八は一心に土を練り鏝を使った。そんなある日、仮小屋
の戸口を細くあけて、星定禅師と茂平がのぞいていた。しかし、そのまま静かに去って行
った。
二月の終わり、また雪が降った。いつのまにか、仮小屋の中には不動明王がそのすさま
じい姿を見せていた。その不動像に、長八は飽くことなく鏝を使っていた。痩せ細った手
に力をふりしぼっているようだった。眼はくぼんで視力が衰えていた。腰がしびれた。そ
れだけに長八は必死だった。
三月になって、ようやく気温もゆるんで来たかと思うと、次の日には急に氷雨が降った
りした。長八はいよいよ痩せ衰えていった。
⑤
杉林の中から小鳥の声が聞こえるようになり、裏山の雑木の梢におずおずと新芽がふく
らんできて、寒い冬もようやく終わろうとしていた。竜沢寺境内の仮小屋には、不動尊と
二童子が荒むしろの上に並び、すっかり出来上がったように見えたが、長八はまだ飽くこ
となく、終日鏝を動かしていた。
とうとう百箇日の満願の朝が来た。彼は徹夜で最後の仕上げをした。げっそりと痩せた
顔に白髪がぼさぼさと伸びていた。くぼんだ眼に高窓から射し入る朝の光を眩しげに受け
て、彼は静かに鏝を置いた。その眼に心なしか安らぎの色が感じられた。
彼は手を合わせて不動明王を拝した。そして、ひょろりと立ち上がった。立ち上がると
背の高い人だけに一層痩せて細って見えた。やがて、板戸をぎしぎしときしませて開いた。
春らしくなった山を仰いだ。静かに庭を横切って行った。朝の勤行に行くためだった。さ
まざまな感慨が走った。百日の間作って来た『おのれの道』を確かめるように、ゆっくり
と歩いて行った。
勤行をすますと、長八は隠寮の戸をたたいた。そこには禅師と茂平が対座していた。
「老師さま、茂平さん」
長八は痩せた膝をぺたりと折って手をついた。
「おかげさまで満願になりました」
「おめでとう」
「おめでとう」
二人が口をそろえて言った。
茶が運ばれて来た。熱い番茶が腸にしみた。
「老師さま、茂平さん、どうぞ仮小屋へ」
と長八は声低く言った。
「うん」
二人が立った。長八が戸を開けた。
仮小屋の中はすっかり整理されて、不動明王と二童子は荒むしろに並んでいた。
先頭に立った禅師が、
「うーむ」
と、不動尊に見入った。そして、静かに膝を折って合掌した。茂平も横に並んで手を合
わせた。
「立派な出来じゃ」
頭を上げて見入っていた禅師がつぶやいた。
「さすがに長八さんだ」
茂平が言った。
さわやかな風が戸口から流れていた。長八は何とも言わず、不動明王の姿に眼を凝らし
ていた。
「百日の参篭と一口に言うが、並大抵なことではない。寒い盛りだし、体にこたえたろう」
「ほんとに、よくやりました」
禅師と茂平がこもごも言った。
「無事に満願の日を迎えて、ほんとうにありがたいことです」
長八は自分のことよりも、この事を成し遂げたことを喜んでいた。
「実はなあ、時々のぞきに来ていたんだよ」
と、茂平がくつろいだ調子で言った。
「長八さんの一心不乱の姿を見て、そうっと帰って行ったよ」
禅師が言った。
その日の午後、不動尊像は大勢の僧たちの手で僧堂に安置された。僧たちの読経の後、
星定禅師によって開眼の儀式が行われた。式後、禅師は長八に居士を允許した。以来、長
八は天祐居士と称し、作品にも署名するようになる。
その日の夕刻、長八と茂平は共に山を下った。山路はもう春の息吹が満ちていた。
「私が山に来たのは一月十一日でした。寒い日でしたねえ」
と長八が独り言のように言った。百日の時の流れが長八の胸に深い感動を呼んでいた。
「草も木も枯れていたのに、それがこんなに生き生きと輝いて」
「全くだ」
茂平が相槌を打った。
「お前さんの心にも春がめぐって来たろうか」
「さあ」
長八は返事をためらった。悟ったようなことは言いたくなかった。ただ、今までのよう
な煩悩は再び繰り返すことはあるまいと思った。
「とにもかくにも不動尊をつくり上げただけでうれしいのです」
長八はそう付け足した。
「そうだな。それでいいんだ」
茂平はいつくしむように言った。
「百日といっても、長いようでもあり、短いようでもあり、不動さまにすがって夢中で過
ぎただけの感じです」
「なるほどなあ。やっぱり、長八さんは参篭をしてよかったのだな」
「ええ、ええ、ほんとに」
二人はいつか山を下りていた。山沿いの道を歩いていた。麦は青く一ぱいに土を埋めて
いた。道のかたわらの草中にしどめの朱の花が咲いていた。
会話が途切れた。
「疲れたか」
茂平が長八の顔を見た。
「安心したからでしょう」
長八は苦笑した。足が重く、茂平と並んで歩くのが苦しかった。
「すっかり痩せたからなあ」
茂平はつぶやいて、少し歩調をゆるめて、長八に寄り添うようにした。
「痩せましたねえ」
長八は自分の手をまくった。ぴたぴたとたたきながら笑った。
「わしの家でしばらく休養すれば、直ぐ元通りになる」
「そうさせて下さい」
二人の友情が、そんな他愛もない会話にもにじんでいるようであった。
二人はのどかな春の夕暮れをゆっくりと歩いて行った。長八の心はなごんで静かであっ
た。百日間の魂の戦いは嶮しかったけれども、今はそれも楽しい過去であった。登り詰め
た山頂から歩いて来た跡を見下ろしているようなさわやかさが胸に満ちていた。
三島の町に入った。水上の若葉の林の下を歩いて行った。水上の水が清らかに光ってい
た。しばらく二人はそこの岩に腰を下ろして休んだ。
「きれいな水ですねえ」
「富士の雪水だ」
「澄んで、無垢で、惜しげもなく湧き出て、流れ去って」
「人生もこうありたいなあ」
「そうですね」
長八は立ち上がって、水の中に足を浸した。底砂が一瞬さっと浮き上がったが、そのま
ま元の清らかさにもどった。長八は水に透る光をしみじみ見ていた。しみじみ見ていたの
は水の光ではなく、おのれの心であったのかも知れない。
水上の水は、熔岩群の隙から湧き出る地下水で、いわゆる『富士の白雪、朝日に溶けて、
溶けて流れて三島にそそぐ』という農兵節の三島の水の源泉である。この水は三島の町を
幾筋にも分かれて流れて行く。
二人はその一つの水路をたどって三島明神の森に出た。二人にとって最も因縁の深いと
ころである。二人は社前に立った。長八は手を打って、深くうなだれた。その時、意識し
なかったが、半兵衛の彫刻が二人を見下ろしていた。若い頃の荒涼とした生活、自虐の日
々が生ま生ましく思い出された。もしあの時茂平さんに会わなかったら………。そう思う
と慄然とした。運命の不思議さを思った。
「懐かしいですねえ」
長八は茂平をかえり見た。これ以上の言葉はなかった。
「そうだなあ」
茂平が微笑した。茂平の頭の中も、同じような感慨が浮かんだことであろう。
二人は社前を背にして大鳥居を潜った。直ぐ東海道の町筋である。かって、長八が茂平
に呼び止められた場である。
三島の町は明治になってから、少しずつ変わっていた。宿場町の面影が薄れて、田方平
野を抱えた商業都市になりつつあった。
茂平の家は三島明神から直ぐだった。
「ようこそ」
と、儀三郎夫婦が待ち構えていたように二人を迎えた。養女おしまもかわいい小さな手
をついて、
「今日は」
と挨拶した。
「しばらく厄介になりますよ」
と、長八は儀三郎夫婦に言った。
「どうぞ、こちらはそのつもりでおりましたから」
と儀三郎が言った。
「随分お痩せになりましたね」
と女房のおとしが言った。
「修行だからねえ」
長八は痩せた顔のひげを撫でた。
座敷に落ち着くと、祝宴の用意がしてあって、次々に運ばれた。家族そろって膳につい
た。酒は腸にしみた。
「酔わないうちに言って置こう」
茂平が言った。茂平は老齢になっていて、酒を節していた。
「老師さんからの頼みでな、あと一と月ばかりすると、隠寮の改築をするんだそうだ。で、
ついでのことにお前さんに壁をやってもらいたいと言うんだが、承知してくれるだろうな。
一と月もすれば体も元通りになるだろう」
茂平は老師と話して、長八の仕事を承知して来たような話しぶりであった。
「そうですか、喜んでやらしてもらいます」
「そうか、やってくれるか」
茂平は安心したように、思う通りにいったことに満足したように口もとに笑みを浮かべ
た。
「今度のことのお礼です」
と長八は言った。
「だが、この体では直ぐに東京に帰るわけには行かない。どうだろう、一と月ばかりのこ
とだ、ここにそれまで居たら」
茂平が提案した。
「そうですよ。その体では当分は旅は無理ですよ」
と儀三郎が応じた。
「遠慮はいらないよ。たった一と月だ」
茂平は長八が黙っているのを見て遠慮していると思ったらしい。
結局、茂平の家で暮らすことになり、この間にいくつかの制作をしている。その一つ、
『浜松の図』(損壊)は三島学校の内壁欄間に描いたもの。灰色地に鏝だけで描いた作品
で、私の友人瀬川真君の話によると、三島学校が移築される時、瀬川君の父君が偶然その
壁を壊すところに来合わせて、その一部をもらい受けて保存していたという。そのまた一
部を私がもらって、大切の保存しているが、それによっておよその構図や鏝さばきが想像
される。その二つは『恵比寿大黒像』。茂平の家のためにつくり、底銘に始めて『豆州天
祐居士』と記している。その外にもいくつかあると想像されるが、今のところわかってい
ない。
さて、長八の百日の参篭は、長八に何を与えたか。これについて、伝説は一切無言であ
る。あるいは、語られるべきことではないかも知れない。ただはっきりわかることは、芸
術的なものではなく、長八個人の精神的なものであったこと、それは彼の以後の行動の中
に十分に察知される。しかし、精神的なものが芸術に関与することは当然で、彼の芸術は、
鏝の芸術から心の芸術へ変化して行ったと言えるようである。それは『浜松の図』が一つ
の証拠とも言えよう。
⑥
長八は日が経つにつれて体力が出、体も元のようになっていった。しばらくは、おしま
を相手に絵を描いたり、茂平と共に近隣を歩いたりしていた。三島学校の壁にいくつかの
作品をのこしたのもこの時期であった。
たちまち五月になって、竜沢寺の隠寮の工事が始まった。頃合いを見て、工事の現場を
検分した。長八が仕事に掛かったのは五月も末の頃だった。
隠寮というのは、老師の居室のことで、般若窟と称していた。書院の裏手に一段高く建
てられ、障子をあけると、裏山が迫り、池庭があり、簡素閑雅なところであった。若葉が
輝いていた。小鳥の声が聞こえた。いい季節であった。
ここで制作したものは、今日もほとんどそのままに保存されていて、長八の円熟期の作
品展の観がある。特に、彼が鏝絵を始めてからの種々の技法がほとんど余すところなく一
堂に見られるのは、ここをおいて外にはない。恐らくは、長八自身が意識的にそうしたの
であろう。いわば、彼の集大成をここに示そうとした。と同時に、すでに老境にある彼が、
これを自己の記念碑として示そうとしたのではないかと思われるのである。
室内の壁に、床脇には『柳につばめ』、次の間には『松に竹』、その欄間には『竹』を
描き、それらは『浜松の図』とは違った着彩で、しかも『浜松の図』に見られるような鏝
に筆意をこめたものを表現している。その外に、壁絵、衝立、扁額、塑像など、極めて多
彩な作品を遺している。中でも注目されるのは、杉戸に施したもので、一方には青緑金碧
の山水図を披麻皺(ひまじわ)の技法で描いた南画風の作品であり、もう一つは、出入口
の二枚戸に白漆喰で『水月坐道場、空花修万行』の筆太の文字である。結城素明氏は『そ
の杉板の脂止めをどうしてあるのかわからないが、余程完全な技法と見えて、保存は非常
によい』と言っているほどで、杉板にじかに漆喰がぴたりと着いているのは不思議である。
いつか竜沢寺にも夏が訪れていた。夜は杉林の奧でふくろうが鳴いた。雨のしとしとと
降り始める梅雨の季節になると、ほととぎすが山をかすめて鳴き過ぎた。長八は制作欲に
かられていた。次々と作品をつくった。山水花鳥、静物風景。あるいは大和絵風に、ある
いは南画風に。彩色的なものと鏝の筆致を示すものと………。長八のあらゆる力が具現さ
れてゆくようであった。
長八が百日の参篭を無事に過ごして、不動明王の造立をなし得たことは、東京の弟子た
ちを喜ばせた。引き続いて隠寮の仕事をするという便りが届いて、弟子たちは次々に長八
を訪ねて来る。師匠の慰問であり、ついでに仕事の手伝いをしようというのである。竹次
郎は兼吉を連れて来た。次いで芝の市五郎が石井勝之助、巳之助の兄弟を連れてやって来
た。工事が終わる頃、静岡の桜井東吉も来た。
東京から来たものは長八への慰労と手伝いのためだったが、桜井東吉には別な用があっ
た。その用事を持って、東吉は上京したのであるが、上京して見て、長八が三島に来てい
ることを知った。用件というのは、清水の鉄舟寺の今川貞山和尚に頼まれて、寺に安置す
べき本尊の観音像を長八に制作してもらうためだった。東吉は同じ用件のため、先に山岡
鉄舟を訪ねていた。鉄舟寺は山岡鉄舟が、廃寺になっていた久能寺を再建して、禅道場と
したのであるから、本尊を制作するについても、当然承認を得なければならなかったので
あろう。鉄舟に会ってみると、鉄舟はすでに長八を知っていて、そのため、長八宛に添書
さえ書いてくれた。東吉はその手紙を持って三島に引き返したのである。言いそびれたが、
桜井東吉は長八の明治になってからの弟子で、その頃は静岡に帰って独立していたのであ
る。
鉄舟の添書まであるからには、静岡へ行かないわけにはいかない。幸い竜沢寺の仕事も
片付いていた。長八は東京の弟子たちを帰し、東吉と共に静岡に出掛ける。
静岡では、東吉の家に居て、仲間の左官たちに鏝絵の指導をしばらくしたが、間もなく
清水に移って、鉄舟寺の観音像の制作に取り掛かる。この制作は僅か十数日のことであっ
たが、この短い期間に、長八はかっての侠客清水の次郎長と知り合う奇縁を持った。
清水の次郎長は、明治になってからは侠客ではない。もちろん博徒でもない。が、その
信望と勢威は衰えてはいなかった。維新後山岡鉄舟の知遇を得、種々の社会事業に尽くし、
鉄舟寺の再建にも助力していた。当時五十八歳。長八よりも六つ若かった。
「山本長五郎です。お名前はかねがね鉄舟先生からうかがっておりました」
と、次郎長は初対面の挨拶をした。
「あなたが次郎長さんですか。どうぞよろしく」
長八も軽く礼を返した。観音像の制作に取り掛かった時のことだった。
観音像は立体像ではなく浮彫であった。まだ形も定まらない土を、次郎長はじっと見詰
めていた。
仕事が一区切りついたので、長八は膝の上の土を払って立った。
「しばらく休みましょう。次郎長さん、どうぞ」
と長八が先に寺の縁先に腰掛けた。次郎長は立ったままだった。住職の貞山和尚が茶を
運んで来た。三人で話ははずんだ。
「三島の竜沢寺の仕事は大変でしたねえ。立派なお不動さまが出来たそうで」
次郎長が言った。頑丈な体格だった。傷跡のある怪偉な顔が印象深かった。
「百日の参篭ですからねえ」
貞山和尚が言った。
「一度拝みたいものです」
次郎長が言った。
「まだお堂が出来ませんので」
「いつになります」
「さあ、老師さまにお任せしてありますから」
そんな話から、竜沢寺の話題になった。
「老師さまはお元気で?」
次郎長が言った。
「私もしばらくお眼に掛かっていないな」
貞山和尚が独りごとのように言った。
「元気です」
「私も長いことごぶさたです。もう三年近くになりますかな」
次郎長が庭の青葉に眼をやりながら言った。港の方から、海の匂いが流れていた。
「鉄舟先生に誘われましてね」
すると貞山和尚が冷やかすように、
「それで、すっかり次郎長は変わりました」
と言った。次郎長が照れ臭そうに笑った。
次郎長はそれから毎日のように訪ねて来て、雑談をしては帰って行った。二人の交情は
次第に親密の度を増して行った。
十四日目、観音像は完成した。その日、開眼供養が行われた。次郎長もこの式に参加し
た。
「いよいよお別れですねえ」
次郎長が名残り惜しそうに言った。
「折角親しくなったのに残念です」
長八も惜別の思いがあった。
「またおいでなさって」
「ええ、機会があったら」
日が高かった。暑そうに裏山で蝉が鳴いていた。
供養が終わって、一同雑談になった。その時次郎長が長八のそばに来て、
「長八さん、お願いがあるのですが」
と言った。
「何でしょう」
「鉄舟先生の像をつくってくれませんか」
「鉄舟先生の?」
長八はおおむ返しに聞いた。
「鉄舟先生は私にとっては命の恩人です。心の親といってもいい方です。これからも、私
は鉄舟先生にすがって生きたいのです」
「なるほどねえ」
「それで、鉄舟先生の代わりに、肌身離さず持っていられるような像をつくってもらいた
いと思いついたのです。私のお護りにしたいのです」
口下手の次郎長だけに真剣さが表にあふれていた。
「いいお考えです」
長八が言った。
「つくってくれますか」
「つくりましょう。ただし、東京に帰ってからになりますよ」
「結構です。是非」
次郎長は正直に喜色をはっきりさせてにっこりした。
次郎長は次の年、明治十二年に死んでいるから、長八との交遊はこの時一回限りであっ
たが、友情は死ぬまで変わらなかった。
鉄舟寺の観音像は、『水月観音』と言われている。
長八は再び静岡に引き返し、頼まれるままに少しの作品をつくり、ようやく秋風の立ち
初めた八月末東京に帰る。一月初めに東京を出ているから、約八箇月ぶりである。
⑦
静岡から東京までの十数日を費やしているのは、恐らく三島に四、五日の滞在をした
のであろう。
久しぶりの東京の町だった。新橋で汽車を降りると、何となく以前と違った空気が感じ
られた。残暑の日射しが強く、長八は人力車に乗っても、日除けに扇子を頭に当てていた。
長八は古風な人間らしく、帽子を用いていなかった。
若い車夫の後から、長八は話し掛けた。
「銀座が立派になったってねえ」
車夫は梶棒をちょっとひかえて聴き耳になり、
「へえ、大方洋館になりまして」
と大声で言った。
「そうだってねえ。久しぶりだ。廻り道してくれないかい」
「へえ、かしこまりました」
返事をすると、車夫は勢いよく走り出した。近くの小路に曲がると、ここは維新前とは
変わらない裏町だった。
間もなく銀座に出た。新しい装いを凝らして赤煉瓦が並んでいた。まばゆいような色が
夏の日を照り返していた。石畳の道を、昔ながらの着物姿にまじって、洋装の男女もちら
ほらと見えた。
「なるほど変わったねえ」
長八は車上で左右を眺めまわした。車夫は気をきかせて、ゆっくり車を運んだ。
「旦那、京橋に来ましたが」
車夫が後ろを振り返った。
「ああ、そうだね」
と長八はやっと気がついた風だった。
「思わず見とれてしまったよ」
京橋の角に来た。
「ここから曲がって、永代を渡っておくれ」
「へえ」
車夫が梶棒を右に向けた。しばらく走って行くと、急に町がざわめいているような気が
した。長八は車夫に声を掛けた。
「何だろうねえ、大分騒々しいようだが」
言われて、車夫は辺りを見廻した。
「何でしょうねえ」
しばらくして、車夫が思い出したように、
「おとといの二十三日に、近衛の兵隊さんたちが騒動を起こしました」
と言った。警官や軍人の姿が、屋並みのかげに立っているのが見えた。
「兵隊が?」
と長八が問い返した。
「よくは知りませんがねえ、兵隊が上官を殺したとかで」
長八は車上から様子を見ていたが、何のこともなかった。もう永代橋近くに来ていた。
隅田川の川風が懐かしかった。
「ここで降りるよ」
長八は車を止めた。ここから土堤道へ出た。日が傾きかかっていた。長八はゆっくりと
永代橋を渡った。
八月二十三日、竹橋にある近衛連隊の兵隊二百余人が、西南戦争の論功行賞が不公平だ
というので、上官に対して激昂し乱暴した。そして、脱走、放火、発砲という騒ぎに発展
し、大挙して皇居へ侵入しようとしたので、これを鎮圧するために兵隊が出動し、反乱兵
を取り押さえて、事なきを得た。いわゆる竹橋事件である。長八が通り掛かって騒々しい
と感じたのは、この事件直後で、まだ反乱兵が隠れていると思う地帯に検察の手が動いて
いたためであった。
このことは、八名川町に帰ってわかったが、この頃、そういう不穏な事件が頻々として
起こるのが、長八には憂慮された。先に岩倉具視が襲われ、今年五月には大久保利通が殺
された。西南戦争を頂点として、その前後のこうした殺伐さは残念でならなかった。それ
は多かれ少なかれ、明治政府の措置に反対するつまり政治不信の証拠だった。長八にはそ
れは、政府の欧米追随のため功を急ぎ過ぎたからではないかと思われた。
八名川町では、家の者が長八の帰りを待ちわびていたように、留守中のことを話してく
れた。家庭のことも、仕事のことも、一切が事なく過ぎていながら、やはり、長八の帰り
を待っている用件もあった。
まずその一つは、七月に沢村田之助が死んだことであった。遅れた弔問のため翌日早速
出掛けた。留守中に、長八の作品の依頼があって、帰るまで保留されていた。その吟味も
しなければならなかった。あたふたと四、五日が過ぎて行った。
九月に入って、やっと山岡鉄舟を訪問することが出来た。竜沢寺のこと、鉄舟寺のこと
を、鉄舟に報告しなければならないのである。この日も蒸し暑い日であった。
会うと、鉄舟は何となく元気がなかった。
「どこかお悪いのじゃあありませんか」
と長八は思わず心配の余りたずねた。
「いや、暑気当たりだろう。それに、このところ忙しくてね。疲れているんだよ。大した
ことはない」
といつもの元気な笑い声を立てた。
早速、竜沢寺のこと、星定禅師のこと、茂平のこと、不動尊造立から隠寮の制作まで、
それから、静岡のこと、鉄舟寺のこと、次郎長や貞山和尚のことなど、詳しく報告した。
鉄舟は興味深げに、時々口を入れては聞いていたが、やはり顔色が優れず、長八は気がか
りだった。話が一通り終わったところで、
「どうも、お疲れのようで、こんな時にお伺いしてすみませんでした」
と、わびを言わないわけにはいかなかった。
「いや、いや」
鉄舟は手を振って、
「そんなに気にするほどのことではないよ」
と笑った。が、いつものような豪快な笑いではなかった。
「気をつけて下さい。医者に診てもらいましたか」
気づかわしくて、長八は聞いた。
「医者に診せるほどの病気じゃあない。大丈夫だよ」
「でも」
「いや、ただの疲れだよ。大丈夫。わしだって死にたくはないからな」
と笑った。そう言いながら、鉄舟は渋団扇をばたばたと動かした。
「とにかく、気をつけて下さい。大切なお体ですから」
「うん」
と鉄舟がうなずいて、ふと思いついたように言った。
「厄介なことがあってね」
「何か、あったんですか」
「今年五月に、大久保が殺された」
「はあ、それは三島で聞きました」
「それから、つい先だって、近衛兵の反乱があった」
「そうですってねえ。東京にもどった日に知りました」
「天皇親政というのに、こういう不祥事件が起きるということは、一体どういうことだろ
う」
そう言われても、長八には返事は出来なかった。
「役目がら、大変でございましょう」
「うん、夜も安心して眠れないこともある」
鉄舟にしては不似合いな弱気な言い方だった。
「お察しいたします」
「こんなことでは、日本もまだまだなのだ」
鉄舟は嘆息した。
「大久保が殺されたことは、国家の大損だ。西郷が死に、木戸が死に、そして大久保だ。
これからがこの国にとって大切な時なのにな。先が思いやられる」
眼をうるませていた。
「私などよくわかりませんが。ですが、それだけに先生などしっかりなさらなければ困り
ます」
長八は励ますように言った。
「いや、いや。もうわしなど出る幕ではない」
鉄舟は真面目な表情で言った。
「そんな」
と長八が言い掛けたのを、鉄舟は団扇でさえぎった。沈痛な顔になっていた。
「まあ聞きな。維新の時、官軍と幕軍が戦ったが、あの時はどっちも国内統一の誠意があ
った。だからこそ、西郷もわしらごとき者の言うことを聞いてくれて、何とかうまくやれ
たのだ。が、今は違う。表面的には内治、外交といい、富国強兵といい、立憲政治という。
いろいろ言っているが、皆それぞればらばらだ。それに、派閥争いだ。勢力争いだ。そう
いうものを、西郷や大久保が死んだ後、誰が押さえる。ただ勢力争いだけしかないじゃな
いか」
鉄舟は興奮したように頬を紅潮させた。
「天皇も大変苦慮していらっしゃる」
とつけたして、ふっと太い息を吐いた。
長八には何も言うべきことはなかった。ただ鉄舟がどんなに苦労しているかを思うと、
同情を禁じ得なかった。
鉄舟は冷たくなった茶をすすった。疲れをこらえている姿だった。長八はいい潮時だと
思って、
「それではこれで失礼いたします」
と居ずまいを直した。鉄舟は黙っていた。
「くれぐれもお体にお気をつけになられて」
長八はていねいに辞儀をした。
玄関で、
「また来て下さい」
と鉄舟が名残り惜しそうに立っていた。
長八は町の通りに出て人力車を拾った。車に揺られながら、鉄舟の疲れを思った。疲れ
は国家への嘆きであった。政治のことはよくわからないが、わからないなりに、心に掛か
るものがあった。
眼に映る文明開化に、何か大切なものが見落とされているような気がした。彼は、自分
の芸術について、技ではない人間だと悟り、鏝ではない心だと悟った今、政治もまた、技
ではないと、はっきり言えるようだった。が、彼は芸術、鏝絵以外のことに関知したくな
かった。彼は一切を捨て去ることを竜沢寺で知った。とは言え、それは逃避ではなく、超
越であった。一切を捨て去ることは、一つに生きることであった。
人力車は日のかげのしみた町道をゆらゆらと揺れて行った。
第7章 終わり
動画