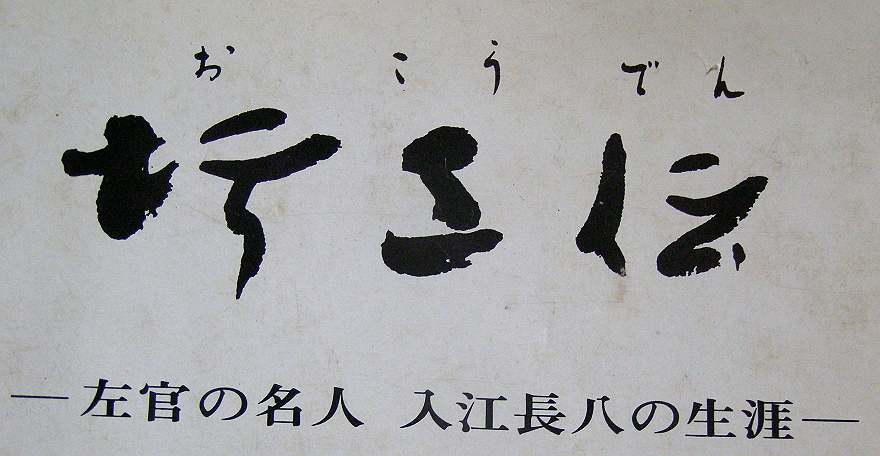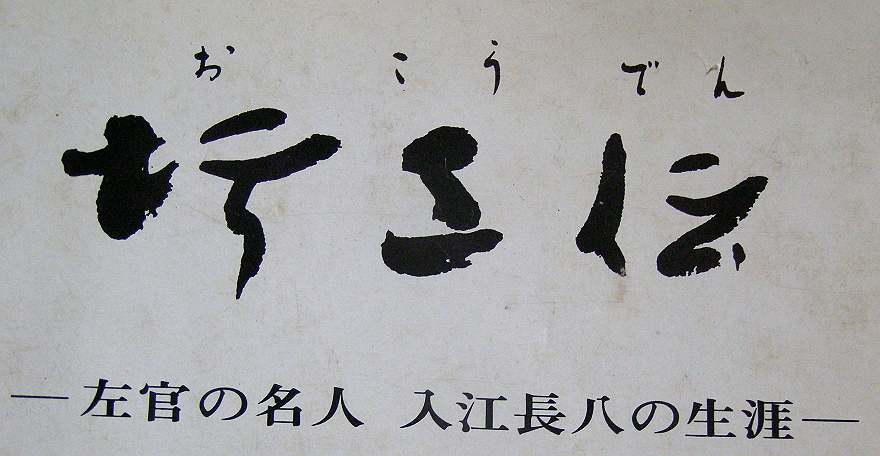須 田 昌 平著
第9章 名 月 秋 風
|
長八は、晩年のなすべきことを、すべてな
し終えて、寂かであった。名月のごとくま
どかに、秋風のごとくすずしげであった。
病中、淡々と死生を想い、心のままに制作
を楽しみ、心置きなく人生を終ろうとする。
(六十九歳から七十五歳まで)
|
①
養子の兼吉は性質が温順で実直だった。才気はなかったが、一本気で、どことなく長八
の若い頃に似ているようであった。長八は、肉親であるということの外に、兼吉のそうい
う人柄を愛していた。それだけに仕事を本気で仕込んだ。兼吉はそれに応えるように仕事
に熱心だった。もう一ぱしの若者になっていて、竹次郎の片腕として働くようになってい
た。長八はそんな兼吉を楽しみに見ていた。入江の血統と共に、ほんとの鏝を継いでくれ
ると思っていた。
その兼吉が死んだ。長八は自分の大切にしていたものを無惨にも奪い去られた悲しみに
打ちひしがれた。自分の死後も兼吉が居ると思うことだけで明るい気持ちだったのに、そ
の明るさが一瞬にして消えた。
長八には多数の優れた弟子があった。中橋善吉を筆頭に、江口庄太郎、吉田亀五郎、井
上市五郎など、今では一流の鏝絵師である。若い者では、竹次郎、兼吉、伝二郎など将来
有望な者がいる。だが、長八はこれらの弟子たちにあきたらないものを持っていた。それ
は、これらの弟子たちは皆長八の技術を習得してはいるけれども、人間的な精神の深さと
いうものが欠けている。彼等はほとんど青年、壮年の時からの弟子で、精神よりも技術を
身につけることを心掛けた者たちである。長八はそういう弟子たちを見るにつけ、人間と
して鍛え上げることの大切さを知った。それには少年時代から育て上げなければならない
と思った。たまたま兼吉を養子にして、日々の仕事や生活の中で、この少年に期待を掛け
るようになった。そのつもりで仕込んで来た。そして、兼吉は期待通りに育って来ていた。
技術的には先輩に到底及ばないが、先輩よりも遙かに大きな翼をひろげてはばたく可能性
を持っているように、長八には思えた。
長八は兼吉をほんとうの後継者だと思っていた。その兼吉に死なれて、今更のように兼
吉をどんなに深く愛していたかを知った。兼吉は長八の分身であった。長八の未来であっ
た。どれだけ悔やんでも及ばない哀惜が長八を悩ませた。
間もなく年改まって明治十七年。長八は七十歳の春を迎えた。兼吉の遺骨はそのまま八
名川町に置かれて、長八にはさびしい喪の春であった。何もしなかった。何をしようとい
う気力もなかった。気の衰えに寒さが加わって、またしても喘息に襲われた。
「兼吉が死んで、師匠はがっかりしたのだ」
と、弟子たちは心配した。
一月が過ぎて、二月も寝たきりの日々が過ぎた。三月になっても、起き上がる元気がな
かった。四月にはようやく起き出て庭を歩くことが出来たが、仕事には一切手をつけなか
った。すっかり痩せ細っていた。
六月に入って、喘息が癒えた。が、体調はまだまだであった。すると、突然菊地幸太郎
の長男の由松が病死した。長八は赤坂田町の幸太郎の家に人力車で行った。数少ない血縁
の一人の葬儀に出たかったのである。遺骨は正定寺に葬ったが、幸太郎の引き止めるのに
甘えて、由松の初七日の忌がすむまで赤坂で過ごすつもりでいたが、その間にまたも喘息
の発作が起き、そのまま幸太郎の家で臥床することになる。
幸太郎を始め家族は長八を大切にしてくれたが、病気はしつこく長八を苦しめた。梅雨
の季節が余計気分をうっとうしくした。
「世話を掛けるなあ」
と長八は家族の一人一人に言った。毎日決まったように発作が来る。誰かが来て背中を
さする。時間を決めて薬湯を飲ませるのは、幸太郎の妻のおとりであった。幸太郎は忙し
い体を、夜は大抵長八の側に居て何かといたわってくれる。そんな日々が続いた。
昼間は座敷にひとりぼっちで寝ていることが多かった。そんな時、長八は天井にくぼん
だ眼を向けていた。頭の中で、とりとめもなく、いろいろなことを思っていた。多くは過
去のことである。
「やっぱり、おれは死ぬのかも知れない」
と、ふと思う時がある。それが胸の中でつぶやくように聞こえる。死んでもいいと思う。
今まで随分『死』ということを考えて来た。失恋の痛手から無頼の酒に酔いしれていた時、
おきんとの日陰の生活で苦しかった時、しかし、若い頃の考えは全く他人事のように見て
いて軽々しいものであった。それから、成田山参篭以来、さまざまな場合に『死』がのぞ
いた。が、それも『死』を見詰めようとしていただけで、観念的だったように思われる。
それらを思い合わせると、今度は違うようである。『死』が直ぐそこに来ている感じであ
る。そして、自分と近々と語り合っているようである。
「お前はもう死期が来たと思っているらしいな」
と問いかけて来る。
「うん、そう思っている」
と長八が答える。答えても、少しも苦悩はない。屈託はない。
「この世に思い残すことはないのか」
と、また声がする。
「ある」
「そんなら、もっと生きたいと思うだろう」
「いや、生きたいとは思わない」
「なら、死にたいか」
「死にたいとも思わないな」
「一体、どっちなのだ。生か、死か」
「どっちとも言えない」
「それはおかしい」
「おかしいか。それなら、どっちでもいい」
「死んでもいいか」
「死んでもいい」
「生きていていいか」
「生きているのもいい」
「ずるいぞ、それは」
「ずるいかも知れない」
「それなら、思い残すことはどうする」
「生きていたら、やる」
「死んだら」
「死んだら仕方ないさ。やりようがない」
「あきらめるのか」
「あきらめるより外なかろう」
とりとめもなく死との対話が続く。しかし、それはかつてなかった親しさで語り合えた。
「確かに心残りはある」
と長八は思う。家のこと、仕事のこと、竹次郎のこと、幸太郎のこと、弟子たちのこと。
が、先の先まで心配するのは凡愚の煩悩だと思う。
「どうなろうとも仕方ないことだ」
と長八は思う。そんなことを寝ながら考えている自分が、案外静かなのに驚く。
赤坂の幸太郎の家に臥床して一と月が過ぎ、梅雨が明けた。病気もいくらか軽くなった。
幸太郎は喜んだ。が、涼しくなるまで居よという。長八はその言葉に甘えて、ぶらぶらし
ながら夏を過ごした。
夏になると、夜は幸太郎が来て、世間話をしてくれた。竹次郎も時々顔を出した。弟子
たちも訪ねてくれた。こういう者たちから、鹿鳴館の舞踏会の話や、不況のことや、会社
倒産のことなど聞いた。
秋になった。
「涼しくなったから、もう帰ろう」
と長八が言ったが、幸太郎は、
「折角よくなったのだから、これからは体を調える必要がある。落ち着いて静養して下さ
い」
と言って引き止め、そのままずるずると日を過ごしているうちに、幸太郎は裏庭に離れ
座敷を建築し始めた。
「あれは何だ」
と長八が聞くと、
「家が手狭で」
と幸太郎は答えた。
離れ座敷は母屋と細い廊下でつながった。八畳の座敷と四畳半の板間で、八名川町の隠
居所と同じ形だった。いよいよ出来上がると、
「伯父さんはここに住んで下さい」
と幸太郎は誘った。
「八名川町へ行けば、職人も居るし、人の出入りもうるさいですよ。それに八名川町は下
町で湿気が多い。伯父さんの養生に向きません。すっかり直り切るまでここに居て下さい」
幸太郎は半ば強制的だった。幸太郎の言うことはもっともであった。長八は不承不承で
新居に移った。
秋がたけて、長八は病気を次第に忘れたようによくなった。すると、板間で土をいじり
だした。菊地家にはたくさんの作品が遺されたが、そのほとんどはその時のものである。
寒くなったというので、ある日おはなが冬物を抱えて訪ねて来た。蜜柑が風呂敷包みか
らころげ落ちた。もう十二月であった。おはなは着物を着替えさせたり、蜜柑をむいたり
してくれた。いつものおはなと違っていた。竹次郎に一切を任せた当座は、不平や愚痴を
並べ、長八にも当てつけていたおはなだったが、長八が病んで、さすがのおはなも強気だ
けではいられなかったのであろう。おはなは長八に蜜柑をむいてやりながら、竹次郎から
ことづかった用件を、ぽつりぽつりと話してくれた。
とうとうその年一ぱい、長八は幸太郎の家で過ごした。
秋から冬への変わり目を心配したが、長八の喘息は再発しなかった。
年も押し迫ったある日、又兵衛がどてらを持ってやって来た。その時、長八は新居の前
の日当たりに筵をひろげて、そこで土を練っていた。戸袋には仁王の像が荒塗りされてあ
った。
「師匠、どてらを持って来ました」
と、又兵衛は後から声を掛けた。長八は鏝を持ったまま振り返った。
「おう、又兵衛か」
「元気そうで」
「うん」
長八は立ち上がって、古いどてらを脱いだ。又兵衛が後から新しいどてらを肩に掛けた。
帯をしめると、長八はそのまま元の座にもどって土を練り出した。
「仁王さんですね」
又兵衛が古いどてらをたたみ終わって戸袋に眼をやった。
「そうだ」
「仁王さんというと、仏様を守護するものでしょう」
又兵衛は不審に思っていたのだ。
「そうだよ」
長八は土を練りながら答えた。
「こういう戸袋に描いてもいいですか」
「おかしいか」
「へえ」
又兵衛は正直に言った。すると、長八はあはははと笑った。
「又兵衛」
「へえ」
「ここに一人、仏さんが居るじゃないか」
と長八はまた笑って又兵衛を見た。
すでに淡々とした心境であったのだろう。こんな逸話が残っている。
②
明治十七年という年は、欧化の風潮が一段と強くなった年で、有名な鹿鳴館全盛の時代
である。毎夜のように舞踏会が開かれ、シャンデリヤの下で洋装の男女がうつつを抜かし
て踊り狂っていた。東京ばかりでなく、地方都市にも流行して、園遊会とか音楽会などと
いう西洋習俗が行われた。が、その一方では、この風潮をにがにがしく思い、あるいは痛
憤し、あるいは激怒する、いわゆる国粋主義者も頭をもたげていた。明治も十七年を経過
したが、まだまだ安定してはいない。所々にひずみが現われていたのである。藩閥への不
平不満もあったし、新政への反抗もあったし、時には険悪な事件さえ起きていた。九月の
加波山事件、十月の秩父事件、十一月の飯田事件などがそれである。それに加うるに、新
政以後のインフレ状態が苦心の結果終息しかかると、今度は反動的に急速に不況が襲って、
会社や銀行が続々と倒産して行った。
幸太郎の家にも不況の風が冷たく吹き込んでいた。離れ座敷に起居していた長八にも、
その様子は手にとるようによくわかった。それは年末に至って一層はっきりと感じられた。
年が改まると、長八は急に八名川町へ帰ると言い出して、一人で風呂敷包みを抱えて出
て行った。長八の病気はほとんどよくなっていたし、それよりも、不況の中でいつまでも
世話をかけているのが心苦しかったのであろう。幸い、竹次郎夫婦とおはなの仲も、平穏
になっていたし、長八は帰るによい潮時だと思った。
八名川町に帰ると、久しぶりで見るわが家は、前とすっかり変わったような感じだった。
竹次郎はもう立派に一家を取りしきっていた。女房のおふくも落ち着いた態度で家事を指
図していた。兼吉の居ないのがさびしかったが、それは仕方のないことであった。
正月が過ぎて、兼吉の一周忌の供養をした。それだけで、長八は隠居所で静かに暮らし
ていく。時折、竹次郎夫婦が顔を出す。幸太郎も三日に一度は見舞ってくれる。弟子たち
が入れかわり来ては、何かと話しては帰る。そんな平和な日々を、長八は楽しむように暮
らしている。
寒さが峠を越して、三月になる。長八はだんだんと元気を取りもどしたようである。だ
が、朝夕はまだ寒い。時には一日中荒い風の吹く日もある。
「油断は出来ません」
と、竹次郎や幸太郎は長八に仕事をさせない。
三月十二日の夜、日本橋から出火して折からの西北風にあおられて、火は見る見るうち
に燃え拡がり、日本橋一帯を焼野にしてしまった。竹次郎の実家の波江野も、茅場町の薬
師堂も焼けてしまった。
竹次郎は日本橋の実家の復興に当たらねばならぬ。すると、外の仕事は手控えなければ
ならない。
「よし、おれがやる。何あに、指図さえすればいいのだ」
と、長八は止めるのをも聞かず、日本橋復興の仕事に掛かった。いざ仕事となると、持
って生まれた性分で、弟子たち職人たちを督励するだけに納まらず、いつの間にか、自分
も鏝をとって働き出していた。が、長八自身が危惧していた疲労も意外に少なく、あわた
だしく二か月が過ぎ、波江野の仕事も終わって、竹次郎がもどって来て、長八に代わって
働くようになる。
すると、長八は健康に自信を持ち出したのであろうか、茅場薬師の再建に掛かると言い
出し、竹次郎が引き止めるのも聞こうとしなかった。
「茅場薬師の再建は長い間の願いだった。とっくに掛かるべきところを資金が集まらず、
のびのびになっていたのだ。今度焼けたのはかえってよかった。この際やるべきだ。一文
の金にならない仕事をやるには、おれのような人間がいい」
と、長八は竹次郎に言った。
そして、関係者の間を走り廻って、とうとう六月には建築を始めるように手はずを決め
た。
いよいよ仕事が始まった。竹次郎は長八の健康が心配で、長八を赤坂の幸太郎の家から
日本橋へ通わせることにする。もちろん、幸太郎と相談の上である。
長八が茅場薬師の仕事を始めたという話はそれからそれへと伝わった。話を聞いたと言
って、中橋善吉、江口庄太郎が腕ききの職人を連れて応援に来た。こうして一か月ばかり
で薬師堂は完成した。
この時の作品は、内陣に仁王像と雲竜を薄肉彩色で仕上げたと伝えられているが、関東
大震災で焼失して今はない。病後第一作として価値ある作品なのだが、今では何の想像も
出来ない。
薬師堂の工事中、赤坂の幸太郎の家から通っていた関係で、この期の作品として推定さ
れるものが菊地家にある。そのうち注目されるものは、守り本尊として菊地家に遺ってい
る観音像と、後に菊地家の菩提寺、郷里の禅海寺に預けた地蔵像とである。共に、明治十
八年首夏と記して、この期のものであることは明らかである。外に、南画風の塗額が遺さ
れている。
その外に、今日残っているもので、明治十八年作とされているのは、沼津の竹沢家にあ
る文殊像、焼津市光心寺の『舞鶴山水』の衝立。これらは恐らく菊地家所蔵の品であった
ものが、何かの関係で散って行ったのであろう。
長八はやがて八名川町に帰り、元の清閑な生活にもどる。茅場薬師の仕事はさすがに長
八にとっては大変だったようで、長八ははっきりと気力の衰えを知るようになる。それは
仕事場へ入っても根気が続かず、製作がはかばかしく進まなくなったことでよくわかった。
冬になると寒さが身にこたえた。寒さがこわかった。長八は終日こたつにぬくもるよう
になる。往年の気魄はもうないようである。しかし、長八は、そういう自分を静かに順応
していた。衰え行くわが身わが生命であればこそ、粗末にしたくなかった。それは命を惜
しむというような気持ちとは大分違っていた。命を大事にすることといった方が当たって
いるだろう。そこにある自分というものは、どうあろうとも世界中に一つしかないものな
のである。しかも、それは生きている間のことなのである。
やがて、明治十九年がめぐって来て、長八は早くも七十二歳となる。幸いにも持病の喘
息は影をひそめていた。
正月、久しぶりに長八は仕事場に入った。縦五尺、横三尺の木綿地に達磨像を描いた。
衣は朱、背景は紺、顔は淡彩で、この描法は明らかに狩野派のそれであった。だが、その
筆勢は異常な気力をみなぎらしていた。少なくとも病弱の老人の筆とは思われないもので
あった。この大軸はそのまま周囲を瑞雲模様に描いて表装仕立てに見せている特殊な趣向
の作品である。
この絵に見る、異常な気力は何なのであろうか。老年の長八の精神像の一部がそこに見
られるような気がする。長八はすでに程遠からぬ寿命を意識している。その意識は自分の
行動について次第に控え目になってゆき、生命を細く微かにしてゆくのが通例なのだが、
時にパッと火花のように燃えることがあり、潮のようにしぶきをあげることがある。それ
は、老人だからといって、べんべんとしてはいられないという焦燥なのかも知れない。自
己の生命の大切さを強く悲しく感じるのかも知れない。長八の達磨像も、そういう現象で
はないかと思われる。が、長八の場合はもっと違った意識があったように思う。もはや、
やりたい仕事は出来るだけやってしまいたいというような意識的な考えは持っていなかっ
た。だが、作ろうと思い、描こうと思う時、自然に素直に作り、描く。作れるから作る。
描けるから描く。そういう自然な気持ちが成立していたように思われる。こんな時、長八
はこれが最後の作品かと思うのだった。だから、興のおもむくままに作り描いた。それは
死を恐れてはいない。むしろ生を喜んでいるようであった。
この達磨像は折よく上京した桜井東吉に寄托して、三島の竜沢寺に届けられた。彼の浄
土欣求の願いであったろう。また竜沢寺への報恩感謝の心でもあったろう。
春になって、長八はますます健康にもどって行った。喘息は根治したように思われた、
三月の末のある日、急に山岡鉄舟に会いたくなって、下谷初音町の全生庵を訪ねた。鉄舟
は今は官を辞して、ここに閑居していた。長いこと会わなかったことを思い出した。道楽
会も二度三度と欠席をしていた。久しぶりにゆっくり話したかった。別に用件があるわけ
ではない。ただ顔を見たかった。話したかった。
いい日和だったから、一人でぶらりと出掛けた。全生庵を訪ねると、鉄舟は書斎に居た。
久しぶりで顔を合わせた。だが、鉄舟の顔色はさえない。
「先生、どうしたんですか」
長八は無遠慮に聞いた。すると、
「胃が痛むんだよ」
と鉄舟が答えた。言葉が思いなしか力弱く響いた。
「それはいけませんね」
長八は眉をひそめた。
「で、どんな様子で?」
と聞いた。
「時々キリキリと痛むんだよ。その度に針で刺されたようでね」
鉄舟は顔をしかめた。
「医者は何というのです?」
「胃がただれているという」
「食べ物は?」
「それがうまく通らないんだ。粥ばかり食べている。それも少しばかり」
と鉄舟はにがく笑った。
「病気はいやなもんです」
長八はふと『同病相憐れむ』という言葉を思い出していた。
「全くだね」
鉄舟が低い声で言った。思いついたように、
「お前さんもひどい目にあったねえ」
と言った。
「へえ、おかげでこの頃やっと元気になりました」
長八が続けて、
「わたしのは、若い頃からの無理がたたってるのでしょう。自業自得です」
と苦笑した。
「いや、わたしもそうだ。元気に任せて無茶なことをしたからね。それに酒を飲むし」
と鉄舟も苦笑した。
話題は両方ともたくさんあった。あれこれと話しているうちに、鉄舟の姿に疲労の色が
見えて来た。
「すみませんでした。長話をしてしまって」
長八はそう言って膝を上げた。
さりげなく全生庵を辞して来たが、長八は鉄舟の病気が気に掛かった。
鉄舟は、長八からすれば遙かに若く、この時五十一歳のはずである。まだ死ぬ年齢では
ないと長八は思うのだった。だが、何となく影が薄い。長八はいまわしい予感を吹き消す
ように、下谷の低い屋並の下を歩いていた。
③
夏が来て、長八はいよいよ元気であった。が、反対に、鉄舟は次第に病み細っていた。
六月十五日は赤坂の氷川神社の祭日だった。前年からの不景気を吹き飛ばそうというの
で、今年は盛大にやることになった。幸太郎が迎えに来て、長八は人力車で赤坂に行く。
この祭礼には、恒例の職人衆の山車が出る。大工仲間の山車、左官の山車、鳶職の山車、
木場の山車というように、それぞれ豪華を競い景気を競うのである。
ところが、祭の当日ひと騒動が起こった。大工職人の山車が四つあって、それが二つに
分かれて大げんかとなり、血の雨が降りかねないような険悪な事態で対峙したのである。
人々は心配げにぐるりを遠巻きにしていたが、その時別な一つの山車が対立している中に
割って入り、双方の山車を引き離して、事なきを得た。その仲裁に入った山車には、長八
を型どった人形を乗せていたという。左官の山車だったのである。………この伝説は一部
違っている。すなわち、山車に乗っていたのは、人形ではなく、本物の入江長八であった
のである。事実は次のようである。赤坂の左官では、長八の弟子の吉田亀五郎が筆頭の棟
梁である。この大工仲間の紛争を見て、亀五郎は自分の手には負えないと思った。一計を
考えついて、幸太郎の家へ飛んだ。そこでくつろいでいる長八を無理に連れ出して山車に
乗せ、けんかの中に割って入り、双方をなだめたというのである。長八はこの時何も言わ
なかったが、亀五郎が長八を楯にして双方を説得したという。ちょっと突飛もない話だが、
長八の仲介を利用したなど、いかにも東京らしい。いや、江戸風らしい感じである。
長八の体は梅雨に入っても悪くはならなかった。その反対に、鉄舟の病気は、見舞いに
行くたびに憂慮された。
「皮肉なものよ。おれがよくなったと思うと、鉄舟先生が悪くなって」
と、長八は竹次郎に嘆息した。
真夏になった。長八は足繁く全生庵を訪れた。じっとしていられないような気持ちだっ
たのである。
今日も全生庵を訪ねた。依然として鉄舟の病気はよくなかった。不吉な予感が脳裡に走
った。その帰り道、下谷の町から隅田川へ出ようとして、見知らぬ裏町にまぎれ込んだ。
すると、どこからか石を刻む音が聞こえた。コツコツコツと単調に無際限に続いていた。
何の気なしに、その音をたよりに歩いて行くと、一軒の家の庭先に葭簀を張って、中老の
石屋が汗をしたたらせていた。
「ああ、ここだったのか」
と、長八はほっとしたような気持ちで、そこに立ち止まった。石屋はコツコツと刻んで
いる。長八には気付かないようである。白い粒が小さく煙のように散っている。長八は汗
をふきながら、石屋の動作をぼんやり見ていた。ふと長八は思いついた。
「石屋さん」
と声を掛けた。
「へえ」
石屋が始めて顔をあげた。ついでにしたたる汗を手ぬぐいで手荒くこすった。葭簀の陰
からすかすように石屋の眼がのぞいて、
「おや、長八さんじゃあございませんか」
と言った。
「知ってたのかい。長八だよ」
長八は微笑した。
「へえ、何か御用で」
と石屋は不審そうに見た。
「お前さんの刻んでいる姿を見ていたら、わたしも刻みたくなった。わたしにも刻めるよ
うな石はないかい」
「あなたが刻むんですか」
石屋はけげんな顔を向けた。
「うん」
と長八は笑った。
「何を刻むんで?」
長八はそう言われて困った。突差に、
「地蔵様だよ」
と言った。
石屋は腰を伸ばして、石置場に案内した。
「大きさは?」
「さあ、二、三尺でいいだろうな。それに台石とね」
石の間を石屋が潜って行った。
「これが手頃でしょう」
「年寄りだから、固くちゃあ困るよ」
「これならいいでしょう。よくやりますねえ。あなたならきっといい地蔵さんが出来まし
ょう」
「じゃあ、すまないが八名川町まで届けてくれないか」
「へえ、承知しました」
全くの思いつきだった。鉄舟の病状を案ずる余り、祈りたい気持ちで通り掛かった石屋
だった。石屋の姿を見て、自分で仏を刻んでみようと思い、石屋に聞かれて、地蔵をと答
えた。それだけのことだが、長八は後からいい考えだと思うようになっていた。鉄舟先生
のため、延命地蔵を刻もうと心に決めた。
石が届くと、長八は待ち構えていたように地蔵を刻み始めた。不馴れな手つきだが、一
心に刻んだ。暑い夏だが、石を刻んでいると暑さも忘れた。七月が過ぎて、間もなく延命
地蔵は出来上がった。
その間も、鉄舟の病気は悪かった。延命地蔵が出来上がった頃、鉄舟は突然激しく血を
吐いた。その時、そばには誰も居なかった。真昼のことで家族も門弟たちもそれぞれの用
事をしていたのである。血を吐いた鉄舟は、息をはずませて、辺りの血をぬぐうと、その
ままぐたりと床に倒れた。彼は命の終わりを感じ取っていた。やがて、そっと床の上に端
座して、数枚の遺書を認めた。
その遺書の一通が今日も残っていて、鉄舟の人間的なものが強く察せられる。が、筆跡
はさすがに往年の気魄はなく、病人らしい弱々しさを漂わせている。
『金を積みて以て子孫に遺すも、子孫いまだ必ずしも守らず。書を積みて以て子孫に遺す
も、子孫いまだに必ずしも読まず。如かず、陰徳を冥々の中に積みて以て子孫長久の計と
為さんに。これ先賢の格言にして、すなわち後人の亀鑑なり』(原文は漢文)
というのである。遺言というより訓戒というべき言葉のようである。
鉄舟は遺書を認め終わると、それを枕の下へ入れて、ゆっくりと仰臥した。そして、死
を待つもののように、黄昏の中を深い眠りに落ちて行った。昏々と眠って朝に至った。家
人は驚いて医者を呼んだ。医師はあるかなきかの脈拍を数えながら、絶望の眉を寄せてい
た。家人や門弟がひっそりと憂愁の眼を向けて、枕べを取り巻いていた。
鉄舟は昏々と眠り続けていたが、夕暮れ近く静かに眼を開いて、ぐるりの人々の顔を見
廻った。微かに明るい笑みを浮かべていた。鉄舟は死ななかった。吐血して、かえって苦
痛が薄らいだように見えた。今で言えば胃潰瘍の症状のようだが、吐血によって軽くなる
ということがあるのか、私にはわからない。とにかく、鉄舟の病状は持ち直した。秋と共
に快方に向かうほどになる。
長八が一心こめた地蔵像があるいは鉄舟の命を救ったのかも知れない。長八はひそかにそんな思いを抱いた。
ある静かな秋、地蔵像は全生庵の庭に据えられた。背銘に、『一心頂礼、七十二天祐居
士』と刻まれてあった。長八が自ら車に載せて運んで来たものだという。
こうして、明治十九年が暮れ、明治も二十年となる。二月、東京に初めて電灯がつく。
この年の冬も長八は元気であった。時たま仕事場に入って、頼まれた塗額の制作をした。
が、四月の声を聞くと、長八は待ちかねていたように故郷に帰った。
何年ぶりの帰郷であろうか。病気になって、もう帰れないと思った故郷へ帰れる喜びは
譬えようがなかった。
「ちょっと行って来るよ」
とおはなと竹次郎に言って、身軽な格好で八名川町を出た。これが最後の帰郷になるだ
ろうと、長八は心ひそかに思っていた。病気は回復してはいるが、体力の衰えは隠しよう
がなかった。いつまでも生きれるとは思わなかった。
ゆっくりと旅を続けた。三島では茂平の家がわが家のようなものだった。茂平は八十歳
の高齢で、相変わらず元気だった。
「先日、横浜へ行ってきたよ」
と、早速話し出した。
「横浜は大層なにぎわいだそうですねえ」
「こんなに発展するとは思わなかったよ」
茂平は横浜での見聞をやや興奮した面持ちで事こまかに話した。にこにこしていて、昔
の厳しさは忘れたように消えていた。
「新開地だし、居留地だし、面白いことが一ぱいだな」
「昔は普通の漁師村だったんだそうですがねえ」
「昔の面影なんぞ少しもありやあしない。港には外国船が 煙を吐いているし、町は洋館
が立っているし、桜木町あたりは軒並みだ。そこを異人がぶらぶらしているんだから」
「景気もいいようですねえ」
「異人相手の仕事が多いからな」
次から次へ話が走っていた。
「そうだ。珍しいものを見せてやろう」
思い出したように、茂平はぽんぽんと手を鳴らした。
「儀三郎」
と次の間に向かって呼んだ。間もなく儀三郎が入って来た。
「写真」
茂平が言うと、儀三郎は持って居た一葉の写真を差し出した。
「何だ、持って来たのか」
「多分そうだろうと思いましてね」
儀三郎はいたずらっぽく笑った。
「こいつ」
茂平が苦笑しながら写真をとった。
「おやじは来る人誰彼となく、この写真を見せるんですよ」
と儀三郎は長八に向いて笑った。
「横浜に着いた日に、異人に会ってな。おれの年を聞くから、八十だと答えたらびっくり
してな、是非写真をとりたいと言うんで写したんだ」
長八は写真を手にした。写真は東京で何度か見ていたが、茂平の自慢の鼻を折らないよ
うに気を使った。そして、写真に見入った。薄くぼけてはいるが、まさしく茂平の姿だっ
た。
「おれの宿まで追っかけて来て、とったんだ」
茂平は得意気であった。
「おやじの一つ話ですよ」
儀三郎が小声で言った。
「日本人でもやっている人があるらしい。東京の浅草辺に写真館があるという」
「聞いたことがあります」
「それがな、何でも下田の人だそうな」
「へえ」
茂平は名前を思い出そうと天井を向いた。
「下岡蓮杖でしょう」
儀三郎が言った。茂平が大きくうなずいて、
「おう、そうそう。下岡蓮杖といった」
と笑った。
日本の写真の始祖、下岡蓮杖のことである。その弟子に鈴木真一がいて、長八と同郷岩
地村の出身者である。岩科学校の開校式、真一の甥の依田勉三が明治十六年、十勝開拓出
発時の写真は彼の撮影である。
④
長八は翌朝、沼津の川口から汽船に乗った。沼津、下田間の定期航路が開かれていたの
である。余談であるが、この会社は先に述べた依田一族の共同出資で設立されたものであ
る。
船は春の静かな海を白波を蹴立てて走った。長八は乗客にまじって甲板に立っていた。
移りゆく風景はやはり懐かしかった。大瀬崎を過ぎると、やがて戸田港である。船上から
松城家の白壁が光って見えた。二人の客が荷物と一しょにはしけに移り、ゆらゆらと船か
ら離れて行った。長八は船が動き出すまで白壁を見ていた。そこには瞼に浮かぶ自分の作
品があった。土肥、宇久須と次第に故郷に近づく。乗客も残り少なくなって行く。
「便利な世の中になりましたなあ」
と長八は隣の客に話し掛けた。
船はなつかしい故郷の港に着いた。ここで大方の乗客は下船する。代わって、下田へ行
く客が乗り込む。共に小さなはしけ舟が送り迎える。
松崎に着くと、おしゅんの居るわが家にその夜を過ごす。翌日父母や姉の墓参をする。
ついでに庫裡に廻って、老い衰えたたきえや若い住職と会う。そんなことにも長八は喜び
を感じている様子であった。別に用事があって帰郷したわけではない。ただ故郷をゆっく
りと噛みしめたかったのである。寺を出ると、近くの知人を訪ねた。また次の知人を訪ね
た。次の日も同じようにぶらぶらと故郷の道を歩いた。道ばたで老いた友だちと立ち話を
するのも楽しかった。通りがかりの家から声を掛けられて、ひょいとそこへ入り込んで世
間話をするのも楽しかった。海へも行った。遠い昔のことが思い出されるが、決してにが
くはなかった。
五日経った。依田善吾の家から使いが来て、そこでいくつかの作品をつくった。そのう
ち、岩科の佐藤甚蔵と山本三四郎が連れ立って来て、半日話して帰った。いつの間にか、
自然と長八の帰郷のことがあちこちに知れて、注文があり、断り切れず仕事を始めるよう
になる。この時の作品で今残っているのは、依田家の『寒牡丹』、壬生家の『不動明王像』、
淨泉寺の絵馬などである。
長八がこうしてのんびりと暮らしていたが、六月、急な用事が出来て、急いで東京にも
どる。急な用事というのは、新しく東京角力協会が設立され、その記念興業が両国回向院
で催されるについて、元の角力会所の世話人だった長八が引き続き協会の相談役になって
いたから、興業に間に合うように帰らなければならなかったのである。
東京に帰って、六月の大角力も無事に千秋楽になると、長八は久しぶりで全生庵に鉄舟
を訪ねた。初夏とはいえ、暑い日射しの日であった。
鉄舟は麦わら帽子をかぶって、庭の草をむしっていた。門を入って来る足音を聞いて、
尻からげの腰をのばした。
「よく来たな。伊豆へ行ってたそうだね」
「ええ、春に」
思いなしか、鉄舟は頬がこけていてまだ病気が本復してはいないようだった。
二人は縁先に腰掛けた。そこから石地蔵が見える。石地蔵の体に楓の木もれ日がまぶし
いようにちらちらと動いていた。
「お体の方は?」
と長八が聞いた。
「大分いいが、まだ力が出ない」
「無理をしてはいけません」
「いや、無理は絶対にしないようにしている。何しろ、ちょっと何かをすると疲れてね」
そこへ娘の松子が茶を運んで来た。
「しばらくです」
と松子は一礼した。
「静岡からの新茶だよ」
鉄舟が先に茶碗に手を掛けながら言った。
「静岡から?………いただきます」
長八は茶碗を手にした。新茶の香がさわやかだった。
「やっぱり新茶はいいですね」
と、長八は喉を通ってゆく香を味わっていた。
「幕臣の連中が一生懸命開拓した牧の原の茶だよ。ようやく今年からとれるようになった」
「なかなかいい香りです」
二人は新茶をすすった。
「うん、思い出したよ。長八さん」
と茶碗を持ったまま鉄舟が言った。
「何ですか」
長八も茶碗を持ったまま聞いた。
「先頃伊東子爵が遊びに来てな。今、離れを建てているんだそうだ。それでね、お前さん
に壁をやってもらいたいと言っていたよ」
「伊東様、お元気で?」
「ああ、相変わらずだね。ああいう達者な奴を見るとうらやましくなる」
「で、お急ぎのようでしたか」
「いや、今普請中ということだ。あの有名なやかまし屋だから、直ぐというわけには行く
まい。そのうち、一度会って下さい」
「へえ」
「この前の仕事がよっぽど気に入ったんだね。くどくどと賞めていたよ」
「恐れ入ります」
鉄舟は思ったより元気っだった。
全生庵を出て赤坂に廻った。幸太郎に会いたかったのである。もう日暮れに近く、方々
で打ち水をしていた。
その夜、幸太郎の家に泊まった。幸太郎の商売も持ち直して、前よりも景気がいいよう
だった。翌日、朝の涼しいうちに八名川町に帰った。そして着物を着替えると、人力車で
伊東祐亨子爵邸向かった。
伊東邸の離れは、鉄舟の言ったように期日が延びて、ようやく秋の半ばに仕事が始まっ
た。
長八は、この離れ座敷の四方の欄間に『三保の松原』の図を描き上げた。さわやかな淡
青の地に、遠く近く連らなる松原を、鏝の描線を巧みに駆使した。得意の無彩色鏝描であ
った。この図はいかにも晩年の澄明な心境を示していて、立派なものであったという。余
談だが、祐亨が幕府に追われた時、伊豆の馬次郎の実家に匿われたことがあるが、それは
たがいの口端に上らなかった。
やがて明治二十一年。長八、七十四歳。
新春、彼は『青不動』の画幅を描いた。先年郷里に帰った時、淨感寺の若い住職との約
束のものだった。折よく、坂倉保が医学の修業を終えて故郷に帰ることになっていて、こ
の画幅は坂倉保が淨感寺に届けた。
三月、日本橋の柳光亭の大改築をするに当たって、二階百畳敷の大広間に、鏝絵を描く。
柳光亭は柳橋の一流料亭で、当時隆盛を極めていたという。ここで長八は何を描いたかわ
からない。が、長八の変わった逸話だけが伝えられている。
柳光亭では改築が着々と進んで、長八もすでに壁の仕事を始めていた。ある日、長八が
来ると、大広間で大変な悶着が起きていた。話を聞くと、大広間の床柱のことであった。
床柱の材料は小金井村にある二た抱えもする椋の木を使うことになっていた。何しろ二百
年以上の古木で、いよいよ鋸を入れたところ、中が空洞になっていた。しかもそこに二疋
の白蛇が出て来た。使いの者の話を聞いて、柳光亭の主人は「白蛇が出たとは吉兆だ」と
喜んだが、妻女や番頭、女中頭まで、気味悪がって絶対反対を唱えた。大変な悶着という
のは主人と反対側とで、床の間を前にして争っていたのである。どっちも、一歩も引かな
い様子を見て、長八が中に入った。
「双方の意見は、それぞれもっともだが、両方立てるわけには行かない。そこで、どうだ
ろう。わたしに任せてくれまいか」
と長八が言うと、主人は直ぐに、
「任せるって、一体どうするんです」
と不承知の顔をした。
「わたしに考えがあります」
と言うと、
「その考えを聞こうじゃないか」
と皆が口々に言う。
「じゃあ話しましょう。白蛇はめでたいものと、昔から言い伝えられていて、それは御主
人の言う通りだ。折角めでたい古木が手に入ったのに捨てるのは惜しい。しかし、白蛇を
気味悪く思い、祟りを恐れるのも無理はない。そこで、白蛇の霊を封じて祟りのないよう
にすればいい」
すると、反対派が、
「白蛇を封じるって、どうするんです?」
と畳み掛けて来た。
「わたしが封じます」
長八がきっぱりと言った。ともかく、押問答していても始まらない。ようやく双方とも
不承不承ながら長八の言葉に従うこととなった。
そこで問題の床柱が運び込まれ据えられた。長八は読経をしながら床柱の空洞を封じた。
が、そこには二疋の白蛇が漆喰で描かれた。これが白蛇の話である。
ところが、これには後日談があって、柳光亭が開店するとたちまちこの柱が有名になり、
見物がてらの客が来て店は大繁盛したということである。
もう一つ、柳光亭にまつわる逸話がある。この大改築の祝いに、はるばる青森県から客
が上京して来た。柳光亭の先代は青森県七戸の出身で、裸一貫から刻苦精励して、一代で
この大店に仕上げた人で、客というのはこの先代の弟である。この叔父が長八の鏝絵の見
事さに驚嘆して、郷里への土産に何か描いてほしいと頼んだ。長八は即座に承知して、不
動明王の図を描いて与えたという。
柳光亭の仕事は主に長八の鏝絵で、百畳の大広間だし、かなり時日を要した。仕事最中
に福田行誡上人がなくなったという知らせを受け、長八は一日仕事を休んで深川本誓寺に
弔問した。
福田行誡といえば、幕末から明治にかけての高僧で、増上寺の管長を勤め、後に京都知
恩院の寺主となり、明治十八年畢生の大事業『縮刷大蔵経』を完成した仏教界の最高峰の
人である。長八とはたった一度しか会っていない。それは昨年の春の帰郷の時であった。
たまたま上人は大蔵経を完成して、その疲労で病気になり、静養のため松崎の淨感寺に滞
在していた。長八は最後の帰郷と思っていたから、散歩のついでに淨泉寺にも立ち寄った。
そこで上人とめぐり合ったのである。行誡はこの時八十二歳だったから、長八より九つ年
上である。四方山の話の末、住職は二人に記念の色紙を書かせた。その色紙が今も残って
いる。妙な寄せ書きで、独楽と煙管が一筆描きされ、それに行誡の筆で、『このようなこ
まもろこしの書にもなし』と狂句めいた文字が書かれてある。絵も言葉もどんなことを意
味しているかはわからないが、二人の超俗的な風格だけは感じられる。 柳光亭の仕事は
五月の末に終わった。その後は赤坂の幸太郎の家で休養した。やがて梅雨の季節である。
長八は幸太郎の言うままに、八名川町の湿気を警戒していて、赤坂で過ごしたのであろう。
七月、朝から強い日射しの日だった。真夏を思わせる暑さだった。そんな日の午後、八
名川町から勝之助が手紙を持って来た。山岡鉄舟の死の知らせだった。長八は暑さに弱っ
て、その日は夏布団に横たわって、ぼんやりと団扇を動かしていたのだった。起きて、手
紙を読むと、長八はがばと起き上がった。
人力車を呼ぶ間ももどかしく玄関先に立っていた。人力車を飛ばして、谷中の全生庵ま
で急がせた。
⑤
鉄舟は静かに眠っているようであった。二人の姉妹が黙然とうなだれていた。
「鉄舟先生」
と、長八は小さく叫んだ。冷たくなった手にすがりつきたい気持ちでいた。長八は合掌
しながら、波乱の生涯を思った。二人の奇しき縁を思った。走馬燈のように過去が移り動
いていた。しみじみと、偉い人であったと思う。歳こそ下だが、長八は教えられることが
多かった。芸術の上ではなく、もっとも根元的な人間の生き方について、長八は鉄舟によ
って救われたという外にないないと思うのだった。
門弟たちがあわただしく動いている中で、死者はただ寂然として微笑さえ浮かべている
かのようであった。長八はその死顔に敬虔な静かさを感じた。死というものは、かくのご
とく美しいものなのかと、長八は鉄舟の死顔に、おのれの顔を重ね合わしていた。
「おれも、死ぬ時、こんな美しい顔になれるだろうか」
と自問してみた。すると、急に自分の死への思いが胸に湧き起こった。鉄舟は恐らくあ
の吐血以来死を覚悟していたであろう。どう考えていたか、どんな内面の苦悩があったの
か、すべて知る由もない。が、あの平素の淡々とした表情、あの自然のままの言動、そう
いう一つ一つが、今は深い意味を持って、長八の胸によみがえるようであった。
長八は遺体から離れて縁先に出た。そこに石地蔵が立っていた。それは生もなく死もな
く、ただ夢想に合掌していた。何のための合掌であろうか。鉄舟の病気平癒を祈った合掌
が、今は空しい。死んでしまっては、もはや祈るべきものはない。長八はじっと石の地蔵
に眼を凝らしていた。
鉄舟の葬儀はさすがに盛大であった。朝野の名士や多数の知人、門弟が参集した。それ
は故人の多彩な生涯を物語るかのようであった。が、垣の外に庶民が群れ囲んで、故人を
かなしんでいる姿は余り目立たなかった。その人群れ中に多くの乞食がまじっていたのも、
多くの人々は気付かなかったであろう。故人のいわゆる陰徳であろうか。長八はその状景
に涙を浮かべていた。
長八は葬儀をすませて、八名川町に帰り着くと、ぐったりと疲れ果てていた。何をする
気力もなく、布団の上に横たわった。が、翌日長八は朝早く眼覚めた。直ぐに仕事場に入
った。彼はそれから数日仕事の没頭した。ものにつかれたように、鉄舟像の製作をしてい
たのである。
鉄舟が死んだ七月には、磐梯山が噴火し、会津富士と言われた麗容が一時に爆発崩壊し
て姿を変えてしまった。
鉄舟の死後、鉄舟像をつくって、一つは全生庵に、一つは自家の仏壇に納めたが、その
製作が終わると、長八はがっくりとしたように身心に衰えが感じられた。この頃、人に依
頼されてつくった作品が今日残っている。春城院禅鼎和尚像を始めとする七点である。が、
これらの作品に共通して見られるのは、かっての精彩や力感が弱まっていることで、彼の
生活に一転機が来たように思われる。
明けて明治二十二年、長八は七十五歳となる。が、この新春には、長い虚脱の季節を抜
け出たように、六曲半双の屏風に大作の画筆をふるっている。が、この作品は南画風で、
淡墨の一見白描と見られるもので、やはり精彩を欠いている。画面には一面に微光が柔ら
かく寂かに漂っていて、何か長八のこの頃の心境を示しているようでもある。死への道程
を暗示するかのように、白道が曲折して遠く遙かに続いている。白道を取り囲む山も草木
も、寂然として微動だもしない。波も躍っていない。一切が息をひそめている。
このような絵は、かって一度も描かれていない。その描法は、しいて言えば田能村竹田
に近いが、竹田のような艶やかさはない。私はこんなことを思う。鉄舟の死に遭遇した長
八が、その愁傷な底から、静かに自己の運命を見詰め、想念を整理し、死への覚悟を決め
たのではないか。この絵はそういうものを表現しているような気がする。それは長八の現
実的な諦悟であったのかも知れない。
屏風絵が出来上がると、菊地幸太郎の家に運ばせた。何のために幸太郎の家に運ばせた
のか。その理由はわからない。ひそかに死場所の一つとして幸太郎の家を考え、おのれの
遺骸を囲む屏風と決めていたのかも知れない。
静かに冬が過ぎ、やがて三月となると、長八は旅仕度をさせて、またも故郷に向かう。
先年、最後の訪問をし、思い残すことのないようにとそのつもりで暮らしたのだが、後で
考えついた用件があったのである。それは長八自身のことであった。
長八は郷里に帰りつくと、まず養女のおしゅんに死後のことを懇々と話している。口だ
けでは心配で、おしゅんに箇条書きの紙を渡した。その箇条はおよそ次のようなことであ
った。遺骨は播磨屋の菩提寺である浅草の正定寺に葬るが、是非淨感寺に分骨してほしい
ということ、葬儀は東京でやるが、分骨の時にも郷里で供養してほしいということ。墓は
予め買ってあった場所に建てること。そして、それらに必要な一切の費用の金と、墓石に
刻む文字『釈天祐居士墓』と自分で書いた紙を渡した。
翌日淨感寺へ行って、若い住職に改めて死後のことを頼み、墓所を定めた。
帰郷したのは、この用件のためだったのである。用件をすますと、もう思い残すことは
なかった。肩の荷をおろしたように、長八はのんびりとわが家の古びた縁先で暖かい春の
日射しを楽しんでいた。眼の前に牛原山が大きくふさがっていた。子供の頃が思い出され
た。
いつの間に出て行ったのか、おしゅんが風呂敷包みを抱えて田圃道を帰って来た。
「どこへ行ってたんだい」
と長八はおしゅんの近づくのに言った。
「水車小屋へ。おじいさんの好きな小麦餅を作ろうと思って」
「そうか」
長八は微笑した。
「小麦餅か」
とつぶやいた。
「食べたいな」
「今直ぐ作りますから、それまで散歩でもしなすったら。浜の方は大分家が建ちましたよ」
おしゅんが勝手場から言った。
「そうか、そうしようか」
と長八はゆっくり腰を上げた。そして、縁先の藁草履をつっかけて外に出た。
大橋を渡って中瀬に出る。ドブ川を通って向浜に来る。ここらはすっかり家が立ち並ん
でいる。真っ直ぐに行くと松原に出る。その松原沿いに新しい一本の道が出来、江奈浜に
続いている。昔砂畑ばかりだった所に、今は点々と家が立っている。去年来た時にはまだ
ほとんど家はなかったのに、たった一年の間に、こんなに変わったのかと、長八は驚いた。
歩いて行くと、一軒の新築中の家があって、大工や左官が働いていた。思わず、そこに
立って見上げていると、
「師匠…」
と驚いた声で中から出て来た男がある。
「三右衛門か」
と長八も驚いた。東京で修業していた弟子の山本三右衛門である。今では郷里に帰って、
父の後を継いでいる。
「お帰りになっていたんですか」
「うん、昨日。内緒で来たんだから、誰にも言うなよ」
「へえ」
「忙しそうだな」
「はあ、おかげで」
「ここは誰の家だ?」
「粂さんの家です。大工の粂五郎さんの」
「そうか、粂さんの家か」
長八はそう言って改めて新しい家を仰いだ。
「粂さん、たっしゃかい」
「へえ、うらで仕事をしています」
「会いたいな」
「呼んで来ましょう」
「いや、おれが行く」
長八はすたすた軒下を潜って行った。
粂五郎は裏庭で台所戸棚を組み立てていた。
「おい、粂さん」
と長八が呼んだ。ひょいと顔を向けた粂五郎は、直ぐに懐かしそうな笑顔になって、
「長さん」
と言った。
「たっしゃでいいな」
「お前さんも」
「いい家が出来るじゃあないか」
「何の、やっとこさ家らしいものをね」
「中を見せておくれ」
「さあどうぞ。散らかっているぜ」
長八は木片の散っている床に上がった。座敷と思われる一室で、職人が欄間を塗ってい
た。長八はそれを見上げていたが、急に、
「粂さん」
と呼んだ。粂五郎は後に居た。
「ここをおれに塗らしてくれ」
粂五郎はびっくりして、
「お前さんが?」
と聞き返した。
「いいだろう?」
長八が笑った。
「そりゃあ構わないが」
粂五郎は恐縮していた。
「幼な馴染みの友だちの家だ。このままじゃあ帰れない。やるそ、いいな」
長八は、着ているどてらの帯をしめ直した。
「三右衛門、たすきはないか」
と、きょろきょろ見廻して、遠くに縄切れを見た。
「三右衛門、あれがいい」
三右衛門が急いで持って来た縄を、長八は手早くたすきにした。
「土は?」
長八は鏝をとった。土が運ばれた。身軽に踏台に乗った。
今塗ったばかりの荒土の上に、たっぷりと赤色の練り土をつけて塗り始めた。大鏝で土
を引くように動かすと、びっしりときめこまかい壁になって行った。一面塗り終わると、
「粂さん、お祝いに絵を描くぞ」
と言ったが、振り向きもせず、細鏝をとって何やら縦横に機敏に動かし、踏台の上で眺
め渡して、
「よし」
と言うと、次の欄間に移った。
四面の欄間には、鏝描きの瀟湘八景が見事に描かれた。長八は描き終わると煙草に火を
つけてゆっくりと吸った。ぐるりと山水を見廻した。一つは横線を漂茫とした大湖の水を
描いていた。起伏する山々は微妙にひだを浮かべて、おのずから遠近を示し、樹林の描線
は鏝の簡潔なタッチを交錯させて、さわやかな風を響かせているようであった。一同はた
だ茫然として、その欄間を仰いでいた。
「じゃ、粂さん、たっしゃでな」
長八は言い捨てて、もうすたすたと草履の音を遠のかせていた。
これが郷里における最後の作品となったことを、長八も三右衛門もその時感じていたこ
とであろうか。
⑥
その翌日、長八は風のように故郷を去った。
東京に帰ると、急に気抜けがしたように元気がなくなり、そのまま床についてしまった。
最後の準備も出来て安堵したのであろうか。持病の喘息ではなく、ただ気力がなく食欲も
薄かった。寝たり起きたりの気ままな生活が続くうち、いつしか四月が過ぎ、五月が過ぎ
ていた。
六月始めのある日、故郷の千葉に帰って独立した石井巳之助が見舞いに来た。長八はい
つものように隠居所に寝ていた。挨拶がすむと、
「師匠、一つ頼みがあります」
と、風呂敷包みを開いた。
「何だ、改まって」
長八は床の上に起きて座っていたが、見るともなしに風呂敷を見ていた。
「何だ、位牌じゃないか」
と、長八は驚いて言った。
「へえ」
巳之助は膝を固くしていた。
「誰の位牌だ」
長八は何の想像もつかない。巳之助は、ちょっと間を置いて、悪びれた表情で、
「師匠の位牌です」
長八は意表を突かれたように、
「おれの位牌だって?」
と聞き返した。
「はい。精魂こめて漆喰の位牌をつくりました。見て下さい」
巳之助が捧げるように位牌を差し出した。長八はそれを手にした。頭の中を悲しい影が
よぎった。巳之助はもうおれの死期の近いのを感じているのか。長八はそんなことを思っ
た。
位牌はずっしりと重かった。表も裏もていねいに金箔を張りつめてあった。長八は不思
議なものを見るように、じっと位牌を見ていた。
「これがおれの位牌か」
とつぶやいた。
「すみません」
巳之助はうつむいた。
「立派なものだ」
長八は改めて眺めた。
「師匠、これに師匠の絵姿を描いて下さい」
巳之助の頼みというのはそのことかと、長八は感じた。と、急に弟子の巳之助の心根が
察しられて、瞼のうるむ思いがした。
「よし。描こう。巳之助、鏝と土を用意しろ」
土は巳之助が持って来ていた。鏝を持って来ると、長八は布団の上に膝をそろえた。位
牌を片手に、土が塗られた。鏝がこまかく動いた。そこに、上半身の自画像が出来上がっ
た。
「ありがとうございました」
巳之助は位牌を押しいただいた。
「時々は線香をあげてくれよ」
長八は静かに言った。巳之助はその言葉に、胸の迫る思いだった。
七月、東海道が開通した。五、六年来低迷していた景気も、ようやく持ち直して来た。
東京も首都らしく活気を見せて来た。長八は、そんな世間の様子を家人や見舞客から聞く
だけで、隠居所にこもり切っていた。
梅雨が続いてうっとうしかった。おはなも老境に入って、この頃しきりに神経痛に悩ま
されて、長八の世話どころでなく、仕方なく母屋に移った。その代わりに竹次郎の女房の
おふくが、隠居所と母屋を往き来していた。
梅雨が明けた頃、幸太郎が訪ねて来た。折よくおはなもそこに居た。長八は寝床の上で
おはなの持って来た薬湯を飲んでいた。半分飲んで盆にもどした。
「飲んでしまいなさいよ」
幸太郎が言うと、長八は黙ったまた茶碗をつかんだ。そんな長八を、幸太郎もおはなも
痛々しく見ていた。
おふくが茶を運んで来た。
「おじいさん、幸太郎さんから鮎をいただきました」
と報告した。
「そうか、ありがとう」
と幸太郎に言った。
「煮つけましょうか、それとも塩焼きにしましょうか」
「塩焼きがいいな」
長八が言った。
「じゃ、そうしましょう」
と言って、おふくが立ち上がったところを、幸太郎が、
「おふくさん、ちょっと話がある」
と幸太郎が引き止めた。
「おばあさんも一しょに話を聞いておくれ。実はおじいさんのことだがねえ」
と切り出した。
「赤坂へ寄越してくれないかい。竹さんには私から話す」
と言われて、おふくとおはなは顔を見合わせた。どっちも黙っていた。
「幸太郎さん、そんなことを言ったって」
とおふくが口を入れた。長八の顔を見た。
「急に、どうしてそんなことを」
とおはなが継ぎ足した。幸太郎は、それを待っていたように言い出した。
「おじいさんの健康のためだよ。ここは湿気があってよくない。夏場は特に風通しもよく
ない。体によくないよ」
そう言われればその通りであった。長八もおはなもおふくも黙っていた。
「それに」
と、今度は長八の方へ言った。
「おふくさんが大変ですよ。子供の世話から、職人たちの世話から、二人の世話ですから
ね」
長八は黙ってうなずいた。幸太郎の言う通りだと思った。
「あたしもね、せめておじいさんの世話ぐらい出来るといいんだけれど」
と、おはなが言いわけのようにつぶやいた。
「あたしは何でもないですよ」
おふくが言った。
「そうはいかないよ。おじいさんにしてみても、ここでは直る病気も直らない」
幸太郎が強い調子で言った。おふくもこれには抗弁出来なかった。が、幸太郎に迷惑を
掛けてはと思っていた。
「でも、幸太郎さんとこが」
とおふくが言った。
「それは心配ない。うちでは、子供ももう世話がかからなくなっている。第一職人など居
ないしね」
と言って、幸太郎は今度は長八の方に、
「どうです、おじいさんは」
と聞いた。長八は考え続けていた。どっちにしても厄介を掛けるのは自分である。同じ
ことなら、楽な方へ行く方がいいかも知れない。そう思った。
「そうするか」
長八はあっさり言って、おはなとおふくを見た。
「折角、幸太郎さんがそう言うのだから」
すると、二人は、
「おじいさんがその気なら」
と、あえて逆らう気持ちはなかった。
「よし、これで決まった」
幸太郎が安心したように言った。
二、三日して、天気のよい日に、長八は幸太郎の迎えの車に乗った。赤坂の家では、暑
い夏でも風が通ってしのぎよかった。しかし、長八は寝たり起きたりのいつものような日
々であった。
九月半ばになって、秋風が立ち始めると、急に八名川町へ帰ると言い出して、長八は一
人で帰ってしまった。体調がいくらかよくなっていた。そうなると、あれこれの仕事を思
い、八名川町の仕事場が恋しくなったのであろう。
が、体調がよくなったのは一時的であった。八名川町に帰って、四、五日仕事をしてい
るうちに、また急に喘息に襲われた。家人はあわてて手当をし薬湯を飲ませた。発作は毎
日三、四回起こった。発作がおさまると、案外元気で、人々を相手に談笑していたが、発
作が起きると、せわしく咳き込んで、眼も当てられないほどの苦しみだった。いつか九月
も末になって、長八は眼に見えて痩せていった。
九月二十七日、十五夜の月が出ていた。静かに月の光を見ていると、そこへ幸太郎がや
って来た。葡萄の篭を提げていた。
「甲州へ行って来ました」
幸太郎は枕元に座った。材木の買い付けに行ったのである。竹次郎もおはなも居合わせ
ていた。
「おばあさん、直ぐあげるといい」
幸太郎は篭をおはなに渡した。おはなは篭を提げて出て行った。
「今夜はいい月ですねえ」
と幸太郎が言った。
「うん」
長八はそう言って明け放した外を見た。縁先に小机を置いて、薄や野菊が揺れていた。
おはながとって来たのであろう。
「おじいさん、起きますか」
竹次郎が長八の顔をのぞいた。
「いいよ」
と長八が枕に載せた頭を横にした。
「幸太郎」
長八が言った。気のせいか力のない声だった。
「何ですえ」
幸太郎が長八の顔をのぞいた。くぼんだ眼蓋に影を落としたまま眼を閉じていた。
「眠いんですか」
「いや」
と長八は微笑したようであった。
「今、松崎の十五夜を思い出していた」
「懐かしいでしょう」
「うん」
長八が頭を動かした。
「裏の牛原山に登ってな、山梨の枝を切って、帰りに野菊を一ぱい摘んで」
と、思い出しながら言った。
「子供の頃ですね」
竹次郎が言った。
長八は夢でも見ているように見えた。
「あっしらもよく上野へ行きました」
と幸太郎が言った。
「山梨と野菊を両手に一ぱい抱えて帰って来ると、おっ母あは団子の粉を引いていた。ゴ
ロ、ゴロってな」
臼の音を聞いているかのように、しばらく黙った。長八は口を薄くあけていた。
「台所の流しに花をほうり出して、お母あのそばで、粉を引く音を聞いていた」
そこでまた途切れた。竹次郎も幸太郎も黙っていた。何かしみじみとしたものを感じて
いた。と、思い出したように、長八がまたつぶやくように話し出した。
「円い大きな十五夜さんが円通寺の山から出て来る。出た出たと言って庭に下りて、手を
たたいて喜んだ」
長八の声がだんだん低くなっていた。
しばらく黙ったままで、やがて、ぽつりと言った。
「つまらねえな」
そして、寝息を立てて眠ったようであった。竹次郎と幸太郎はその寝顔をじっと見詰め
ていた。母屋の方からおはなとおふくの話し声が聞こえた。
養子の兼吉は性質が温順で実直だった。才気はなかったが、一本気で、どことなく長八
の若い頃に似ているようであった。長八は、肉親であるということの外に、兼吉のそうい
う人柄を愛していた。それだけに仕事を本気で仕込んだ。兼吉はそれに応えるように仕事
に熱心だった。もう一ぱしの若者になっていて、竹次郎の片腕として働くようになってい
た。長八はそんな兼吉を楽しみに見ていた。入江の血統と共に、ほんとの鏝を継いでくれ
ると思っていた。
その兼吉が死んだ。長八は自分の大切にしていたものを無惨にも奪い去られた悲しみに
打ちひしがれた。自分の死後も兼吉が居ると思うことだけで明るい気持ちだったのに、そ
の明るさが一瞬にして消えた。
長八には多数の優れた弟子があった。中橋善吉を筆頭に、江口庄太郎、吉田亀五郎、井
上市五郎など、今では一流の鏝絵師である。若い者では、竹次郎、兼吉、伝二郎など将来
有望な者がいる。だが、長八はこれらの弟子たちにあきたらないものを持っていた。それ
は、これらの弟子たちは皆長八の技術を習得してはいるけれども、人間的な精神の深さと
いうものが欠けている。彼等はほとんど青年、壮年の時からの弟子で、精神よりも技術を
身につけることを心掛けた者たちである。長八はそういう弟子たちを見るにつけ、人間と
して鍛え上げることの大切さを知った。それには少年時代から育て上げなければならない
と思った。たまたま兼吉を養子にして、日々の仕事や生活の中で、この少年に期待を掛け
るようになった。そのつもりで仕込んで来た。そして、兼吉は期待通りに育って来ていた。
技術的には先輩に到底及ばないが、先輩よりも遙かに大きな翼をひろげてはばたく可能性
を持っているように、長八には思えた。
長八は兼吉をほんとうの後継者だと思っていた。その兼吉に死なれて、今更のように兼
吉をどんなに深く愛していたかを知った。兼吉は長八の分身であった。長八の未来であっ
た。どれだけ悔やんでも及ばない哀惜が長八を悩ませた。
間もなく年改まって明治十七年。長八は七十歳の春を迎えた。兼吉の遺骨はそのまま八
名川町に置かれて、長八にはさびしい喪の春であった。何もしなかった。何をしようとい
う気力もなかった。気の衰えに寒さが加わって、またしても喘息に襲われた。
「兼吉が死んで、師匠はがっかりしたのだ」
と、弟子たちは心配した。
一月が過ぎて、二月も寝たきりの日々が過ぎた。三月になっても、起き上がる元気がな
かった。四月にはようやく起き出て庭を歩くことが出来たが、仕事には一切手をつけなか
った。すっかり痩せ細っていた。
六月に入って、喘息が癒えた。が、体調はまだまだであった。すると、突然菊地幸太郎
の長男の由松が病死した。長八は赤坂田町の幸太郎の家に人力車で行った。数少ない血縁
の一人の葬儀に出たかったのである。遺骨は正定寺に葬ったが、幸太郎の引き止めるのに
甘えて、由松の初七日の忌がすむまで赤坂で過ごすつもりでいたが、その間にまたも喘息
の発作が起き、そのまま幸太郎の家で臥床することになる。
幸太郎を始め家族は長八を大切にしてくれたが、病気はしつこく長八を苦しめた。梅雨
の季節が余計気分をうっとうしくした。
「世話を掛けるなあ」
と長八は家族の一人一人に言った。毎日決まったように発作が来る。誰かが来て背中を
さする。時間を決めて薬湯を飲ませるのは、幸太郎の妻のおとりであった。幸太郎は忙し
い体を、夜は大抵長八の側に居て何かといたわってくれる。そんな日々が続いた。
昼間は座敷にひとりぼっちで寝ていることが多かった。そんな時、長八は天井にくぼん
だ眼を向けていた。頭の中で、とりとめもなく、いろいろなことを思っていた。多くは過
去のことである。
「やっぱり、おれは死ぬのかも知れない」
と、ふと思う時がある。それが胸の中でつぶやくように聞こえる。死んでもいいと思う。
今まで随分『死』ということを考えて来た。失恋の痛手から無頼の酒に酔いしれていた時、
おきんとの日陰の生活で苦しかった時、しかし、若い頃の考えは全く他人事のように見て
いて軽々しいものであった。それから、成田山参篭以来、さまざまな場合に『死』がのぞ
いた。が、それも『死』を見詰めようとしていただけで、観念的だったように思われる。
それらを思い合わせると、今度は違うようである。『死』が直ぐそこに来ている感じであ
る。そして、自分と近々と語り合っているようである。
「お前はもう死期が来たと思っているらしいな」
と問いかけて来る。
「うん、そう思っている」
と長八が答える。答えても、少しも苦悩はない。屈託はない。
「この世に思い残すことはないのか」
と、また声がする。
「ある」
「そんなら、もっと生きたいと思うだろう」
「いや、生きたいとは思わない」
「なら、死にたいか」
「死にたいとも思わないな」
「一体、どっちなのだ。生か、死か」
「どっちとも言えない」
「それはおかしい」
「おかしいか。それなら、どっちでもいい」
「死んでもいいか」
「死んでもいい」
「生きていていいか」
「生きているのもいい」
「ずるいぞ、それは」
「ずるいかも知れない」
「それなら、思い残すことはどうする」
「生きていたら、やる」
「死んだら」
「死んだら仕方ないさ。やりようがない」
「あきらめるのか」
「あきらめるより外なかろう」
とりとめもなく死との対話が続く。しかし、それはかつてなかった親しさで語り合えた。
「確かに心残りはある」
と長八は思う。家のこと、仕事のこと、竹次郎のこと、幸太郎のこと、弟子たちのこと。
が、先の先まで心配するのは凡愚の煩悩だと思う。
「どうなろうとも仕方ないことだ」
と長八は思う。そんなことを寝ながら考えている自分が、案外静かなのに驚く。
赤坂の幸太郎の家に臥床して一と月が過ぎ、梅雨が明けた。病気もいくらか軽くなった。
幸太郎は喜んだ。が、涼しくなるまで居よという。長八はその言葉に甘えて、ぶらぶらし
ながら夏を過ごした。
夏になると、夜は幸太郎が来て、世間話をしてくれた。竹次郎も時々顔を出した。弟子
たちも訪ねてくれた。こういう者たちから、鹿鳴館の舞踏会の話や、不況のことや、会社
倒産のことなど聞いた。
秋になった。
「涼しくなったから、もう帰ろう」
と長八が言ったが、幸太郎は、
「折角よくなったのだから、これからは体を調える必要がある。落ち着いて静養して下さ
い」
と言って引き止め、そのままずるずると日を過ごしているうちに、幸太郎は裏庭に離れ
座敷を建築し始めた。
「あれは何だ」
と長八が聞くと、
「家が手狭で」
と幸太郎は答えた。
離れ座敷は母屋と細い廊下でつながった。八畳の座敷と四畳半の板間で、八名川町の隠
居所と同じ形だった。いよいよ出来上がると、
「伯父さんはここに住んで下さい」
と幸太郎は誘った。
「八名川町へ行けば、職人も居るし、人の出入りもうるさいですよ。それに八名川町は下
町で湿気が多い。伯父さんの養生に向きません。すっかり直り切るまでここに居て下さい」
幸太郎は半ば強制的だった。幸太郎の言うことはもっともであった。長八は不承不承で
新居に移った。
秋がたけて、長八は病気を次第に忘れたようによくなった。すると、板間で土をいじり
だした。菊地家にはたくさんの作品が遺されたが、そのほとんどはその時のものである。
寒くなったというので、ある日おはなが冬物を抱えて訪ねて来た。蜜柑が風呂敷包みか
らころげ落ちた。もう十二月であった。おはなは着物を着替えさせたり、蜜柑をむいたり
してくれた。いつものおはなと違っていた。竹次郎に一切を任せた当座は、不平や愚痴を
並べ、長八にも当てつけていたおはなだったが、長八が病んで、さすがのおはなも強気だ
けではいられなかったのであろう。おはなは長八に蜜柑をむいてやりながら、竹次郎から
ことづかった用件を、ぽつりぽつりと話してくれた。
とうとうその年一ぱい、長八は幸太郎の家で過ごした。
秋から冬への変わり目を心配したが、長八の喘息は再発しなかった。
年も押し迫ったある日、又兵衛がどてらを持ってやって来た。その時、長八は新居の前
の日当たりに筵をひろげて、そこで土を練っていた。戸袋には仁王の像が荒塗りされてあ
った。
「師匠、どてらを持って来ました」
と、又兵衛は後から声を掛けた。長八は鏝を持ったまま振り返った。
「おう、又兵衛か」
「元気そうで」
「うん」
長八は立ち上がって、古いどてらを脱いだ。又兵衛が後から新しいどてらを肩に掛けた。
帯をしめると、長八はそのまま元の座にもどって土を練り出した。
「仁王さんですね」
又兵衛が古いどてらをたたみ終わって戸袋に眼をやった。
「そうだ」
「仁王さんというと、仏様を守護するものでしょう」
又兵衛は不審に思っていたのだ。
「そうだよ」
長八は土を練りながら答えた。
「こういう戸袋に描いてもいいですか」
「おかしいか」
「へえ」
又兵衛は正直に言った。すると、長八はあはははと笑った。
「又兵衛」
「へえ」
「ここに一人、仏さんが居るじゃないか」
と長八はまた笑って又兵衛を見た。
すでに淡々とした心境であったのだろう。こんな逸話が残っている。
②
明治十七年という年は、欧化の風潮が一段と強くなった年で、有名な鹿鳴館全盛の時代
である。毎夜のように舞踏会が開かれ、シャンデリヤの下で洋装の男女がうつつを抜かし
て踊り狂っていた。東京ばかりでなく、地方都市にも流行して、園遊会とか音楽会などと
いう西洋習俗が行われた。が、その一方では、この風潮をにがにがしく思い、あるいは痛
憤し、あるいは激怒する、いわゆる国粋主義者も頭をもたげていた。明治も十七年を経過
したが、まだまだ安定してはいない。所々にひずみが現われていたのである。藩閥への不
平不満もあったし、新政への反抗もあったし、時には険悪な事件さえ起きていた。九月の
加波山事件、十月の秩父事件、十一月の飯田事件などがそれである。それに加うるに、新
政以後のインフレ状態が苦心の結果終息しかかると、今度は反動的に急速に不況が襲って、
会社や銀行が続々と倒産して行った。
幸太郎の家にも不況の風が冷たく吹き込んでいた。離れ座敷に起居していた長八にも、
その様子は手にとるようによくわかった。それは年末に至って一層はっきりと感じられた。
年が改まると、長八は急に八名川町へ帰ると言い出して、一人で風呂敷包みを抱えて出
て行った。長八の病気はほとんどよくなっていたし、それよりも、不況の中でいつまでも
世話をかけているのが心苦しかったのであろう。幸い、竹次郎夫婦とおはなの仲も、平穏
になっていたし、長八は帰るによい潮時だと思った。
八名川町に帰ると、久しぶりで見るわが家は、前とすっかり変わったような感じだった。
竹次郎はもう立派に一家を取りしきっていた。女房のおふくも落ち着いた態度で家事を指
図していた。兼吉の居ないのがさびしかったが、それは仕方のないことであった。
正月が過ぎて、兼吉の一周忌の供養をした。それだけで、長八は隠居所で静かに暮らし
ていく。時折、竹次郎夫婦が顔を出す。幸太郎も三日に一度は見舞ってくれる。弟子たち
が入れかわり来ては、何かと話しては帰る。そんな平和な日々を、長八は楽しむように暮
らしている。
寒さが峠を越して、三月になる。長八はだんだんと元気を取りもどしたようである。だ
が、朝夕はまだ寒い。時には一日中荒い風の吹く日もある。
「油断は出来ません」
と、竹次郎や幸太郎は長八に仕事をさせない。
三月十二日の夜、日本橋から出火して折からの西北風にあおられて、火は見る見るうち
に燃え拡がり、日本橋一帯を焼野にしてしまった。竹次郎の実家の波江野も、茅場町の薬
師堂も焼けてしまった。
竹次郎は日本橋の実家の復興に当たらねばならぬ。すると、外の仕事は手控えなければ
ならない。
「よし、おれがやる。何あに、指図さえすればいいのだ」
と、長八は止めるのをも聞かず、日本橋復興の仕事に掛かった。いざ仕事となると、持
って生まれた性分で、弟子たち職人たちを督励するだけに納まらず、いつの間にか、自分
も鏝をとって働き出していた。が、長八自身が危惧していた疲労も意外に少なく、あわた
だしく二か月が過ぎ、波江野の仕事も終わって、竹次郎がもどって来て、長八に代わって
働くようになる。
すると、長八は健康に自信を持ち出したのであろうか、茅場薬師の再建に掛かると言い
出し、竹次郎が引き止めるのも聞こうとしなかった。
「茅場薬師の再建は長い間の願いだった。とっくに掛かるべきところを資金が集まらず、
のびのびになっていたのだ。今度焼けたのはかえってよかった。この際やるべきだ。一文
の金にならない仕事をやるには、おれのような人間がいい」
と、長八は竹次郎に言った。
そして、関係者の間を走り廻って、とうとう六月には建築を始めるように手はずを決め
た。
いよいよ仕事が始まった。竹次郎は長八の健康が心配で、長八を赤坂の幸太郎の家から
日本橋へ通わせることにする。もちろん、幸太郎と相談の上である。
長八が茅場薬師の仕事を始めたという話はそれからそれへと伝わった。話を聞いたと言
って、中橋善吉、江口庄太郎が腕ききの職人を連れて応援に来た。こうして一か月ばかり
で薬師堂は完成した。
この時の作品は、内陣に仁王像と雲竜を薄肉彩色で仕上げたと伝えられているが、関東
大震災で焼失して今はない。病後第一作として価値ある作品なのだが、今では何の想像も
出来ない。
薬師堂の工事中、赤坂の幸太郎の家から通っていた関係で、この期の作品として推定さ
れるものが菊地家にある。そのうち注目されるものは、守り本尊として菊地家に遺ってい
る観音像と、後に菊地家の菩提寺、郷里の禅海寺に預けた地蔵像とである。共に、明治十
八年首夏と記して、この期のものであることは明らかである。外に、南画風の塗額が遺さ
れている。
その外に、今日残っているもので、明治十八年作とされているのは、沼津の竹沢家にあ
る文殊像、焼津市光心寺の『舞鶴山水』の衝立。これらは恐らく菊地家所蔵の品であった
ものが、何かの関係で散って行ったのであろう。
長八はやがて八名川町に帰り、元の清閑な生活にもどる。茅場薬師の仕事はさすがに長
八にとっては大変だったようで、長八ははっきりと気力の衰えを知るようになる。それは
仕事場へ入っても根気が続かず、製作がはかばかしく進まなくなったことでよくわかった。
冬になると寒さが身にこたえた。寒さがこわかった。長八は終日こたつにぬくもるよう
になる。往年の気魄はもうないようである。しかし、長八は、そういう自分を静かに順応
していた。衰え行くわが身わが生命であればこそ、粗末にしたくなかった。それは命を惜
しむというような気持ちとは大分違っていた。命を大事にすることといった方が当たって
いるだろう。そこにある自分というものは、どうあろうとも世界中に一つしかないものな
のである。しかも、それは生きている間のことなのである。
やがて、明治十九年がめぐって来て、長八は早くも七十二歳となる。幸いにも持病の喘
息は影をひそめていた。
正月、久しぶりに長八は仕事場に入った。縦五尺、横三尺の木綿地に達磨像を描いた。
衣は朱、背景は紺、顔は淡彩で、この描法は明らかに狩野派のそれであった。だが、その
筆勢は異常な気力をみなぎらしていた。少なくとも病弱の老人の筆とは思われないもので
あった。この大軸はそのまま周囲を瑞雲模様に描いて表装仕立てに見せている特殊な趣向
の作品である。
この絵に見る、異常な気力は何なのであろうか。老年の長八の精神像の一部がそこに見
られるような気がする。長八はすでに程遠からぬ寿命を意識している。その意識は自分の
行動について次第に控え目になってゆき、生命を細く微かにしてゆくのが通例なのだが、
時にパッと火花のように燃えることがあり、潮のようにしぶきをあげることがある。それ
は、老人だからといって、べんべんとしてはいられないという焦燥なのかも知れない。自
己の生命の大切さを強く悲しく感じるのかも知れない。長八の達磨像も、そういう現象で
はないかと思われる。が、長八の場合はもっと違った意識があったように思う。もはや、
やりたい仕事は出来るだけやってしまいたいというような意識的な考えは持っていなかっ
た。だが、作ろうと思い、描こうと思う時、自然に素直に作り、描く。作れるから作る。
描けるから描く。そういう自然な気持ちが成立していたように思われる。こんな時、長八
はこれが最後の作品かと思うのだった。だから、興のおもむくままに作り描いた。それは
死を恐れてはいない。むしろ生を喜んでいるようであった。
この達磨像は折よく上京した桜井東吉に寄托して、三島の竜沢寺に届けられた。彼の浄
土欣求の願いであったろう。また竜沢寺への報恩感謝の心でもあったろう。
春になって、長八はますます健康にもどって行った。喘息は根治したように思われた、
三月の末のある日、急に山岡鉄舟に会いたくなって、下谷初音町の全生庵を訪ねた。鉄舟
は今は官を辞して、ここに閑居していた。長いこと会わなかったことを思い出した。道楽
会も二度三度と欠席をしていた。久しぶりにゆっくり話したかった。別に用件があるわけ
ではない。ただ顔を見たかった。話したかった。
いい日和だったから、一人でぶらりと出掛けた。全生庵を訪ねると、鉄舟は書斎に居た。
久しぶりで顔を合わせた。だが、鉄舟の顔色はさえない。
「先生、どうしたんですか」
長八は無遠慮に聞いた。すると、
「胃が痛むんだよ」
と鉄舟が答えた。言葉が思いなしか力弱く響いた。
「それはいけませんね」
長八は眉をひそめた。
「で、どんな様子で?」
と聞いた。
「時々キリキリと痛むんだよ。その度に針で刺されたようでね」
鉄舟は顔をしかめた。
「医者は何というのです?」
「胃がただれているという」
「食べ物は?」
「それがうまく通らないんだ。粥ばかり食べている。それも少しばかり」
と鉄舟はにがく笑った。
「病気はいやなもんです」
長八はふと『同病相憐れむ』という言葉を思い出していた。
「全くだね」
鉄舟が低い声で言った。思いついたように、
「お前さんもひどい目にあったねえ」
と言った。
「へえ、おかげでこの頃やっと元気になりました」
長八が続けて、
「わたしのは、若い頃からの無理がたたってるのでしょう。自業自得です」
と苦笑した。
「いや、わたしもそうだ。元気に任せて無茶なことをしたからね。それに酒を飲むし」
と鉄舟も苦笑した。
話題は両方ともたくさんあった。あれこれと話しているうちに、鉄舟の姿に疲労の色が
見えて来た。
「すみませんでした。長話をしてしまって」
長八はそう言って膝を上げた。
さりげなく全生庵を辞して来たが、長八は鉄舟の病気が気に掛かった。
鉄舟は、長八からすれば遙かに若く、この時五十一歳のはずである。まだ死ぬ年齢では
ないと長八は思うのだった。だが、何となく影が薄い。長八はいまわしい予感を吹き消す
ように、下谷の低い屋並の下を歩いていた。
③
夏が来て、長八はいよいよ元気であった。が、反対に、鉄舟は次第に病み細っていた。
六月十五日は赤坂の氷川神社の祭日だった。前年からの不景気を吹き飛ばそうというの
で、今年は盛大にやることになった。幸太郎が迎えに来て、長八は人力車で赤坂に行く。
この祭礼には、恒例の職人衆の山車が出る。大工仲間の山車、左官の山車、鳶職の山車、
木場の山車というように、それぞれ豪華を競い景気を競うのである。
ところが、祭の当日ひと騒動が起こった。大工職人の山車が四つあって、それが二つに
分かれて大げんかとなり、血の雨が降りかねないような険悪な事態で対峙したのである。
人々は心配げにぐるりを遠巻きにしていたが、その時別な一つの山車が対立している中に
割って入り、双方の山車を引き離して、事なきを得た。その仲裁に入った山車には、長八
を型どった人形を乗せていたという。左官の山車だったのである。………この伝説は一部
違っている。すなわち、山車に乗っていたのは、人形ではなく、本物の入江長八であった
のである。事実は次のようである。赤坂の左官では、長八の弟子の吉田亀五郎が筆頭の棟
梁である。この大工仲間の紛争を見て、亀五郎は自分の手には負えないと思った。一計を
考えついて、幸太郎の家へ飛んだ。そこでくつろいでいる長八を無理に連れ出して山車に
乗せ、けんかの中に割って入り、双方をなだめたというのである。長八はこの時何も言わ
なかったが、亀五郎が長八を楯にして双方を説得したという。ちょっと突飛もない話だが、
長八の仲介を利用したなど、いかにも東京らしい。いや、江戸風らしい感じである。
長八の体は梅雨に入っても悪くはならなかった。その反対に、鉄舟の病気は、見舞いに
行くたびに憂慮された。
「皮肉なものよ。おれがよくなったと思うと、鉄舟先生が悪くなって」
と、長八は竹次郎に嘆息した。
真夏になった。長八は足繁く全生庵を訪れた。じっとしていられないような気持ちだっ
たのである。
今日も全生庵を訪ねた。依然として鉄舟の病気はよくなかった。不吉な予感が脳裡に走
った。その帰り道、下谷の町から隅田川へ出ようとして、見知らぬ裏町にまぎれ込んだ。
すると、どこからか石を刻む音が聞こえた。コツコツコツと単調に無際限に続いていた。
何の気なしに、その音をたよりに歩いて行くと、一軒の家の庭先に葭簀を張って、中老の
石屋が汗をしたたらせていた。
「ああ、ここだったのか」
と、長八はほっとしたような気持ちで、そこに立ち止まった。石屋はコツコツと刻んで
いる。長八には気付かないようである。白い粒が小さく煙のように散っている。長八は汗
をふきながら、石屋の動作をぼんやり見ていた。ふと長八は思いついた。
「石屋さん」
と声を掛けた。
「へえ」
石屋が始めて顔をあげた。ついでにしたたる汗を手ぬぐいで手荒くこすった。葭簀の陰
からすかすように石屋の眼がのぞいて、
「おや、長八さんじゃあございませんか」
と言った。
「知ってたのかい。長八だよ」
長八は微笑した。
「へえ、何か御用で」
と石屋は不審そうに見た。
「お前さんの刻んでいる姿を見ていたら、わたしも刻みたくなった。わたしにも刻めるよ
うな石はないかい」
「あなたが刻むんですか」
石屋はけげんな顔を向けた。
「うん」
と長八は笑った。
「何を刻むんで?」
長八はそう言われて困った。突差に、
「地蔵様だよ」
と言った。
石屋は腰を伸ばして、石置場に案内した。
「大きさは?」
「さあ、二、三尺でいいだろうな。それに台石とね」
石の間を石屋が潜って行った。
「これが手頃でしょう」
「年寄りだから、固くちゃあ困るよ」
「これならいいでしょう。よくやりますねえ。あなたならきっといい地蔵さんが出来まし
ょう」
「じゃあ、すまないが八名川町まで届けてくれないか」
「へえ、承知しました」
全くの思いつきだった。鉄舟の病状を案ずる余り、祈りたい気持ちで通り掛かった石屋
だった。石屋の姿を見て、自分で仏を刻んでみようと思い、石屋に聞かれて、地蔵をと答
えた。それだけのことだが、長八は後からいい考えだと思うようになっていた。鉄舟先生
のため、延命地蔵を刻もうと心に決めた。
石が届くと、長八は待ち構えていたように地蔵を刻み始めた。不馴れな手つきだが、一
心に刻んだ。暑い夏だが、石を刻んでいると暑さも忘れた。七月が過ぎて、間もなく延命
地蔵は出来上がった。
その間も、鉄舟の病気は悪かった。延命地蔵が出来上がった頃、鉄舟は突然激しく血を
吐いた。その時、そばには誰も居なかった。真昼のことで家族も門弟たちもそれぞれの用
事をしていたのである。血を吐いた鉄舟は、息をはずませて、辺りの血をぬぐうと、その
ままぐたりと床に倒れた。彼は命の終わりを感じ取っていた。やがて、そっと床の上に端
座して、数枚の遺書を認めた。
その遺書の一通が今日も残っていて、鉄舟の人間的なものが強く察せられる。が、筆跡
はさすがに往年の気魄はなく、病人らしい弱々しさを漂わせている。
『金を積みて以て子孫に遺すも、子孫いまだ必ずしも守らず。書を積みて以て子孫に遺す
も、子孫いまだに必ずしも読まず。如かず、陰徳を冥々の中に積みて以て子孫長久の計と
為さんに。これ先賢の格言にして、すなわち後人の亀鑑なり』(原文は漢文)
というのである。遺言というより訓戒というべき言葉のようである。
鉄舟は遺書を認め終わると、それを枕の下へ入れて、ゆっくりと仰臥した。そして、死
を待つもののように、黄昏の中を深い眠りに落ちて行った。昏々と眠って朝に至った。家
人は驚いて医者を呼んだ。医師はあるかなきかの脈拍を数えながら、絶望の眉を寄せてい
た。家人や門弟がひっそりと憂愁の眼を向けて、枕べを取り巻いていた。
鉄舟は昏々と眠り続けていたが、夕暮れ近く静かに眼を開いて、ぐるりの人々の顔を見
廻った。微かに明るい笑みを浮かべていた。鉄舟は死ななかった。吐血して、かえって苦
痛が薄らいだように見えた。今で言えば胃潰瘍の症状のようだが、吐血によって軽くなる
ということがあるのか、私にはわからない。とにかく、鉄舟の病状は持ち直した。秋と共
に快方に向かうほどになる。
長八が一心こめた地蔵像があるいは鉄舟の命を救ったのかも知れない。長八はひそかにそんな思いを抱いた。
ある静かな秋、地蔵像は全生庵の庭に据えられた。背銘に、『一心頂礼、七十二天祐居
士』と刻まれてあった。長八が自ら車に載せて運んで来たものだという。
こうして、明治十九年が暮れ、明治も二十年となる。二月、東京に初めて電灯がつく。
この年の冬も長八は元気であった。時たま仕事場に入って、頼まれた塗額の制作をした。
が、四月の声を聞くと、長八は待ちかねていたように故郷に帰った。
何年ぶりの帰郷であろうか。病気になって、もう帰れないと思った故郷へ帰れる喜びは
譬えようがなかった。
「ちょっと行って来るよ」
とおはなと竹次郎に言って、身軽な格好で八名川町を出た。これが最後の帰郷になるだ
ろうと、長八は心ひそかに思っていた。病気は回復してはいるが、体力の衰えは隠しよう
がなかった。いつまでも生きれるとは思わなかった。
ゆっくりと旅を続けた。三島では茂平の家がわが家のようなものだった。茂平は八十歳
の高齢で、相変わらず元気だった。
「先日、横浜へ行ってきたよ」
と、早速話し出した。
「横浜は大層なにぎわいだそうですねえ」
「こんなに発展するとは思わなかったよ」
茂平は横浜での見聞をやや興奮した面持ちで事こまかに話した。にこにこしていて、昔
の厳しさは忘れたように消えていた。
「新開地だし、居留地だし、面白いことが一ぱいだな」
「昔は普通の漁師村だったんだそうですがねえ」
「昔の面影なんぞ少しもありやあしない。港には外国船が 煙を吐いているし、町は洋館
が立っているし、桜木町あたりは軒並みだ。そこを異人がぶらぶらしているんだから」
「景気もいいようですねえ」
「異人相手の仕事が多いからな」
次から次へ話が走っていた。
「そうだ。珍しいものを見せてやろう」
思い出したように、茂平はぽんぽんと手を鳴らした。
「儀三郎」
と次の間に向かって呼んだ。間もなく儀三郎が入って来た。
「写真」
茂平が言うと、儀三郎は持って居た一葉の写真を差し出した。
「何だ、持って来たのか」
「多分そうだろうと思いましてね」
儀三郎はいたずらっぽく笑った。
「こいつ」
茂平が苦笑しながら写真をとった。
「おやじは来る人誰彼となく、この写真を見せるんですよ」
と儀三郎は長八に向いて笑った。
「横浜に着いた日に、異人に会ってな。おれの年を聞くから、八十だと答えたらびっくり
してな、是非写真をとりたいと言うんで写したんだ」
長八は写真を手にした。写真は東京で何度か見ていたが、茂平の自慢の鼻を折らないよ
うに気を使った。そして、写真に見入った。薄くぼけてはいるが、まさしく茂平の姿だっ
た。
「おれの宿まで追っかけて来て、とったんだ」
茂平は得意気であった。
「おやじの一つ話ですよ」
儀三郎が小声で言った。
「日本人でもやっている人があるらしい。東京の浅草辺に写真館があるという」
「聞いたことがあります」
「それがな、何でも下田の人だそうな」
「へえ」
茂平は名前を思い出そうと天井を向いた。
「下岡蓮杖でしょう」
儀三郎が言った。茂平が大きくうなずいて、
「おう、そうそう。下岡蓮杖といった」
と笑った。
日本の写真の始祖、下岡蓮杖のことである。その弟子に鈴木真一がいて、長八と同郷岩
地村の出身者である。岩科学校の開校式、真一の甥の依田勉三が明治十六年、十勝開拓出
発時の写真は彼の撮影である。
④
長八は翌朝、沼津の川口から汽船に乗った。沼津、下田間の定期航路が開かれていたの
である。余談であるが、この会社は先に述べた依田一族の共同出資で設立されたものであ
る。
船は春の静かな海を白波を蹴立てて走った。長八は乗客にまじって甲板に立っていた。
移りゆく風景はやはり懐かしかった。大瀬崎を過ぎると、やがて戸田港である。船上から
松城家の白壁が光って見えた。二人の客が荷物と一しょにはしけに移り、ゆらゆらと船か
ら離れて行った。長八は船が動き出すまで白壁を見ていた。そこには瞼に浮かぶ自分の作
品があった。土肥、宇久須と次第に故郷に近づく。乗客も残り少なくなって行く。
「便利な世の中になりましたなあ」
と長八は隣の客に話し掛けた。
船はなつかしい故郷の港に着いた。ここで大方の乗客は下船する。代わって、下田へ行
く客が乗り込む。共に小さなはしけ舟が送り迎える。
松崎に着くと、おしゅんの居るわが家にその夜を過ごす。翌日父母や姉の墓参をする。
ついでに庫裡に廻って、老い衰えたたきえや若い住職と会う。そんなことにも長八は喜び
を感じている様子であった。別に用事があって帰郷したわけではない。ただ故郷をゆっく
りと噛みしめたかったのである。寺を出ると、近くの知人を訪ねた。また次の知人を訪ね
た。次の日も同じようにぶらぶらと故郷の道を歩いた。道ばたで老いた友だちと立ち話を
するのも楽しかった。通りがかりの家から声を掛けられて、ひょいとそこへ入り込んで世
間話をするのも楽しかった。海へも行った。遠い昔のことが思い出されるが、決してにが
くはなかった。
五日経った。依田善吾の家から使いが来て、そこでいくつかの作品をつくった。そのう
ち、岩科の佐藤甚蔵と山本三四郎が連れ立って来て、半日話して帰った。いつの間にか、
自然と長八の帰郷のことがあちこちに知れて、注文があり、断り切れず仕事を始めるよう
になる。この時の作品で今残っているのは、依田家の『寒牡丹』、壬生家の『不動明王像』、
淨泉寺の絵馬などである。
長八がこうしてのんびりと暮らしていたが、六月、急な用事が出来て、急いで東京にも
どる。急な用事というのは、新しく東京角力協会が設立され、その記念興業が両国回向院
で催されるについて、元の角力会所の世話人だった長八が引き続き協会の相談役になって
いたから、興業に間に合うように帰らなければならなかったのである。
東京に帰って、六月の大角力も無事に千秋楽になると、長八は久しぶりで全生庵に鉄舟
を訪ねた。初夏とはいえ、暑い日射しの日であった。
鉄舟は麦わら帽子をかぶって、庭の草をむしっていた。門を入って来る足音を聞いて、
尻からげの腰をのばした。
「よく来たな。伊豆へ行ってたそうだね」
「ええ、春に」
思いなしか、鉄舟は頬がこけていてまだ病気が本復してはいないようだった。
二人は縁先に腰掛けた。そこから石地蔵が見える。石地蔵の体に楓の木もれ日がまぶし
いようにちらちらと動いていた。
「お体の方は?」
と長八が聞いた。
「大分いいが、まだ力が出ない」
「無理をしてはいけません」
「いや、無理は絶対にしないようにしている。何しろ、ちょっと何かをすると疲れてね」
そこへ娘の松子が茶を運んで来た。
「しばらくです」
と松子は一礼した。
「静岡からの新茶だよ」
鉄舟が先に茶碗に手を掛けながら言った。
「静岡から?………いただきます」
長八は茶碗を手にした。新茶の香がさわやかだった。
「やっぱり新茶はいいですね」
と、長八は喉を通ってゆく香を味わっていた。
「幕臣の連中が一生懸命開拓した牧の原の茶だよ。ようやく今年からとれるようになった」
「なかなかいい香りです」
二人は新茶をすすった。
「うん、思い出したよ。長八さん」
と茶碗を持ったまま鉄舟が言った。
「何ですか」
長八も茶碗を持ったまま聞いた。
「先頃伊東子爵が遊びに来てな。今、離れを建てているんだそうだ。それでね、お前さん
に壁をやってもらいたいと言っていたよ」
「伊東様、お元気で?」
「ああ、相変わらずだね。ああいう達者な奴を見るとうらやましくなる」
「で、お急ぎのようでしたか」
「いや、今普請中ということだ。あの有名なやかまし屋だから、直ぐというわけには行く
まい。そのうち、一度会って下さい」
「へえ」
「この前の仕事がよっぽど気に入ったんだね。くどくどと賞めていたよ」
「恐れ入ります」
鉄舟は思ったより元気っだった。
全生庵を出て赤坂に廻った。幸太郎に会いたかったのである。もう日暮れに近く、方々
で打ち水をしていた。
その夜、幸太郎の家に泊まった。幸太郎の商売も持ち直して、前よりも景気がいいよう
だった。翌日、朝の涼しいうちに八名川町に帰った。そして着物を着替えると、人力車で
伊東祐亨子爵邸向かった。
伊東邸の離れは、鉄舟の言ったように期日が延びて、ようやく秋の半ばに仕事が始まっ
た。
長八は、この離れ座敷の四方の欄間に『三保の松原』の図を描き上げた。さわやかな淡
青の地に、遠く近く連らなる松原を、鏝の描線を巧みに駆使した。得意の無彩色鏝描であ
った。この図はいかにも晩年の澄明な心境を示していて、立派なものであったという。余
談だが、祐亨が幕府に追われた時、伊豆の馬次郎の実家に匿われたことがあるが、それは
たがいの口端に上らなかった。
やがて明治二十一年。長八、七十四歳。
新春、彼は『青不動』の画幅を描いた。先年郷里に帰った時、淨感寺の若い住職との約
束のものだった。折よく、坂倉保が医学の修業を終えて故郷に帰ることになっていて、こ
の画幅は坂倉保が淨感寺に届けた。
三月、日本橋の柳光亭の大改築をするに当たって、二階百畳敷の大広間に、鏝絵を描く。
柳光亭は柳橋の一流料亭で、当時隆盛を極めていたという。ここで長八は何を描いたかわ
からない。が、長八の変わった逸話だけが伝えられている。
柳光亭では改築が着々と進んで、長八もすでに壁の仕事を始めていた。ある日、長八が
来ると、大広間で大変な悶着が起きていた。話を聞くと、大広間の床柱のことであった。
床柱の材料は小金井村にある二た抱えもする椋の木を使うことになっていた。何しろ二百
年以上の古木で、いよいよ鋸を入れたところ、中が空洞になっていた。しかもそこに二疋
の白蛇が出て来た。使いの者の話を聞いて、柳光亭の主人は「白蛇が出たとは吉兆だ」と
喜んだが、妻女や番頭、女中頭まで、気味悪がって絶対反対を唱えた。大変な悶着という
のは主人と反対側とで、床の間を前にして争っていたのである。どっちも、一歩も引かな
い様子を見て、長八が中に入った。
「双方の意見は、それぞれもっともだが、両方立てるわけには行かない。そこで、どうだ
ろう。わたしに任せてくれまいか」
と長八が言うと、主人は直ぐに、
「任せるって、一体どうするんです」
と不承知の顔をした。
「わたしに考えがあります」
と言うと、
「その考えを聞こうじゃないか」
と皆が口々に言う。
「じゃあ話しましょう。白蛇はめでたいものと、昔から言い伝えられていて、それは御主
人の言う通りだ。折角めでたい古木が手に入ったのに捨てるのは惜しい。しかし、白蛇を
気味悪く思い、祟りを恐れるのも無理はない。そこで、白蛇の霊を封じて祟りのないよう
にすればいい」
すると、反対派が、
「白蛇を封じるって、どうするんです?」
と畳み掛けて来た。
「わたしが封じます」
長八がきっぱりと言った。ともかく、押問答していても始まらない。ようやく双方とも
不承不承ながら長八の言葉に従うこととなった。
そこで問題の床柱が運び込まれ据えられた。長八は読経をしながら床柱の空洞を封じた。
が、そこには二疋の白蛇が漆喰で描かれた。これが白蛇の話である。
ところが、これには後日談があって、柳光亭が開店するとたちまちこの柱が有名になり、
見物がてらの客が来て店は大繁盛したということである。
もう一つ、柳光亭にまつわる逸話がある。この大改築の祝いに、はるばる青森県から客
が上京して来た。柳光亭の先代は青森県七戸の出身で、裸一貫から刻苦精励して、一代で
この大店に仕上げた人で、客というのはこの先代の弟である。この叔父が長八の鏝絵の見
事さに驚嘆して、郷里への土産に何か描いてほしいと頼んだ。長八は即座に承知して、不
動明王の図を描いて与えたという。
柳光亭の仕事は主に長八の鏝絵で、百畳の大広間だし、かなり時日を要した。仕事最中
に福田行誡上人がなくなったという知らせを受け、長八は一日仕事を休んで深川本誓寺に
弔問した。
福田行誡といえば、幕末から明治にかけての高僧で、増上寺の管長を勤め、後に京都知
恩院の寺主となり、明治十八年畢生の大事業『縮刷大蔵経』を完成した仏教界の最高峰の
人である。長八とはたった一度しか会っていない。それは昨年の春の帰郷の時であった。
たまたま上人は大蔵経を完成して、その疲労で病気になり、静養のため松崎の淨感寺に滞
在していた。長八は最後の帰郷と思っていたから、散歩のついでに淨泉寺にも立ち寄った。
そこで上人とめぐり合ったのである。行誡はこの時八十二歳だったから、長八より九つ年
上である。四方山の話の末、住職は二人に記念の色紙を書かせた。その色紙が今も残って
いる。妙な寄せ書きで、独楽と煙管が一筆描きされ、それに行誡の筆で、『このようなこ
まもろこしの書にもなし』と狂句めいた文字が書かれてある。絵も言葉もどんなことを意
味しているかはわからないが、二人の超俗的な風格だけは感じられる。 柳光亭の仕事は
五月の末に終わった。その後は赤坂の幸太郎の家で休養した。やがて梅雨の季節である。
長八は幸太郎の言うままに、八名川町の湿気を警戒していて、赤坂で過ごしたのであろう。
七月、朝から強い日射しの日だった。真夏を思わせる暑さだった。そんな日の午後、八
名川町から勝之助が手紙を持って来た。山岡鉄舟の死の知らせだった。長八は暑さに弱っ
て、その日は夏布団に横たわって、ぼんやりと団扇を動かしていたのだった。起きて、手
紙を読むと、長八はがばと起き上がった。
人力車を呼ぶ間ももどかしく玄関先に立っていた。人力車を飛ばして、谷中の全生庵ま
で急がせた。
⑤
鉄舟は静かに眠っているようであった。二人の姉妹が黙然とうなだれていた。
「鉄舟先生」
と、長八は小さく叫んだ。冷たくなった手にすがりつきたい気持ちでいた。長八は合掌
しながら、波乱の生涯を思った。二人の奇しき縁を思った。走馬燈のように過去が移り動
いていた。しみじみと、偉い人であったと思う。歳こそ下だが、長八は教えられることが
多かった。芸術の上ではなく、もっとも根元的な人間の生き方について、長八は鉄舟によ
って救われたという外にないないと思うのだった。
門弟たちがあわただしく動いている中で、死者はただ寂然として微笑さえ浮かべている
かのようであった。長八はその死顔に敬虔な静かさを感じた。死というものは、かくのご
とく美しいものなのかと、長八は鉄舟の死顔に、おのれの顔を重ね合わしていた。
「おれも、死ぬ時、こんな美しい顔になれるだろうか」
と自問してみた。すると、急に自分の死への思いが胸に湧き起こった。鉄舟は恐らくあ
の吐血以来死を覚悟していたであろう。どう考えていたか、どんな内面の苦悩があったの
か、すべて知る由もない。が、あの平素の淡々とした表情、あの自然のままの言動、そう
いう一つ一つが、今は深い意味を持って、長八の胸によみがえるようであった。
長八は遺体から離れて縁先に出た。そこに石地蔵が立っていた。それは生もなく死もな
く、ただ夢想に合掌していた。何のための合掌であろうか。鉄舟の病気平癒を祈った合掌
が、今は空しい。死んでしまっては、もはや祈るべきものはない。長八はじっと石の地蔵
に眼を凝らしていた。
鉄舟の葬儀はさすがに盛大であった。朝野の名士や多数の知人、門弟が参集した。それ
は故人の多彩な生涯を物語るかのようであった。が、垣の外に庶民が群れ囲んで、故人を
かなしんでいる姿は余り目立たなかった。その人群れ中に多くの乞食がまじっていたのも、
多くの人々は気付かなかったであろう。故人のいわゆる陰徳であろうか。長八はその状景
に涙を浮かべていた。
長八は葬儀をすませて、八名川町に帰り着くと、ぐったりと疲れ果てていた。何をする
気力もなく、布団の上に横たわった。が、翌日長八は朝早く眼覚めた。直ぐに仕事場に入
った。彼はそれから数日仕事の没頭した。ものにつかれたように、鉄舟像の製作をしてい
たのである。
鉄舟が死んだ七月には、磐梯山が噴火し、会津富士と言われた麗容が一時に爆発崩壊し
て姿を変えてしまった。
鉄舟の死後、鉄舟像をつくって、一つは全生庵に、一つは自家の仏壇に納めたが、その
製作が終わると、長八はがっくりとしたように身心に衰えが感じられた。この頃、人に依
頼されてつくった作品が今日残っている。春城院禅鼎和尚像を始めとする七点である。が、
これらの作品に共通して見られるのは、かっての精彩や力感が弱まっていることで、彼の
生活に一転機が来たように思われる。
明けて明治二十二年、長八は七十五歳となる。が、この新春には、長い虚脱の季節を抜
け出たように、六曲半双の屏風に大作の画筆をふるっている。が、この作品は南画風で、
淡墨の一見白描と見られるもので、やはり精彩を欠いている。画面には一面に微光が柔ら
かく寂かに漂っていて、何か長八のこの頃の心境を示しているようでもある。死への道程
を暗示するかのように、白道が曲折して遠く遙かに続いている。白道を取り囲む山も草木
も、寂然として微動だもしない。波も躍っていない。一切が息をひそめている。
このような絵は、かって一度も描かれていない。その描法は、しいて言えば田能村竹田
に近いが、竹田のような艶やかさはない。私はこんなことを思う。鉄舟の死に遭遇した長
八が、その愁傷な底から、静かに自己の運命を見詰め、想念を整理し、死への覚悟を決め
たのではないか。この絵はそういうものを表現しているような気がする。それは長八の現
実的な諦悟であったのかも知れない。
屏風絵が出来上がると、菊地幸太郎の家に運ばせた。何のために幸太郎の家に運ばせた
のか。その理由はわからない。ひそかに死場所の一つとして幸太郎の家を考え、おのれの
遺骸を囲む屏風と決めていたのかも知れない。
静かに冬が過ぎ、やがて三月となると、長八は旅仕度をさせて、またも故郷に向かう。
先年、最後の訪問をし、思い残すことのないようにとそのつもりで暮らしたのだが、後で
考えついた用件があったのである。それは長八自身のことであった。
長八は郷里に帰りつくと、まず養女のおしゅんに死後のことを懇々と話している。口だ
けでは心配で、おしゅんに箇条書きの紙を渡した。その箇条はおよそ次のようなことであ
った。遺骨は播磨屋の菩提寺である浅草の正定寺に葬るが、是非淨感寺に分骨してほしい
ということ、葬儀は東京でやるが、分骨の時にも郷里で供養してほしいということ。墓は
予め買ってあった場所に建てること。そして、それらに必要な一切の費用の金と、墓石に
刻む文字『釈天祐居士墓』と自分で書いた紙を渡した。
翌日淨感寺へ行って、若い住職に改めて死後のことを頼み、墓所を定めた。
帰郷したのは、この用件のためだったのである。用件をすますと、もう思い残すことは
なかった。肩の荷をおろしたように、長八はのんびりとわが家の古びた縁先で暖かい春の
日射しを楽しんでいた。眼の前に牛原山が大きくふさがっていた。子供の頃が思い出され
た。
いつの間に出て行ったのか、おしゅんが風呂敷包みを抱えて田圃道を帰って来た。
「どこへ行ってたんだい」
と長八はおしゅんの近づくのに言った。
「水車小屋へ。おじいさんの好きな小麦餅を作ろうと思って」
「そうか」
長八は微笑した。
「小麦餅か」
とつぶやいた。
「食べたいな」
「今直ぐ作りますから、それまで散歩でもしなすったら。浜の方は大分家が建ちましたよ」
おしゅんが勝手場から言った。
「そうか、そうしようか」
と長八はゆっくり腰を上げた。そして、縁先の藁草履をつっかけて外に出た。
大橋を渡って中瀬に出る。ドブ川を通って向浜に来る。ここらはすっかり家が立ち並ん
でいる。真っ直ぐに行くと松原に出る。その松原沿いに新しい一本の道が出来、江奈浜に
続いている。昔砂畑ばかりだった所に、今は点々と家が立っている。去年来た時にはまだ
ほとんど家はなかったのに、たった一年の間に、こんなに変わったのかと、長八は驚いた。
歩いて行くと、一軒の新築中の家があって、大工や左官が働いていた。思わず、そこに
立って見上げていると、
「師匠…」
と驚いた声で中から出て来た男がある。
「三右衛門か」
と長八も驚いた。東京で修業していた弟子の山本三右衛門である。今では郷里に帰って、
父の後を継いでいる。
「お帰りになっていたんですか」
「うん、昨日。内緒で来たんだから、誰にも言うなよ」
「へえ」
「忙しそうだな」
「はあ、おかげで」
「ここは誰の家だ?」
「粂さんの家です。大工の粂五郎さんの」
「そうか、粂さんの家か」
長八はそう言って改めて新しい家を仰いだ。
「粂さん、たっしゃかい」
「へえ、うらで仕事をしています」
「会いたいな」
「呼んで来ましょう」
「いや、おれが行く」
長八はすたすた軒下を潜って行った。
粂五郎は裏庭で台所戸棚を組み立てていた。
「おい、粂さん」
と長八が呼んだ。ひょいと顔を向けた粂五郎は、直ぐに懐かしそうな笑顔になって、
「長さん」
と言った。
「たっしゃでいいな」
「お前さんも」
「いい家が出来るじゃあないか」
「何の、やっとこさ家らしいものをね」
「中を見せておくれ」
「さあどうぞ。散らかっているぜ」
長八は木片の散っている床に上がった。座敷と思われる一室で、職人が欄間を塗ってい
た。長八はそれを見上げていたが、急に、
「粂さん」
と呼んだ。粂五郎は後に居た。
「ここをおれに塗らしてくれ」
粂五郎はびっくりして、
「お前さんが?」
と聞き返した。
「いいだろう?」
長八が笑った。
「そりゃあ構わないが」
粂五郎は恐縮していた。
「幼な馴染みの友だちの家だ。このままじゃあ帰れない。やるそ、いいな」
長八は、着ているどてらの帯をしめ直した。
「三右衛門、たすきはないか」
と、きょろきょろ見廻して、遠くに縄切れを見た。
「三右衛門、あれがいい」
三右衛門が急いで持って来た縄を、長八は手早くたすきにした。
「土は?」
長八は鏝をとった。土が運ばれた。身軽に踏台に乗った。
今塗ったばかりの荒土の上に、たっぷりと赤色の練り土をつけて塗り始めた。大鏝で土
を引くように動かすと、びっしりときめこまかい壁になって行った。一面塗り終わると、
「粂さん、お祝いに絵を描くぞ」
と言ったが、振り向きもせず、細鏝をとって何やら縦横に機敏に動かし、踏台の上で眺
め渡して、
「よし」
と言うと、次の欄間に移った。
四面の欄間には、鏝描きの瀟湘八景が見事に描かれた。長八は描き終わると煙草に火を
つけてゆっくりと吸った。ぐるりと山水を見廻した。一つは横線を漂茫とした大湖の水を
描いていた。起伏する山々は微妙にひだを浮かべて、おのずから遠近を示し、樹林の描線
は鏝の簡潔なタッチを交錯させて、さわやかな風を響かせているようであった。一同はた
だ茫然として、その欄間を仰いでいた。
「じゃ、粂さん、たっしゃでな」
長八は言い捨てて、もうすたすたと草履の音を遠のかせていた。
これが郷里における最後の作品となったことを、長八も三右衛門もその時感じていたこ
とであろうか。
⑥
その翌日、長八は風のように故郷を去った。
東京に帰ると、急に気抜けがしたように元気がなくなり、そのまま床についてしまった。
最後の準備も出来て安堵したのであろうか。持病の喘息ではなく、ただ気力がなく食欲も
薄かった。寝たり起きたりの気ままな生活が続くうち、いつしか四月が過ぎ、五月が過ぎ
ていた。
六月始めのある日、故郷の千葉に帰って独立した石井巳之助が見舞いに来た。長八はい
つものように隠居所に寝ていた。挨拶がすむと、
「師匠、一つ頼みがあります」
と、風呂敷包みを開いた。
「何だ、改まって」
長八は床の上に起きて座っていたが、見るともなしに風呂敷を見ていた。
「何だ、位牌じゃないか」
と、長八は驚いて言った。
「へえ」
巳之助は膝を固くしていた。
「誰の位牌だ」
長八は何の想像もつかない。巳之助は、ちょっと間を置いて、悪びれた表情で、
「師匠の位牌です」
長八は意表を突かれたように、
「おれの位牌だって?」
と聞き返した。
「はい。精魂こめて漆喰の位牌をつくりました。見て下さい」
巳之助が捧げるように位牌を差し出した。長八はそれを手にした。頭の中を悲しい影が
よぎった。巳之助はもうおれの死期の近いのを感じているのか。長八はそんなことを思っ
た。
位牌はずっしりと重かった。表も裏もていねいに金箔を張りつめてあった。長八は不思
議なものを見るように、じっと位牌を見ていた。
「これがおれの位牌か」
とつぶやいた。
「すみません」
巳之助はうつむいた。
「立派なものだ」
長八は改めて眺めた。
「師匠、これに師匠の絵姿を描いて下さい」
巳之助の頼みというのはそのことかと、長八は感じた。と、急に弟子の巳之助の心根が
察しられて、瞼のうるむ思いがした。
「よし。描こう。巳之助、鏝と土を用意しろ」
土は巳之助が持って来ていた。鏝を持って来ると、長八は布団の上に膝をそろえた。位
牌を片手に、土が塗られた。鏝がこまかく動いた。そこに、上半身の自画像が出来上がっ
た。
「ありがとうございました」
巳之助は位牌を押しいただいた。
「時々は線香をあげてくれよ」
長八は静かに言った。巳之助はその言葉に、胸の迫る思いだった。
七月、東海道が開通した。五、六年来低迷していた景気も、ようやく持ち直して来た。
東京も首都らしく活気を見せて来た。長八は、そんな世間の様子を家人や見舞客から聞く
だけで、隠居所にこもり切っていた。
梅雨が続いてうっとうしかった。おはなも老境に入って、この頃しきりに神経痛に悩ま
されて、長八の世話どころでなく、仕方なく母屋に移った。その代わりに竹次郎の女房の
おふくが、隠居所と母屋を往き来していた。
梅雨が明けた頃、幸太郎が訪ねて来た。折よくおはなもそこに居た。長八は寝床の上で
おはなの持って来た薬湯を飲んでいた。半分飲んで盆にもどした。
「飲んでしまいなさいよ」
幸太郎が言うと、長八は黙ったまた茶碗をつかんだ。そんな長八を、幸太郎もおはなも
痛々しく見ていた。
おふくが茶を運んで来た。
「おじいさん、幸太郎さんから鮎をいただきました」
と報告した。
「そうか、ありがとう」
と幸太郎に言った。
「煮つけましょうか、それとも塩焼きにしましょうか」
「塩焼きがいいな」
長八が言った。
「じゃ、そうしましょう」
と言って、おふくが立ち上がったところを、幸太郎が、
「おふくさん、ちょっと話がある」
と幸太郎が引き止めた。
「おばあさんも一しょに話を聞いておくれ。実はおじいさんのことだがねえ」
と切り出した。
「赤坂へ寄越してくれないかい。竹さんには私から話す」
と言われて、おふくとおはなは顔を見合わせた。どっちも黙っていた。
「幸太郎さん、そんなことを言ったって」
とおふくが口を入れた。長八の顔を見た。
「急に、どうしてそんなことを」
とおはなが継ぎ足した。幸太郎は、それを待っていたように言い出した。
「おじいさんの健康のためだよ。ここは湿気があってよくない。夏場は特に風通しもよく
ない。体によくないよ」
そう言われればその通りであった。長八もおはなもおふくも黙っていた。
「それに」
と、今度は長八の方へ言った。
「おふくさんが大変ですよ。子供の世話から、職人たちの世話から、二人の世話ですから
ね」
長八は黙ってうなずいた。幸太郎の言う通りだと思った。
「あたしもね、せめておじいさんの世話ぐらい出来るといいんだけれど」
と、おはなが言いわけのようにつぶやいた。
「あたしは何でもないですよ」
おふくが言った。
「そうはいかないよ。おじいさんにしてみても、ここでは直る病気も直らない」
幸太郎が強い調子で言った。おふくもこれには抗弁出来なかった。が、幸太郎に迷惑を
掛けてはと思っていた。
「でも、幸太郎さんとこが」
とおふくが言った。
「それは心配ない。うちでは、子供ももう世話がかからなくなっている。第一職人など居
ないしね」
と言って、幸太郎は今度は長八の方に、
「どうです、おじいさんは」
と聞いた。長八は考え続けていた。どっちにしても厄介を掛けるのは自分である。同じ
ことなら、楽な方へ行く方がいいかも知れない。そう思った。
「そうするか」
長八はあっさり言って、おはなとおふくを見た。
「折角、幸太郎さんがそう言うのだから」
すると、二人は、
「おじいさんがその気なら」
と、あえて逆らう気持ちはなかった。
「よし、これで決まった」
幸太郎が安心したように言った。
二、三日して、天気のよい日に、長八は幸太郎の迎えの車に乗った。赤坂の家では、暑
い夏でも風が通ってしのぎよかった。しかし、長八は寝たり起きたりのいつものような日
々であった。
九月半ばになって、秋風が立ち始めると、急に八名川町へ帰ると言い出して、長八は一
人で帰ってしまった。体調がいくらかよくなっていた。そうなると、あれこれの仕事を思
い、八名川町の仕事場が恋しくなったのであろう。
が、体調がよくなったのは一時的であった。八名川町に帰って、四、五日仕事をしてい
るうちに、また急に喘息に襲われた。家人はあわてて手当をし薬湯を飲ませた。発作は毎
日三、四回起こった。発作がおさまると、案外元気で、人々を相手に談笑していたが、発
作が起きると、せわしく咳き込んで、眼も当てられないほどの苦しみだった。いつか九月
も末になって、長八は眼に見えて痩せていった。
九月二十七日、十五夜の月が出ていた。静かに月の光を見ていると、そこへ幸太郎がや
って来た。葡萄の篭を提げていた。
「甲州へ行って来ました」
幸太郎は枕元に座った。材木の買い付けに行ったのである。竹次郎もおはなも居合わせ
ていた。
「おばあさん、直ぐあげるといい」
幸太郎は篭をおはなに渡した。おはなは篭を提げて出て行った。
「今夜はいい月ですねえ」
と幸太郎が言った。
「うん」
長八はそう言って明け放した外を見た。縁先に小机を置いて、薄や野菊が揺れていた。
おはながとって来たのであろう。
「おじいさん、起きますか」
竹次郎が長八の顔をのぞいた。
「いいよ」
と長八が枕に載せた頭を横にした。
「幸太郎」
長八が言った。気のせいか力のない声だった。
「何ですえ」
幸太郎が長八の顔をのぞいた。くぼんだ眼蓋に影を落としたまま眼を閉じていた。
「眠いんですか」
「いや」
と長八は微笑したようであった。
「今、松崎の十五夜を思い出していた」
「懐かしいでしょう」
「うん」
長八が頭を動かした。
「裏の牛原山に登ってな、山梨の枝を切って、帰りに野菊を一ぱい摘んで」
と、思い出しながら言った。
「子供の頃ですね」
竹次郎が言った。
長八は夢でも見ているように見えた。
「あっしらもよく上野へ行きました」
と幸太郎が言った。
「山梨と野菊を両手に一ぱい抱えて帰って来ると、おっ母あは団子の粉を引いていた。ゴ
ロ、ゴロってな」
臼の音を聞いているかのように、しばらく黙った。長八は口を薄くあけていた。
「台所の流しに花をほうり出して、お母あのそばで、粉を引く音を聞いていた」
そこでまた途切れた。竹次郎も幸太郎も黙っていた。何かしみじみとしたものを感じて
いた。と、思い出したように、長八がまたつぶやくように話し出した。
「円い大きな十五夜さんが円通寺の山から出て来る。出た出たと言って庭に下りて、手を
たたいて喜んだ」
長八の声がだんだん低くなっていた。
しばらく黙ったままで、やがて、ぽつりと言った。
「つまらねえな」
そして、寝息を立てて眠ったようであった。竹次郎と幸太郎はその寝顔をじっと見詰め
第9章 終わり
動画