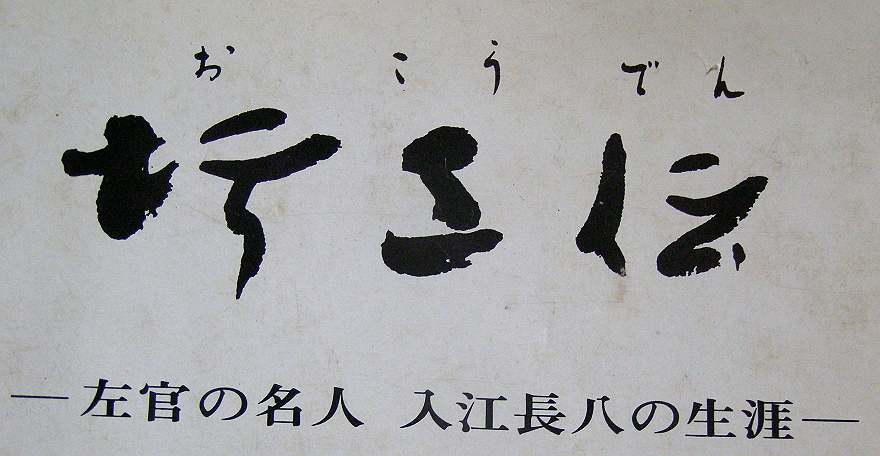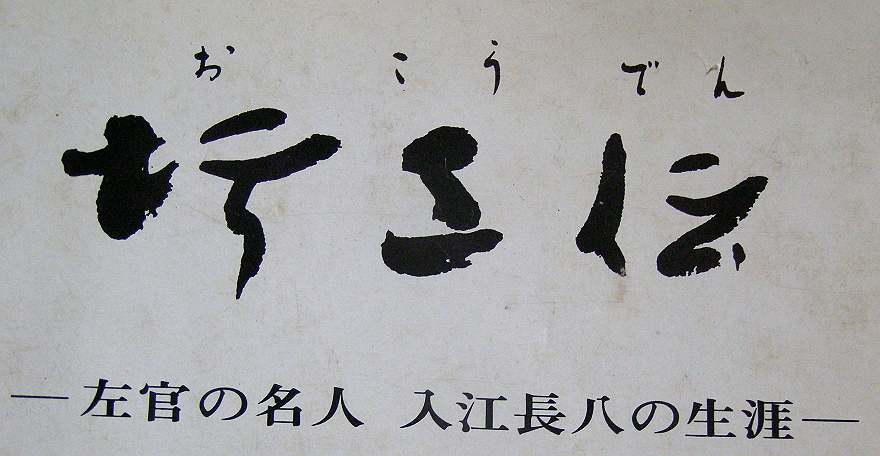改訂「お工伝」編集者の言葉 松本晴雄
(注=「お工」の「お」は、土偏に「汚」の旁を書く)。
私は、「ふるさとガイド松崎」の会員で、ボランティアガイドをしている。ある時、淨
感寺(長八記念館)を案内すると、お客様から「長八の一代記はありませんか」と聞かれ
た。松崎町最大の観光資源である「入江長八」の伝記のないのが、残念でならなかった。
実は、こよなく入江長八を愛し、松崎を愛した松崎人が著したものがあるのである。それ
も、私が深く関わった本である。昭和五十年四月発刊だが、今は絶版状態になっている。
私とその本の関わりとは、松崎中学校時代の恩師・須田昌平校長の著作で、誰からとも
なく「先生は長八の伝記を書き上げたが、出版出来ずに困っておられる」と耳にした。
今日あるは先生のお陰と思っている私は、極端に言えば命を張ってでも出版に漕ぎつけ
たいと決心した。ペイをするまでの販売を誓約し、勤務していた文寿堂印刷所社長肥田一
弥氏に頼み込んだ。私は百册を買い取り、各機関施設の贈呈した。
私は闇雲に手紙を書き、松崎中学校OBなどの協力を得た。同OBで左官業の関賢助氏
の尽力で、全日本左官業連合会へ繋がりがつき、瞬く間にペイ出来たのである。
しかし、初版「お工伝」発刊数年後、私も「伊豆の一仙」なる小冊子を、伊豆を愛する
会から発行していただいた。もちろん須田先生にも差し上げた。ほどなくして先生に出会
うと「小沢一仙の生年を間違えて設定したよ」と、頭を掻かれた。
これが再版されなかった最大な要因と思う。「お工伝」は、淨感寺塾で学んだ長八と同
年の、土屋三余、高柳天城、小沢一仙が絡み合って進行する物語である。本書の一仙は、
彼等より十五歳年下であったのである。ちょっとした勘違いが、立派な物語に傷をつける
ことは往々あるものなのである。そんなことから本書が消え去るのは惜しい。そこで一仙
の表現個所を、私の文責において加筆をお許し願うことにした。
須田昌平先生は、教育者としても歌人としても著名な人物である。これほどまで丹念に
取材し、研究し、心を込めた長八伝記はないと確信する。
希望者が多ければ、文寿堂印刷所からの再版も考えたい。
須 田 昌 平著
序章『お 工 伝』記
|
入江長八という人間を愛するゆえに、入江
長八を愛する人々に、この『お工伝』を捧
げる。入江長八の正しい人間像、心の旅路
を追い続け、探り求めて来た私の心の記録
として。
|
①
この長編の主人公入江長八は、伊豆国松崎村(現、静岡県賀茂郡松崎町松崎) の出身
で、幕末から明治にかけて、左官の名人として知られた人物である。だが、長八自身は、
その作品には、左官という世間的な呼称を用いず、『お工』(オコウ)とか『お者』(オシ
ャ)という特殊な語をしばしば使っている。……『お』とは鏝のことであるから、お工、
お者は、鏝を用いる工人というような意味である。彼は左官を業としながら、単なる壁塗
りの常識を越えて、漆喰土をさまざまに工夫し、鏝を使って装飾的な壁絵を描き、更に立
体彫塑や浮彫にまで技術を開拓し、彼独特の芸術を創造し完成させた。いわば、左官の技
術を芸術にまで引き上げる努力をし、それに成功した一代の名匠と言うべき人物である。
彼が自らを称して、あえてお工とかお者とか言ったのは、こういう彼の自負があったから
であろう。この長編の題名を『お工伝』としたのも、長八のこの心を尊んでのことである。
彼はその生涯に数多くの鏝絵作品を制作し、名人名工の名を残した。まさしく、その作
品は彼独特の発想であり、創造であり、文字通り古今独歩の人と言ってよい。が、惜しい
ことに、その作品は材質が漆喰土で脆く(長八はその耐久性に工夫を凝らし、ある程度は
成功しては居るが)火災や地震などの災害で、今日では大部分が失われて、残存している
ものは、おそらく百点を欠きはしないかと推測される。地域的には東京が最も多かったの
だが、度々の火災で焼失したり、ことに関東大震災では、僅かに残っていた作品もほとん
ど消滅してしまった。今、彼の作品を見ることの出来るのは、彼の郷里松崎町と静岡県三
島市とに集中し、その他は個人所有の小品が各地に散在しているといった状態である。
もしこのままで過ぎて行くなら、この僅かに残された作品もいつか消滅してしまうであ
ろうし、それと共に、入江長八という名匠の名も、その苦心も、その芸術的実質も、すべ
て消え失せてしまうような気がしてならない。
「これでいいのか」
と、私は人々に問いただしたい。この思いは若年からのものだが、しかし、年を経るご
とに一層切実に感じられるようになり、今や私自身の悲願とさえ思われるようになった。
日本人は芸術を愛好する国民だと言われている。奈良、京都の古美術、建造物が遺され、
今も大切にされているのは、その証拠であろう。それは素晴らしいことである。この心を、
近世近代にも向けて、その文化を伝承し、保護し愛護して、この国や国民が一層素晴らし
いものであってほしいと、私はつくづく思うのである。こういうものは消滅してしまって
はもう取り返しがつかない。消滅しないうちに、早く適切な措置をすべきである。
明治になって、日本は西洋の刺激を受けて新しく開花した。芸術もまたそうであった。
それは新しい日本の国づくりに有意義なことで、必要なことであった。しかし、何もかも
西洋の風にしたがう愚はいけない。西洋のものは何でもよいもので、日本のものは何でも
いけないという風潮が明治にはあった。ことに芸術において、今日もそのそしりがないわ
けではない。
日本の芸術は、見ようによっては、西洋のそれとは異質である。異質なものを、西洋の
尺度で評価すれば劣るのは当然である。むしろ同等に見るとか、あるいはその調和を考え
るとかすることが、今日の日本のなすべきことではなかろうか。
こういう考え方に立って、私は入江長八とその作品を、今日の時点において再考しても
らいたいと思うのである。長八は素朴ながらも、そのような志を持って、独特な芸術を創
造した人なのである。
②
入江長八の鏝の芸術は前人未踏のもので、その意味で異色であったから、今までにも数
々の伝記や研究や調査がなされ、それぞれ世に発表されている。その中で、最も優れた労
作は、結城素明氏の『伊豆長八』と、白鳥金次郎氏の『名工入江長八』である。両者とも
伝記的記述であるが、それぞれに特色を持っていて、またそれぞれに欠点をも持っている。
結城氏の労作は、優れた日本画家としての氏の鑑賞眼が、よく長八の作品を評価してい
る点や、晩年の一時期、丹念に実地踏査をして、伝聞を採集し、資料を求め、それを刻銘
に記述していて、その点で最良の書というべきであろう。白鳥氏の労作は、結城氏の研究
の上に、新しい資料を加えたもので、特に静岡市関係の事蹟を発掘したことや、氏が左官
業者であるらしく、長八の制作技術について解明していることなど、その特色と言えよう。
しかし、この二つの貴重な労作にも、欠点や誤謬があった。名人長八を語るに当たって、
伝聞や逸話の真偽を確かめることなく、あれもこれもと取り上げて、かえって伝記を混乱
させている点。長八の偉大さを強調して、その業績や美談が並べられ、人間としての掘り
下げがほとんど見られない点。この二つの欠点は、それなりに止むを得ない事由が考えら
れる。従来の伝記がほとんどそうであったように、形式的、表面的に偉大さを記述(ある
いは誇張)するのが伝記作者の常識であったから、両者も、その常識に従ったのであろう。
また、一人は画家、一人は左官という、それぞれの専門的な立場で記述しているので、
その意味では、部分的な特長は認められるが、それはまた欠点ともなっている。
もう一つ重要な欠点がある。それは二人とも入江長八を既成の名人名工としてだけしか
見ていないことである。そのための伝聞や調査にとどまり、長八の人間性、人間的成長の
過程、鏝絵創造の動機、その経過などにはほとんど答えてくれていない。冷酷に言えば、
生きた血の通った長八ではなく、偶像としての長八しか表現されていないのである。
私はこういう問題点を解明して、少なくとも入江長八の人間らしい姿を描きたいと思う
ようになった。
幸いにも、私は入江長八と郷里を同じくしている。従って、幼時からその名を聞き馴れ
ていた。近親や隣人から長八の話を聞くことも多かった。長八の弟子で、日常起居を共に
していた二人の老人(山本三右衛門、入江又兵衛)が、私の友人の祖父で、しかも家が近
かったから、随分昔話をしてもらったし、長八と幼な友達であった松本某は私の縁戚であ
ったし、長八と関係深い依田家や近藤家、あるいは淨感寺、淨泉寺は少年の頃よく出入り
していた所であったし、そういう環境の中で、私はいつとはなしに、長八という人をだん
だん知るようになっていた。
そして、やがて教師となり、郷土研究の流行期にたまたま郷里に勤めていたために、長
八の事蹟を採取し始め、長八に対する親愛と尊敬の心を持つようになった。伯父が持って
いた『伊豆長八』をもらい受けて、当時健在であった入江又兵衛老に、いろいろ疑義をた
だしたりしたのは、この時期であった。
後、私は静岡に住み、また三島に住むようになった。偶然なことながら、それは私の長
八研究に、いろいろな資料と研究の糸口を与えられ、こうして私の長八研究は、断続的に
三十余年を経過した。そして、それは徐々に長八の人間像に一つの形をつくるようになっ
ていた。
③
終戦後、再び郷里に帰った私は、ここで入江長八伝を書こうとしたが、公私とも多忙の
ために出来なかった。が、その頃、私はこんなことを考えていた。
………私がもし入江長八伝に手をつけなかったら、一体誰がやるだろうか。郷里には熱
心な長八崇拝者はある。しかし、この人々には長八伝に関心はないだろう。仮に誰かが手
をつけるとして、私が長い間採集したもの(今となっては採集不可能であろう)はどうな
る? 私が考え続けて来た、長八の人間像はどうなる? ………もし私が長八伝に手をつ
けなかったら、それらが全部、永久に消えてしまうだろう。それは私にとって忍びがたい
ことだ。何とかして長八伝を私の手で書こう。
この思いは切実であったが、私の郷里の生活はそれどころでなかった。ついに、何のな
すこともなく、郷里の七年間は過ぎて、再び私は三島に転勤した。
三島の九年間は、郷里の七年間よりももっとあわただしく、長八研究どころではなかっ
た。しかし、昭和三十八年三月、めでたく退職することになって、私の多年の宿望を果た
す時がようやく来た。
私は待ちかねたように、資料の整理を始めた。ノート一冊を年表にして、採集した資料
をそれに当てはめて行った。不備な個所があれば、それを調査した。そんなことをしてい
るうちに、早くも二年が経過していた。
いよいよ長八伝の筆をとる段になって、新しい疑問に突き当たり、不備な点が見つかっ
た。それを確かめるために、また別な勉強をしたり、専門家の意見を聞いたり、もう一度
川越に行ったりした。そんなことで、原稿書きは思うようにはかどらなかった。不備な点
を究明しようとしても、時はすでに遠く隔たり、助言をしてくれる人もなく、仕方なく自
分だけの考えで解決するしかなかったが、それも遠く霞の彼方を望見するようなもどかし
さであった。何の実証も出来ないまま、仕方なく仮設を立て、推理して進めざるを得ない
こともあった。推理するとしても、小説作家のように自由放胆にふるまうことは許されな
い。事実の前後の脈絡をさぐってまとめなければならない。私の真意にそむくようなこと
だが、そうしなければ長八の実人間像が出来ないのだった。
こうして、私のこの労作は、小説のようで小説でなく、伝記のようで伝記らしくないも
のになってしまった。
ちなみに、書き上げてしまったのは、昭和四十四年十二月。遅筆四年を要した。
④
『鏝絵』という用語は、長八が造ったもののようである。世間では『壁絵』というが、
鏝絵と言ったのは、壁面に絵具を塗ったような平面的なものに見られるのをきらったので
あろう。事実、長八は更に立体彫塑や浮彫にまで技法を進めているから、『鏝絵』という
用語さえ適当ではない。ほんとうには『鏝芸』と言うべきなのかも知れない。が、とにか
く以後の記述にも、この『鏝絵』という特殊な語を使うことを、ここに断って置く。
長八は鏝を命のように大切にした。後に記述するように、彼が工夫した『柳葉』と名づ
けた鏝などは、常時白布に巻いて懐中にしていたというほどである。確かに長八にとって
は鏝が唯一絶対の道具であった。鏝で土を練り色を混ぜ、鏝で塗り描き、鏝で形をつくり
物を整え、鏝で額装して立体化した。まさに鏝の芸というべきものである。
鏝は長八の場合、筆の代用ではなく、同様に、壁や板は紙の代用ではない。絵具や墨は
土そのもので、徹底的に土の造形であり、そのための鏝である。そういう彼独特の芸術を
慕って、多くの弟子が出来たが、ほとんど、ついに長八の芸術を継承し得るような作家は
現われなかった。それほど、長八の芸は深く高かったと言えよう。不世出の天才であった
のかも知れない。
しかも、時代は国情混沌の幕末から文明開化に激動した明治前期という大変な時期で、
その渦の流れの中で、俗情に流されず、時局にまみれず、一人の力をこの事一つにこめて、
ついに独歩の道を拓いたのである。確かに天才であったのかも知れない。
が、同時に、長八自身の努力精進の並々でなかったことをも想像されるであろう。彼は
貧農の家に生まれ育ち、それゆえに当然のことながら苦難の人生をたどった。さまざまな
逆流に揉まれ、運命にさいなまれながら、彼はよく生き抜き、乗り切って行った。一生を
左右するような危機も何度かあった。人生を絶望した時もあった。しかし、長八はそれを
乗り越えて行った。彼の一生を考えると、努力精進などという言葉さえ生ぬるいほどに感
じる。
このような人間形成の道程は、今日のわれわれに、何か大切なものを教えてくれるよう
である。私が入江長八伝を書こうと思い、書かねばならないと思い至った根本的な理由は
ここにある。
⑤
この一篇は、私なりに苦心して書き上げたのだが、八百枚に及ぶ原稿を通観してみると、
思うに任せぬこと、意に満たぬことが多く、残念でならない。しかし、入江長八という一
人の人間を、偶像としてではなく、生きた人間として捉え、その形成過程を、彼の芸術の
歩みとして説明しようとした私の意図は、ある程度実現できたと思い、このことによって、
入江長八とその芸術が、今後もっと大切に理解され、敬重されるよすがとなったらいいな
と思い、念願して、ここに世に問うのである。
序章 終わり
動画