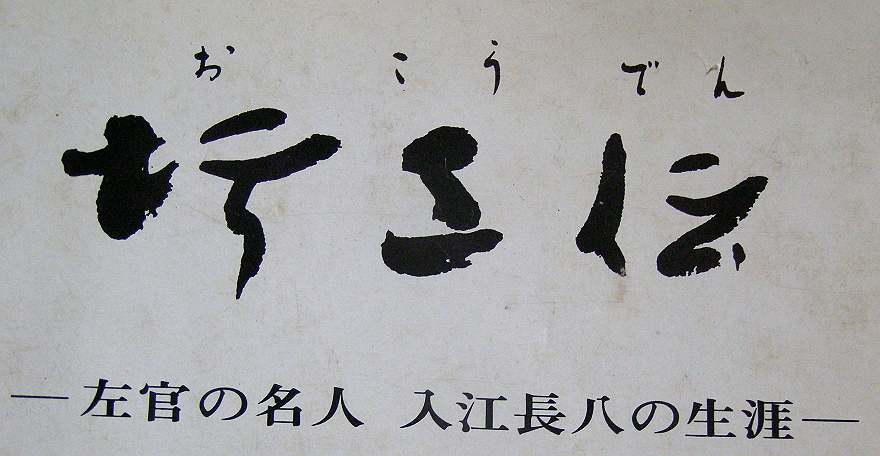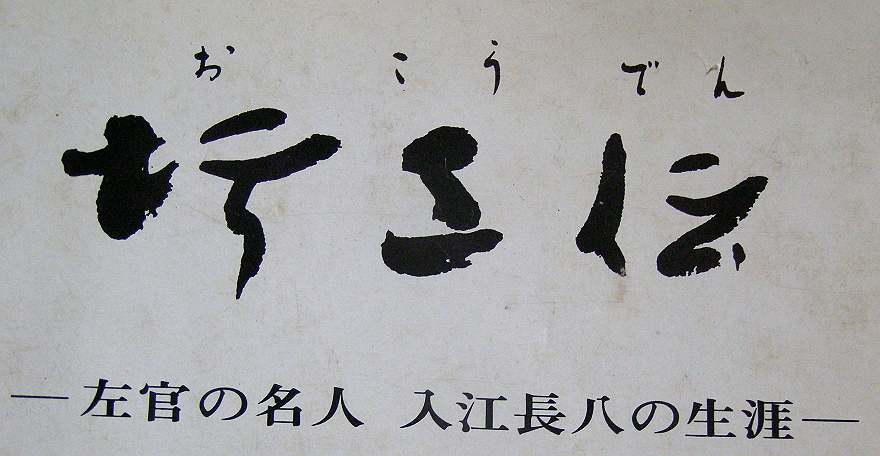須 田 昌 平著
第8章 愛 と 孤 独
|
長八にも老境が自覚された。身近の人間た
ちの葛藤が長八を孤独にさせた。親しい人
に作品を贈ったり、死後の事を考えたり、
そして彼は一層制作に力をそそぐ。
(六十五歳から六十九歳まで)
|
①
秋たけて、長八は次郎長から頼まれた山岡鉄舟像をようやくつくり上げた。高さ四寸の
座像で、伝説によれば、次郎長は死ぬまでこの像を肌から離さなかったという。
続いて、竜沢寺の星定禅師のために、漆喰塗りの杖をつくった。禅師の長寿を祈る気持
ちからだった。もちろん、頼まれたものではない。長八の報謝の心からのものである。
長八は竜沢寺の参篭以後めっきりと体力の衰えて来たことを感じ出していた。そして、
老齢を意識するようになった。そんな気持ちは、一方では自分の芸術にひたむきに没入し
ようという切迫した意欲ともなり、また一方では知己の人々への親愛を一層深めて行った。
鉄舟像をつくると、ていねいな手紙と一しょに清水へ送った。星定禅師の杖もていねいに
箱詰めにして送った。こんなことにも長八の気持ちがにじんでいるようであった。
しかし、彼の現実は逆に世俗的なわずらわしさをいつも抱えていた。清太郎のことは忘
れようとしても忘れられないことであった。おはなと竹次郎の対立は、時には陰湿に黴臭
く家の中に漂った。時には不気味な醜い炎を燃やした。長八が長い旅から帰った当座は、
二人ともなごやかに見えたが、それも一時であった。次第に、長八の前でも互いの意地を
張って口論することも度々になった。
そんな状況でこの年も終わり、明けて明治十二年となる。皇都となり東京となって、次
第に江戸風が減っていった。政治も経済も生活も風俗も、江戸から脱皮しようと急いでい
るようだった。町の建築もそれに応じて活発に改装され新築されるようになった。これら
の仕事は竹次郎が指揮していたが、それでも竹次郎の手に余ることもあり、長八も一しょ
に働かなければならない時もあった。
春と共に仕事は忙しくなっていた。長八もしばらくは本業の左官の仕事に明け暮れた。
が、五月に入ると、待ちかねていた竜沢寺の不動堂建立が始まって、急いで三島に出向く。
町の仕事は職人に肩代わりさせて、長八はひとまず竹次郎と兼吉を伴って出発した。仕事
が片付き次第、善吉が後から来ることなった。
竜沢寺では、もう不動堂は大方出来て、瓦も載せられていた。長八たちの壁仕事を待っ
ている状態だった。早速壁の仕事に掛かった。小さな堂だから、それほどの日数は掛から
ない。五日目、中橋の善吉が、芝の市五郎と連れ立って来て、終わり間近の壁を塗った。
すっかり塗り終って、僧たちも一しょに、不動尊像を移し、一同そろって供養をした。
供養の後、長八は弟子たちに一つの提案をした。
「この不動堂の完成を記念して、ここに奉納額を掲げたいと思う。皆一枚ずつ奉納してく
れ」
と言うのだった。弟子たちは突然のことで、一瞬顔を緊張させたが、程なく中橋善吉が、
「やろうじゃないか。親方の不動様にあやかるように、一世一代の腕を見せようじゃない
か」
と言い出した。
「やろうよ。おいらにもいい記念になるぜ」
芝の市五郎も賛成した。
「竹次郎と兼吉は」
「やりましょう」
と二人は一しょに答えた。
「それでは、日を限ろう。今日から五日、精進潔斎して、この堂にこもって、精一ぱいの
ものをつくろう。他からの助言や手助けは一切しないこと」
と長八は言った。
長八をまじえた五人は、てんでに想を練り、下絵を描き、思い思いに土をこね、鏝を使
った。
この時の作品は今もそのまま残っている。竹次郎が『風神雷神』、中橋善吉が『仁王相
撲の図』などである。長八はこの時『橋弁慶の図』『臼に鶏』『常盤御前』の三点を描き
上げ、それでも弟子たちがまだ描き上げないのを見て、杉板をとって直接『群鳥の図』を
描き加えた。
不動堂の掲額をすますと、弟子たちは直ぐに東京に帰らせ、長八だけ居残って、星定禅
師像の制作に掛かる。これは禅師をモデルにして写実したもので、禅師の温和な風格の中
に徹底的な求道の厳しさ、高邁な気宇などの感じられる傑作である。禅師は本来病弱な肉
体であったといわれるが、そこの蔵された仏道献身の崇高な精神がほうふつと感じられ、
単なる形の写実でないことが受け取れる。
『お者入江長八あり。また師の徳化を慕い、寄留ほとんど三寒暑、かつて師の寿像を造り、
竜沢寺に安置す』(竜沢寺星定禅師和尚伝)
とあるのがそれである。禅師は明治十年紫衣を賜っていたから、この像も紫衣姿である。
あるいは祝賀の気持ちからの制作かも知れない。
六月、この制作が終わると、長八は山をくだった。東京へ帰ると、清水の次郎長が死ん
だという知らせが山岡鉄舟から届いていた。
「次郎長が死んだ」
と、長八は嘆息した。意外だった。それだけに、しきりに人の命がさびしく思われた。
長八自身、いつ終点が来るかわからなかった。長い道程ではないことは常識的にわかって
いた。が、どれだけの道程なのかわからない。もう、少ししかないような気もする。それ
とは逆に、やりたいことが山ほどあるように思える。そのいくつを、これからの短い人生
になし得るか。それもわからない。
一切を捨てて、この一筋に生きたいと思う。それは竜沢寺の参篭の中で得た一つの悟り
のはずであった。しかし、その一切を捨て切れないでいる。凡愚というべきであろう。人
間の自愛の哀しみでもあろう。
次郎長の死をいたみ悲しむ心は、おのれの心に跳ね返っていた。長八は、次郎長のため
というより、自分自身のために仏壇に念誦しているのを感じた。
が、いつまでも悲しんではいられなかった。竹次郎から、信濃伝(しなでん}の大工事
が知らされたのである。
信濃伝というのは、亀戸五の橋にある材木問屋で、当主を丸山伝右エ門といい、一代に
して巨富を築いたという傑物であった。時の北海道開拓使長官黒田清隆はその人の女婿で
ある。たまたまアメリカ大統領グラント将軍が日本を訪問するということで、政府は準備
に忙しかった。その予定の中に、牧羊場視察があり、その帰途休息所をほしいということ
で、信濃伝がその場所に選ばれた。当時の外務卿は井上馨で、黒田とも親しかったので、
選ばれたのだろう。信濃伝としては大変な栄誉である。そこで大急ぎに休息用の建物を新
築することになったのである。
長八が信濃伝に行くと、建築は大方出来上がっていて、長八の仕事の壁だけが残されて
いた。仕事は急がれていた。グラント将軍を迎える日が八月二十一日で、それに合わせて、
落成祝いを七月二十六日に決めてあった。すると、長八は一箇月ほどで仕上げなければな
らないことになる。すでに梅雨期に入っているので仕事はかなり長びくと見なければなら
ない。夜を日についでやるようなことになるかも知れなかった。
信濃伝の敷地は広大なもので、千葉街道口から河岸に沿って亀戸五の橋に至る一町四方
といわれ、建物だけでも四百坪というから大邸宅と言える。後に没落してその一部が今戸
に移され今戸御殿と呼ばれ、浅草へ移築して花屋敷となったが、これを考えれば豪勢さも
想像されよう。
長八はこの時どんな作品を残したかは、ただ今戸御殿や花屋敷で見た人の話だけが残っ
ていて、外に知る由もない。
今戸御殿については、
『茶室四畳半の壁三方に、蘭竹梅菊の四君子を浮彫になしたる、是ぞ伊豆の長八と呼ぶ左
官が苦心の暁鏝にて絵画を現わす術を発明したるその事績なりと伝えられ、座敷七畳半の
格天井にも菓物の浮彫り、十畳に二畳の床を有する一室の格天井には同じく竜の雲を呼ぶ。
これら絵画の巧妙なる、一片の鏝先細工とは嘆称の外なし』(明治四十年『毎日電報』所
掲)とある。
また花屋敷のことについては、
『花屋敷四階の下に文人堂という小座敷があって、そこに長八の作品があったことを知っ
ている。脇座敷の書院の縁側の壁に、多摩川の鴎を描いてあって、その鴎は中指の先ほど
の大きさで、一つ一つに玉眼がはめ込んであった』(伊藤伊三郎氏談)とある。
恐らく移築の際、大きな壁は壊されたのであろう。上部の小さな壁だけにしか触れてい
ないのである。
明治十二年七月二十六日、予定通り盛大な落成祝いの宴が開かれ、三条実美、岩倉具視
などの政府の高官や、福地桜痴、渋沢栄一などの民間有名人、守田勘弥などの芸能人など、
天下一流の人々が参会したという。
信濃伝の工事をすますと、かぶと町の吉川邸、次いで尾州徳川侯邸、明治病院と仕事が
続いて、その年も忙しく暮れて行った。
②
ところが、年も押し詰まって、一騒動が起きた。養子の竹次郎と養母のおはなが職人た
ちへの年末手当のことで衝突したのである。竹次郎は一度別居したが、長八が三島の竜沢
寺に参篭するについて、八名川町にもどっていた。長八が居ないということで、二人とも
大事に留守して、事なく過ぎたのであった。が、今度の衝突は互いに今まで我慢していた
ことが爆発して、とうとう竹次郎の妻のおふくを連れて家を出てしまったのである。
もともと二人はうまく行っていなかった。おはなは金銭に執着が強く、職人たちからも
強欲ばばあと陰口をたたかれていた。たまたま年末で職人たちへの手当が遅く、その上意
外に少ないので、竹次郎が仕事の責任者の立場からおはなに忠告したのが騒動の発端だっ
た。竹次郎は、今年は特別の仕事もあり、忙しく働いてもらったのだからと割増しを頼ん
だのだが、おはなはにべもなく例年通りでいいと言い張った。物価も上がったからと言え
ば、それだから、こちらも物入りが多くやりくりが容易じゃあないと主張する。押し問答
をしたが互いに譲らず、とうとう竹次郎が職人たちの手前、家出をするということになっ
たのである。
長八が知らぬ間の出来事であった。朝になって、竹次郎が食事にも顔を出さないし、お
ふくも居ないので、
「竹次郎はどうした?」
とおはなに聞いて、やっと家出とわかった。おはなは、始めは、
「出て行きましたよ」
と無愛想に答え、
「どこへ?」
と聞けば、
「さあ」
と、とぼけていた。
「いつ?」
と聞くと、
「昨夜」
と答えるだけだった。その素振りから、おはながけんかの相手だとわかった。
長八はどういうわけか聞きたかったが、おはながこんな風では聞いても無駄だと思った。
「仕方のない奴らだ」
と、にがにがしくつぶやいた。争いのもとは金銭問題だろうとは、およそ見当がついて
いた。それだけに長八は口を入れるのを遠慮した。長八は、前にも触れたように金銭的に
は淡白で、今ではすべておはなに任せていた。家にどれぐらいの金があるのやら知らなか
った。竹次郎は大恩ある波江野亀次郎の子だから、長八は大事にしていた。生活の上でも、
他の職人のように厳しくしなかった。多少気の荒い性質だが、仕事には熱心だし、職人た
ちにもよく面倒を見て信頼されていたが、本来下町育ちで遊芸好きなところがあった。お
ふくとは長唄の稽古で知り合い、それで結局夫婦になった仲で、どちらかといえば、派手
好みな浪費家であった。そういうところが、養母のおはなと対称的で、丁度水と油みたい
なところがあった。
直ぐ正月だというのに、家庭内にこんなもめごとがあってはいけないと、長八は思うの
だった。といって、二人を前に説諭する気になれなかった。
大晦日の日、長八は兼吉に言いふくめて、竹次郎の居場所を探させた。兼吉は間もなく
常盤町に居ることを突き止めた。
長八は、直ぐ出掛けて行った。
「もどって来い。もう直ぐ正月だというのに、播磨屋がこんな無ざまな格好でどうする」
と長八は竹次郎をしかったが、
「へえ」
と竹次郎は生ま返事をするだけだった。そしておふくと顔を見合わせて、もじもじした。
やっと、
「八名川町へもどるのは勘弁して下さい」
と申しわけなさそうに頭を下げた。
竹次郎は長八には心服していた。家業の責任も感じていた。が、おはなのことになると
どうにもならなかった。
「わっしにも悪いところはありますが、帰ればまたいやな思いをしなければなりません。
どうか勘弁して下さい」
と言う。
「それほどに言うなら、しばらくお前の言う通りにしよう。だが、そのうち考え直して帰
って来るんだぞ」
長八はそう言って帰った。しかし、とうとう竹次郎は正月になっても帰らなかった。
明治十三年。長八、六十六歳。
正月五日、夜、長八は竹次郎夫婦を呼んだ。中橋善吉にも来てもらって、おはなと兼吉
を同席させて、これからの家のことについて、一同に意見を述べさせ、長八自身の考えを
伝えた。暮れ以来、心に掛かっていたことである。余命の短いことを思えば、死後のこと
が心配だったのである。
長八の意見は、まず第一に播磨屋のことである。竹次郎に継がせることにはしてあるが、
今まではただ名目だけのことだった。それを実質的にも竹次郎にやらせる。つまり、一切
の責任を竹次郎にまかせることにした。したがって、長八夫婦は播磨屋から離れて、入江
姓にもどし、後を兼吉が継ぐことにする。そして、長八夫婦は仕事場を増築してそこで暮
らす。兼吉は修業中であるから、竹次郎が面倒を見る。以上のように言い渡して、中橋善
吉に竹次郎の後見人として頼んだ。
これには、おはなとしては不満があり、竹次郎には不安があったが、善吉はさすがの苦
労人らしく、二人を説得して承知させた。
長八には、別に郷里のことも考えないわけに行かなかった。郷里の家には淨感寺の養女
だったおもんが、一人娘のおしゅんと住んでいた。すでにおしゅんを養女にして郷里の家
を継がせるつもりでいるが、そのことはまだ本人たちには知らせていない。郷里へ帰った
時、はっきりと決めたいと思っていた。
長八はこうして死後のことまで考えるようになっていた。
三月末、長八は故郷に帰る。兼吉を正式に入籍させることと、おしゅんを養女にするた
めである。
おしゅんのことは、淨感寺のたきえに相談すると、一も二もなく賛成してくれ、おしゅ
ん親子は異存はなく、直ぐさま入籍させた。おしゅんは弘化三年生まれだから、もう三十
五歳である。どういうわけか、未婚であった。
用件はすませたが、折角のことだから四、五日遊ぶつもりでいると、隣村の岩科で新し
く小学校を建てているので、これに長八の鏝絵を塗ってほしいと頼まれた。学校は木造二
階建ての洋風の土蔵造りで、当時の学校建築の一つの典型であった。
岩科小学校の工事はほとんど完成に近かった。長八は二つの客室に得意の鏝を振るった。
そのうち、最も著名なのは、四方の欄間に描いた『千羽鶴』の図である。地土を青く薄く
塗って空に見立て、その空一面に無数の鶴が描かれている。青地に白点が散りばめられ、
遠くは小さく微かに、近くは大きくくっきりと、鶴の群れが次第にこちらに飛んで来る状
景である。じっと見ていると、その羽ばたきが聞こえて来るような気がする。小さく遙か
な空の彼方の鶴の向こうにも、まだまだ無数の鶴が続いて来るような錯覚を起こさせる。
脇床の杉戸に、唐美人が蓮を見ている図があり、それに唐詩らしい七言絶句が書かれて
ある。もちろん、すべて鏝で書いたものである。この作品は学校には不似合いのように感
じるが、どういうわけで描いたか、私にはわからない。脇床には、山水を南画風に描いて
いる。木地に金砂子をまき散らし、それに山水の線描をしたもので、線描といっても鏝で
漆喰を塗ったものだが、鏝の運びの跡がいかにも美しいし、力強い。
なお、バルコニー上の「岩科学校」の扁額は太政大臣三条実美の筆である。、また、山
岡鉄舟の書が寄せられた。
『いうなかれ 今日学ばずして 来日有りと、
いうなかれ 今年学ばずして 来年有りと、
日月は逝く 歳は延びず ああ、
老いたり これ誰の愆(あやまち)ぞ』
と、達筆そのものである。
なお、実美の書は、学校建設に熱心な静岡県令(知事)大迫貞清が依頼したものか、長
八が鉄舟に頼んだかはさだかでない。
小学校の仕事が終わると、村役場の壁を塗った。村役場はもはや跡形もないが、その作
品は今も一部保存されている。いずれも長八の技法を自在に駆使したものである。結城素
明氏の実見によれば、『清少納言の図』『貴人寝所の図』『天井竜』『梅図』(掛軸『蘭』『霊
芝』『笛』などがあった。
この仕事の間に、二人の左官が弟子となって仕事を手伝った。二人とも岩科の者で、佐
藤甚三と山本三四郎である。甚三は四十六歳、すでにりっぱな棟梁であった。後に自分の
養子富蔵を特に東京にやって修業させている。三四郎は三十九歳、これもすでに一人前の
職人であった。この人も息子の三右エ門を弟子入りさせている。
岩科村の仕事が四方に伝わって、またもあちこちから依頼を受けて、いくつかの作品を
つくった。そうこうしているうちに、早くも梅雨期に入った。そのいくつかの仕事の中に、
春城院の三天像がある。
春城院は臨済宗妙心寺派の寺だから、竜沢寺と同門である。住職禅鼎和尚は竜沢寺の星
定禅師と親しく、そんな関係から、長八に依頼したのであろう。
長八は本堂の一角に蓆を敷いてそこを仕事場にした。甚三や三四郎が手伝ってくれた。
この時、中西伝二郎が弟子入りをする。後の中西祐道である。長八がまだ少年の頃、兄弟
子だった勘松の子で、時に三十二歳の働き盛りであった。腕もよく才知にもたけていた。
ただ功名心が強く、自尊心が高く、そんなところが長八には気に入らなかったらしく、こ
んな話が残っている。
ある日、伝二郎は弘法大師像を塗っていた。寺にある木造を見て模造したのであろう。
自分なりに気に入って、やや得意気に長八に見せた。すると、長八は手にとって見たもの
の、そのまま黙って横に置いて何も言わない。
「師匠、すみませんが」
と重ねて言うと、
「そうか」
と、長八は仕事中の鏝を持ったまま、
「格好だけは仏様だ」
とだけ言った。伝二郎は不審だったし、賞めてもらえると思ったのが酷評だったのに、
いくらか不愉快だった。
「格好だけではいけませんか」
と聞いた。虫の居所が悪かったのだろう。あるいは、そんな所で満足している弟子を戒
めるためだったろう。長八は持っていた鏝でいきなり仏像を一撃した。
「作り直せ」
と一言いって、後はとりつく島もなく仕事を続けたという。こんな話の中に、長八の芸
術への態度が厳しく感じられる。
春城院の三天像というのは、弁財天、毘沙門天、大黒天の三つで、現存しているが、ど
うも長八の作品らしくない。郷里の伝説の中に、伝二郎が後に彩色し直したという話があ
る。何かで破損したか汚れたのを、伝二郎が補修したのであろう。
も一つ、伝二郎について、長八が佐藤甚三に語ったという話がある。
『伝二郎は器用な男で、自分で何でも出来るように思っているが、どうも腰がすわってい
ない。お前は年配者でもあるし、兄弟子だから、あいつが慢心しないようによく気をつけ
てくれ』
と言ったという。
③
春城院の仕事が終わって、長八は帰京する。出発の前夜、伝二郎が来て、沼津に用事が
あるので一しょにという話で、早朝の沼津行きの船に同船した。伝二郎はその時若い妻を
同行させていた。
梅雨期が過ぎてもう真夏であった。間もなく土用波の出る季節となる。すると、船は海
が荒れるから欠航する。今が一番いい船旅の季節である。案の定いい日和で、海風が涼し
かった。甲板で風に吹かれながら、島山を眺め、乗り合わせた人々と話をして過ぎた。伝
二郎夫婦も始終長八のそばにいて、話の中に入っていた。
昼過ぎ、狩野川の川口に入り、我入道の漁家の建ち並ぶ川岸をさかのぼった。長八はふ
と思いついて、伝二郎に言った。
「ついでのことに一しょに三島に行かないか。お前に見せたいものだある」
長八は伝二郎に竜沢寺へともないたかった。才気走った若者に、禅道場の修行の大切さ
を伝えたかった。
「竜沢寺ですか」
伝二郎はすばやく相手の意図を見てとったようである。
「うん」
と長八は軽くうなずいた。
「是非」
と伝二郎が言った。
沼津で馬車に乗って、東海道を伝わって三島に来た。三島では当然茂平の家に泊まる。
「勘松さんの息子ですよ」
と、長八が茂平に紹介すると、
「ああ、勘松さんの?」
と、茂平は懐かしそうに若い夫婦を眺めた。
「齢は?」
「三十二になります」
「ほう、三十二か」
茂平はちょっと考えていた。
「三十二というと、お前さんが淨感寺の竜を描いた年だな」
と、長八の方を向いて言った。こんな昔のことをはっきり記憶している茂平に驚いた。
長八自身はとうに忘れていたことだった。
「そう言われると、確か三十二でした」
と微笑した。
「そんな若い時分でしたか」
伝二郎は改めて長八の顔を見た。
「伝二郎さん、師匠ほどになるのには、容易なことじゃあないよ」
と茂平が言った。軽く笑いながら言ったが、茂平は早くも伝二郎の性質を見抜いている
ようだった。
「そうでしょうねえ」
伝二郎は殊勝にうなずいた。
「長八さんの苦労は、私がよく知っている。並大抵の苦労ではこれほどになれやしないな。
苦労に苦労をして、しかも自分で創り出した芸だからね。伝二郎さんも余っ程勉強しなけ
りゃあいけないな」
長八は黙っていたが、ふと、
「伝二郎はなかなか筋はいいようです。親父さんの血がありますからねえ」
と茂平に言った。続けて、どちらにともなく、
「しかし、まだまだ修行が足りません。腕や小手先にたよっていましてね」
と付け加えた。
「そこなんだよ」
茂平が言った。
「腕や小手先だけの仕事では、結局師匠の真似しか出来ない。師匠の真似だけでは師匠以
上にはならない。いや、長八さんの仕事の真似はとても出来まいな」
「そうですね」
と長八が相槌を打った。
「若い頃、川越で絵の修業していて、そういうことをしみじみ思いました。師匠はいろい
ろな手本の絵を見せてくれるのですが、いよいよ描く段になると、さっさと手本をしまっ
て、私に見せないのです。自分の絵を描けと言うのです。始めは大分困りましたが、それ
だから力がつくのだと思うようになりました」
「いい話だな」
茂平が言った。伝二郎は戸惑ったように黙っていた。その姿を見て、茂平が言った。
「どうしたらよかろうかと考えるのだ。悩むのだ。そこから悟るのだ」
「そうですね」
と長八が言った。
「明日、伝二郎を連れて竜沢寺へ行きます」
長八が話題をかえた。
「そうか」
「久しぶりに星定禅師に会えます」
「そうだな。よろしく言っておくれ。わしも行きたいが、この頃脚が弱くなって歩くのが
つらいのだ」
「そうしましょう。直ぐもどるつもりです」
「それはそうと、春城院の仕事をしたそうだな」
茂平が言った。
「どうして知ってるのですか?」
長八が聞いた。
「禅師から」
「そうですか。やっぱり禅師の口添えだったんですか。禅鼎和尚はそんなことを一ことも
言いませんでした」
「変わった坊主だからな。禅鼎はたっしゃか」
「ええ、至極元気で。高声で何やかや職人たちを相手に説教していました」
「面白い坊主だ。あれでなかなか抜け目のない計算をしているのだな。お前さんの作品で
寺を売り込むつもりだろう」
「まさか」
「いや、そうかも知れないよ。禅師に膝詰め談判をしたというから」
「そうですか」
夜は外出していた儀三郎をまじえて歓談した。
翌日、長八は伝二郎だけを連れて竜沢寺に出掛けた。あいにく禅師は留守だった。顔見
知りの役僧が、
「原の村へ参りまして」
と申しわけなさそうに言った。
長八は伝二郎を案内して、隠寮と不動堂を見て廻った。
別に、長八は何も言わなかった。
その日の夕方、伝二郎夫婦は沼津にもどった。長八はもう一晩泊まって、茂平と語り合
った。とりとめもない話だった。しかし、二人とも老境にあって、これが最後かも知れな
いという切実な哀惜が話の中にこもっていた。
翌日、別れがたい気持ちをこらえて、長八は馬車に乗った。
東京に帰ると、芝高輪の泉岳寺で、天野屋利兵衛の像を依頼された。
天野屋利兵衛といえば、赤穂浪士の義挙に協力して、武器、装束の調達を引き受け、侠
商としてうたわれた人である。明治になって、歌舞伎が勃興し、中でも忠臣蔵が人気を呼
び、天野屋の義侠は一層有名になっていた。ところで、長八と親しかった中島座の俳優た
ちも忠臣蔵を興行して大当たりをとっていて、これを記念して泉岳寺に何か寄進しようと
いうことになり、相談の結果天野屋利兵衛像をということで長八に依頼があったのである。
世は欧化の風潮が滔々と打ち寄せている時であった。西南戦争以後、その行き過ぎを憂
慮する者もあり、また反動的に国粋論を唱える者も出て来ていた。歌舞伎が盛んになった
のもその一徴候であったろう。長八は明らかに欧化の風潮に批判的であった。西洋の風を
毛ぎらいするというのではなく、やはり日本人らしく日本文化を愛したと言った方が当た
っているだろう。
長八は、もちろん天野屋利兵衛の制作を承知した。早速仕事に掛かった。しばらく史実
の考証に没頭した。風俗や衣装、利兵衛の人品、骨柄。書物をあさり、人に聞き、そして
ようやく構想がまとまった。制作に入ったのは八月の末近くだった。九月半ば完成して、
泉岳寺で記念法要が催された。
この仕事を待って、念願の隠居所の増築に掛かった。播磨屋を竹次郎に明け渡すためで
ある。おはなと二人の『ついのすみか』である。年の暮れに出来上がって、直ぐ二人はこ
こに引き移った。
明治十四年、長八は六十七歳の春をここで迎え、正月早々仕事場にこもった。彼は珍ら
しく紙をひろげて、聖徳太子像を描いていた。母屋の方から年賀客のにぎやかな声が聞こ
えたが、長八はそれには無関心に絵を描いていた。長八に挨拶しようと庭を廻って来る者
があったが、『無用の者入るべからず』と書かれた標札を見て、おはなだけに挨拶して帰
った。
正月を過ぎると、播磨屋は急ににぎやかになった。郷里から四人の若者がそろってやっ
て来たのである。入江又兵衛は入江一族で、長八の親族の若者である。山本三右エ門は三
四郎の息子。佐藤富蔵は甚三の養子で、この三人は弟子入りである。もう一人は坂倉保で
ある。保は遠い縁戚で医学の勉強に上京して来たのである。
七日正月も過ぎて、聖徳太子像は出来上がった。ようやくくつろぐ気持ちになって、郷
里から来た若者と話をした。長八にとっては、こんなことは珍しいことで、竹次郎が意外
に思うほど快活に、若者たちを笑わせたりした。
「明日は薬師さまにお参りに行こうか」
「茅場のですか」
と竹次郎が聞いた。
「薬師さまは八日ですよ。もう過ぎました」
竹次郎は薬師堂の縁日は月々八日であることを知っていて、念のために言い添えた。
「八日でなくてもいいだろう。思い立ったら吉日よ」
と長八はふざけた口調で言った。皆が声を合わせて笑った。
「若い者と一しょに、一日ぶらぶらするのもいいもんだ」
と若者たちの顔を見渡した。
「行くか」
長八は三右エ門に言った。
「はい」
「外の者もいいな」
「はい」
と外の三人が答えた。
④
翌日約束通り四人の若者を連れて、長八は茅場薬師に出掛けた。出際に、養子の兼吉が
一しょに行きたいというので、総勢六人になった。
風もなく暖かだった。大橋を渡り日本橋に向かった。日本橋一帯は眼に見えて新しくな
っていた。西洋風にきらびやかな街を、田舎出の若者たちはおずおずと固まって歩いた。
月の八日は茅場薬師の縁日で、境内の左右にはいろいろの店が並んだ。飴屋、駄菓子屋、
煮豆屋、おもちゃ屋、特に有名なのが植木市で、季節に応じた植物を並べる。
この日は九日だから、縁日の店も並んでいない。昨日の店の跡は小ぎれいに片付いてい
て、境内はひっそりとしていた。六人はかえってのんびりと歩いていた。
長八は御拝柱を見た。懐かしげだった。安政五年の火災で、すっかり変わり果てた御拝
柱だが、そこにはありありと若かりし頃の思い出があった。
「これですね。師匠の竜のあったのは」
と三右エ門が言った。
「そうだよ」
兼吉が答えた。
「焼けたのですね」
又兵衛が木の柱に触った。富蔵はまだ少年である。黙って皆の話を聞き入っていた。坂
倉保はそんな話に格別な興味もないように、境内のあちこちを眺め廻していた。
一同はぶらりと踵を返した。
「又兵衛」
不意に長八が呼んだ。
「へえ」
又兵衛が丸い眼をして見上げた。
「お前、いくつだ」
「二十になりました」
と、又兵衛が不審そうに答えた。
「三右エ門は?」
「二十一です」
「富蔵は?」
「十七です」
「兼吉は?」
「十八になりました」
「保は?」
「二十になりました」
若者たちは次々に年齢を聞かれて、何のことかと、長八の次の言葉を待った。
「おれが江戸に出て来たのは十九の年だった」
と長八はつぶやくように言った。若者たちはおれたちと同じ年頃だったのかと、意外に
思った。
「不景気のどん底でな。ろくに仕事もなし、食うことも出来ない。さんざんな眼に合った。
土方をやったり、どぶ掃除をしたり、二年間は左官らしい仕事が出来なかった」
と言った。若者は長八を囲んでゆっくり歩きながら、長八の言葉をてんでの気持ちで受
けとめていた。
「だが、おれは一生懸命だった」
とぼそっと言った。
「何に一生懸命だったかわかるか」
と若者たちの顔を見た。若者たちはわからない表情で黙っていた。
「生きることで一生懸命だった」
と自分で答えた。その言葉には実感がにじんでいた。
「生きるってことは大切なことだ。大変なことだ」
付け足すように言った。
「お前たちは、親から許されて、こうして来ているし、ちゃんと食べている。仕合わせだ
と思えよ。それだけ、生きることを大切にしないといけないな」
若者たちは黙っていた。が、てんでの胸の中で、師匠の言葉を噛みしめていた。
「仕合わせに甘えるなよ」
長八は思っていた。この若者たちが五年先、十年先、いや二十年、三十年先にはどうな
っているか。今は仕合わせであっても、十年先、二十年先のことはわからない。
やがて境内を出た。低い屋並の続く裏町で、長八はふと深川割下水の裏長屋の生活を思
い浮かべた。貧しい、暗い、みじめな生活であった。ほろ苦い思いが胸にかげろうのよう
に揺れた。そんな思いを振り払うように、
「帰ろうか」
と長八は言った。
今度は狭い道を足早やに歩き出した。所々に武家屋敷があったり、小さな祠があったり、
日本橋の表通りとは違って、ここは古びた息吹きが流れていた。
いつか新大橋の手前に来ていた。
「お茶でも飲むか」
そう言って、長八は八橋ののれんを跳ねた。若者たちがとまどっていた。長八はのれん
の中から顔を出して、黙って手招ぎした。
「まあ、お珍しい」
顔見知りの女中が笑って迎えた。
「居るか」
と、長八は親指を立てた。ここの主人善吉は明治五年に病死しているから、親指は息子
の徳次郎を示している。
「いえ」
と言って、眼をちらと奧に動かして、
「おかみさんが居ります」
と言った。
若者たちは所在なさそうに立っていた。
「お前たち、掛けな」
長八が言うと、長八の前に肩を寄せ合って腰掛けた。
「おかみさん」
女中が奧へ呼んだ。
「八名川町の親方ですよ」
すると、奧から返事が聞こえた。
「二階は?」
と長八は女中に聞いた。
「朝のうちは誰もまだ」
と女中が言って、
「さあ、どうぞ」
と女中は上にあがった。
「まあまあ、お久しぶり」
およしが奧ののれんから顔を出した。
「しばらく。元気ですかい」
長八もおよしに笑顔を向けた。
「親方もお変わりなく」
およしが土間に下りて、深くお辞儀をした。五十歳を越えたばかりだが若々しい。がど
こかさびしさが宿っていた。
「二階へあげてもらうよ。今日はね、若い者と茅場町へお参りして来たんだ」
およしが若者たちに眼をやった。
「今度新しく?」
「うん、田舎からね。皆私の身寄りの者だ」
「それはお楽しみで」
女中が階段の上がり口で待っているのが眼についた。
「じゃあ、あげてもらうか。皆一しょにあがれ」
長八が立ち上がった。若者たちも立って、長八の後ろからついて行った。
およしも二階に来て、長八の前に座った。
「親方が茅場町の帰りにここに寄るなんて、主人の引き合わせかも」
とおよしが言った。
「そうかも知れないね。何となく足がこっちに向いたんだよ」
二階には長八の作品がぐるりとある。若者たちは逸早く気づいて、きょろきょろと見て
いる。女中が団子とお茶を運んで来た。
「どうぞ」
とおよしが皿を並べた。
「じゃ、あんた方もゆっくりね」
およしと女中が障子の外に姿を消した。
「食べな」
「いただきます」
若者たちは勢いよくうまそうに団子を食べた。
「これが名物の八橋団子だ」
と長八が説明した。長八もひと串食べた。
「こっちへ来な」
皆の食べ終わるのを待って、長八は川に面した障子をあけた。
「これが隅田川だ。川上を見な。橋がいくつ見える?」
そう言われて、若者たちはてんでに首をのばして川上を見た。
「川下にはいくつある?」
若者たちは今度は川下に首を曲げた。小声で数えている者もあった。
「全部で八つ見えるか」
「へえ」
「それで、この家を八橋と言うんだ」
若者たちが、感心したように川を見渡した。
「おれが塗ったものを見て置け」
と、今度は座敷の中に眼をやった。長八はそう言っただけで、外に何も言わなかった。
帰りは新大橋から土堤沿いに歩いた。
八名川町には昼過ぎに帰り着いた。すると、竹次郎が待っていた。
「この手紙が届きました」
竹次郎が差し出した手紙は、第二回勧業博覧会の開催と出品要請の手紙だった。三月開
催ということであった。
長八はこの手紙を読んで、どうしようかと考えた。博覧会の趣旨には大賛成である。国
の産業を興し、芸術を進めるためのいい企画である。しかし、長八は第一回の時のように、
欧化に傾き、西洋に媚びるようなやり方にはついて行けないと思うのだった。長八は竹次
郎には何とも言わず、手紙を握って、そのまま仕事場に入って行った。
静かに座った。特に芸術部門に、日本芸術を軽視する態度が不満だった。むしろ日本の
芸術をこそ大切にすべきではないかと、長八は思うのだった。芸術の特質は個性にある。
日本には日本の個性がある。欧州の芸術を尊敬することは正しいことである。しかし、そ
のために日本の芸術、つまり日本の個性が軽視されるのは間違っている。長八は長いこと
座っていた。
長八は結局、博覧会出品を断わった。
竹次郎が、
「折角の機会だから出品しては」
と奨める口ぶりだったが、
「いや、またいやな思いをしたくない」
と長八は笑っていた。
晩年、長八は入江又兵衛にこの時の話をしたことがあった。
「おれは日本の芸を大切にしたいんだよ。文明開化が何でも西洋西洋ではおかしいよ。文
明開化であればあるほど、日本を大切にしなけりゃあいけないと思う。何もかも西洋がよ
くて、日本は下等だと思うのはおかしいよ」と。
⑤
内国勧業博覧会はその後も督促めいた書状をよこしたが、長八は何にも言わなかった。
一月二十七日、神田、深川が火災に遭い、またひとしきり復興の仕事に追われる。多く
は竹次郎を棟梁として働くが、長八も時には職人たちと一しょに壁を塗った。齢をとった
とはいえ、敏捷で、仕事は早かった。一仕事が終わると、ぷいとどこかへ行ってしまって
いた。
そんな仕事の時、静岡の桜井東吉が突然やって来た。静岡で美術展覧会を開くことにな
り、東吉を含めて仲間の者が出品する手はずになっている。で、一月ばかり指導してくれ
ないかという話である。長八は後を竹次郎に頼んで、東吉と一しょに静岡に向かう。
東吉の家は本通りにあった。長八はここを本拠にして五月末まで静岡で暮らす。すでに
長八の名は静岡にも知れていた。長八の作品を懇望する人々が静岡の市内はもちろん近村
からもやって来た。東吉たちの制作の世話をしながら、頼まれた作品をつくる忙しさだっ
た。一月ばかりして、東吉たちの作品もおよそ出来上がった。
そのうち、近くの淨元寺で観音堂を新築したが、それに東吉が棟梁で壁を塗った。とこ
ろが、本陣の天井に竜を塗る段になり、東吉は困って長八に泣きついた。そろそろ東京へ
帰ろうという矢先のことであった。
「いくつになっても師匠を頼りにするようでは、末が案じられる」
と長八はたしなめたが、とうとう東吉の願いを入れて、淨元寺に通うはめになってしま
った。もちろん東吉につくらせるのだが、そばに居て世話を焼くのである。この時の様子
は白衣に袈裟、手に数珠をつまぐり、観音経を口ずさんでいたという。
そうこうしているうちに五月になり、いい気候が続いた。突然清水の鉄舟寺の貞山和尚
が訪ねて来た。竜沢寺の星定禅師が病気だというのである。星定禅師の病気は気にかかっ
た。くわしいことはわかっていない。東吉にはこれからのことを話して、長八は急いで三
島に向かった。
三島で茂平に会うと、禅師は重態だという。翌朝、茂平と共に竜沢寺へ急いだ。降りそ
そぐ五月の陽光と眩しいばかりの若葉の道だったが、それどころではなかった。二人は黙
々と歩いていた。参道には遅咲きのつつじが咲いていた。
侍僧の案内ももどかしく二人は隠寮に入った。禅師は座敷の中央に横臥していた。もと
もと痩身の人だから、薄い布団が小さくふくれて、顔は小さくやつれて青白かった。くぼ
んだ眼に陰が隈どっていた。のぞくと眠っているようだった。
「老師さま」
侍僧がひざまずいて小声で呼んだ。禅師は静かに薄い眼蓋を開いた。
視線が何かをもとめるようにゆっくりと動き、やがてすぐそばにのぞき込んでいる二人
の来訪者に向いた。禅師の口もとが微かな笑みを浮かべた。そして直ぐものういように眼
蓋を閉じた。
茂平と長八は黙然と禅師の顔を見詰めていた。その顔には死の影が静かによどんでいる
ような気がした。音もない時間が流れた。
「では」
侍僧がささやくように言って、眼で促す。二人はうやうやしく合掌して退座した。
二人は黙りこくって、竜沢寺の山道を下っていた。杉の下道は湿っぽくひんやりとして、
心にしみるようであった。 茂平がつぶやくように言った。
「老師さまはもう覚悟をしていられる」
長八はうなずいた。
「そうですねえ」
と小さな声で言った。それっきり、二人は口をきかないで歩いた。
村里に下りて来ても黙っていた。二人はてんでに禅師のことを思っていた。
翌朝、長八は思いを残しながら東京に向かった。車に揺られながら、星定禅師のことを
思った。死は一定と言うけれども、やはり悲しいことであった。走馬灯のように過去のお
もかげが移り動いた。そのどれにも、禅師の暖かい愛情が胸にしみた。長八は車窓から見
る箱根の山の若葉も富士の麗谷も見ないで、うつむいたまま思い続けていた。
すっかり疲れて、その夜は小田原に泊まった。何か気力の衰えを感じていた。うちしお
れたように禅師のことを考え続けているうちに、いつか自分のことを考えていた。禅師は
長八より一つ年下の六十六歳であった。ということは、自分もまた余生の短いことを思わ
せた。
日暮れ近く平塚に来ていた。とうとう平塚でも泊まった。次の日ようやく八名川町の家
に帰り着いた。
帰ったその夜、長八は急に喘息の発作に襲われた。旅の疲れでもあったろう。禅師のこ
とで衝撃をうけたのかも知れない。喘息はしつこく長八を苦しめた。とうとう床に入った
きりの日々を過ごすようになる。
六月十二日、星定禅師死去。知らせは鉄舟から翌々日あった。
「とうとう」
長八は病床で嘆息した。予期していたことであるが、現実となってみると、また新しい
感傷に落ちた。長八は鉄舟の手紙を置いておはなを呼んだ。おはなは縁側で縫い物をして
いた。
「起きる」
長八は仰臥した体を片手で支えて起きようとした。おはながあわてて背中を抱えた。急
に咳き込んで、長八は背を曲げた。
「仏壇に灯明を」
咳ながら、長八は言った。おはなが長八の背をさすっていた手を離して、仏壇に行って
灯をつけた。
長八は這うように仏壇の前ににじり寄った。手に持った数珠をつまぐりながら、長いこ
と眼をつぶっていた。
長八は六月中病床で過ごした。梅雨に入って、気候が不順で喘息にはよくなかったので
ある。七月になり梅雨が明けると、いくらか気分もよく、起きたり寝たりの生活を続けて
いた。
七月の末、湯島の鱗祥院で、星定禅師の四十九日忌の法要が行われた。山岡鉄舟の肝い
りで、在京の縁故者が集まって故人をしのんだ。病み上がりの長八は、どうしても出席す
ると言い張って出掛けた。
鱗祥院は竜沢寺の末寺になっていた。かつて春日の局が隠居していたという由緒の寺で
ある。
この法要の後で、道楽会が催された。道楽会というのは、鉄舟主催で鉄舟道場や禅関係
者の知友が加わり、乞食二十人ばかりを正客として招待し、いろいろと隠し芸をしたり、
馳走して一日を楽しむ会である。普通には乞食供養と言って、従来からあったものだが、
鉄舟はわざと道楽会と名付けていた。時勢は文明開化を謳歌しているけれども、裏側では
悲惨な現実が多かった。特に物価は高騰するばかりで、各地に百姓騒動が起き、失職者が
ふえ、東京では浮浪者が集まって来ていた。鉄舟はそうした社会の底辺に喘ぎ喘ぎ生きて
いる人々を慰めようと、道楽会を発案したのである。
この年も二月にも同じ鱗祥院で催されたが、その廻状が今日も残っていて、およその状
況が察知出来る。
『千双屏風落成供養のため芸人二十名を以て芸尽し相催し候。右人数周旋の面々、一人に
て芸者三名を引受け、当日正午まで湯島鱗祥院に相会し、人々持前の芸を尽し、午後三時
散会す。但し正午の折詰、赤飯料理、莚一枚、茶碗一箇、小皿一箇を用意し、各芸人に相
贈り候事』
とある。ここに示された芸人というのは、もちろん乞食のことである。繁栄の底にはこ
うした衣食に事欠く惨めな落伍者がいる。そういう人たちを少しでも慰めようとする、さ
さやかな福祉事業である。二月の道楽会には、長八は静岡に出向いた後だったので、欠席
している。
道楽会の会場の鱗祥院には、さほど広くもない庭に、もう乞食たちを中にしてにぎやか
な宴になっていた。話をしている者、歌い踊っている者、食っている者、飲んでいる者、
それぞれ屈託なく笑いさざめいていた。長八は痩せ細った体に麻の着物を着流していた。
鉄舟に挨拶すると、
「よく来てくれたね。体はどうなんだね」
とねぎらってくれた。
しばらく人々と一しょに居たが、どうも体がだるく、そっと離れて庫裡の日陰に腰掛け
ていた。
そこへ鉄舟が来た。
「どうだね、体の具合は?」
「大分長病みをしました。秋までには癒るでしょう」
「お互いに、気をつけなければならない年齢だからね」
「先生は?」
「私もこの頃どうも気力が衰えて来ました」
鉄舟がそう言って、長八の横に腰を下ろした。
「こんな所でするのもおかしいが」
「実は宮中で今度大修理をすることになってね。東京で始めてなので、東京の職人にやら
せたいということになった。といって、江戸城出入りの職人というわけにいかず、幾人か
の候補を選んで、その中の一人にやらせることになった」
「結構ですね」
「そこでお前さんもやってみる気はないか。と思うんだが」
「でも、この病み上がりでは」
「いや、今直ぐというのではない」
と区切って、
「ただ、厄介なことがあるんだ。役所という所は面倒なもので、幾人かの出願者の中から
一人を選ぶために試験もするんだよ」
「そういう所は間々ありますね」
「ま、厄介だろうがやってみないか」
「外ならぬ鉄舟先生のお話ですから。喜んで………と言いたいのですが、この体ではまだ
心配です」
「秋になって、やる気が起きたら、是非やってもらいたいね」
こんな話があって、やがて秋になった。ある日、宮内庁から呼び出しがあった。長八の
体はもう仕事の出来る程元気になっていたので、指定の日に出頭した。
候補者は五人だった。役人の指示で、一枚ずつ板が渡り、それに見本塗りをしろという
のである。材料が調って、一同が塗り始めたが、長八はただ漆喰を練っているだけで、一
向に塗ろうとしない。役人が注意したが、
「へえ」
と言っただけで、なかなか塗らない。他の候補者が仕上げに掛かった時、長八はようや
く板をとって、鏝に一ぱいの漆喰を勢いよく走らせるように一気に塗って、それですまし
ていた。他の職人はまだていねいに仕上げていた。
やがて検査が始まって、係の役人たちは長八の塗板に驚いた。塗りは滑らかで光沢があ
り、厚さは寸分の狂いもない。それが一息に刷毛ではいたようにしたものとは、思われな
いのである。役人たちは異議なく長八に請けさせることにした。
この仕事は年の暮れまでかかった。が、どんな仕事をしたのか、何もわかっていない。
⑥
明治十五年新春、長八の喘息が再発して、また床に臥す身となった。発作は前の時より
はひどくなかったから、ただ寝ているだけで別段なことはなかったが、彼は十分にわが身
の老衰を意識していた。
気分のよい時は起きて仕事をしたかった。だが、竹次郎やおはなが強く戒めるので、長
八は仕方なく床に居た。一日のうちで、せいぜい新聞を見、仏書をひもとくぐらいのこと
しかしなかった。
一月、軍人勅諭が出た。三月、伊藤博文らが憲法調査のため渡欧した。それに刺激され
て、政党が組織され立憲政治への準備が進む。四月、板垣退助が岐阜で遭難する。民権思
想が火のように全国に拡がってゆく。………そんな新聞記事が、長八の心に新しい息吹き
を与えているようであった。
四月にはいると、ようやく春も落ち着いて、長八の病気も癒えて来た。長八は待ってい
たように仕事場に入る。
正月以来頼まれた仕事がいくつかあった。頼まれたことはやらなければいけないという
のが長八の信条である。仕事場で出来ることだから、長八は気ままな気持ちで仕事をして
いた。
ところが、四月半ばに大きな仕事が二つ出来た。一つは池田侯の今戸別荘、もう一つは
参謀本部からであった。長八の病状がよくなったというので、早速の注文だったのである。
今戸別荘の方を四月中に仕上げ、五月から参謀本部の仕事に掛かった。参謀本部はイタ
リヤ・ルネサンス様式を忠実に伝えた建築として有名である。洋風建築の代表的なものの
一つと言われている。長八がこういう洋風建築に立ち向かったことは、彼が単なる固陋な
国粋主義者ではないことを証明するものであろう。ただし、今戸別荘も参謀本部も現存し
ていないから、どんな仕事をしたのか、どんな作品だったのか、今はわからない。特に参
謀本部の作品が、長八の心境を解明する重要な証拠となったであろうから、返す返すも残
念なことである。
長八は参謀本部の仕事を六月末までやったはずだから、この期間に重大な軍議が何回か
開かれたろうと思われるのに、長八自身はもちろん、竹次郎らもこのことについて何も語
っていないのが不思議である。というのは、この時期、朝鮮との国交が危うく、国論も沸
騰していたからである。翌七月には遂に朝鮮事変が起き、日本軍が出動し、戦争の構えに
なっている。事変は八月には収まり、戦争にはならなかったが、参謀本部には異常な動き
があったはずである。よほど秘密が厳守されていたのに違いない。
二つの仕事をすませて、さすがに長八も疲れて、二、三日のんびりと骨休めをしていた。
そこへ、山岡鉄舟の手紙が来た。例の道楽会の通知であった。
今度の道楽会はすっかり趣向を変えていた。場所は両国一の料亭万八楼で、納涼を兼ね
ての集まりとなっていた。集まる人々は乞食ではなくて、当代一流の芸能人というのであ
る。歌舞音曲、あるいは和歌、俳諧、川柳、漢詩、更に書画、工芸に及ぶ広範囲な華麗な
顔ぶれであった。
「こんな時勢に、何たることを、と憤慨する者もあるだろうな」
と、長八は書状を読み終わってつぶやいた。長八は鉄舟の気持ちがわかり過ぎるくらい
わかっていた。鉄舟は恐らくそういう非難を予測しているだろう。そして、いつものよう
に不敵な微笑を浮かべているだろうと、長八は思った。
「おれはいつでも縁の下の力持ちだ」
というのが、鉄舟の口癖だった。多くの芸能人を招いたのも、縁の下の力持ちの働きに
違いないと、長八は思った。世は滔々と欧化の濁流のまにまに進んでいた。政治経済はも
ちろん、芸能の道もひたすら欧化に明け暮れしていた。が、そのために今日まで続いた日
本固有の芸能が忘れられ捨て去られていいはずはない。多くの名人たちが、優れた芸を持
ちながら、次第に世の中から消えてゆき、埋もれてゆく現状は決していいことではない。
大切にすべき人々である。鉄舟はそう考えたに違いない。
たとえ、人々がこの道楽会の催しを、反時代的、反社会的と言おうとも、それは一時的
な一方的な感覚に過ぎない。むしろ、こういう人々を守り、芸能を絶やさないように、後
世に残さなければならない。鉄舟はそう考えたに違いない。
長八は無論出席の返信をした。幸いにも仕事がひと区切りした時である。
当日の道楽会は盛大であった。集まった芸能人が次々に得意の実演を披露し、いつまで
も興は尽きなかった。宴半ばで、早くも夕風が川面を渡って吹き通った。この時、余興と
して、山岡鉄舟の二人の娘が美しい振袖姿で出て、日本画を描いた。姉の松子は二十歳、
妹の島子は十八歳であった。満座の中で、二人の娘は臆する表情もなく絵筆を走らせた。
が、どうしたことか、姉の松子が縮緬伏紗地に蟹を墨描きしていたところ、筆の先の墨汁
がぽたりと一滴落ちた。墨汁は見る間に布地ににじんでいった。はっとしたが、松子には
失敗したという気だけが走った。筆を持ったまま茫然としていた。眼には涙を浮かべてい
た。見物の客たちもぼんやり見ているだけだった。すると、長八が松子のそばにすり寄っ
た。黙って、筆を握っている松子の手をとって、にじんだ墨跡から上へと筆を走らせた。
また走らせた。三本、四本、五本と描いているうちに、それは芦の茂りになっていった。
蟹は芦の茂みの中に遊んでいた。突差の機転に、満座の客はほっとし、見事な絵の出来に
喝采した。
こういう話が伝えられているが、真偽のほどはわからない。しかし、長八の逸話として
はあり得ることのように思われる。すでに長八は自分の作品の中で、こうした類のことを
幾度もやって来ているのだから、当たり前のことであったろう。
夏も終わって、涼しい風が吹き始めると、長八はまたも喘息の発作を起こした。気候の
変わり目がいけないのだった。が、寝込むほどではなく、静かに暮らしていればよかった。
医師には老齢を気遣って、無理をせぬよう、外出も仕事も禁じた。が、容体はさしたるこ
ともなく、そのまま秋を過ごした。
十一月、郷里の春城院の禅鼎和尚から寄付金募集の趣意書が届いた。禅鼎らしい漢文ば
りの気取った文章で、要するに、大般若経を安置する壇を設けるための費用の募金だった。
長八は竹次郎に言い付けて、春城院に金を送らせた。春城院の記録を見ると、翌年一月十
日に受領している。一箇月余もかかった当時の郵便状況が察せられる。
長八の喘息は十一月を通り過ぎると快方に向かった。明けて明治十六年正月には、長八
は仕事場に入っていた。
「まだ早いから、およしなさい」
とおはなは止めたが、長八は、
「気分がいいから、ちょっとだけ」
と言った。
しかし、一たん仕事を始めると、夢中になるのが長八の癖である。始めはよかったが、
そのうち、朝から入りびたるようになった。おはなは長八の疲れが眼について、しきりに
止めさせようとしたが、
「疲れれば止めるよ。おれの体はおれが知っているから」
と言っては仕事場に入った。
この時、長八は『十六善神画像』を描いていた。幅四尺、縦七尺の絹に、精緻な筆で極
彩の図である。いかにも心ゆくまで描き上げたといった感じの絵であった。十六善神とは
夜叉大将で、十六人の将が各七千の族を従えて、般若経の誦持者を護り、危難から救うと
いうもので、正確には般若十六善神という。長八が春城院の般若経護持のために心をこめ
て描いたものである。春城院へ寄付を送っただけで満足せず、長八はこんなことを考えて
いたのである。
このことに見られる長八の心境を、私は次のように考える。長八は喘息にかかって以来、
老年の思いが深く、それは明日をも保障しない生と死を現実に直面する。長八は六十九歳
になっていた。当時としては長命であった。が、それゆえに生と死は現実の問題であった。
その上に喘息という、いわば老人病にかかり、再三にわたって苦しみを嘗めた。苦しみの
中で、彼は恐らく人生の終末を意識したことであろう。明日をも保証しがたい生命、それ
は逆らうことの出来ない人間の運命である。神妙に従うしかないのである。が、それはそ
れとして、だからこそ現世に未練はあった。残り少ない人生だから、やりたい仕事をやり
とげたい。やりたい仕事は山ほどあった。そして、恐らくその全部をやりとげることは不
可能と、今は思うようになっていた。せめて、やれるだけのことはやりたいと、長八の心
は燃えた。それはもちろん名誉などというものではない。ただおのれの生命を洗いざらい
曝らけ出したいだけのことなのである。
そういう心境になった時、人は回帰の衝動にかられるようである。老人が過去を追想し、
古いものを愛するというのはその心であろう。長八の場合、彼が若い時代に絵師を夢み、
川越で修業したことが、六十九歳の回帰として頭をもたげた。絵師の夢は鏝の芸術に変貌
した。そして一世の名人となった。それはそれで悔いはない。が、夢は依然として老境に
入っても持っていた。いや、若き日の夢がよみがえったというべきであろうか。絵筆を握
って、思う存分に描きたかった。
絵筆を握ると、心がときめいた。楽しかった。彼は一筆一筆力をこめた。十六善神画像
の精緻な筆や極彩色はそうした長八の心を映しているように刻明である。
『十六善神画像』は二月四日郷里の春城院に届いた。二月十三日、般若経真読の会があ
って、その席上で、長八の画は披露されて、人々はこの華麗な画像を拝礼した。
実はこの時長八は故郷に帰っていたのかも知れないという誤伝の材料がある。それは依
田家の土蔵に『竹に虎の図』を描き、その時、『平遠山水図』の塗額を制作したと伝えら
れている。依田家は前にしばしば出た名主の家で、たまたまこの年三月、依田善六の義弟
の依田勉三が北海道十勝の開拓に出発するに当たって、善六の妹のリクとの婚礼があり、
そのため、屋敷内の大修理したので、土蔵の鏝絵をこの年に制作したものと誤り伝えられ
たようである。『平遠山水図』は確かにこの年の作品だが、これは東京で制作されたもの
を後日に依田家に渡したと見る方が正しいようである。もし長八が帰郷していたとしたら、
たった二点しか作品がないというのはおかしいのである。
ところで、長八と依田勉三とはまんざら無縁ではない。勉三は兄佐二平と共に、土屋三
余、すなわち宗三郎の甥で、しかも少年時代を三余塾で教育を受けている。つまり、長八
とは間接的ながら同学の人であった。
⑦
明治十六年四月、長八は日本橋小伝馬町の祖師堂建設に着手する。小伝馬町といえば、
幕末の志士たちが安政の大獄によって投獄された牢舎のあるところとして有名である。明
治八年、政府は牢舎を市ヶ谷に移し、小伝馬町の跡地は東京市に売ろうとしたが、気味悪
がって誰も買わない。仕方なく公有地とし、供養の気持ちもあって、ここに祖師堂を建立
することにしたのである。
かつて茅場町の薬師堂のこともあり、ここも土蔵造りにしようということで、長八に委
嘱することになったのである。
四月といっても、まだ肌寒い日があった。長八は毎日石井勝之助と石井巳之助を連れて
小伝馬町へ通った。二人は千葉から来ている兄弟である。外に中橋善吉と江口庄太郎が手
伝いに来ていた。二人はすでに独立しているのだが、師匠の老体を気遣って来ているので
ある。長八はもっぱら堂内の装飾に当たり、善吉と庄太郎は内陣に祭る鬼子母神、弘法大
師、日蓮上人の三体を原型造りをし、石井兄弟は壁を塗った。
ある日、長八は正面入口の天井に、得意の竜を塗っていた。足場が組まれ、その上に座
布団と火鉢が置いてあった。
「師匠」
と、堂の奥から善吉が顔を出した。長八は手を休めて、善吉を見下ろした。善吉が身軽
に足場をくぐって上がって来た。
「ここんとこですがねえ」
善吉は持って来た下絵を指で示した。日蓮上人の座像図であった。長八は黙ったまま下
絵に眼をやった。
「どうなってるんでしょう」
善吉が指で下絵の線をなどった。長八は絵図を引き寄せた。
「脚だな」
「へえ」
「衣の裾が膝に掛かって」
長八はそう言いながら、腰から矢立てを取って、素早く筆を抜いた。
「膝の頭がふくらんで」
言いながら、長八は筆で下絵に太い線を描いた。
「衣の裾がこういう具合に皺をつくって」
と、また筆をゆっくり走らせた。
「ああ、わかりました」
善吉が納得したようにうなずいた。
「膝の丸みと皺との釣り合いに気をつけろよ」
と、長八は念を押すように言った。
「わかりました」
善吉が忙しそうに下絵を手にして後ずさりをした。
「ちょっと待てよ」
長八が言った。
「へえ」
「日蓮さんは気性の強いお方だから、膝のあたりも柔らかいよりはいくらかごつくした方
がいい。足の先にも力が入ったようにな。それから両膝が左右にぐっと開き切った格好に
してくれ。上体も胸もやはりゆるんじゃあいけないぞ」
長八は気づいたことを付け加えた。善吉は一つ一つうなずき、
「はい、わかりました」
と一礼して足場を下りて行った。長八はその後ろ姿に眼をくれず、直ぐ鏝をとって、天
井の竜を描き始めた。長八の仕事は素早い。土をぶっつけるようにして塗って行く。泥が
飛び散るような勢いだが、不思議と泥は落ちない。漆喰はたちまち塗り尽くされてしまう。
「勝!」
長八は勝之助を呼んだ。
「はい!」
とどこかで返事をして、勝之助が漆喰を運んで来る。それを手際よく受け取ると、また
無心に天井を塗る。
「おい、伊豆の先生」
と、下からどら声が聞こえた。河鍋暁斎だ。
「やあ、暁斎先生」
長八もちらりと下を見て返事をした。が、それだけで、もう相手にせず天井を塗り続け
た。
河鍋暁斎はこの時五十三歳。日光東照宮の古画の修理をしたり、芝の黒不動の補修など
で世に知られている画人である。生来酒好きで、随分奇行ももあったらしく、自ら狂斎と
称していた。この祖師堂の杉戸に絵を描くことになっていたから、毎日のようにやって来
るが、杉戸には手に触れず、そのままいつとなく帰ってしまっていた。
暁斎は長八の鏝さばきを見上げていた。
「うーむ」
とうなった。
「お前さんの鏝は、筆よりもよく走りますなあ」
と言うと、もう堂の内に消えて行った。
「勝!」
長八の声が響いた。勝之助が土を運んで来た。
本堂の須弥壇の前では、茣蓙を敷いた上で善吉と庄太郎が日蓮の像をつくっていた。
「よくやりますなあ」
暁斎が声を掛けた。
「暁斎先生、今日は」
二人は顔を向けて挨拶した。暁斎は赤ら顔をにやっとさせて、脇の板縁の外明かりの中
に影を引きずりながら行ってしまった。
昼食の時になった。まだ日光がほしい季節で、皆縁先の日の中で弁当を開いた。長八は
いつものように握り飯を手づかみにしていた。
「暁斎先生は?」
長八があたりを見廻した。
「さっき、ここを通って行きましたが」
庄太郎が言った。
「とっくに帰りましたよ」
巳之助が言った。巳之助は外の壁に荒土を塗っていたのである。
「今日も帰ったか」
と長八が感心したように言った。
「相変わらずだなあ」
と善吉が言った。つられたように皆が笑った。
昼から風も静かになり、暖かい日射しになった。長八は天井に竜を描き続けていた。
「勝!」
「はい」
長八の声に勝之助が顔を出した。
「今度は白漆喰だ」
「はい」
勝之助は白漆喰を運んで来た。そこへ巳之助が来た。
「親方、今から欄間に掛かります」
と長八を仰いだ。
「うん」
長八が天井を塗りながら、短く言った。
巳之助は直ぐ近くの欄間に脚立を立てた。長八と背中合わせの格好がおかしいと思って
巳之助が、くっくっくと笑った。
「何だ」
長八が聞きとがめた。
「親方と背中合わせで」
巳之助が尚も笑い続けた。
「そんなにおかしいか」
「何だか、けんかしたみたいで」
巳之助がまた笑った。
そのまま仕事になった。しばらく静かな時が過ぎた。長八は竜のこまかい部分に柳葉の
鏝を使っていた。
その時、下で働いていた勝之助が、誰かと話す声がした。長八は何の気なしに下を見る
と、そこに立っている老女と視線が合った。
「お懐かしゅうございます」
老女はていねいに頭を下げた。六十歳前後かと思われる上品な服装の老女だった。挨拶
されて、長八は狼狽した。
「おきんか」
長八は思わず言って、息を飲んだ。紛れもなく、最初の妻であったおきんである。
「はい、お久しぶりでございます」
老女は懐かしそうに長八を仰いでいた。
が、長八はそれっきり言葉を出さず、忘れたように天井に鏝を動かしていた。老女はそ
の姿をしばらく見ていたが、あきらめたようにその場を立ち去って行った。
その日の帰り道、巳之助が無遠慮に、
「さっきのおばあさんは誰です?」
と長八に聞いた。長八は一瞬暗い影を浮かべたが、さっぱりと言った。
「おきんと言ってな、おれの初めの女房だった女だ」
そして、思い出すようにつぶやいた。
「何年ぶりかなあ」
後は黙りこくって、すたすた歩いて行った。
祖師堂の仕事は一箇月足らずで終わった。天井の竜は『顎出しの竜』と呼ばれて評判に
なった。平板な浮彫であるが、頭部だけ突き出ていて、今にも天井から抜け出しそうな様
相をしていた。
六月三日、先妻おたきの十三回忌の法要をした。その時、菩提寺の正定寺に墓参し、寺
の荒廃しているのに驚いた。ここ数年、仕事のことや病気のため訪れることがなかったか
ら、今更のように荒れ果てた寺が身にしみた。
明治以来、寺は政府の保護を受けられなくなった。自立しなければならなかった。その
上、西洋崇拝の思想は寺院や仏教を軽視した。先には神道主義者の圧迫を受け、また文明
開化にうとんじられて、檀家の援助も自然と消極的になっていたのである。どこの寺でも
そうであるが、わけて小さな寺ほどひどかった。正定寺もその例である。
「何とかしなくては」
と長八は思った。住持と話をしたが、住持は望みを失ったようにあきらめていた。
長八はひそかに正定寺改築を考え続けた。寺には財力がない。檀家も無力である。とす
ると、有志の寄付に待つ外はない。
「やってみよう」
長八は決心した。
それから後、長八は夏の日射しの中を小まめに歩き廻った。幸い、長八の善意を理解し
て、厚意の寄付が増して行った。が、まだまだ到底改築までには至らない金額だった。
八月も半ば過ぎて、長八は今日も汗を流しながら町を歩いた。赤坂に来て、一息入れよ
うと、菊地幸太郎の家に立ち寄った。
ここで突然菊地幸太郎という人物が出て来るのだが、創作でないから仕方がない。伝説
の中でも、長八の晩年にしか出て来ない人物なのである。しかし、晩年の長八にとっては
重要な人物である。菊地幸太郎は、長八の妹のふでが隣村江奈村の大工菊地虎松に嫁し、
幸太郎はその長男として生まれた。父の虎松は実兄に子がなかったために、その跡を継い
だが、やがて八王子に定住し、大工から材木商となり、次第に商売をひろげていた。明治
になって東京赤坂に移り、材木商兼建築請負を業としていたが、明治十二年に病死し、幸
太郎が跡を継いでいた。母のふではすでに八王子の頃に病死している。おふでには子供が
三人あった。上が女で、おえいと言った。次が幸太郎で、下が順助と言う。順助は養子に
行って東京にはいない。おえいは八王子に嫁入りしている。幸太郎はこの時まだ三十歳を
越えたばかりだが、仕事熱心な男で、父親の代よりも繁盛していた。長八にとっては数少
ない肉親の一人だから、何かにつけて交渉があったはずだが、私の力不足で、その間の実
状は一切わかっていない。先に述べた長八の養子問題の時の候補者の幸太郎はこの人であ
る。
⑧
久しぶりの伯父の来訪を、幸太郎は喜んで迎えた。
「ちょっと休ませておくれ」
と、長八は遠慮なく座敷に上がり、風の通る縁近くに脚を投げ出した。
「この暑い日盛りを、何か特別な用事でもあったんですか」
幸太郎は伯父の身を案じて、とがめるように言った。長八は胸を拡げて、扇子で風を入
れていた。黙ったまま笑った。
「無理なことをしないようにして下さいよ」
幸太郎が団扇であおいだ。
「特別な用事というわけじゃあないがね。ちょっとこの辺を通ったもんだから」
幸太郎の女房が茶を運んで来た。長八は待ち受けていたように直ぐ手にとった。
「うまい」
と一息に飲んで、無邪気に舌鼓を打った。
「体はすっかりいいんですか」
幸太郎は、少し痩せて来た胸のあたりを見て言った。
「もう大丈夫だろう。この間は、日本橋の祖師堂の仕事もやったし、少しまだ疲れるがね。
それだって、齢だものな、若い時のようには行かないよ」
「そうですね。だから、用事があるなら涼しい時刻にすればいいんですよ」
「そうしてもおれないんだ」
「何です、その用事というのは」
幸太郎の問いに答えず、長八はただ笑った。言えば、また幸太郎に心配されると思った。
が、ふと頭の中にひらめいたものがある。正定寺の資金集めも限界に来ている。まだ十分
に集まっていない。幸太郎にも出してもらおう。そんな気持ちが動いた。
「実はな、幸太郎」
と、長八は真顔に帰って言った。
「正定寺の基金集めをしているんだ」
「へえ」
幸太郎は驚いた眼をした。
「この間、おたきの十三回忌の法事をしたっけな」
「へえ」
「その翌日、寺へ行ったんだよ。久しぶりに墓参りにな」
「へえ」
「ところが、寺の荒れようが大変なんだ。あれでは後五、六年も持つまいと思った」
「どこの寺も大変なようですね」
「ことに正定寺のような小さな寺は困るんだよ。寺に財産はなし、檀家は少ないし」
「そうでしょうね」
「といって、腕を組んでいるわけにも行かない。で、和尚と相談したが、何しろ先立つも
のは金だ。その金がないんだから」
「それで資金集めということになったんですね」
「うん、そうなんだ」
「で、幾人で集めているんで?」
「わたし一人で、だよ」
幸太郎はあきれた顔になった。
「一人で始めたんですか」
「うん、正定寺にはそんなことをする檀家はないからね」
「それにしても一人じゃあ無理ですよ」
「無理は承知だよ」
「それで、金は集まりましたか」
「うん、そこだよ。六月から始めたから、もう大分頂戴した」
「それは結構です」
幸太郎はほっとした表情をした。
「結構とまでは行ってないな。まだとても足りない」
「どのくらい?」
「そうだな、あと百両はほしいな」
「百両とは大金だ」
この場合、百両というのは百円のことである。
「お前が檀家なら、たっぷり出してもらうんだがなあ」
長八は、そう言って笑った。すると、幸太郎が突然、
「檀家になりましょうか」
と言った。
「外ならぬ伯父さんの寺だ。かまわないでしょう」
真顔だった。
「冗談だよ」
「いや、本気です」
「寺ってものは先祖さんからのものだからな。そうはいかないよ」
「そりゃあそうですが、わっしらのような伊豆の人間が東京に出て来て、東京が死に場所
だとすれば、東京に寺があっていいわけでしょう」
「それはそうだ」
「親父やおふくろは郷里に埋葬しましたが、わっしの代からは東京が故郷ですからね」
「なるほどな」
長八は感心したように言った。
「伯父さんの寺に、わっしらも一しょだということになるとうれしいな」
幸太郎はさも愉快そうに言った。
長八はしばらく考えていた。別にこだわる必要のないことだと思った。
「じゃ、そうするか」
と笑った。
「それで決まった」
幸太郎は満足そうだった。
「するってえと、早速寄付をさせてもらいましょうか」
幸太郎は今にも現金を出しそうな顔だった。
「待てよ」
と長八は言った。
「それは後廻しにして、まずお前の眼で寺を見てくれよ。なるべく近いうちに」
「それはどういうことです」
「改築するとして、お前の眼でどのくらいの費用がかかりそうなのか調べてもらいたいの
だ」
「そうですね。なるべく正確な見積りをしてみましょう」
話が飛んだ方向に反れて、ようやく夕風が涼しく庭先から流れて来る時刻になった。
「涼しくなったから」
と、長八はゆっくり腰をあげて、
「じゃ、たのんだよ」
と言った。
それから数日して、幸太郎が八名川町を訪ねた。
「今朝、言って見ました」
「で、どうだった?」
と長八が気掛かりのように聞いた。
「ひどいもんですねえ。あれじゃあ使える材料はありませんよ」
「そんなにひどいか」
長八は考えた。皮算用が違っていた。
「あと一年持つかどうかってところです」
幸太郎は専門家だから見方が厳しい。
「それで、見積りはどうなんだ」
と長八が心配げに聞いた。幸太郎は懐中の紙を出しながら、
「最低五百円と踏みました」
ずばりと言った。
「五百円とは驚いたな」
長八は一たん見ひらいた眼をさりげなく元の静けさにもどしていた。
「新築より手が掛かりますよ。取り壊しも計算しなければなりませんからね」
「それはそうだ」
と長八はうなずいたが、
「これは参った」
とつぶやいた。
「寄付はどうなんです」
「とても足りない。やっと二百円ほどだ」
「わっしが百円出すとして、三百円か」
幸太郎も嘆息した。長八も途方に暮れた。
「せめてあと一年の猶予があれば、何とかなると思うんだが」
「一年は無理ですね」
幸太郎が力を落とした声で言った。
二人は黙ってしまった。困り果てたように長八はうなだれていた。やがて、
「幸太郎」
と長八が言った。強い眼だった。
「こうなちゃあ仕方がない。お前が檀家になった記念に、材木全部寄付しておくれ。おれ
は左官の仕事一切を寄付する。そうすれば大工の手間賃だけだ。それなら二百円でやれる
だろう」
幸太郎はあきれた顔で聞いていた。が、直ぐ微笑を浮かべた。
「ひどいことを考えましたねえ」
「そうでもしなければ、寺は建たないだろう。幸太郎、眼をつぶってくれよ」
長八は哀願する言い方だった。
「大変なことになりました」
幸太郎の表情は言葉ほどに深刻ではなかった。
「土蔵造りにするんだ。そうすれば材木も少しですむ」
「へえ」
「おれだって、金があり余っているわけじゃあない。三度の飯を二度にしてでも、この仕
事をやる遂げたい。頼むよ、幸太郎」
必死な声だった。
「伯父さん、私も一肌脱ぎます。がんばりましょう」
幸太郎はとっくに覚悟をしていたのである。この伯父の誠実を、そうにでもして実現し
ようと思っていたのである。
秋になると材木が高くなるというので、八月中に材木を集めた。九月に入って普請に取
り掛かった。始めたからには、秋の彼岸の法会には間に合わせたいと、急な話になって、
二十日ばかりで普請してしまおうという突貫工事となった。本堂は間口七間、奥行き五間、
屋根はもちろん瓦葺きである。
長八と幸太郎が中心になって、解体から新築までの作業が総掛かりで始められた。そし
て予定通り秋の彼岸までに落成した。
この時、長八は本堂に数多くの作品を残した。欄間に飛天の図、御拝欄間に丸に竜の三
体、正面壁に波千鳥、内陣扉に天女の図、本陣壁に天女楽人と迦陵頻伽の図などである。
これらの作品は関東大震災で、寺と共に跡形もなく崩れ果ててしまった。
こんな異常な執心をしたことは、長八には珍らしいことであった。先にも述べたように、
六十九歳という年齢が、余命いくばくもないという切迫した感懐を抱かせていたからには
違いないが、同時に、播磨屋を始終思い続けていた深い恩愛の情でもあったろう。しかし、
それも裏を返せば、晩年の意識であり、死へのあせりでもあったのではあるまいか。
いうなれば、それは長八の愛と孤独のからまり合いの心の表われであったろう。明らか
に、ここには、長八が現世の時間の短いことを意識し、やらなければならない仕事として
強い執心を示したものと思われるのである。
正定寺の建築が終わると、長八はしばらく体を休めた。この仕事はやはり老体には無理
な労働であった。九月とはいえ、残暑は厳しかったのである。十月はぶらりと過ごした。
十一月も何となく仕事をせず過ぎた。
そして、年も押し迫った十二月になった。急な寒さで、養子の兼吉が風邪を引き、寝て
いるうちに、二十五日、一晩中高熱で苦しんだ挙句、その翌朝あえなく息を引き取った。
年の暮れのうちに葬儀をすませたが、長八はこれを機にいたましいほどに気落ちして、再
び病床の人となる。
第8章 終わり
動画