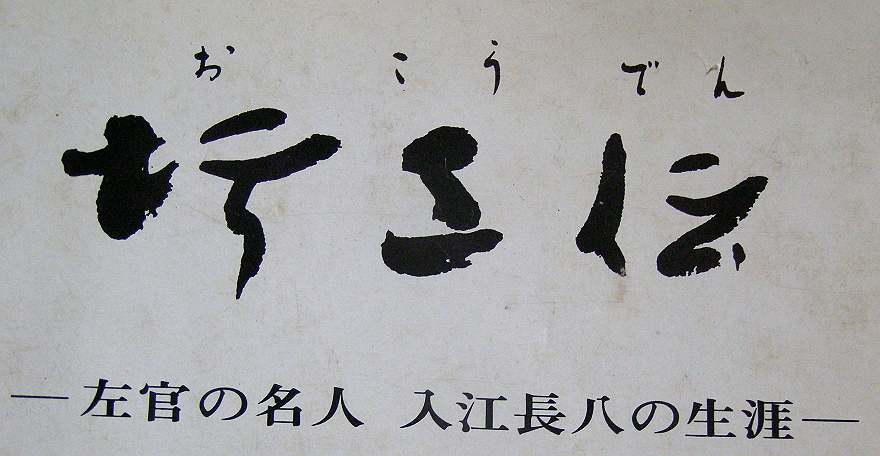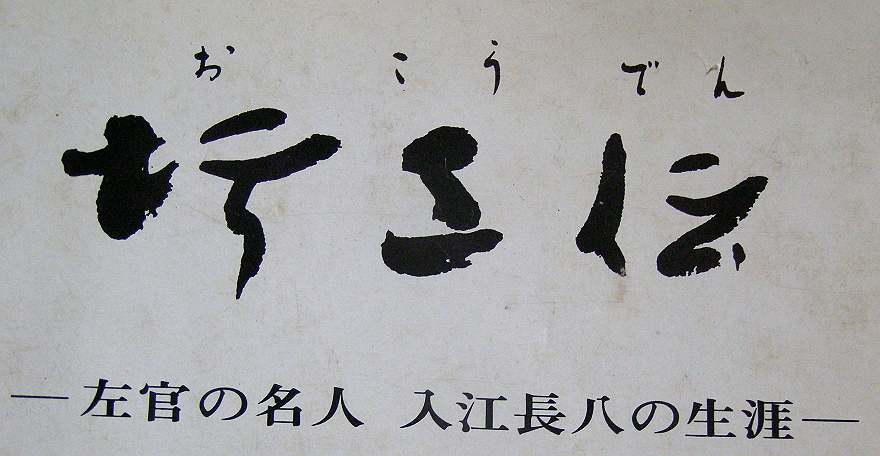須 田 昌 平著
終 章 わ が 秋 や
|
ついに、この人に終焉の時が来た。静かに
自分の一生を振り返るように、辞世の句を
書いた『わが秋や月一夜も見残さず』と、
その満足感を思う。そして、「どうも うま
くないなあ」とつぶやいた。その寂けさを
思う。
|
※
そのまま、長八は深い眠りに落ちて行った。おはなが葡萄を載せた皿を運んで来たが、
枕べにおいだだけで、幸太郎も竹次郎も手をつけなかった。
夜が更けて行った。幸太郎と竹次郎はしみじみと長八の寝顔を見ていた。二人はてんで
に長八の在りし日の思い出を追っていた。二人とも、もう駄目かも知れないという予感を
抱いていた。それだけに、胸に一ぱいの涙をためて長八の寝顔に向いていた。
翌朝、幸太郎と竹次郎は、母屋から起きて来たおはなに頼んで、それぞれの仕事場に出
て行った。長八は静かに眠っていた。
おはなが朝の食膳を運びに行ってもどって来て、長八の容体のおかしいのに気付いた。
呼吸がひどく荒らかった。が、それはいつもの喘息の発作とは違っていた。
「おふくさん」
と、おはなは大声で母屋を呼んだ。おふくは急いで医師に知らせた。
医師は様子を見て、やはり喘息だと判断して、
「しかし、老衰しているから、眼を離さないように」
と注意しただけで帰って行った。
その日から、長八は寝たきりの状態になった。家族が交替で付き添うようになった。こ
うして、とうとう十月になった。気力も衰え食事もとらなくなった。眼に見えて衰弱して
行った。
十月八日、長八はもうろうとしていた。付き添いの者も、誰も皆最期の近いことを感じ
ていた。その夜、長八は落ちくぼんだ眼を静かにあけた。そばに座っている幸太郎を見た。
「おじいさん」
幸太郎が小声で言った。
「幸太郎」
長八は乾いた唇を動かした。
「はい」
幸太郎は耳を寄せながら言った。
「竹次郎は?」
微かな声だった。
「ここに居ますよ」
竹次郎が幸太郎の肩越しに、長八の方に顔を出した。
「竹次郎か」
納得するように言った。
「何か御用ですか」
と竹次郎が言ったが、返事はなかった。
「どうですか、気分は?」
と、今度は幸太郎が聞いたが、これにも返事をせず、眼をつぶった。
「お茶でも飲みませんか」
竹次郎がのぞくようにして言った。
「ああ」
と長八は言った。竹次郎が茶碗を口に持って行くと、一口飲んで舌なめずりをした。直
ぐ、もういいというように顔を振った。
「何か食べますか」
と幸太郎が言ったが、今度は首を振った。
夜が更けていた。庭から虫の音が聞こえていた。長八は眼を閉じて、虫の音を聞いてい
るかのようだった。静かな時が過ぎて行った。と、長八が低い声で、
「幸太郎」
と呼んだ。
「はい」
幸太郎が前かがみに耳を寄せた。
「紙と硯」
微かな声で、よく聞きとれなかった。
「何ですか」
と問い返した。
「紙、と、硯」
長八が低く言った。
竹次郎が立って、仏壇の下から紙と硯を持って来た。
幸太郎が水をさすと、竹次郎が墨をすった。
渡された紙と筆を持って、仰臥したままの長八が、何か考えるように眼をつぶった。や
がて眼を開くと、紙に筆が走った。幸太郎と竹次郎はじっと見ていた。
わが秋や月一夜も見のこさず
と書かれた。書き終わると、筆ごと幸太郎に渡しながら、
「どうも、うまくないなあ」
とつぶやいた。
幸太郎は手にした紙を見ながら、小声で二回その句を繰り返し、それを竹次郎に渡した。
竹次郎は黙って見ていた。心の中で繰り返して読んでいるようだった。二人とも、いつか
涙を浮かべていた。
長八は再び眠りに落ちて行った。静かな寝顔であった。微かな寝息が更けた夜に短く尾
を引いていた。
その夜の明け方近く、長八は静かに命を終わった。七十五歳であった。
※
遺骸は予定通り、浅草の正定寺に葬った。愛妻たきと一しょの墓である。法名を『仰誉
天祐乾道居士』とつけられた。後に、その上に『光照院』という院号が加えられた。
やがて、郷里から養女のおしゅんが上京して、遺言通り分骨してもらい、淨感寺に埋葬
した。
一代の名匠はその生涯を終わった。跡目は竹次郎が相続し、二代目長八を名乗るように
なる。おはなは四十九日忌をすますと、先夫の子をたよって千葉に去って行った。すべて
が終わった。
※
私もようやく宿願の『入江長八伝』を書き終わった。ほっとした安堵と共に、これでよ
かったかのという不安と危惧もある。
思えば、この原稿を書き始めてから何年になるのだろう。気に入らなくて書き改めるこ
と三回、そして、今はこれ以上書き直すことは、もう出来ないような気がする。が、不満
がないわけではない。これ以上の労働にはもう耐えられない。不満は不満としてあきらめ
るべきであろう。私は心にそう言い聞かせる。
非凡な一人の人物を刻明にたぐって来て、ペンを持ちながら、時には涙を浮かべ、時に
は悲憤し、その人物と密着して来たと思っていたが、さて書き終わって振り返ってみると、
平凡なわれらと少しも違っていないようにも見える。恋をし、色に溺れ、争い、傷つき、
流され、つまずき、そして、市井に老い、音もなく死んでゆく。全く平凡である。
しかし、それはそれで正しいのではないかと私は思う。いや、それでなくてはならない
のではないかと思う。人間だからである。非凡ということは、そういう常凡の上に別な何
かを備えていることであって、人間離れをしていることではないはずである。
別な何かを備えているというのは、その平凡な人間の中に、チカリと光る宝玉みたいな
ものがあって、それが非凡という決定的な価値を持つのではないか。世に言う偉人とか英
雄とか、名人とか達人とか、そういう人のそのチカリと光る宝玉みたいなものを考えるが
いい。人間の全部が宝石ではない。人間の全部が非凡であるはずはない。
私は長八の伝記を書き続けながら、その平凡と非凡を、常に私の心に照射していた。何
が長八の非凡なのか。天性の才能でもあるようである。あるいは意志の力でもあるようで
ある。しかし、そういうふうに分析してはかえってわからなくなるような気がする。結局
はよくわからない。が、わからないなりに、長八の人間の中に何かそれらしいものが見え
る。そういう意味で、非凡とは平凡の中にあると悟った。非凡とは当たり前の生活の中で、
それを当たり前以上にやり遂げることだといってもいいかも知れない。
(完)
動画